僕は今、愛知県・半田市のビジネスホテルでキーボードを叩いている。
旅の目的は2つ。
今回はその1つ --- 「新美南吉」の足跡を訪ねた様子を投稿する。
「新美南吉(にいみ・なんきち)」は、
大正2年(1913年)生まれ、昭和18年(1913年)没。
結核が命を奪うまでの29年間、赤貧に洗われつつ勉学に励み、病を押して働きながら、
児童文学、小説、詩歌、随筆、戯曲などを著した。
代表作は「ごん狐」。
小学校国語教科書の教材の定番であり、
これをキッカケに「南吉文学」を知った方は少なくないだろう。
僕もその1人。--- 以来、数冊の本を手に取った。
生地・半田市には「新美南吉記念館」がある。

芝生で覆われたウエーブを描く屋根を持つ半地下構造。
多くの「南吉」作品に登場する、知多半田の自然・風景に溶け込むユニークな外観。
打ち放しコンクリート仕上げの館内も、当然の事ながら「南吉」ワールド。
何点か写真を掲載して紹介したい。
「新美南吉」近影。
教員時代のものか?理知的で線が細い印象を受ける。

「南吉」が小学生時代に書いた「綴り方帳」。
しっかりした文字に、利発で誠実な人柄が滲むよう。
何より、早くも萌芽した美しい文体に驚く。

「光村図書出版」国語教科書の「ごん狐」。
僕が学んだ「津幡小学校」でも、これを採用していた。
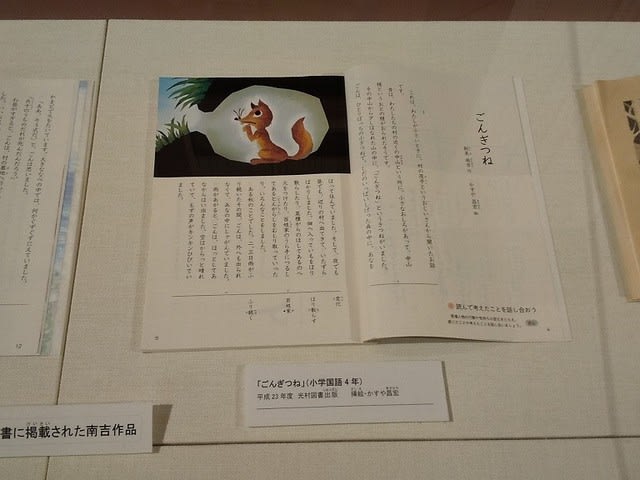
「南吉」の人生と時間を同じくする大正~昭和初期、文学史に残る児童雑誌「赤い鳥」。
「ごん狐」もここに掲載された。

記念館売店で買い求めた「南吉」の著作。

数ある展示の中で、個人的に最も感慨深かったのは、
「南吉」が東京時代に暮らした下宿を再現した一角である。

殺風景なわずか三畳の狭い空間で、彼は、命の火を燃やし創作に打ち込んだ。
今と違い、ネットはおろか、テレビもラジオもない。
無為に外界と繋がる事もなく、たった独りで、
まだ短い人生の経験と蔵書から得る着想を頼りに、
時に創造の翼を広げ、時に深慮の海に潜り、熟考を重ね、原稿用紙に向かったのだ。
「南吉」は、昭和15年(1910年)の日記に、こんな言葉を残している。
<一日の中の非常に多くの時間を、
(殆どすべてを)僕は詩の、美の探究につとめているのだ。
僕は一日のうちに三十分だけ創作的なよい気分に酔うことが出来、
一つだけ満足のゆく詩が書けさえすれば、あとはどうだっていいのだ。
いや一寸過言だ。>
「新美南吉記念館」、ご興味があり都合が許せば訪れてみてはいかがだろうか。

他にも「南吉」の生家や、
自身の幼年期を題材にした作中に登場する「常夜灯」を見学したり、
亡骸が眠る墓に詣でたりした。
また、草鞋を脱いだ「ホテルルートイン半田亀崎」周辺の、
坂のある風景を眺めたりしたが、これ以上は長きに過ぎるので割愛。
また別の機会があれば掲載したい。

さて、本日は、旅の目的のもう一つ --- 「常滑競艇場」へ向かう。
コロナショックにより、長らく無観客開催を続けてきたが、ようやく再出発。
その歴史的なタイミングをこの目で見てみたいと思い、
僕がファンになって初めて足を運んだ本場、常滑を選ぶ。
「密」を避けるため、月曜日の旅打ちにした次第である。
では!
旅の目的は2つ。
今回はその1つ --- 「新美南吉」の足跡を訪ねた様子を投稿する。
「新美南吉(にいみ・なんきち)」は、
大正2年(1913年)生まれ、昭和18年(1913年)没。
結核が命を奪うまでの29年間、赤貧に洗われつつ勉学に励み、病を押して働きながら、
児童文学、小説、詩歌、随筆、戯曲などを著した。
代表作は「ごん狐」。
小学校国語教科書の教材の定番であり、
これをキッカケに「南吉文学」を知った方は少なくないだろう。
僕もその1人。--- 以来、数冊の本を手に取った。
生地・半田市には「新美南吉記念館」がある。

芝生で覆われたウエーブを描く屋根を持つ半地下構造。
多くの「南吉」作品に登場する、知多半田の自然・風景に溶け込むユニークな外観。
打ち放しコンクリート仕上げの館内も、当然の事ながら「南吉」ワールド。
何点か写真を掲載して紹介したい。
「新美南吉」近影。
教員時代のものか?理知的で線が細い印象を受ける。

「南吉」が小学生時代に書いた「綴り方帳」。
しっかりした文字に、利発で誠実な人柄が滲むよう。
何より、早くも萌芽した美しい文体に驚く。

「光村図書出版」国語教科書の「ごん狐」。
僕が学んだ「津幡小学校」でも、これを採用していた。
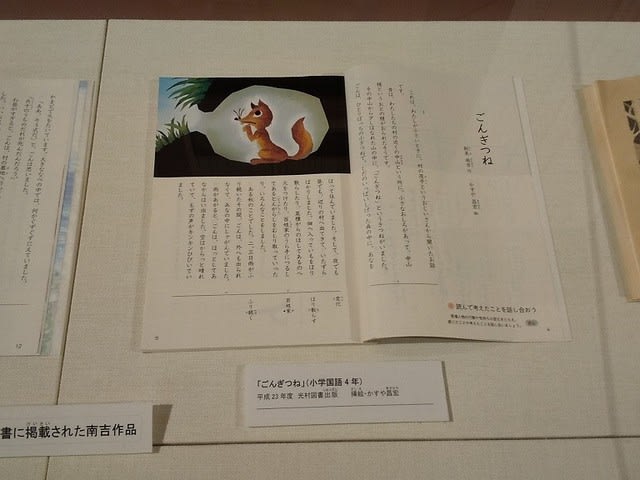
「南吉」の人生と時間を同じくする大正~昭和初期、文学史に残る児童雑誌「赤い鳥」。
「ごん狐」もここに掲載された。

記念館売店で買い求めた「南吉」の著作。

数ある展示の中で、個人的に最も感慨深かったのは、
「南吉」が東京時代に暮らした下宿を再現した一角である。

殺風景なわずか三畳の狭い空間で、彼は、命の火を燃やし創作に打ち込んだ。
今と違い、ネットはおろか、テレビもラジオもない。
無為に外界と繋がる事もなく、たった独りで、
まだ短い人生の経験と蔵書から得る着想を頼りに、
時に創造の翼を広げ、時に深慮の海に潜り、熟考を重ね、原稿用紙に向かったのだ。
「南吉」は、昭和15年(1910年)の日記に、こんな言葉を残している。
<一日の中の非常に多くの時間を、
(殆どすべてを)僕は詩の、美の探究につとめているのだ。
僕は一日のうちに三十分だけ創作的なよい気分に酔うことが出来、
一つだけ満足のゆく詩が書けさえすれば、あとはどうだっていいのだ。
いや一寸過言だ。>
「新美南吉記念館」、ご興味があり都合が許せば訪れてみてはいかがだろうか。

他にも「南吉」の生家や、
自身の幼年期を題材にした作中に登場する「常夜灯」を見学したり、
亡骸が眠る墓に詣でたりした。
また、草鞋を脱いだ「ホテルルートイン半田亀崎」周辺の、
坂のある風景を眺めたりしたが、これ以上は長きに過ぎるので割愛。
また別の機会があれば掲載したい。

さて、本日は、旅の目的のもう一つ --- 「常滑競艇場」へ向かう。
コロナショックにより、長らく無観客開催を続けてきたが、ようやく再出発。
その歴史的なタイミングをこの目で見てみたいと思い、
僕がファンになって初めて足を運んだ本場、常滑を選ぶ。
「密」を避けるため、月曜日の旅打ちにした次第である。
では!

















