コメントありがとうございます。話が問題にまで広がって来ましたが、関東に被差別がなかったわけではありません。江戸川区で言えば篠崎、葛飾区で言えば青砥が該当します。教師の中にも妙に熱心な人がいて、授業中に民の女の子に自分は民だとカミングアウトさせて良いことをしたような気になっている人がいました。
しかし、東京の場合、大阪とは多少事情が異なるかもしれません。たとえば浅草を含めて、そこから北は昔の言い方をすれば「エタ」の居住地でした。浅草に太鼓やのような、皮革を扱う業者が今でも見られるのはその名残です。足立区には弾左衛門と呼ばれるエタの元締めが住んでおり、江戸の皮革業を一手に支配下に置いていました。エタは農業をしませんので、荒川区や足立区には荒れ地が沢山残っていました。この弾左衛門は屋号のようなもので、代々受け継がれており、被差別階級ではありますが、正月に江戸城に登城し、将軍に挨拶することが許されていました。
一方と呼ばれる人たちは、主に牛馬の死体の処理や、川をさらったりする、清掃局の代わりのようなことをしていましたが、こちらには車善七という元締めがおり、たちとその業務を一手に取り仕切っていました。細かく言えば被差別民は他にも様々な限定的職業があったのですが、大きく分ければこの二つに整理することが出来ます。
関西の様子は知識がないのですが、東京の場合には大規模な組織として被差別民がまとめられており、もしかしたらその点が関西とは異なる点かも知れません。また、江戸の昔から東京は膨大な流入人口があり、対その周辺の一般人という対立構造が薄かったのかも知れません。少なくとも私の知る限り、朝鮮人や韓国人に対する差別意識はあっても、というものそのものが東京人の念頭に無かったという気がしています。職業柄、民の子を教えることはあった訳ですが、生徒たちは、誰も気にしないどころか、気が付きもしませんでした。
従って東京の場合には、放って置けば完全に消滅してしまう運命にある差別というものを、改めてほじくり返して意識させる必要がなかった、ということになるのではないでしょうか。しかし、いつも思うのですが、「○○差別反対!」と気勢を上げるのはいいのですが、その際には必ず、誰を差別しなければいいの?という疑問が伴うような気がしてならないのです。大阪の皆さんの考え方は分かりませんが、とりあえず東京では意識させる必要がないから問題に関する教育は行っていないということだと思います。私自身、の存在についてすらも、教室で教えようと思ったことが一度もないのです。
しかし、東京の場合、大阪とは多少事情が異なるかもしれません。たとえば浅草を含めて、そこから北は昔の言い方をすれば「エタ」の居住地でした。浅草に太鼓やのような、皮革を扱う業者が今でも見られるのはその名残です。足立区には弾左衛門と呼ばれるエタの元締めが住んでおり、江戸の皮革業を一手に支配下に置いていました。エタは農業をしませんので、荒川区や足立区には荒れ地が沢山残っていました。この弾左衛門は屋号のようなもので、代々受け継がれており、被差別階級ではありますが、正月に江戸城に登城し、将軍に挨拶することが許されていました。
一方と呼ばれる人たちは、主に牛馬の死体の処理や、川をさらったりする、清掃局の代わりのようなことをしていましたが、こちらには車善七という元締めがおり、たちとその業務を一手に取り仕切っていました。細かく言えば被差別民は他にも様々な限定的職業があったのですが、大きく分ければこの二つに整理することが出来ます。
関西の様子は知識がないのですが、東京の場合には大規模な組織として被差別民がまとめられており、もしかしたらその点が関西とは異なる点かも知れません。また、江戸の昔から東京は膨大な流入人口があり、対その周辺の一般人という対立構造が薄かったのかも知れません。少なくとも私の知る限り、朝鮮人や韓国人に対する差別意識はあっても、というものそのものが東京人の念頭に無かったという気がしています。職業柄、民の子を教えることはあった訳ですが、生徒たちは、誰も気にしないどころか、気が付きもしませんでした。
従って東京の場合には、放って置けば完全に消滅してしまう運命にある差別というものを、改めてほじくり返して意識させる必要がなかった、ということになるのではないでしょうか。しかし、いつも思うのですが、「○○差別反対!」と気勢を上げるのはいいのですが、その際には必ず、誰を差別しなければいいの?という疑問が伴うような気がしてならないのです。大阪の皆さんの考え方は分かりませんが、とりあえず東京では意識させる必要がないから問題に関する教育は行っていないということだと思います。私自身、の存在についてすらも、教室で教えようと思ったことが一度もないのです。











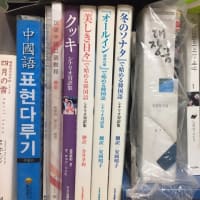
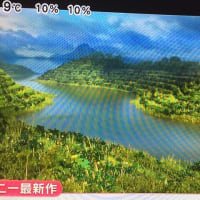
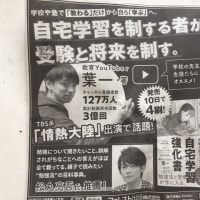
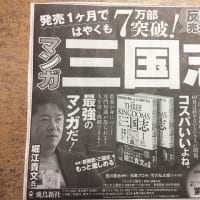



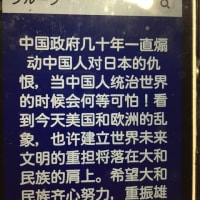


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます