今日の新聞を見たら、桐生選手のコーチに当たる土江良吉さんが、やはり典型的なダメコーチだったんですね。入学早々桐生選手の反発を買って、そっぽを向かれていたようです。その後も、土江氏が課したウエイト・トレーニングのせいで走る時の感覚が失われたと言われれば、重量物を引っ張ってダッシュする練習に代えたり(これはボルトがやっている練習です)、桐生選手がハンマー投げの室伏氏の下でトレーニングしたいと言えば、橋渡しをしてやったり・・・。土江氏には確固たる理念などない、行き当たりばったりの人だったとしか思えません。
短距離選手と言っても、いろいろあるのです。カール・ルイスや、10秒フラットの日本記録を長らく保持していた選手は、上体を鍛えるウエイト・トレーニングはしていませんでした。(カール・スイスは晩年衰えを感じ出したころ、下半身のウエイト・トレーニングを取り入れましたが。)東京オリンピックの200mで優勝したヘンリー・カー選手(私はこの時生で見ていました。)や、メキシコ・オリンピックの200mで優勝したトミー・スミス選手も、ウエイト・トレーニングをしたムキムキの体形ではありませんでした。
桐生選手は恐らくウエイト・トレーニングを必要とするタイプだと思われますが、筋トレ志向の強いトレーニングと短い距離のダッシュに偏り、長めの距離を伸び伸びと走る練習が不足すれば、堅苦しい走り方に陥ってしまうのは自然な成り行きだったのだと思います。残念ながら土江コーチには、新入学して来た桐生選手に対して、リオ・オリンピックを見据え、そこから逆算して効果的な練習を積み重ねていくという視点が全く欠けていたように思います。
一流のコーチというものは、選手から見たらカリスマでなければなりません。かつて瀬古選手の全盛期、日体大出身の長距離選手が数名、瀬古選手のコーチの下で学びたいとして、SB食品に入り、日体大閥から追放されたこともありました。それでも彼らはSB食品を選んだのです。
コーチがカリスマとなることに成功し、かつその指導方針が正しければ、選手は面白いように伸びて行きます。だから、運動部の顧問は面白くて止められないのです。
もっとも、ダメな人はどこまでいってもダメです。私が楽しく陸上部の指導をしていた頃、体育大出身、バレーボール専攻の男性体育教師が、女バレの選手たちがちっとも言う事を聞いてくれないとこぼしていました。女子の指導は壺にはまりさえすればベルトコンベアー式に驚異的に進んで行くものなのですが、指導者にカリスマ性が無いと、(カリスマ性が身に着くほどの努力をしないと、とも言えますが)、完全にそっぽを向かれてしまうので、どうにもならなくなってしまいます。
話がだんだん反れてきました。正直なところ、カリスマ性を身に着けることが出来ないと感じたら、その人はコーチ業を続けるべきではありません。誰より自分がみじめになってしまいます。最近耳にすることが多い、「学校における部活顧問の異常なまでの労働時間」というい問題も、顧問自身がカリスマになれないために、練習時間や内容についてキッパリと削減できないからだと私は考えています。カリスマ性を身に着け、短時間でも依然と変わらない成果を上げて見せれば、それで一件落着なのです。
短距離選手と言っても、いろいろあるのです。カール・ルイスや、10秒フラットの日本記録を長らく保持していた選手は、上体を鍛えるウエイト・トレーニングはしていませんでした。(カール・スイスは晩年衰えを感じ出したころ、下半身のウエイト・トレーニングを取り入れましたが。)東京オリンピックの200mで優勝したヘンリー・カー選手(私はこの時生で見ていました。)や、メキシコ・オリンピックの200mで優勝したトミー・スミス選手も、ウエイト・トレーニングをしたムキムキの体形ではありませんでした。
桐生選手は恐らくウエイト・トレーニングを必要とするタイプだと思われますが、筋トレ志向の強いトレーニングと短い距離のダッシュに偏り、長めの距離を伸び伸びと走る練習が不足すれば、堅苦しい走り方に陥ってしまうのは自然な成り行きだったのだと思います。残念ながら土江コーチには、新入学して来た桐生選手に対して、リオ・オリンピックを見据え、そこから逆算して効果的な練習を積み重ねていくという視点が全く欠けていたように思います。
一流のコーチというものは、選手から見たらカリスマでなければなりません。かつて瀬古選手の全盛期、日体大出身の長距離選手が数名、瀬古選手のコーチの下で学びたいとして、SB食品に入り、日体大閥から追放されたこともありました。それでも彼らはSB食品を選んだのです。
コーチがカリスマとなることに成功し、かつその指導方針が正しければ、選手は面白いように伸びて行きます。だから、運動部の顧問は面白くて止められないのです。
もっとも、ダメな人はどこまでいってもダメです。私が楽しく陸上部の指導をしていた頃、体育大出身、バレーボール専攻の男性体育教師が、女バレの選手たちがちっとも言う事を聞いてくれないとこぼしていました。女子の指導は壺にはまりさえすればベルトコンベアー式に驚異的に進んで行くものなのですが、指導者にカリスマ性が無いと、(カリスマ性が身に着くほどの努力をしないと、とも言えますが)、完全にそっぽを向かれてしまうので、どうにもならなくなってしまいます。
話がだんだん反れてきました。正直なところ、カリスマ性を身に着けることが出来ないと感じたら、その人はコーチ業を続けるべきではありません。誰より自分がみじめになってしまいます。最近耳にすることが多い、「学校における部活顧問の異常なまでの労働時間」というい問題も、顧問自身がカリスマになれないために、練習時間や内容についてキッパリと削減できないからだと私は考えています。カリスマ性を身に着け、短時間でも依然と変わらない成果を上げて見せれば、それで一件落着なのです。











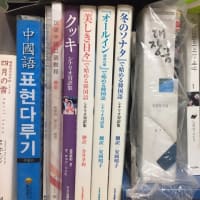
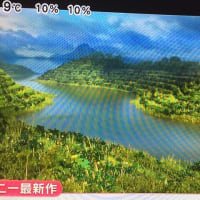
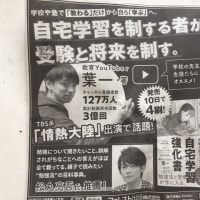
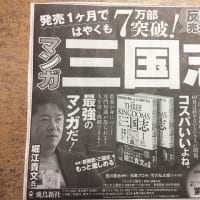



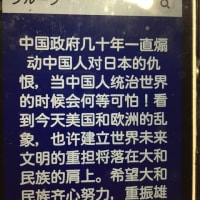


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます