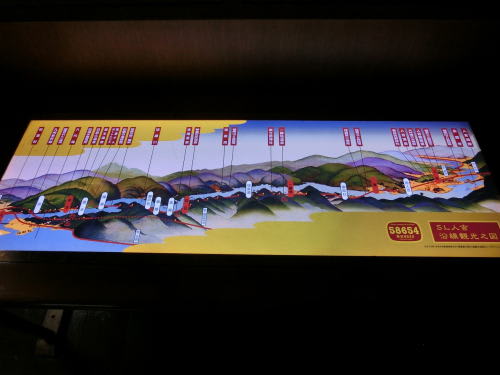久留米競輪場の入り口にある 「 ドイツ兵俘虜慰霊碑 」

慰霊碑の正面には 「 剣の上に1914下に1919 」 と刻まれている

右側面にはKOCHなどの名前が刻まれている
KOCH(コッホ),Heinrich(?-1914): 海軍膠州砲兵隊第1中隊・1等砲兵。
[鍛冶職人]。1914年9月28日ヴァルダーゼー高地で俘虜となったが、
負傷していたため久留米衛戍病院に送られた。
10月25日、重病になったコッホは、所長樫村弘道少佐、
所員の山本茂中尉に「故国の母親によろしく伝えて欲しい」との遺言を残し同日、同病院で死亡。
グラボウ(Grabow)中尉、ベスラー(Boe sler)少尉及び下士2名が病院に駆けつけた。
葬儀に際してはグラボウ中尉の別れの言葉、弔辞(樫村所長・通訳は山本中尉)、
久留米市代表の弔辞、仏教の僧侶が線香を焚く。
写真家達が葬儀の様子を撮影し、100人に及ぶ群衆が見つめていたという。ハンブルク出身。
EMOAN(エーモアン),Max(1887-1915): 第3海兵大隊第4中隊・予備副曹長。
1914年12月14日、収容されていた熊本西光寺を脱柵した科で、憲兵留置所で重謹慎2日の処罰を受けた。
1915年7月21日の晩に久留米で死亡、23日に久留米山川陸軍墓地に埋葬された。
バイエルンのトロスベルク(Trossberg)出身。
SIMON(ジーモン),Robert(?-1916): 第3海兵大隊第2中隊・伍長。
1916年3月19日久留米で死亡。
ザクセンのグリューン(Gru"n)出身。
BOESLER(ベスラー),Ernst(1880-1916): 第3海兵大隊第2中隊・後備陸軍歩兵少尉。
1914年9月28日、浮山で日本軍に包囲され、退却を求めて協議を申し出るが武装解除され俘虜となる。
グラーボウ(Grabow)中尉等60名が俘虜となった。
10月9日、日本への俘虜第一陣として門司に到着し、久留米俘虜収容所に送られた。
1916年4月18日、肺結核兼肋膜炎により久留米で死亡。
ドイッチュアイラウ(Deutscheylau)出身。
SANZ(ザンツ),Josef(?-1916): 巡洋艦皇后エリーザベト乗員(オランダ・ハンガリー)
日本へ親善訪問で来る途中、開戦に巻き込まれ、ドイツ軍に合流した・2等水兵。
1916年4月21日久留米で死亡。
ボヘミアのニームブルク(Niemburg)出身。
SCHLUND(シュルント),Alfred(?-1918): 海軍膠州砲兵隊第5中隊・後備1等機関兵曹。
1918年3月13日久留米で死亡。
ツヴィッカウ郡のシュタインプライス(Steinpleis)出身。

左側面にはPALUYなどの名前が刻まれている
PALUY(パオリー)Karl(1886-1918)第3海兵大隊第2中隊・軍曹。
1886年3月9日、商人の子としてザールブリュッケンに生まれた。
1914年9月28日、浮山周辺で日本軍に包囲され、グラーボウ中尉等60名が俘虜となったが、
その折りパオリー軍曹は、部下11名とともに逃れた。
1918年3月26日久留米で死亡。ザールブリュッケン出身。
WERNER(ヴェルナー),Alfred(?-1918): 第3海兵大隊機関銃隊・2等焚火兵。
1918年5月8日久留米で死亡。
シュレージエンのローンシュトッホ(Rohnstoch)出身。
KETTGEN(ケットゲン),Johann(?-1919): 第3海兵大隊機関銃隊・上等兵。
1919年3月2日、久留米で死亡。
ラインラントのホムベルク(Homberg)出身。
P‘O’NITZ(ペーニッツ),Erich(?-1919): 第3海兵大隊第4中隊・2等歩兵。
1919年8月2日肺結核により久留米で死亡。
西プロイセンのプロイスィッシュ=シュタルガルト(Proissisch-Stargard)出身。
BAUER(バウアー),Josef(?-1919): 第3海兵大隊第6中隊・補充後備兵。
(1919年11月7日久留米で死亡)
ドナウ河畔のヴェルト出身。

競輪場への道沿いから見た慰霊碑

慰霊碑の横にある説明板
久留米競輪場へは100回くらい訪れている。
競輪選手としてのデビュー戦も久留米だったし、
そして何より九州地区で行なわれる競輪学校の入学試験も久留米だった。
そんな久留米競輪場の入り口に 「 ドイツ兵俘虜慰霊碑 」 がある。
競輪場内にある参加選手の宿舎管理棟の入り口にもドイツ兵の墓らしきものがあったし、
「 ドイツ兵の俘虜収容所が3コーナーの裏手にあった 」 と聞いたことがあるが、
当時は気にも止めていなかったので写真すら撮っていない。
第一次大戦に参加した日本は中国青島のドイツ要塞を攻略し、
俘虜となった5000名近くが各地の収容所に分散収容された。
「ドイツ兵俘虜」といっても親善訪問で日本に来る途中、開戦に巻き込まれ、
青島でドイツ軍に合流したオーストリア・ハンガリーの巡洋艦「カイゼリン・エリーザベト」号の
乗組員も含まれるほか、現在のドイツ、オーストリアの他、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、
ハンガリー、ユーゴ、北イタリア出身者が含まれている。
戦闘に携わった18師団司令部もあったためか、久留米収容所はその中でも最も多く、
大正3年(1914)10月6日開始、大正9年(1920)3月12日閉鎖された。
11名の死者が久留米山川陸軍墓地に埋葬されたが、
大戦終結後の1920年1月16日、土葬されていたコッホとパウリ―以外の9名の遺骨は火葬されていて
ドイツ側委員に引渡された。
現地説明板によると、
第一次世界大戦に参戦した我が国は、中国青島のドイツの要塞を攻め落とし、
多数のドイツ兵を俘虜としました。
彼等を収容するため、大正3年(1914)10月から同9年(1920)3月まで、久留米に俘虜収容所が置かれました。
多い時には1319名を収容し、全国12ヵ所の収容所で最大でした。
5年余の収容期間に戦場での傷がもとで2名、病気などで9名、合わせて11名が亡くなりました。
これらの死者の追悼のため、俘虜達は帰国に際し、この慰霊塔を建立しました。
碑の正面には収容期間を示す西暦と剣が、両側面には死者の姓が記されます。
背面にはドイツ語で「運命の力により剣を奪われ、捕らわれの人となり黄泉の国に去った汝ら」、
台座には「故郷はるか遠く逝った同志たちの思い出のために」と鎮魂の詩が刻まれています。
俘虜は長い抑留生活の中でも、音楽会・作品展示会・スポーツ大会などを催し、
市民との交流を深め、近代の久留米の芸術・文化や市民生活に大きな影響を与えています。
またドイツの進んだ科学技術は後に久留米の基幹産業たるゴム産業の技術革新に大きな貢献をしています。
久留米の歴史にドイツ兵俘虜は大きな足跡を残すものです。
と書かれてある。