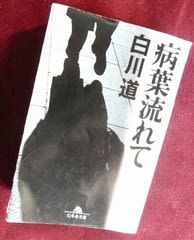←最初にクリックおねがいいたします。
←最初にクリックおねがいいたします。


上下二冊のずっしりとした本。
本の重さではなくて、密度の高い物語自体の内容の重さなのだ。
素晴らしい本に出会えた喜び、いつものように、トンボさんに見せてもらった本です。
今年は、日本が無条件降伏をして太平洋戦争が終結してから65年目に当たる。
我々団塊の世代は、戦争を知らない。運が良ければこのまま生涯戦争を知らずに済むという、文字通り有難い世代なのだ。
しかし 我々は決してこの日(8月15日)を忘れてはいけない。ということを痛切に感じる本だ。
作者の浅田次郎は毎日聞でこの本についてこう語っていた。
『戦後65年、帝国陸軍は悪という象徴的イメージでとらえられがち。しかし本当に兵隊は赤紙で引っ張られた庶民です。そういう軍隊のとらえ方が忘れられているんじゃないか。書きたかったのは戦争に巻き込まれた人間の小説です。』そして『僕は高度成長期に育った世代だからこそ、自分の知らない一番つらい時代を書くのは義務だと思う』とも・・・
1945年・8月15日。ポツダム宣言を受け入れた日本が負けて太平洋戦争は終わった。しかし、その3日後に、はるか北の、北海道よりもっと先の千島列島の果てで、アメリカではない敵・・・ソ連軍から侵攻を受ける形でもうひとつの戦争が始まった・・・。
というところから物語は始まるのだけど・・
私は何度も言うように 歴史に疎く、知らないことばかり、北方領土はこのようにしてソ連領になったのですよね。
で、物語は、東京の出版社で翻訳書の編集長をしている片岡は45歳。妻と息子とともに、江戸川橋のおしゃれなアパートメントに住み、いずれは家族そろってニューヨークに住むことを夢見ている。
そんな片岡に、ある日赤紙が届く。制限年齢のぎりぎりの今になって。誰がどう考えても、勝ち目のない戦争が終わろうとしている、ぎりぎりの時期になって。
そして、彼が向かった北千島の占守島には、開戦以来一度も戦ったことのない、まさに精鋭といっていい戦車部隊が手付かずで残っていたのだった。
そして、片岡と一緒に召集されたのは、伝説の英雄だが右手の指を無くし銃も撃てない富永熊男、軍医の教育を受けていない帝大医学部在学中の菊池忠彦。なぜ、この3人が招集されなければならなかったのか。
赤紙を受け取る者の悲しみと、赤紙を届ける側の痛み。夫の無事を祈り千人針に想いを託すしかない片岡の妻の久子の思い。疎開先で父の応召の知らせを聞き、たまらず東京へ向かう尋常小学校4年生の息子譲。出荷されるはずのない缶詰工場で働く10代の女子挺身隊員たち・・・。
召集された者たちを支える家族をはじめ、それぞれの立場のそれぞれの苦悩。国民の誰一人として自由に生きることを許されなかった戦争という時代を浅田ワールドはリアリティに書いている。
第二次世界大戦という戦争の悲劇は、「総力戦」となったことだ。既に敗戦を感じていたこのころの軍隊の正体は、軍人ではない一般市民だ。そうした個人が、赤紙一枚でたった1週間で軍隊に組み込まれていく過程。そして残された家族も、国民全てが個人の自由もすべて束縛され、戦力として組み込まれていくという状況。「総力戦」という名のもとに、どんな矛盾も押し通されてしまう状況下で、力強く生きようとする人々。
そしてこの『終わらざる夏』に登場する人たちの中で、誰ひとりとして戦争がいいことだと思っている人はいないのだ。
長い物語ながらこの小説の中で一番浅田次郎が言いたかったことは、片岡の息子譲と一緒に信州に疎開していた少女の静代が東京に逃げ出す時、助けてくれたやくざ者の言葉に表わされていたように思う。
『戦争に勝ったも負けたもない、そんなのはお国の理屈だ。人間には生き死にがあるだけだ。アメ公だってそれは同じだ、勝ったところで親兄弟がくたばったんじゃ うれしくもなんともあるめぇ。負けたところで悔しいはずはない。戦争に勝ちも負けもあるか、戦争をする奴は皆負けだ。大人たちは勝手に戦争をしちまったが、このざまをよく覚えておいて、お前らは二度と戦争をするんじゃねぇ、一生戦争をしないで畳の上で死ねるならその時が勝ちだ。その時本物の万歳をしろ!』
今まで、歴史の表舞台にあがったことのない、知られざる戦争。終戦後に開戦した、唯一の戦争と言われる占守島の闘い。
まさに今 旬の小説、重いテーマながら浅田次郎独特の人としての優しさと、力強さがたっぷりのこの本、
是非にも読んでください。
晴れ 32℃
 ←最初にクリックおねがいいたします。
←最初にクリックおねがいいたします。 読み始めは、「お!学園ものか、好きなのよね。面白そう・・・」それにこの主人公の蓮実聖司教諭はステキ、カッコいい。
読み始めは、「お!学園ものか、好きなのよね。面白そう・・・」それにこの主人公の蓮実聖司教諭はステキ、カッコいい。