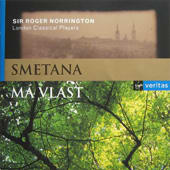 Bedřich Smetana: Má vlast
Virgin Veritas 07243 5 45301 2 8
演奏:London Classical Players, Sir Roger Norrington (Direction)
ベドリチ・スメタナ(Bedřich Smetana, 1824 - 1884)は、東ボヘミアのリトミシュルでビール醸造業の家に生まれた。当時のチェコは、オーストリア帝国の支配下にあり、その地方ではドイツ語が使われており、スメタナの名も当初はフリートリヒであった。4歳の頃からヴァイオリンとピアノを学び、1843年から1847年までプラハで音楽教師として働いた。1848年にフランスの2月革命をきっかけとしてヨーロッパ各地で起こった一連の革命運動の一環として、1848年6月にプラハで起こった「精霊降臨祭の暴動」にスメタナも加わり、その一方で同年、音楽学校を設立した。暴動はオーストリア帝国軍によって鎮圧され、ハプスブルク家の支配が続いた。1856年には政治的な理由でスウェーデンのイェーテボリに逃れ、その地で音楽活動を続けた。オーストリアの絶対主義的支配が終わった1861年にプラハに戻り、音楽活動と並行して民族運動にも加わった。スメタナは1865年から1869年まで、チェコのフィルハーモニー演奏会の指揮を行うなど、様々な音楽機関の指導者として活動した。1874年に重い病気にかかり、公職から退いたが、作曲活動は続けた。1884年になって、スメタナは梅毒に起因すると思われる精神障害を起こし、精神病院に収容され、5月12日に死亡した。
チェコの作曲家としては、 国外に於いてはアントニン・ドヴォルザーク(1841 - 1904)の方が良く知られているが、国内に於いてはチェコの民族楽派の創始者として、スメタナが高く評価されている。作品としては、オペラ、管弦楽作品、室内楽、ピアノ曲などがあるが、国際的にはオペラ「売られた花嫁(Prodaná nevěsta)」、管弦楽組曲「わが祖国(Má vlast)」、中でもその内の「ヴルタヴァ(Vltava)」で知られている。
「わが祖国」は、1872年に作曲されたオペラ「リブサ( Libusa)」の主題と密接な関連の下に作曲され、当初は「ヴィシェフラード( Vyšehrad)」、「 ヴルタヴァ( Vltava)」、「シャールカ( Šárka)」、「ボヘミアの森と野から( Z českých luhů a hájů)」の4曲からなっていたが、3年の間を挟んで、「ターボル( Tábor)」と「ブラニーク( Blaník)」の2曲が付け加えられ、「神話(ヴィシェフラードとシャールカ)」、「景観( ヴルタヴァとボヘミアの森と野)」、「歴史(ターボルとブラニーク)」の3つの主題6曲の組曲となった。「ヴィシェフラード」は、プラハの同名の城砦を主題としたもので、1874年9月終わりから11月18日にかけて作曲され、1875年3月14日にプラハで初演された。曲の冒頭でハープで奏される主題が非常に印象的である。「 ヴルタヴァ」は、同名の河の2つの源流から湧き出した流れが、やがて合流して森や野、村を通って流れ、やがてプラハのヴィシェフラード城の横を経て流れて行く様を描写した標題音楽の形式を取っている。スメタナは1874年11月20日から12月8日にかけて、全く耳の聞こえない状態で作曲し、1875年4月4日に初演された。ロンド形式のように繰り返し奏される主題は、合唱曲にもなっている。「シャールカ」は、同名の神話上の女武族の女王を主題とした曲で、1875年2月20日に完成したが、初演は1877年3月17日であった。「ボヘミアの森と野から」についてスメタナは、「故郷ボヘミアの景観を眺めた時の思いと感情を表現した」と述べている。1875年10月18日に完成し、1878年12月10日に初演された。「ターボル」は、15世紀前半ヤン・フスによって起こされた宗教改革の拠点となった処で、19世紀にはチェコの民族再生の中心地となった。この曲は、フス派のコラールに基づいている。この曲は1878年12月13日に完成し、1880年1月4日に初演された。「ブラニーク」は、チェコの伝説上の人物、聖ヴェンツェルに導かれた騎士団が眠っている山の名前で、騎士団はチェコが危機にある時に救ってくれると言い伝えられていた。この曲の終結部には、「ターボル」に使われたフス派のコラールと「ヴィシェフラード」の主題が現れ、組曲全体の結びとしている。この曲は、1879年3月9日に完成し、1880年1月4日に「ブラニーク」とともに初演された。組曲全曲としては、1882年11月5日に初演された。この組曲「わが祖国」は、今日でも毎年5月12日のスメタナの命日に演奏されている。
今回紹介するのは、ロンドン・クラシカル・プレイヤーズの演奏、サー・ロジャー・ノリントンの指揮によるヴァージン・レーベルのCDである。ノリントンの指揮による他の19世紀のオーケストラ曲と同様、モダン・オーケストラの「伝統的」演奏にとらわれず、オリジナルの楽譜に立ち戻り、楽器、奏者の人数、配置はもちろんのこと、奏法についても詳細に調査した上で演奏されている。添付の解説には、オーケストラの楽器ごとの人数は記されていないが、弦楽器は合計46人で、当時のヴィーン・フィルハーモニーの編成をもとに決められた。弦楽器はもちろんガット弦が張られており、管楽器、打楽器も当時のものが使われている。奏法に関しては、1920年以前にはそうであったように、ヴィヴラートを極力排している。曲のオーケストレーションによるところもあるのかも知れないが、 その響きはくすんだものである。
なおこのCDでは、組曲に先立って、フランティシェク・シュクロウ(František Jan Škroup, 1801 - 1862)の作曲になる現在のチェコ共和国の国歌が演奏される。
このCDは、現在もEMIのカタログに掲載されているので、容易に入手可能である。
発売元:EMI Classics
スメタナの生涯に関しては、 ドイツ語版ウィキペディアの”Bedřich Smetana”、「わが祖国」に関しては、同じくドイツ語版ウィキペディアの”Mein Vaterland”を参考にした。

クラシック音楽鑑賞をテーマとするブログを、ランキング形式で紹介するサイト。
興味ある人はこのアイコンをクリックしてください。
| Trackback ( 0 )
|
|
御紹介により愛聴盤がまた一枚増えることとなりました。心より感謝致します。
チェコの国歌が今回紹介したCDに入っていることは、書き漏らしましたので、早速追加しました。