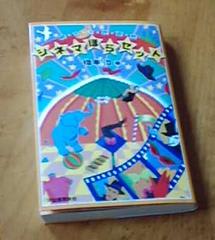今日は、再来週のピアノ発表会のリハーサルの手伝い。
出番が済めば見てるだけで、テレビの3倍くらいスローテンポのドラえもんとか、たどたどしい「びっくりシンフォニー」のお子様メドレーを聞きながらリラダンの「未来のイヴ」読んでいました。
これは、恋した女性の持つ高雅な姿と裏腹の魂の卑俗に悩む青年貴族のために、発明家が恋人そっくりの人造人間を作る話です。結局のところ皮肉な結末になりますが。
今日は、逃げ場のない状況で1冊しか持たずに、その人造人間が作られるまでのところを丹念に読もうという計画でした。古典うんちくオンパレードで発明家を紹介する部分と、人造人間に姿を写した女性のどこが気に入らないか、を紹介する部分。
案の定眠くなった。やっぱりここを味わうのは私には無理みたい。というわけで後半は次回へ。
出番が済めば見てるだけで、テレビの3倍くらいスローテンポのドラえもんとか、たどたどしい「びっくりシンフォニー」のお子様メドレーを聞きながらリラダンの「未来のイヴ」読んでいました。
これは、恋した女性の持つ高雅な姿と裏腹の魂の卑俗に悩む青年貴族のために、発明家が恋人そっくりの人造人間を作る話です。結局のところ皮肉な結末になりますが。
今日は、逃げ場のない状況で1冊しか持たずに、その人造人間が作られるまでのところを丹念に読もうという計画でした。古典うんちくオンパレードで発明家を紹介する部分と、人造人間に姿を写した女性のどこが気に入らないか、を紹介する部分。
案の定眠くなった。やっぱりここを味わうのは私には無理みたい。というわけで後半は次回へ。