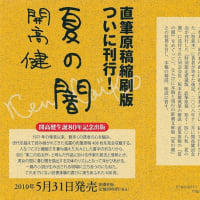およそ2年ぶりに中島敦(1909~1942年)の「李陵」を読み返したので、書評を書いておきたくなった。つつみ隠さずにいえば、読みながらわたしは、滂沱たる涙にかきくれ、幾度か本を擱いて、それを拭わねばならなかった 。
。
新潮文庫「李陵・山月記」には「李陵」「山月記」「弟子」「名人伝」の4編が収録されていて、小さな活字の本ではあったが、長らくこれが手許にあった。しかし、数年前に武田泰淳の「司馬遷」を読む機会があって、その書に深く胸を衝かれた。そこで「中島敦の狼疾について」を収めた角川文庫を、あらためて買いなおしたのであったが、このたび「李陵」「名人伝」を読み返すにあたって、はじめて通読することができた
ほかの人は知らず、わたしは本を読みながら「滂沱たる涙にかきくれる」ということなど、そうめったにない。
「李陵」の感動のなかで思い出したのは、司馬遼太郎さんの「草原の記」であった。似ているのは、舞台となったモンゴルの荒漠たる空間だけで、時代も作品の文体もまったく違うのだが、「感動の質」はひどくよくにているなあ~、と思ったのであった。「草原の記」の終わりで、わたしはただ無性に涙が流れてとまらなかった。
中島敦はよく知られているように、漢学者の名門の家系に生まれている。父が妻を三度取り替えたことから、思春期の彼は父を憎むようになる。またかなりの小男で、分厚いメガネをかけ、幼いころから健康にめぐまれなかったようだ。
<(自分は)失望しないために、初めから希望をもつまいと決心するようになった。落胆しないために初めから欲望をもたず、成功しないであろうとの予見から、てんで努力しようとせず、辱めを受けたり気まずい思いをしたくないために人中に出まいとし、自分が頼まれた場合の困惑を誇大して類推しては、自分から他人にものを依頼することが全然できなくなってしまった。外へ向かって展らかれた器官を凡て閉じ、まるで堀上げられた冬の球根類のようになろうとした。それに触れると、どのような外からの愛情も、途端に冷たい氷滴となって凍りつくような石となろうと私は思った。>(かめれおん日記)
これが彼の青春の自画像であったとみて大過あるまい。
こういった男が「李陵」という、鬼気迫るほどの峻烈な人間ドラマを生み出したのであった。喘息の発作で惜しまれつつ世を去ったのは、昭和19年12月、わが国が絶望的な太平洋戦争に突入して、1年後であった。これは中島の遺稿である。
「山月記」を読むものは、彼がどのような「狼疾」に苦しんでいたか、およそ想像がつく。李徴の苦しみを彼も共有していたのである。いま、わたしには、それがよく見える気がする。
彼は父を憎み、狼疾をかかえた「我」を憎んだのである。
さまざまないきさつがあったにせよ、ついに匈奴に降伏した男、李陵の生涯で、もっとも感動的なシーン、・・・それはバイカル湖のほとりに蟄居する蘇武との出会いと交流を描いたあたりである。
中島は、こう書く。
<蘇武は義人、自分は売国奴と、それほどハッキリ考えはしないけれども、森と野と水との沈黙によって多年の間鍛え上げられた蘇武の厳しさの前には己の行為に対する唯一の弁明であった今までのわが苦悩のごときは一溜《ひとたま》りもなく圧倒されるのを感じないわけにいかない。>
<飢餓も寒苦も孤独の苦しみも、祖国の冷淡も、己の苦節がついに何人にも知られないだろうというほとんど確定的な事実も、この男にとって、平生の節義を改めなければならぬほどのやむを得ぬ事情ではないのだ。
蘇武の存在は彼にとって、崇高な訓誡でもあり、いらだたしい悪夢でもあった。>
やがて、漢の武帝逝去の報がもたらされる。
<李陵は武帝の崩じたのを知った。北海の滸《ほとり》に到ってこのことを告げたとき、蘇武《そぶ》は南に向かって号哭した。慟哭数日、ついに血を嘔くに至った。・・・今目の前に蘇武の純粋な痛哭を見ているうちに、以前にはただ蘇武の強烈な意地とのみ見えたものの底に、実は、譬《たと》えようもなく清洌な純粋な漢の国土への愛情(それは義とか節とかいう外から押しつけられたものではなく、抑えようとして抑えられぬ、こんこんと常に湧出る最も親身な自然な愛情)が湛《たた》えられていることを、李陵ははじめて発見した。
李陵は己《おのれ》と友とを隔てる根本的なものにぶつかっていやでも己自身に対する暗い懐疑に追いやられざるをえないのである。>
中島敦はおのれの心をとざす闇を「李陵」に封じ込めた。主人公は司馬遷でも、蘇武でもない、モンゴルの奥地についに消息を絶ってしまった李陵その人である。
武帝を父に見立て、己を李陵に見立てる。司馬遷はあまりに偉大であるが、死を目前にひかえた彼には「史記」を叙する時間が許されてはいなかったのである。
中島敦は「己自身に対する暗い懐疑」をかかえたまま、死の床につく。
いまのわたしにはそう見える。だからこそ、われわれは、「李陵」に、かくも激しく胸撲たれるのではないか?
なぜなら、これが「遺稿」だかである。
国家も父も、彼にとっては相克の対象であった。これを否定しては生きていけない、卑小な自分をはるかに超えた巨大なもの、・・・。
「述ベテ作ラズ」とは、司馬遷の姿勢であり、また「明治終焉」以降の森鴎外の手法であった。大学院で鴎外の研究に携わった中島もまたこの手法を踏襲する
国家とは、いったい何者であるか?
プラトンの「国家」は、ニーチェ「ツァラトウストラ」やゲーテの「ファウスト」とならんで、彼の愛読書であったようだ。蘇武の出処進退と対比させながら、彼は李陵の「国家」に対する愛憎の深淵を、抑制の効いた筆致で彫りあげていく。残酷きわまりない三者の運命の物語なのだが、その三者の像は、地面からたったいま掘り起こされたばかりのギリシャ彫刻のように、厳しく美しい、・・・といった印象をうける
中島は惜しくも夭折してしまったが、この問いを敗戦後になって、別な角度から照射して見せた小説家がふたりいる。「司馬遷」を書いた武田泰淳、「俘虜記」「出征」「野火」を書いた大岡昇平である。
彼らは私小説という手法をとらなかった。あのような「私」つまり己など、信頼するに足らぬ、と考えたからである。中島は私情でしかない「父」への屈折した複雑な思いを、「国家」に投影することで、「李陵」を書き得たのである。わたしには武田や大岡は、中島敦が倒れた場所から出発していったように見えるが、間違っているだろうか?
死を間近にひかえてなお、中島敦の胸底に渦巻いていた「己自身に対する暗い懐疑」。
文庫本でざっと計算して、400字詰め換算でわずか94枚。中島の問いかけが、民族の興亡と、そこに浮沈する人間の巨大な舞台を必要としたことは、凄いというほかない。人は何のために、何によって生きるのか?
李陵、蘇武、そして司馬遷。彼らはよくたたかい、己の運命を全うした三人の戦士であった。そしてまた、中島敦も・・・
角川文庫には、あの有名な司馬遷の「任少卿に報ずる書」の書き下し文が併載されている。
本書とあわせて読むと「史記」の周囲を生涯に渡ってさまよった中島敦の、いわば「気配」のようなものが、生々しくつたわってくる。
中島敦「李陵・山月記」角川文庫>☆☆☆☆☆
 。
。新潮文庫「李陵・山月記」には「李陵」「山月記」「弟子」「名人伝」の4編が収録されていて、小さな活字の本ではあったが、長らくこれが手許にあった。しかし、数年前に武田泰淳の「司馬遷」を読む機会があって、その書に深く胸を衝かれた。そこで「中島敦の狼疾について」を収めた角川文庫を、あらためて買いなおしたのであったが、このたび「李陵」「名人伝」を読み返すにあたって、はじめて通読することができた

ほかの人は知らず、わたしは本を読みながら「滂沱たる涙にかきくれる」ということなど、そうめったにない。
「李陵」の感動のなかで思い出したのは、司馬遼太郎さんの「草原の記」であった。似ているのは、舞台となったモンゴルの荒漠たる空間だけで、時代も作品の文体もまったく違うのだが、「感動の質」はひどくよくにているなあ~、と思ったのであった。「草原の記」の終わりで、わたしはただ無性に涙が流れてとまらなかった。
中島敦はよく知られているように、漢学者の名門の家系に生まれている。父が妻を三度取り替えたことから、思春期の彼は父を憎むようになる。またかなりの小男で、分厚いメガネをかけ、幼いころから健康にめぐまれなかったようだ。
<(自分は)失望しないために、初めから希望をもつまいと決心するようになった。落胆しないために初めから欲望をもたず、成功しないであろうとの予見から、てんで努力しようとせず、辱めを受けたり気まずい思いをしたくないために人中に出まいとし、自分が頼まれた場合の困惑を誇大して類推しては、自分から他人にものを依頼することが全然できなくなってしまった。外へ向かって展らかれた器官を凡て閉じ、まるで堀上げられた冬の球根類のようになろうとした。それに触れると、どのような外からの愛情も、途端に冷たい氷滴となって凍りつくような石となろうと私は思った。>(かめれおん日記)
これが彼の青春の自画像であったとみて大過あるまい。
こういった男が「李陵」という、鬼気迫るほどの峻烈な人間ドラマを生み出したのであった。喘息の発作で惜しまれつつ世を去ったのは、昭和19年12月、わが国が絶望的な太平洋戦争に突入して、1年後であった。これは中島の遺稿である。
「山月記」を読むものは、彼がどのような「狼疾」に苦しんでいたか、およそ想像がつく。李徴の苦しみを彼も共有していたのである。いま、わたしには、それがよく見える気がする。
彼は父を憎み、狼疾をかかえた「我」を憎んだのである。
さまざまないきさつがあったにせよ、ついに匈奴に降伏した男、李陵の生涯で、もっとも感動的なシーン、・・・それはバイカル湖のほとりに蟄居する蘇武との出会いと交流を描いたあたりである。
中島は、こう書く。
<蘇武は義人、自分は売国奴と、それほどハッキリ考えはしないけれども、森と野と水との沈黙によって多年の間鍛え上げられた蘇武の厳しさの前には己の行為に対する唯一の弁明であった今までのわが苦悩のごときは一溜《ひとたま》りもなく圧倒されるのを感じないわけにいかない。>
<飢餓も寒苦も孤独の苦しみも、祖国の冷淡も、己の苦節がついに何人にも知られないだろうというほとんど確定的な事実も、この男にとって、平生の節義を改めなければならぬほどのやむを得ぬ事情ではないのだ。
蘇武の存在は彼にとって、崇高な訓誡でもあり、いらだたしい悪夢でもあった。>
やがて、漢の武帝逝去の報がもたらされる。
<李陵は武帝の崩じたのを知った。北海の滸《ほとり》に到ってこのことを告げたとき、蘇武《そぶ》は南に向かって号哭した。慟哭数日、ついに血を嘔くに至った。・・・今目の前に蘇武の純粋な痛哭を見ているうちに、以前にはただ蘇武の強烈な意地とのみ見えたものの底に、実は、譬《たと》えようもなく清洌な純粋な漢の国土への愛情(それは義とか節とかいう外から押しつけられたものではなく、抑えようとして抑えられぬ、こんこんと常に湧出る最も親身な自然な愛情)が湛《たた》えられていることを、李陵ははじめて発見した。
李陵は己《おのれ》と友とを隔てる根本的なものにぶつかっていやでも己自身に対する暗い懐疑に追いやられざるをえないのである。>
中島敦はおのれの心をとざす闇を「李陵」に封じ込めた。主人公は司馬遷でも、蘇武でもない、モンゴルの奥地についに消息を絶ってしまった李陵その人である。
武帝を父に見立て、己を李陵に見立てる。司馬遷はあまりに偉大であるが、死を目前にひかえた彼には「史記」を叙する時間が許されてはいなかったのである。
中島敦は「己自身に対する暗い懐疑」をかかえたまま、死の床につく。
いまのわたしにはそう見える。だからこそ、われわれは、「李陵」に、かくも激しく胸撲たれるのではないか?
なぜなら、これが「遺稿」だかである。
国家も父も、彼にとっては相克の対象であった。これを否定しては生きていけない、卑小な自分をはるかに超えた巨大なもの、・・・。
「述ベテ作ラズ」とは、司馬遷の姿勢であり、また「明治終焉」以降の森鴎外の手法であった。大学院で鴎外の研究に携わった中島もまたこの手法を踏襲する

国家とは、いったい何者であるか?
プラトンの「国家」は、ニーチェ「ツァラトウストラ」やゲーテの「ファウスト」とならんで、彼の愛読書であったようだ。蘇武の出処進退と対比させながら、彼は李陵の「国家」に対する愛憎の深淵を、抑制の効いた筆致で彫りあげていく。残酷きわまりない三者の運命の物語なのだが、その三者の像は、地面からたったいま掘り起こされたばかりのギリシャ彫刻のように、厳しく美しい、・・・といった印象をうける

中島は惜しくも夭折してしまったが、この問いを敗戦後になって、別な角度から照射して見せた小説家がふたりいる。「司馬遷」を書いた武田泰淳、「俘虜記」「出征」「野火」を書いた大岡昇平である。
彼らは私小説という手法をとらなかった。あのような「私」つまり己など、信頼するに足らぬ、と考えたからである。中島は私情でしかない「父」への屈折した複雑な思いを、「国家」に投影することで、「李陵」を書き得たのである。わたしには武田や大岡は、中島敦が倒れた場所から出発していったように見えるが、間違っているだろうか?
死を間近にひかえてなお、中島敦の胸底に渦巻いていた「己自身に対する暗い懐疑」。
文庫本でざっと計算して、400字詰め換算でわずか94枚。中島の問いかけが、民族の興亡と、そこに浮沈する人間の巨大な舞台を必要としたことは、凄いというほかない。人は何のために、何によって生きるのか?
李陵、蘇武、そして司馬遷。彼らはよくたたかい、己の運命を全うした三人の戦士であった。そしてまた、中島敦も・・・

角川文庫には、あの有名な司馬遷の「任少卿に報ずる書」の書き下し文が併載されている。
本書とあわせて読むと「史記」の周囲を生涯に渡ってさまよった中島敦の、いわば「気配」のようなものが、生々しくつたわってくる。
中島敦「李陵・山月記」角川文庫>☆☆☆☆☆