
「レ・フレール」 のコンサートを聞きに行った日、会場となったまつもと市民芸術館2階シアターパークに設置された、
今月5日に亡くなった 歌舞伎俳優・中村勘三郎さんの遺影に、献花と記帳をさせていただきました。
同会場にて、献花、記帳を期間を決めずに当分の間受け付けている、というのは新聞やニュース等で知っていたので、もしかしたら16日に行くときに、まだあるかもしれない、と思いながら出かけて行ったのだが、果たして、ありました。
開演前は時間がなかったので、終演後にさせていただきましたが、コンサートの前にも後にも、献花や記帳に、その日コンサートに来た人が主だと思いますが、人の波が途切れることはありませんでした。
まず、手前の記帳台にて記帳したのち、左手脇に設置されたお花を置く台から、白いカーネーションを一本いただいて、遺影の前に設置された献花台に置きます。
壁に貼られた、中村座の定式(じょうしき)幕に飾られたお写真では、勘三郎さんが、訪れる人たちに 「ようこそいらっしゃいました」 とでも言いたげな、満面の笑顔で語りかけてくれています。
静かに手を合わせ、周りに飾られたパネルなどを見ていると、コンサートの幸せ気分もしぼんでしまうほどに、なんだか悲しい気持ちになってきました。
本当に、松本で、平成中村座のお芝居を見ておきたかった。
そして、なんで、こんなに早くお亡くなりになってしまったのかなぁ、という寂しい気持ち。
中村勘三郎さんが、初めて芝居で松本を訪れたのは、2008年7月5日~13日まで、まつもと市民芸術館で全12公演を行った 信州まつもと大歌舞伎・平成中村座 『夏祭浪花鑑(なつまつりなにわはなかがみ)』 の上演のとき。
この年の6月、東京のシアターコクーン(コクーン歌舞伎の名称)を皮切りに、ドイツ、ルーマニアで公演を行った後、その、ツアーの締めくくりとして松本にやってきたもので、
最大の呼び物は、この歌舞伎の上演に先立って 「市民サポーター」(公演を応援し、スタッフとして手伝うメンバー) を募り、300人以上が参加したこと。
また、松本独自の取り組みとして、市民キャストを起用。100人を超えるメンバーが、夏祭りのシーンに登場、にぎやかに踊りまくって舞台を盛り上げました。
舞台がはねた後には、市街地を通って松本城まで向かう、役者たちの登城行列(お練り)を行い、人力車に乗った、勘三郎さんや当劇場芸術監督の串田和美さんらを一目見たいと集まった市民で大変なにぎわいを見せたそうです。
先日も書いたが、私はまつもと市民芸術館のDM会員なので、この時の公演のことはよく覚えていて、
今度、当劇場で中村勘三郎さん率いる 「平成中村座」 のお芝居を上演すること、
そのための市民サポーターや市民キャストを募集すること、なども知った。
芸術館便りには、串田館長と勘三郎さんとの、この公演に関する意気込みなどを語った対談も載っていたと思う。
このとき、市民キャストはともかく、市民サポーターには、ちょっと心惹かれるものはあったのだが、
夜遅くまで仕事があること、土日にも休めないこと、また、遠方であることなどから、まあ、参加は無理だわな、とすぐに思った。
何より、この頃は、例の体調を崩している真っ最中の、一番サイアクだった年(2007~8年)なので、生きていくのに精いっぱい、公演案内やサポーター、キャスト募集のチラシはさらりと目を通し、串田・勘三郎対談など難しくて長いものを読むのはしんどくて、多分読んでない。( それでもチラシや対談集は、多分、取っておいてあるはずだが、整理が悪いため、現段階では行方不明・笑 )
つまり、その時の私は実のところ、あんなに大好きだった芝居などの公演にでさえ、心を配るという余裕がなかった。
何より、どこかへ出かけて行ったり、何かをする意欲もなかったし、それ以上に、人と交わりたくなかった。
それでも、串田さんと勘三郎さんのやることなので、心惹かれるものと、体調の悪さに無理だろうという、両方の気持ちの間で揺れていた。
次に 「信州まつもと大歌舞伎」 が上演されたのは、2年後の2010年。演目は 『佐倉義民傳(さくらぎみんでん)』。
このときも まつもと市民芸術館で、7月2日~8日まで、全11公演が行われ、前回同様70人もの市民キャストが参加、300人以上の市民サポーターが登録されたといいます。
また、前回と同じような、終演後の お練りも行われました。
このころの私はというと、2009年の正月ころから体調が少しずつ良くなってきていて、秋には薬と病院通いからおさらばできたので、嬉しくって、
2010年はまさにゼッコーチョー!!、 2年目となった 「スポット」 の取材に飛び回ったり、気持ちの赴くままに毎月のように東京に行ったりなんかして、精力的に活動 & 遊びまわっていたため、なんか今となっては、色んな事をあまりよく覚えていない。
 (逆ハイとでもいおうか・(^^;)ゞ)
(逆ハイとでもいおうか・(^^;)ゞ)一つには、地元で行われる公演より、やっぱ東京での公演が一番よ、などと思っていた節も、無きにしも非ず。( しーません
 )
)なので、二度目の 「信州まつもと大歌舞伎」 も、送られてきたDMで目にするも、あまり気に留めていなかったやも知れぬ。
開けた2011年1月、中村勘三郎さんは、体調不良のために2月の舞台を降板、
2月に入ってから、「突発性難聴」 であることを明かし、5末までの休養を発表する。
約半年間の休養ののち、勘三郎が 「心のふるさと」 として、全国に先駆けて 「復帰公演地」 として選んでくれたのが、松本であった。
※ 7月23、24日と、まつもと市民芸術館で行われた 「中村勘三郎特別公演」 と銘打たれたもので、勘三郎は 『身替座禅』 にフル出演。
終演後の舞台挨拶では、「まだ完璧ではないですが、これからもよろしくお願いします。」 と号泣したという。
そのまま退場する予定であったらしいが、約1400人もの観客が 「中村屋!」 「お帰りなさい」 などと叫びながらスタンディングオベーション。割れんばかりの拍手に、1、2歩前に出ると、
「本当にありがとうございます。こんなによくしてくださって…」と、両手で顔を覆って号泣。
「本当に完璧ではないんですが…こんな病気なので長くかかるとは思います…。でも、応援してくださってありがとう。これからもよろしくお願いいたします」と声を絞り出し、正座して深々と頭を下げた。
それに先立ち、今回の復帰公演にむけて、町を挙げて応援の意を表した松本は、
JR松本駅構内に 「おかえりなさい、勘三郎さん」の横断幕を用意。
楽屋には、400人以上の市民が寄せ書きした1・5メートル四方の布12枚を届けた。
22日に劇場入りした勘三郎は、壁に貼られた激励メッセージを目にして、涙を流したという逸話もある。 ※
( 以上、「スポニチ・アネックス」 より、一部を掲載、または抜粋 )
翌、2012年の初夏。
2011年11月から2012年5月にかけ、長男:中村勘太郎の六代目勘九郎襲名披露舞台を含む、7か月にも及ぶ 「平成中村座ロングラン公演」 を成功させ、まだ病気が完治していないうちに走り出し、正直、7か月も持つかと思ったがやり遂げることができたと、打ち上げの席で嬉しそうに語った勘三郎。
数日後の5月30日は、自身の57歳の誕生日だったので、本人いわく 「バースデー・ケーキにダイビングしたりしてどんちゃん騒ぎをした」、翌々日の6月1日に受けた健康診断で、初期の食道癌と判明。まさに青天の霹靂だったことと思うが、初期だということで覚悟を決め、年内の活動を停止して療養に専念することを、6月18日に発表した。
しかし、その後リンパ節へ転移していることがわかったため、手術が延期されることとなり、事態は、急激に暗転する。
いったん自宅に戻り、抗がん剤治療を受けながら、手術するか否かをずいぶんと悩んだらしい。
このあたりのことは、12月7日に早くも放送された、フジテレビ 金曜プレステージ・緊急特別追悼番組 『さようなら勘三郎さん 独占密着…最期の日々』 に詳しいが、
初期の食道がんと判明されてから、2004年からの同テレビ「番付記者」 を自宅に呼び、事実を話し、自身の姿を撮っておいてくれ、と頼み込んで、偽らざる胸中を語る姿には、胸を打つ。
なんという役者魂、そして生き様であろうか。
不安もあったであろうに、そのようなことを微塵も見せず、淡々と心中を語り、ときに冗談で笑わせたり、回りを気遣うような姿すら見せる。
おりしも、信州・まつもと大歌舞伎 『天日坊(てんにちぼう)』 が、その年の7月12日から18日までの予定(全9回公演・まつもと市民芸術館)で、長男中村官九郎主演、弟の七之助や中村獅童らの出演で、上演されていた。 ( この公演のことももちろん知っていたが、私は7/28のアルフィー夏イベにかけていたので、見に行けなかった。)
千秋楽となった7月18日、舞台クライマックスにて、木曽義仲の役で、ごく一部の関係者以外のだれにも(息子たち出演者さえも)内緒で、突然舞台に立った勘三郎は、カーテンコールで、息子の官九郎に呼ばれるままに姿を現した。
そして、思いがけないサプライズに湧き上がる観客の 「勘三郎さん、がんばって。」 という声援に応えて「必ずや松本(の舞台)に帰って来てみせます」と挨拶した。
盛り上がった出演者たちが、客席に降りてサービスする姿を、まるでいとおしいものを見るかのように、舞台上で感慨深げに見つめていた勘三郎の胸の中には、どんな思いが去来していたのだろうか。
これが、歌舞伎役者中村勘三郎の、事実上最後の舞台出演であり、公の場での最後の姿となった。
7月27日に食道がん摘出手術を実施することになったその3日前、親しい仲間を集めて、「ノリアキ(勘三郎の本名)癌晴れコンペ」 という名のゴルフコンぺを行い、見事準優勝をさらい、元気ぶりをアピールして心配をかけまいとする心くばりを見せた (一方では、もしものことを考え、親しい仲間と楽しい時を過ごしておきたかったと取れなくもないが) というのも、いかにも勘三郎らしいエピソードであるが、
そのときに、フジテレビ記者を呼んで語った、実質最後となったインタビューでは、
「(親友の)笹野高史らが呼び掛けて、玉三郎さんのファンとか、そんな人たちまでが40何人かで、中村屋の定式幕の色で、千羽鶴を折ってくれたんだよ。嬉しくて、病室に持っていこうと思ってるんだけど、
松本の人たちなんて、こんなに(と、手で3、40㎝くらいの高さを示して) 葉書かいてくれてさぁ、全部読んだけど、泣けたよ。」
と、嬉しそうに、話してくれた。
一時は病棟内を歩行できるまでに回復したというが、肺炎を起こし、4か月の闘病ののち、12月5日、ついに、本人いわく 「癌を晴らす」 ことなく、旅立たれてしまった。
本当に残念であるが、2008年以来、舞台公演を通してたびたび訪れ、市民との触れ合いに心を許してくれた勘三郎さんは、松本が大のお気に入りだったようで、温泉や酒などを楽しみに、プライベートでも時折訪れるほどであったといい、
2011年の復帰公演として松本の地を選んでくれたり、また、事実上最後となった舞台も松本であったというのは、大変感慨深く、地元民としては、とても誇りに思える話だと思う。
願わくば、中村勘三郎を感激させてやまなかった松本市民たち (サポーターや観劇者) の、その、一員の中に、自分も入れていたらなぁー、と、今となってはかなわぬ思いが、ほんの少し、胸に去来するのみである。
情に厚く、人間味あふれるチャーミングな勘三郎さんは、お弟子さんやスタッフなどの心配りにも長けていて、周囲の誰からも愛されたという。
中村勘三郎さん、松本を愛してくれてありがとう。
改めて、心より、ご冥福をお祈りいたします。
《 新聞記事より、地元関係分を中心として 》

12月6日付 『市民タイムス』 より。
写真左:最後の舞台となった 『天日坊』 にて、挨拶をする勘三郎さん。
写真右:舞台写真は、初めての信州まつもと大歌舞伎 2008年7月8日 『夏祭浪花鑑』 でのもの。
ほか3枚は、左上から2010年の、「お練り」、左下「串田和美館長と千秋楽でのあいさつ」、右下「笹野高史さんと松本市民手打ちのそばを食べる」、などの写真。

12月6日 『朝日新聞』 長野・中部版 より。
写真上:2010年お練りと、下は最後となった舞台。

『朝日新聞』 12月11日付 「論説」
勘三郎さんと親交の深かった、まつもと市民芸術館館長・芸術監督で、演出家・劇作家 串田和美さんの 「芝居の神様の子ども-中村勘三郎さんを悼む-」 と、
下は、同じ年で20年来の親友という 演出家・劇作家 野田秀樹 さんの寄せたコメント 「ただの損失ではすまない」。
野田は毎日のように勘三郎を見舞い、最後まで付き添った。一説によると、勘三郎は、「このたびの闘病の様子を芝居にしてほしい」 と野田に頼み、その他にも、来年以降の新作の歌舞伎台本を野田に依頼して、病院でもその構想を熱く語り、役者復帰のためのリハビリに精を出していたという。
お二人の舞台をつい最近見ただけに、自分の好きな人たちが繋がっているということに、何か感慨深いものを覚える私。

まつもと市民芸術館に設けられた 「献花台」 の左わきには、「信州まつもと大歌舞伎」 の公演ポスター。

右わきには、「天日坊」 などのはっぴや、勘三郎さん思い出の、舞台やお練り、市民との触れ合いなどの写真パネルが飾られており、献花に訪れた皆さんが、食い入るように見つめていらっしゃいました。
( ※ 文中、特に注意書きのない部分も、登場するテレビ番組、上記(他にスポーツニッポン)新聞記事、等を参考にさせていただきました。 )












 )
)






















 です。
です。

 、 流行っていたことは知っていたが見てなかった 『上海バンスキング』 のLP。(歌、吉田日出子、演奏、自由劇場団員)
、 流行っていたことは知っていたが見てなかった 『上海バンスキング』 のLP。(歌、吉田日出子、演奏、自由劇場団員)
 昔から演劇界の大物であったことはよく覚えていたので、大変感激したが
昔から演劇界の大物であったことはよく覚えていたので、大変感激したが 





 、 エンディングでは不覚にも号泣しそうになった。
、 エンディングでは不覚にも号泣しそうになった。 




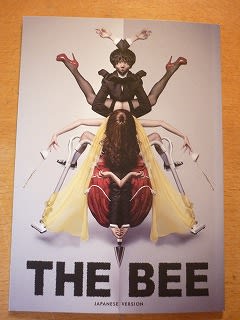












 信州では今、「がんばろう日本!信州元気宣言」を発表!
信州では今、「がんばろう日本!信州元気宣言」を発表!  )
)






 コーナー」。
コーナー」。