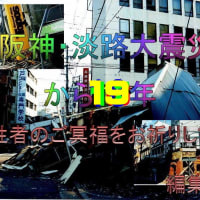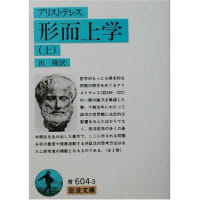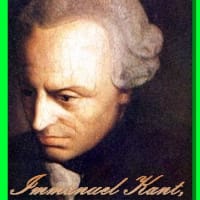『諸君!』2007年11月号には、青沼[2007]、[2007]、宮崎[2007]からなる「中華スパイラル経済が世界を呑み込む」という特集論文が掲載されている。
3つの論文は、いずれも刺激的な内容を含んでいる。本稿を含む以下3つの論考は、それに刺激されて、3論文の内容紹介をしながら、日本があまりにも安易に米国に寄りかかりすぎて、生き馬の目を抜く、したたかな大国の戦略に対応できぬ、ひ弱な国になってしまったことを歎くものである。
日本の食料自給率が40%を割ることの危険性を2003年に警告していた
青沼陽一郎氏は(青沼[2003])、日本食ブームの落とし穴を青沼[2007]で指摘している。
日本の食料自給率は、2006年についに40%を割り、39%になった。これは、先進国の中では異常なことである。第2次世界大戦前の英国も、自給率が50%を下回っていた。植民地で食糧生産をさせていたからである。しかし、ドイツ海軍のUボートによる攻撃で食糧危機で苦しんだ経験から戦後一貫して自給率の向上に努めた結果、いまでは、70%を上回るようになった。
日本も戦後は懸命に自給率を向上させてきた。戦後の食糧難に喘いできた日本は、1960年には79%にまで向上した。しかし、1960年に事情は一転した。日本政府は、日米安保条約に明記された「日米相互の経済協力」に従って、1961年に「農業基本法」を制定し、食糧輸入の「選択的拡大」路線に転換して、コメを除く食糧は、飼料も含めて米国から輸入することになった(青沼[2007]、167ページ)。
近年、日本の食料輸入先に大きな変化が生じた。中国の台頭である。
1990年には、1位米国31.9%、2位台湾7.6%、3位オーストラリア6.9%、4位中国6.6%、5位タイ5.3%、上位5か国で58.4%であった。
しかし、2006年になると、1位米国22.2%、2位中国18.3%、3位オーストラリア9.2%、4位タイ5.5%、5位カナダ4.6%、上位5か国59.8%になった。中国は、1990年の6.6%から18.3%と3倍のシェアにまで上昇した(同、168ページ)。
きっかけは、1985年9月のG5における「プラザ合意」である。これを契機として日本経済は戦後の工業生産の自給体制を大転換させた。農業も同じ途を歩んだ。強い円で開発輸入に踏み切ったのである。
流通大手が、シイタケとネギの開発輸入を開始した。日本人の求める野菜を中国で調達するようになったのである(同、169ページ)。その結果、冷凍食品、出来合いの総菜「中食」等の、大量の野菜流入が日本の農家を直撃した。
2002年に、中国産冷凍ホウレンソウと冷凍枝豆から残留農薬が検出されて、日本の食卓に衝撃が走った。じつは、中国人はホウレンソウを食べないのである。日本の商社が、ホウレンソウの種を中国に持ち込み、怪しげなブローカーが、日本の農薬を魔法の薬だとして契約農家に売りつけてきた。中には、禁止農薬もあった。その危険な農薬に毒されたホーレンソウが、ブーメランとして日本に戻ってきたのである。
それまでは、日本の商社は、ブローカーを通していた。日本商社が、契約農家に技術指導をしていたが、生産された野菜は、農家の手によって、ブローカーに渡されていた。野菜は、ブローカーによって、加工工場に運び込まれ、冷凍加工されていた。生鮮野菜とは異なり、冷凍野菜には明確な残留農薬規制はなかった(同、170ページ)。
冷凍ホウレンソウにショックを受けた日本の商社は、農家の直轄管理に乗り出すようになった。村単位で契約農家を選定し、冷凍加工場も商社が管理するようになった。指令通りの農薬を散布させ、肥料を施させる。農薬と肥料は他の業者を介入させず、商社が責任をもって配給する。中国では、この種の農地は「基地」と呼ばれている。収穫時に企業が残留農薬検査をする。しかし、依然としてブローカーは暗躍していて、アウトサイダー取引が行われている。
日本政府は、2006年に入って、検査を厳しくするようになった。世界一厳しい「ポジティブリスト制度」が2006年5月29日に施行された。それまでは検査対象は250種類であったが、これに新たに799種が追加された。リストに載っていなくても0.01ppmを超えると販売が禁止される。企業も独自検査施設をもつようになった。そのために、数億円の追加費用が必要になった。しかし、食毒騒動は続いている(同、171ページ)。
米国のジャーナリズムは、中国産ペット-フードで猫が死んだとか、中国産風邪薬で死者が出たとか、中国製練り歯磨きから毒が検出されたとか、騒ぎ立て、例によって、そうした反中国キャンペーンで米中経済交渉を米国に有利に運ぼうとしている。
とは言え、中国産食料に残留農薬が多く検出されているのは確かである。日本では、2006年の違反事例が658件あった。うち、中国は234件であった。内訳は、ウナギ46件、ショウガ31件、キクラゲ28件、ニンニクの芽15件、ネギ11件であった。2007年前半(1~6月)では、中国の違反は45件であった。うち、ウナギが20件あった(同ページ)。
中国からの輸入食料は、金額面では、最大が「鶏肉調整品」、次が「うなぎ調整品」、そして、「冷凍野菜」、「生鮮野菜」と続く。
数量面では、「生鮮野菜」、「冷凍野菜」が突出している。まさに中国は日本の「野菜基地」となった。
中国政府による農薬規制も厳しくなった。日本向けはとくに厳しい。中国検験検疫局(CIQ)の指定した池以外でのウナギ養殖は許されていない。ウナギ加工工場も登録池以外から買ってはいけないとされるようになった。CIQの検査は、日本よりも厳しくなっている(同、172ページ)。
しかし、ことは安全性の問題だけではない。農産物の開発輸入が日本の農家を苦しめているのである。青沼氏は、こうして現状を、間借り国家=日本と糾弾されている(同、177ページ)。
農水省試算によれば、日本の耕地面積は2006年時点で、約467万haである。日本向けに農産物を生産している海外の農地は、約1200haと推定される。つまり、日本は、日本の農地の2.5倍を海外に依存しているのである。農業には、水が必要である。農産物を輸入することは、現地の水を輸入していることになる。そうした水は、「バーチャル・ウォーター」と呼ばれている。牛肉100グラムを生産するのに必要な水は約2トンである。日本のバーチャル・ウォーターは、年間627億トンである。まさに日本は間借り国家である。このような国家は家主の都合で、大変なことになる。
そして、世界的な日本食ブームが困った事態を引き起こしている。ブーム自体は、嬉しいことに違いはないが、日本食ブームによって、これまで、日本人しか食べなかった食材が、世界中で外国人によって買い漁られ、日本人が「買い負け」するようになたのである。
「買い負け」という用語は、2007年の『水産白書』で初めて使用されたものである。食料争奪戦で日本は連戦連敗の惨状にある。
青沼氏は、バンコック郊外の寿司ネタ工場を紹介されている。これは、日本の企業によって設立されたものである。アフリカの沖合で水揚げされた紋甲イカが冷凍されて、バンコックの工場に運び込まれる。そこで、足と内臓を除去して、1枚の開きにする。表面の薄皮を剥ぎ取り、形を整え、真空冷凍パックにする。
モロッコ産のタコも巨大な釜で一気に茹で上げ、スライスカッターで一定の厚さと大きさにカットし、数枚ずつ真空パックにする。
これらの具材が日本に輸送されて、解凍されて、シャリの上に乗せられれば江戸前寿司になる。
日本の企業が、魚を捌く習慣がなく、包丁も押し切りで使うタイ人に、日本流の包丁の使い方や三枚下ろしの作り方を教え、包丁も現地で作らせたのである(同、174ページ)。
ところが、そうした食材が、日本だけに向けられるのではなく、欧米に大量に輸送されるようになってしまったのである。
青沼氏は、バンコック郊外にあるたこ焼き工場も紹介されている。これは、1990年に日本の総合商社が設立したもので、従業員は2200人、うち40%がミャンマーからの出稼ぎである。従業員の80%は女性で、従業員の平均年齢は20歳である。
タコは地場産、タコ切りは手作業、そして、たこ焼き鍋でできあがったタコ焼きをベルトコンベアに乗せる。冷凍されたタコ焼きが日本に空輸され、大手スーパーにならべられる。そして、日本人はチンするだけ。
広島流お好み焼きもタイで作られている。鉄板と串の作業が女工さんに作られる(同、176ページ)。
このタコやイカでも困ったことが起きている。タコやイカが途上国の戦略物資になった結果、倍々ゲームのような値上がりぶりとなった。世界で水揚げされるタコとイカの30%が日本人に胃袋に収まっていた。これにも、異変が生じているのである(同、177ページ)。
そして、アジフライ。タイ周辺の海でとれるアジは脂乗らず、骨は硬くて太い、処分されていた代物であった。これを逆手にとって日本の企業が、現地で工場を設立した。骨をとり、フライにして脂を足すというアジフライを考案したのである。欠点を利点に変えたのである。いまや日本人はアジフライに骨がないのが当たり前と思うようになっている(同、175ページ)。これもアジの値段の高騰で従来通りにいかなくなってしまった。
そもそも、アジは日本人しか食べなかった。昔は格安で独占的に購入できた。国連は、食料援助として安価なアジをアフリカ諸国に送っていたほどである。ところが、アフリカの所得水準が高まるとともに、アジフライの美味を知ったアフリカ人が積極的にアジを買い付けるようになった。いまやアジの買い付けで、日本のバイヤーは、アフリカ勢に買い負けるようになってしまった。日本ではアジは高値では食ってくれないので、セリ負けするのである(同、175ページ)。
日本食ブームによって、魚の美味しさを世界中が理解するようになった。多くの種類の魚介類が、米国、中国、アフリカに買い負け留用になってしまった。
EUは、2013年までに欧州産ウナギの稚魚の漁獲量の60%削減することを決めた。そしてウナギは、ワシントン条約の国際取引規制の対象になった。欧州ウナギの稚魚は中国で養殖され、日本に輸出されている。日本のウナギは6割が中国からのものでるし、その中国は25%が欧州ウナギ稚魚である。これが規制されることになったのである(同、177ページ)。
養殖のエビを使い、タイで作られたエビ天ぷらも米国に出荷されるようになった。これも、剥き身、衣、コンベアの網、油、等々、手作業である。温度管理は徹底しており、尻尾の破損点検も完全である。そもそも、尻尾のないエビを日本人が食べないからである。
ところが、米国で日本食ブームが起きた。ホームパーティでエビ天ぷらが好まれるようになった。2000年に日本資本が撤退するや否や、日本企業から工場を買い取った現地資本が、出荷先を欧米に切り換えた。それまでの出荷量が2200万トンであったのに、2006年時点では1万トンを超える。厳しい品質管理を欧米が評価し、日本よりも高値で引き取っている。かつては、80%を占めていた日本向けは35%にまで低下した。文句ばかりをつけ、安値でしか引き取ってくれない日本がアジを扱う業者から見捨てられ始めたのである。ここでも日本は買い負けをしている(同、176ページ)。
オーストラリアは、日本の「6Pチーズ」とか、「スライス・チーズ」の原料となるチェダー・チーズの生産を減らした。脱脂粉乳の生産に切り換えたのである。中国人が保存の効く脱脂粉乳を高値で買い取るようになった。脱脂粉乳は加工が簡単で利益率も高い。結局、オーストラリアの生産者は脱脂粉乳に傾斜し、日本向けのチェダー・チーズ生産を縮小させた。2002年になってからである。日本のチーズ・メーカーは、値上げせずに重量を下げた。結局、10%ほどの実質的値上げとなった。消費者は気づかなかった(同、178ページ)。
食糧を、軍事、石油に次ぐ第3の武器として宣言したのは、1974年8月のCIA報告である(『世界の人口.食糧生産.気候傾向の潜在的意味』、同、178ページ)。
ニクソン大統領による大豆禁輸がその直後にあった。以後、米国は、食糧を武器として使うようになった。2007年の米国の中国食料批判キャンペーンは、「米中経済戦略対話」に合わせたものであったことは明白である。2330億ドルの対中赤字と人民元切り上げ問題が中心的なテーマではあるが、その交渉を有利に運ぶキャンペーンが米国の対中食料批判であった。自給率128%の米国は、中国の食料を必要としていない。しかし、人民元が切り上げられると、日本の食料輸入は大打撃を受ける(同、179ページ)。
いよいよ、食料争奪時代の幕開けである。
引用文献
青沼陽一郎[2003]、「『食料植民地』ニッポンの危険な食物」『文藝春秋』2003年6月号。
青沼陽一郎[2007]、「中国産<毒菜>がいやなら日本人は飢えて死ぬしかない」 『諸君!』
2007年11月号。
岩瀬政則[2007]、「中国企業の貪欲すぎる『技術喰い』」『諸君!』2007年11月号。
宮崎政弘[2007]、「アフリカ.南米、2大陸を蹂躙する中国エネルギー戦略」『諸君!』2007
年11月号。