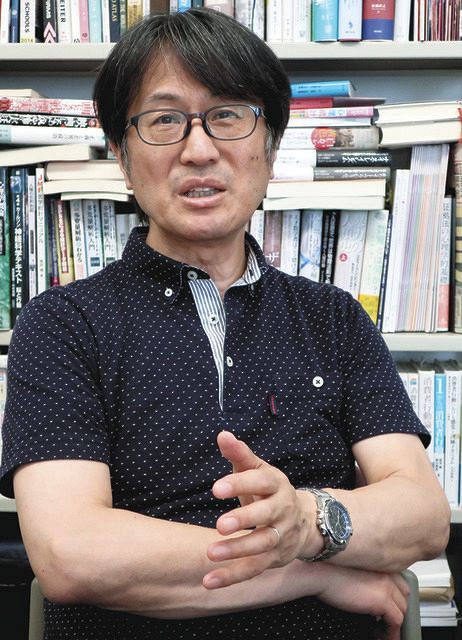従業員が客から高圧的な態度や攻撃的な言動で嫌がらせを受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が社会問題となっている。分析・対策にかかわってきた元山形県警科学捜査研究所(科捜研)研究員で東洋大の桐生正幸教授(犯罪心理学)が6月、「カスハラの犯罪心理学」(インターナショナル新書)を出版した。なぜカスハラは生まれるのか、対策はどうあるべきなのかを聞いた。(山田祐一郎)
◆暴言、土下座強要…深刻な被害実態
「カスハラによってストレスを感じたり心身の不調を訴えるケースが相次いでいる。被害者がいるということは犯罪なんです」。約20年間、科捜研の研究員として活動した経験を持つ桐生さん。カスハラの深刻さをこう指摘する。
科捜研では犯罪者プロファイリングを担当。「事件発生後、容疑性が高い人物が出る前の現場で情報収集し、犯人の行動を分析して絞り込む」と説明する。カスハラの分析にかかわるようになったきっかけは約10年前、企業や団体の消費者関連部門の担当者らでつくる団体に、クレーマー問題についての講演を依頼されたことだ。「各企業に多くの被害事例がある。実際にデータを集めて分析し、対策を考えることが必要と考えた」と研究を始めた。
事例を分析する中で「カスハラにはストーカーと似た加害者心理がある」と感じた。孤独感が問題行動を引き起こし、感情のコントロールが難しく攻撃的になる、執拗につきまとうなど、ストーカー行為の特徴はカスハラにも当てはまるという。2000年にストーカー規制法が施行されるまでは、何がストーカー行為なのかグレーな部分が多かった。カスハラも線引きが難しいという点で同様だ。
労働組合「UAゼンセン」が17年に実施した調査では、75%を超える人が被害経験があると回答。業種や性別によって「暴言」「返品要求」「土下座強要」など多様な被害が出ていることが判明した。被害を訴えた約4万人のうち、「精神疾患になったことがある」と答えたのは375人に上った。「現場のレジ打ちや接客の従業員が被害を受けている実態がまざまざと見え、対策が急務であることが露見した」と強調する。
◆「犯罪行為と明文化を」法整備訴え
一方の加害者はどのような人なのか。20年実施のウェブ調査に約2000人が回答し、加害経験があると答えたのは45%だった。多かったのは45~59歳の世代で、職業では営業担当や経営者、自営業が多く、世帯年収が1000万円を超えると割合が増えた。「嫌な思いをさせることへの共感がなく、攻撃行動を抑えるブレーキが利かない、偏った信念を通す頑固さが重なり合っている」とみる。
新型コロナによる自粛生活がカスハラにも大きな影響を与えた。コロナ対策に非協力的な客やマスク着用徹底を過度に求める「マスク警察」などトラブルが多発。20年のUAゼンセンの調査では、ドラッグストア関連の67%で被害の回答があった。「コロナによって問題が顕在化した」
厚生労働省は昨年、カスハラに対応するための企業向けのマニュアルを公表。事業主に対し、被害防止のために必要な措置を求めるが、カスハラの判断基準については「企業ごとに違いが出てくる可能性がある」として明確に定義していない。本の出版後、企業や団体から問い合わせや相談が寄せられているといい、「カスハラの被害を放置することは、企業の大きな損失になることに気付く必要がある」と訴える。
その上で被害者の立場に立った各種ハラスメントを防止するための法整備を求める。「法律で何がハラスメントに当たるかを規定し、犯罪行為であることを明文化する必要がある」