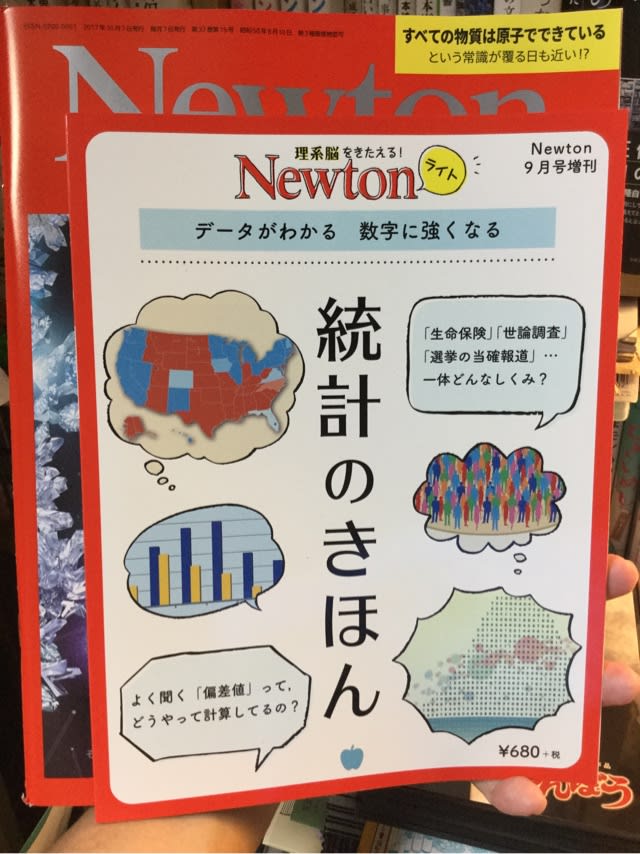台風18号のせいで大荒れだった前日から一転、朝から抜けるようなきれいな青空が宮崎市に広がった9月18日。映画祭3日目となるこの日は、全部で3作品を立て続けに鑑賞いたしました。
台風に振り回された初日と2日目。やはり観客の出足にも影響したようで、台風が宮崎県に最接近して大荒れだった2日目の午前中の回などは、観客がわずか6名というありさまだったとか。しかし、朝から晴天に恵まれた3日目はお客さんもそこそこ入っていて、とりわけこの日最初の上映となった『アニメーションの神様、その美しき世界』はかなりの入りでありました。

ユーリ・ノルシュテイン監督特集上映『アニメーションの神様、その美しき世界』(1968〜1979年、ソビエト)
監督=ユーリ・ノルシュテイン
ロシア・アニメーションの巨匠として名高く、日本アニメーション界の巨匠である宮崎駿・高畑勲両監督からも敬愛されている、ユーリ・ノルシュテイン監督の主要な中短編アニメーション6作品を特集したプログラムでした。ノルシュテイン監督のことは知ってはいたものの、実際にその作品を観るのは今回が初めてでありました。
ロシア革命を題材にして、1920年代の前衛芸術的な絵柄と構成で作り上げたデビュー作『25日・最初の日』(1968年)。西暦998年のロシアとタタールとの戦いを、中世の細密画・フレスコ画を動かすという手法で描いた『ケルジェネツの戦い』(1971年)。自分の住みかを乗っ取ったキツネを追い出そうとするウサギと、その仲間たちを描く『キツネとウサギ』(1973年)。互いに惹かれ合いながらも、それとは裏腹な拒絶の態度を取り続けるメスのアオサギとオスのツルのお話『アオサギとツル』(1974年)。友だちの子グマの家に向かおうと夕霧の中を急ぐハリネズミが、さまざまな出来事に遭遇する『霧の中のハリネズミ』(1975年)。そして、自伝的な要素と心情を強く反映させた中編『話の話』(1979年)。
ノルシュテイン監督を代表する傑作といわれる『話の話』は、ストーリーらしいストーリーに沿うことをせず、多様な詩的イメージの連続で綴られていて、少々難解に思えるところがありました。祝日の上映、それもアニメーションということで、劇場には親子連れも何組か見られましたが、小さなお子さんには戸惑いも大きかったかもしれません。とはいえ、30分ほどの時間の中に盛り込まれた画風や手法は実に多彩なものがあり、イマジネーションの豊かさを感じとることができました。
その他の諸短編も、それぞれが違った画風や手法によって作られていて、ノルシュテイン監督の持つ多様な才能が感じられました。中でも、ロシア民話を題材にした『キツネとウサギ』と『アオサギとツル』は、実にユーモラスな雰囲気をたたえた愛すべき小品という感じで楽しめました。
今回のプログラムは、ロシアから取り寄せた素材を日本で修復、リマスタリングした映像を使用したとのこと。時の流れを感じさせない美しい映像で、伝説のアニメーション作家の作品を味わうことができたのは嬉しいことでした。
続いて観たのは、今年2月に逝去された鈴木清順監督の回顧企画として上映された一本『ツィゴイネルワイゼン』。清順監督の代表作としてこれまた名高い作品なのですが、キチンと観たのはこれが初めてのことでありました。
『ツィゴイネルワイゼン』(1980年 日本)
監督=鈴木清順 製作=荒戸源次郎 脚本=田中陽造 撮影=永塚一栄 音楽=河内紀
出演=原田芳雄、大谷直子(二役)、大楠道代、藤田敏八
気ままな放浪生活を続けている男、中砂。旅先でひょんなことから合流した友人の青地とともに、弟を自殺で亡くしたばかりの芸者と出会う。その後、中砂が名家の娘と結婚したという話を聞いた青地が中砂の家を訪れると、その妻は旅先で出会った芸者と瓜二つだった。その夜、中砂は青地にサラサーテが演奏する「ツィゴイネルワイゼン」のSPレコードを聴かせるが、そこにはサラサーテ自身のものと思われる声が入っていた・・・。
内田百閒の小説「サラサーテの盤」をモティーフに、「ツィゴイネルワイゼン」のレコードをめぐる男女4人が入り込む、現実と幻想、正気と狂気、そして生と死の境目があいまいとなった迷宮世界を描き尽くした、いわゆる「清順美学」の極北といえそうな本作。特異な世界観と、一癖も二癖もある登場人物たちが織りなす物語は一筋縄ではいかないところがございましたが、清順監督ならではのイマジネーションがあふれていて、「こういう世界観も面白いかも」という感じで楽しみました。
観ていて印象に残ったのが、登場人物たちが食べたり飲んだりする場面がやけに多かったということ。うなぎの蒲焼から始まって、牛鍋にそば、さらには腐りかけの水蜜桃・・・。そんな中で、牛鍋に入れるこんにゃくをひたすらちぎり続けたあげく、それを鍋に山盛りにする大谷直子さんと、腐りかけの水蜜桃をべちゃべちゃと味わう大楠道代さんのシーンは、とりわけ強い印象を与えてくれました。
そしてさらにもう一本。こちらも観るのがとても楽しみだったドキュメンタリー作品『人類遺産』を鑑賞いたしました。
『人類遺産』(2015年 オーストリア・ドイツ・スイス)
監督=ニコラウス・ゲイハルター(ドキュメンタリー)
世界の各所に存在している、さまざまな建造物の「廃墟」や、人がいなくなってしまった町の風景を、カメラの目を通してじっくりと見つめ、まとめ上げたドキュメンタリー映画です。
監督のニコラウス・ゲイハルター氏は、日本でも話題となった『いのちの食べかた』(2007年。この作品も2008年の宮崎映画祭で上映されました)を製作した気鋭のドキュメンタリー映画作家。野菜や果物、精肉などの食糧生産の現場を、ナレーションや音楽、テロップを一切排して淡々と捉えた『いのちの食べかた』に見られるゲイハルター流ドキュメンタリー作法は、この『人類遺産』でもしっかり健在でした。
かつてはショッピングモールや映画館、学校、図書館、病院、教会、発電所だった建物。遊園地。放棄された戦車や軍艦。炭鉱の島として栄えながらも、閉山後は廃墟が連なる無人の島となった長崎県の「軍艦島」こと端島。水没してしまった町や砂漠に飲み込まれようとしている町・・・。そんな世界各地の「廃墟」や、人のいなくなってしまった町の風景を、映画は一切の説明的な要素を示さず、次々と映し出していきます。
風や雨の音、鳥のはばたきや鳴き声、波の音などの現場音だけが響く、荒れ果てた「廃墟」や人のいない町の風景。それらを、ゲイハルター監督はカメラを一切動かさない、固定したままの視点で絵画のようにじっくりと、そして美しく切り取っていきます。とりわけ、水の溜まっている洞窟のような場所に、たくさんの廃車が積み重なっている光景には、ハッと息を飲むような美しさがありました。
説明的な要素を一切排することで、特定の方向に沿った解釈に陥ることなく、観る側がそれぞれの見方で映像を捉え、解釈できるのが、本作が持つ最大の魅力だといえるでしょう。
しかしながら、現在は立ち入りが制限されている福島県の浪江町とおぼしき風景が、映画の冒頭に映し出されたときには(そのことを示す要素も一切画面には出てはこないのですが)「いまは立ち入りができないとはいえ、住んでいた方々の多くがいつかは帰りたいという思いを持っているはずなのに・・・」と、ちょっと複雑な思いを抱かざるを得なかったのですが・・・。
余分な説明を一切省いて映し出される、多くの「廃墟」や町の光景。かつては間違いなくそこにあったはずの人びとのいとなみを、わたしはいろいろと想像しました。
多くの人で賑わっていたショッピングモール。子どもたちの元気な声があふれていた学校。生と死のドラマが繰り広げられていた病院。暮らしと社会を支えていた発電所・・・。時が移ろう中で人びとから忘れられ、朽ちていきながらも、そこには確かに人びとの喜怒哀楽に彩られたいとなみがあったということを、「廃墟」の数々が静かに語りかけているように、わたしには思えました。
現実の光景を淡々と映し出す向こうから、さまざまなイマジネーションを感じ取ることができるドキュメンタリーでした。
ノルシュテインのアニメーション、「清順美学」の極北である『ツィゴイネルワイゼン』、そして異色のドキュメンタリー『人類遺産』。いずれもそれぞれの形で、イマジネーションを刺激してやまない作品たちでありました。
台風に振り回された初日と2日目。やはり観客の出足にも影響したようで、台風が宮崎県に最接近して大荒れだった2日目の午前中の回などは、観客がわずか6名というありさまだったとか。しかし、朝から晴天に恵まれた3日目はお客さんもそこそこ入っていて、とりわけこの日最初の上映となった『アニメーションの神様、その美しき世界』はかなりの入りでありました。

ユーリ・ノルシュテイン監督特集上映『アニメーションの神様、その美しき世界』(1968〜1979年、ソビエト)
監督=ユーリ・ノルシュテイン
ロシア・アニメーションの巨匠として名高く、日本アニメーション界の巨匠である宮崎駿・高畑勲両監督からも敬愛されている、ユーリ・ノルシュテイン監督の主要な中短編アニメーション6作品を特集したプログラムでした。ノルシュテイン監督のことは知ってはいたものの、実際にその作品を観るのは今回が初めてでありました。
ロシア革命を題材にして、1920年代の前衛芸術的な絵柄と構成で作り上げたデビュー作『25日・最初の日』(1968年)。西暦998年のロシアとタタールとの戦いを、中世の細密画・フレスコ画を動かすという手法で描いた『ケルジェネツの戦い』(1971年)。自分の住みかを乗っ取ったキツネを追い出そうとするウサギと、その仲間たちを描く『キツネとウサギ』(1973年)。互いに惹かれ合いながらも、それとは裏腹な拒絶の態度を取り続けるメスのアオサギとオスのツルのお話『アオサギとツル』(1974年)。友だちの子グマの家に向かおうと夕霧の中を急ぐハリネズミが、さまざまな出来事に遭遇する『霧の中のハリネズミ』(1975年)。そして、自伝的な要素と心情を強く反映させた中編『話の話』(1979年)。
ノルシュテイン監督を代表する傑作といわれる『話の話』は、ストーリーらしいストーリーに沿うことをせず、多様な詩的イメージの連続で綴られていて、少々難解に思えるところがありました。祝日の上映、それもアニメーションということで、劇場には親子連れも何組か見られましたが、小さなお子さんには戸惑いも大きかったかもしれません。とはいえ、30分ほどの時間の中に盛り込まれた画風や手法は実に多彩なものがあり、イマジネーションの豊かさを感じとることができました。
その他の諸短編も、それぞれが違った画風や手法によって作られていて、ノルシュテイン監督の持つ多様な才能が感じられました。中でも、ロシア民話を題材にした『キツネとウサギ』と『アオサギとツル』は、実にユーモラスな雰囲気をたたえた愛すべき小品という感じで楽しめました。
今回のプログラムは、ロシアから取り寄せた素材を日本で修復、リマスタリングした映像を使用したとのこと。時の流れを感じさせない美しい映像で、伝説のアニメーション作家の作品を味わうことができたのは嬉しいことでした。
続いて観たのは、今年2月に逝去された鈴木清順監督の回顧企画として上映された一本『ツィゴイネルワイゼン』。清順監督の代表作としてこれまた名高い作品なのですが、キチンと観たのはこれが初めてのことでありました。
『ツィゴイネルワイゼン』(1980年 日本)
監督=鈴木清順 製作=荒戸源次郎 脚本=田中陽造 撮影=永塚一栄 音楽=河内紀
出演=原田芳雄、大谷直子(二役)、大楠道代、藤田敏八
気ままな放浪生活を続けている男、中砂。旅先でひょんなことから合流した友人の青地とともに、弟を自殺で亡くしたばかりの芸者と出会う。その後、中砂が名家の娘と結婚したという話を聞いた青地が中砂の家を訪れると、その妻は旅先で出会った芸者と瓜二つだった。その夜、中砂は青地にサラサーテが演奏する「ツィゴイネルワイゼン」のSPレコードを聴かせるが、そこにはサラサーテ自身のものと思われる声が入っていた・・・。
内田百閒の小説「サラサーテの盤」をモティーフに、「ツィゴイネルワイゼン」のレコードをめぐる男女4人が入り込む、現実と幻想、正気と狂気、そして生と死の境目があいまいとなった迷宮世界を描き尽くした、いわゆる「清順美学」の極北といえそうな本作。特異な世界観と、一癖も二癖もある登場人物たちが織りなす物語は一筋縄ではいかないところがございましたが、清順監督ならではのイマジネーションがあふれていて、「こういう世界観も面白いかも」という感じで楽しみました。
観ていて印象に残ったのが、登場人物たちが食べたり飲んだりする場面がやけに多かったということ。うなぎの蒲焼から始まって、牛鍋にそば、さらには腐りかけの水蜜桃・・・。そんな中で、牛鍋に入れるこんにゃくをひたすらちぎり続けたあげく、それを鍋に山盛りにする大谷直子さんと、腐りかけの水蜜桃をべちゃべちゃと味わう大楠道代さんのシーンは、とりわけ強い印象を与えてくれました。
そしてさらにもう一本。こちらも観るのがとても楽しみだったドキュメンタリー作品『人類遺産』を鑑賞いたしました。
『人類遺産』(2015年 オーストリア・ドイツ・スイス)
監督=ニコラウス・ゲイハルター(ドキュメンタリー)
世界の各所に存在している、さまざまな建造物の「廃墟」や、人がいなくなってしまった町の風景を、カメラの目を通してじっくりと見つめ、まとめ上げたドキュメンタリー映画です。
監督のニコラウス・ゲイハルター氏は、日本でも話題となった『いのちの食べかた』(2007年。この作品も2008年の宮崎映画祭で上映されました)を製作した気鋭のドキュメンタリー映画作家。野菜や果物、精肉などの食糧生産の現場を、ナレーションや音楽、テロップを一切排して淡々と捉えた『いのちの食べかた』に見られるゲイハルター流ドキュメンタリー作法は、この『人類遺産』でもしっかり健在でした。
かつてはショッピングモールや映画館、学校、図書館、病院、教会、発電所だった建物。遊園地。放棄された戦車や軍艦。炭鉱の島として栄えながらも、閉山後は廃墟が連なる無人の島となった長崎県の「軍艦島」こと端島。水没してしまった町や砂漠に飲み込まれようとしている町・・・。そんな世界各地の「廃墟」や、人のいなくなってしまった町の風景を、映画は一切の説明的な要素を示さず、次々と映し出していきます。
風や雨の音、鳥のはばたきや鳴き声、波の音などの現場音だけが響く、荒れ果てた「廃墟」や人のいない町の風景。それらを、ゲイハルター監督はカメラを一切動かさない、固定したままの視点で絵画のようにじっくりと、そして美しく切り取っていきます。とりわけ、水の溜まっている洞窟のような場所に、たくさんの廃車が積み重なっている光景には、ハッと息を飲むような美しさがありました。
説明的な要素を一切排することで、特定の方向に沿った解釈に陥ることなく、観る側がそれぞれの見方で映像を捉え、解釈できるのが、本作が持つ最大の魅力だといえるでしょう。
しかしながら、現在は立ち入りが制限されている福島県の浪江町とおぼしき風景が、映画の冒頭に映し出されたときには(そのことを示す要素も一切画面には出てはこないのですが)「いまは立ち入りができないとはいえ、住んでいた方々の多くがいつかは帰りたいという思いを持っているはずなのに・・・」と、ちょっと複雑な思いを抱かざるを得なかったのですが・・・。
余分な説明を一切省いて映し出される、多くの「廃墟」や町の光景。かつては間違いなくそこにあったはずの人びとのいとなみを、わたしはいろいろと想像しました。
多くの人で賑わっていたショッピングモール。子どもたちの元気な声があふれていた学校。生と死のドラマが繰り広げられていた病院。暮らしと社会を支えていた発電所・・・。時が移ろう中で人びとから忘れられ、朽ちていきながらも、そこには確かに人びとの喜怒哀楽に彩られたいとなみがあったということを、「廃墟」の数々が静かに語りかけているように、わたしには思えました。
現実の光景を淡々と映し出す向こうから、さまざまなイマジネーションを感じ取ることができるドキュメンタリーでした。
ノルシュテインのアニメーション、「清順美学」の極北である『ツィゴイネルワイゼン』、そして異色のドキュメンタリー『人類遺産』。いずれもそれぞれの形で、イマジネーションを刺激してやまない作品たちでありました。