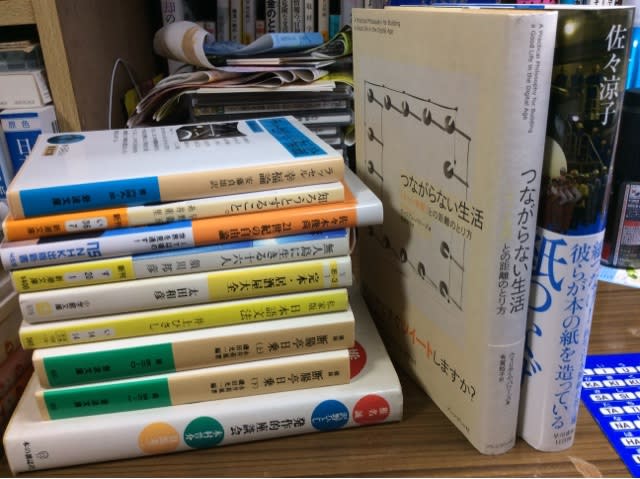今年で第21回目となる宮崎映画祭が、19日(土曜日)に開幕いたしました。
これまで夏の時期に開催されることが多かった宮崎映画祭ですが、今年は秋のシルバーウイークに合わせる形での開催となり、まさに「芸術の秋」を実感するような催しとなっております。


初日のオープニングを飾ったのは、今回の映画祭の目玉となるプレミア上映作品『地獄の黙示録』でした。フランシス・フォード・コッポラ監督が手がけた映画史に残る作品ですが、わたくしは土曜のお昼までは仕事ということで観られませんでした。でもこれは26日にも、アニメーション映画監督の原恵一さんを招いての「映画塾」のときにも上映されるということで、その時にしっかり観ようということでお預け。
初日に上映された5作品のうち、わたくしは午後から上映された宮崎県出身の故・黒木和雄監督が手がけた2作品をじっくり鑑賞いたしました。今回の映画祭の目玉企画の一つが、黒木監督の作品の特集上映でした。戦後70年、そして黒木監督の没後10年を意識しての企画でした。
まずは数多くの映画賞を総なめにした『美しい夏キリシマ』です。
『美しい夏キリシマ』(2003年、日本)
監督=黒木和雄
脚本=松田正隆・黒木和雄
撮影=田村正毅
音楽=松村禎三
出演=柄本佑、原田芳雄、石田えり、香川照之、小田エリカ
1945年夏、霧島を眺める宮崎県西部。動員先の工場で空襲に遭い、友人を亡くしてしまった15歳の少年、日高康夫。空襲のショックと、友人を助けることができなかったことへの罪悪感から肺浸潤を患い、満州で暮らす両親と離れて祖父の重徳のもとで療養しながら日々を過ごしていた。なぜ自分が生き残り、友が死ななければならなかったのかと、聖書と宗教画を見ながら悶々としている康夫に、厳格な重徳は苛立ちを募らせ、非国民と罵倒する。重徳宅に奉公している娘・なつは、そんな康夫に頼りなさを感じつつも親近感を抱いている。ある日康夫は、死んだ友人の妹・波のもとを訪れるが、波からは冷たく拒絶されてしまう。
康夫たちが住む村には兵士たちが駐屯していて、上陸が噂されるアメリカ軍を迎え撃つべく訓練に余念がない。そんな厳しい訓練から逃れた一等兵は、なつの母であるイネのもとにやってきては密会を重ねている。
それぞれの人びとの暮らしが流れていく中で、日本の敗色は増していくのであった・・・。
戦争と人間を映画で描くことをライフワークとしていた黒木監督。長崎の原爆をテーマとした『TOMORROW/明日』(1988年)や、広島の原爆がテーマの『父と暮せば』(2004年)とともに「戦争レクイエム三部作」に数えられる本作『美しい夏キリシマ』は、黒木監督自身の空襲体験を色濃く反映させた作品となりました。
黒木監督自身を投影した主人公・康夫を演じたのは、柄本明さんの息子さんでもある柄本佑さん。これが映画デビュー作にして初主演とのことですが、一見存在感がないようでいて、観ていくうちに実に不思議な存在感を残すようなキャラクターをしっかりと演じきっていました。
康夫の祖父・重徳役は、黒木監督の作品では常連だった原田芳雄さん。厳格だけれども時に滑稽さも感じさせる芝居は、さすが原田さんと思える達者ぶりでした。また、密会を重ねるイネ役の石田えりさんと、一等兵役の香川照之さんも、強烈で忘れがたい印象を残してくれました。
黒木監督の出身地である、宮崎県えびの市でロケーションを行い製作された本作。タイトル通り、霧島連山の風景がしばしば登場するほか、セリフの大部分も南九州のことばがふんだんに使われていて、とても身近な感じがいたしました。それだけに、自分が住んでいるところからも近い南九州の田舎も、否応なしに戦争の時代に押し流され、影響を受けていたのだということが、よりリアルに感じられてきました。
静かなトーンの中から、戦争がいかに人びとの生活や生き方を狂わせてしまうのかということが、じんじんと伝わってくる作品でありました。
『美しい夏キリシマ』に引き続き上映されたのは、黒木監督の遺作となった『紙屋悦子の青春』でした。
『紙屋悦子の青春』(2006年、日本)
監督=黒木和雄
脚本=黒木和雄・山田英樹
原作=松田正隆
撮影=川上皓市
音楽=松村禎三
出演=原田知世、永瀬正敏、小林薫、本上まなみ、松岡俊介
昭和20年春、鹿児島。兄夫婦のもとで暮らしている紙屋悦子に、兄の後輩である海軍少尉・明石から縁談が持ち込まれる。相手は明石の親友でもある同僚の少尉・長与であった。秘かに明石に想いを寄せていた悦子は逡巡しつつ見合いの席に臨むが、不器用ながらも誠実な長与に惹かれ、縁談を受け入れることに。実は明石は沖縄への出撃を控えていて、悦子のことを長与に託そうとしていたのだった。明石の思いを知り、それを受け入れようとする悦子と長与。そして桜が散る頃、明石が沖縄へと出撃する日がやってきたのであった・・・。
松田正隆さんによる舞台劇(松田さんは、先の『美しい夏キリシマ』で、黒木監督とともに脚本を手がけた方でもあります)を映画化した『紙屋悦子の青春』。ときおり挿入される、現在の年老いた悦子と長与が語り合っている病院の屋上のシーン以外は、すべて昭和20年に悦子が暮らしていた兄夫婦の家の中だけで物語が進んでいきます。そして登場人物は悦子と兄夫婦、長与と明石の5人のみです。
しかし、映画にはまったく単調さはありませんでした。聡明な悦子を好演した原田知世さん。ちょっととぼけたところはあっても頼りがいのありそうな兄を演じた小林薫さん。それを支えるしっかり者の兄嫁(にして悦子の幼なじみ)を演じた本上まなみさん。不器用だけど朴訥で誠実な長与を演じた永瀬正敏さん。長与の不器用さにやきもきしながらも、悦子への想いを断ち切って出撃していく明石を演じた松岡俊介さん。この芸達者な5人による、ユーモラスでほのぼのとした掛け合いはまことに見事で、笑いとともに一気に物語へと引き込まれました。そこには、戦争をテーマにした作品にありがちな重苦しさもありませんでした。
しかし、それだからこそ、戦争によって失われた者への哀惜の念、そして失われた者たちの想いを受け継いで生きていこうとする者たちの決意が、自然に胸を打ってきました。悦子が、胸のうちでこらえていた思いを表出させる場面では、涙を抑えることができませんでした。
これから先、何度でも観直してみたい、と思えるような素晴らしい作品を、黒木監督は最後に遺してくれました。
戦後70年の今年は、安保法制をめぐる問題で戦争と平和についての議論が巻き起こった年にもなりました。ですがそれらの「議論」には、いささか声高でヒステリックなものが目立っていたことも事実でしょう。
そのようなあり方に疲れ、嫌悪感すら抱いていたわたくしに、黒木監督の2作品は静かに、しかししっかりと、戦争と平和の意味を問いかけてくれました。
❇︎第21回宮崎映画祭は27日(日曜日)まで開催されます。詳しいことは、下記の映画祭公式サイトをどうぞ。
http://www.bunkahonpo.or.jp/mff/
(次回につづく)
これまで夏の時期に開催されることが多かった宮崎映画祭ですが、今年は秋のシルバーウイークに合わせる形での開催となり、まさに「芸術の秋」を実感するような催しとなっております。


初日のオープニングを飾ったのは、今回の映画祭の目玉となるプレミア上映作品『地獄の黙示録』でした。フランシス・フォード・コッポラ監督が手がけた映画史に残る作品ですが、わたくしは土曜のお昼までは仕事ということで観られませんでした。でもこれは26日にも、アニメーション映画監督の原恵一さんを招いての「映画塾」のときにも上映されるということで、その時にしっかり観ようということでお預け。
初日に上映された5作品のうち、わたくしは午後から上映された宮崎県出身の故・黒木和雄監督が手がけた2作品をじっくり鑑賞いたしました。今回の映画祭の目玉企画の一つが、黒木監督の作品の特集上映でした。戦後70年、そして黒木監督の没後10年を意識しての企画でした。
まずは数多くの映画賞を総なめにした『美しい夏キリシマ』です。
『美しい夏キリシマ』(2003年、日本)
監督=黒木和雄
脚本=松田正隆・黒木和雄
撮影=田村正毅
音楽=松村禎三
出演=柄本佑、原田芳雄、石田えり、香川照之、小田エリカ
1945年夏、霧島を眺める宮崎県西部。動員先の工場で空襲に遭い、友人を亡くしてしまった15歳の少年、日高康夫。空襲のショックと、友人を助けることができなかったことへの罪悪感から肺浸潤を患い、満州で暮らす両親と離れて祖父の重徳のもとで療養しながら日々を過ごしていた。なぜ自分が生き残り、友が死ななければならなかったのかと、聖書と宗教画を見ながら悶々としている康夫に、厳格な重徳は苛立ちを募らせ、非国民と罵倒する。重徳宅に奉公している娘・なつは、そんな康夫に頼りなさを感じつつも親近感を抱いている。ある日康夫は、死んだ友人の妹・波のもとを訪れるが、波からは冷たく拒絶されてしまう。
康夫たちが住む村には兵士たちが駐屯していて、上陸が噂されるアメリカ軍を迎え撃つべく訓練に余念がない。そんな厳しい訓練から逃れた一等兵は、なつの母であるイネのもとにやってきては密会を重ねている。
それぞれの人びとの暮らしが流れていく中で、日本の敗色は増していくのであった・・・。
戦争と人間を映画で描くことをライフワークとしていた黒木監督。長崎の原爆をテーマとした『TOMORROW/明日』(1988年)や、広島の原爆がテーマの『父と暮せば』(2004年)とともに「戦争レクイエム三部作」に数えられる本作『美しい夏キリシマ』は、黒木監督自身の空襲体験を色濃く反映させた作品となりました。
黒木監督自身を投影した主人公・康夫を演じたのは、柄本明さんの息子さんでもある柄本佑さん。これが映画デビュー作にして初主演とのことですが、一見存在感がないようでいて、観ていくうちに実に不思議な存在感を残すようなキャラクターをしっかりと演じきっていました。
康夫の祖父・重徳役は、黒木監督の作品では常連だった原田芳雄さん。厳格だけれども時に滑稽さも感じさせる芝居は、さすが原田さんと思える達者ぶりでした。また、密会を重ねるイネ役の石田えりさんと、一等兵役の香川照之さんも、強烈で忘れがたい印象を残してくれました。
黒木監督の出身地である、宮崎県えびの市でロケーションを行い製作された本作。タイトル通り、霧島連山の風景がしばしば登場するほか、セリフの大部分も南九州のことばがふんだんに使われていて、とても身近な感じがいたしました。それだけに、自分が住んでいるところからも近い南九州の田舎も、否応なしに戦争の時代に押し流され、影響を受けていたのだということが、よりリアルに感じられてきました。
静かなトーンの中から、戦争がいかに人びとの生活や生き方を狂わせてしまうのかということが、じんじんと伝わってくる作品でありました。
『美しい夏キリシマ』に引き続き上映されたのは、黒木監督の遺作となった『紙屋悦子の青春』でした。
『紙屋悦子の青春』(2006年、日本)
監督=黒木和雄
脚本=黒木和雄・山田英樹
原作=松田正隆
撮影=川上皓市
音楽=松村禎三
出演=原田知世、永瀬正敏、小林薫、本上まなみ、松岡俊介
昭和20年春、鹿児島。兄夫婦のもとで暮らしている紙屋悦子に、兄の後輩である海軍少尉・明石から縁談が持ち込まれる。相手は明石の親友でもある同僚の少尉・長与であった。秘かに明石に想いを寄せていた悦子は逡巡しつつ見合いの席に臨むが、不器用ながらも誠実な長与に惹かれ、縁談を受け入れることに。実は明石は沖縄への出撃を控えていて、悦子のことを長与に託そうとしていたのだった。明石の思いを知り、それを受け入れようとする悦子と長与。そして桜が散る頃、明石が沖縄へと出撃する日がやってきたのであった・・・。
松田正隆さんによる舞台劇(松田さんは、先の『美しい夏キリシマ』で、黒木監督とともに脚本を手がけた方でもあります)を映画化した『紙屋悦子の青春』。ときおり挿入される、現在の年老いた悦子と長与が語り合っている病院の屋上のシーン以外は、すべて昭和20年に悦子が暮らしていた兄夫婦の家の中だけで物語が進んでいきます。そして登場人物は悦子と兄夫婦、長与と明石の5人のみです。
しかし、映画にはまったく単調さはありませんでした。聡明な悦子を好演した原田知世さん。ちょっととぼけたところはあっても頼りがいのありそうな兄を演じた小林薫さん。それを支えるしっかり者の兄嫁(にして悦子の幼なじみ)を演じた本上まなみさん。不器用だけど朴訥で誠実な長与を演じた永瀬正敏さん。長与の不器用さにやきもきしながらも、悦子への想いを断ち切って出撃していく明石を演じた松岡俊介さん。この芸達者な5人による、ユーモラスでほのぼのとした掛け合いはまことに見事で、笑いとともに一気に物語へと引き込まれました。そこには、戦争をテーマにした作品にありがちな重苦しさもありませんでした。
しかし、それだからこそ、戦争によって失われた者への哀惜の念、そして失われた者たちの想いを受け継いで生きていこうとする者たちの決意が、自然に胸を打ってきました。悦子が、胸のうちでこらえていた思いを表出させる場面では、涙を抑えることができませんでした。
これから先、何度でも観直してみたい、と思えるような素晴らしい作品を、黒木監督は最後に遺してくれました。
戦後70年の今年は、安保法制をめぐる問題で戦争と平和についての議論が巻き起こった年にもなりました。ですがそれらの「議論」には、いささか声高でヒステリックなものが目立っていたことも事実でしょう。
そのようなあり方に疲れ、嫌悪感すら抱いていたわたくしに、黒木監督の2作品は静かに、しかししっかりと、戦争と平和の意味を問いかけてくれました。
❇︎第21回宮崎映画祭は27日(日曜日)まで開催されます。詳しいことは、下記の映画祭公式サイトをどうぞ。
http://www.bunkahonpo.or.jp/mff/
(次回につづく)