
















ヨシタケシンスケ著、新潮社、2020年
子どもと大人のワクを超えた絶大な人気を誇り、2020年も新作が次々に刊行されるなど快進撃が続いている、絵本作家のヨシタケシンスケさんが今月(7月)に刊行したばかりの新著『欲が出ました』。ヨシタケさんが折に触れて描きためてきたスケッチの数々を選び、それらを描きとめた意図をエッセイ風に語っていく一冊で、同じ版元から昨年刊行された『思わず考えちゃう』の第二弾に当たります。前著はスケッチを解説するエッセイのみでしたが、今回はスケッチのみで構成されたページも設けられております。
 独特のセンスで切り取られた、日常のふとした光景から、その時々の心情を反映させた呟きのようなものまで。ヨシタケさんならではの愛嬌たっぷりのスケッチの数々にニンマリさせられつつ、時にいろいろと考えさせられるような洞察も散りばめられていて、第一弾同様、面白く読むことができました。
独特のセンスで切り取られた、日常のふとした光景から、その時々の心情を反映させた呟きのようなものまで。ヨシタケさんならではの愛嬌たっぷりのスケッチの数々にニンマリさせられつつ、時にいろいろと考えさせられるような洞察も散りばめられていて、第一弾同様、面白く読むことができました。ヨシタケさんの次男くんが「ハイチュウたべていい?」とせがんでいるところを描いたスケッチも、わたしのお気に入りです。とにかく甘いものを食べるのが好きだという次男くん、それでも勝手に食べたりはせずに、毎回律儀に許可をもらいに来るとのことで、なんだかとてもカワイイなあと顔がほころんでくるのであります(これに限らず、次男くんネタのスケッチはどれもカワイくて好き)。
愛嬌があってクスッとさせてくれるところも、ヨシタケ流スケッチのお楽しみです。天狗の顔の形になっていて、長く伸びた鼻を下げると「ピンポーン」と鳴る〝テングチャイム〟や、ホウキを持って二本足で立っている〝雑用犬〟のスケッチは、カワイくていい感じです。椅子の頭を噛んでいる子どもに〝イスカンダル〟と添書きしているスケッチは、他愛ないといえば他愛ない上わかる人にしかわからないシャレ(笑)だったりするのですが、そういうのにもまた、えもいわれぬ味があったりいたします。
クスッとさせてくれる愛嬌とユーモアが溢れるスケッチだけでなく、考えさせられたり深く頷けたりするようなスケッチも。
大きく輝いている星の近くを飛行している宇宙船のイラストに〝引力の強すぎるものには近付かないようにしています。離れられなくなっちゃうから。〟と添書きしたスケッチ。それについてヨシタケさんは、世の中には「影響力の強い人や、思想だったり、団体だったり、ものの言い方」といった「すごい引力が強い」存在があるといい、年をとってそういった引力の強いものから逃れる体力が減ってきたこともあって、最近は引力の強すぎるものには近付かないようにしている、と語ります。
わたしはこれには大いに共感いたしました。確かに、そういった引力の強いものから刺激をを受けることで自分をステップアップさせることができるのも、一面の事実ではありましょう。しかし、それらに過度に影響されることで自分を見失い、おかしな方向へ行ってしまう危険性があることも、また事実であるように思うのです。
影響力の強い存在から取り入れられるものは吸収しつつ、それらに過度に飲み込まれないようなバランス感覚も、生きる上での大事な知恵であると感じました。
「大吉」と書かれたおみくじを手に持ってニコニコするおじいちゃんの絵に、〝実際にいいことがなくても、「幸せの予感」さえあればどうにかやっていける〟と添書きしたスケッチ。これについて、ヨシタケさんはこう言います。
「現実に、幸せかどうか、満ち足りてるかどうかではなくて、この先満ち足りるかもしれないっていう予感が心の中で発動するかどうかで、実は幸せって決まるのではないかと。
実際には、起きたいいことなんかすぐ忘れちゃうし、すぐあきちゃうし、この先いいことが起こる確率なんてすごく低いはずだけど、でも、それだけじゃないはずだ、もっと楽しいことだって起きるかもしれないって、大した根拠もなしに思えるかどうか。希望って、つまりそういうことだと思うのです」
このことばにもまた、深く深く頷かされました。目下の新型コロナパニックの中では、ともすると「幸せ」と思えるような感覚を忘れてしまいそうになります。そんな世の中だからこそ、「もっと楽しいことが起きるかもしれない」という「希望」を持ち続けることの大切さを、ヨシタケさんのことばで痛感いたしました。
ヨシタケさんが創作において心がけている〝流儀〟を語っているところもいくつかあり、それらにも興味を惹かれます。
この世界のいろんなところに出ている「しっぽ」を丁寧に手繰り寄せるという話や、大事そうなものを「おもしろおかしいもの」として表現する努力が必要という話にも興趣が湧きましたが、とりわけ気持ちに響いたのは、「その問題に一番興味のない人々の視点」を保ち続ける、という話でした。そういった視点こそ大事にしなきゃいけないし、したいなと思っている、とヨシタケさんは語り、こう続けます。
「内輪からの言葉だけしかないと、絶対それは「外側」には届かないだろうから。
一番興味のない人に興味を持たせるには、じゃあどういう言い方があるのか。「一番届いてほしい人」に届けるためには、そうとう工夫が必要なはずです。
「遅刻しないように」って朝礼で言っても、遅刻してる人はその朝礼にいない、みたいな話ですね」
何かを主張するときに、「内輪からの言葉」ばかりで語ってしまっている向きを、しばしば目にします。同じような考え方を持つ「内輪」の人たち同士でそうだそうだと頷き合ったり、単に自己満足に浸りたいというのであれば、それでもいいのでしょう。しかしそれでは、異なった考え方や興味を持つ、多くの「外側」の人びとに届くことも、伝わることもないことは明らかでしょう。
その事柄に興味がない人たちに向けてどう伝えるのか、それを考え工夫することの大切さは、創作に関わる人のみならず、さまざまな人たちにも当てはまることのように、わたしには思われました。
クスッと笑えるユーモアと、思わず膝を打つ洞察をスケッチとエッセイで見せる『欲が出ました』。絵本だけでは窺い知れない、ヨシタケさんの多面的な魅力と人間性を感じることができる一冊であります。
【関連おススメ本】
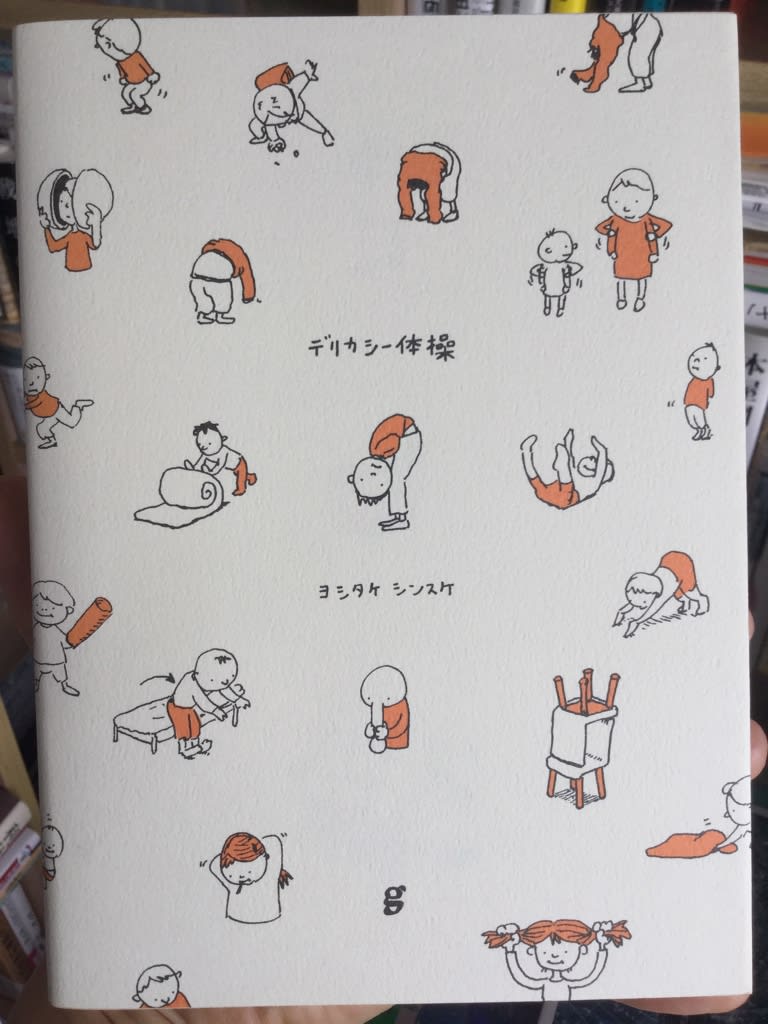

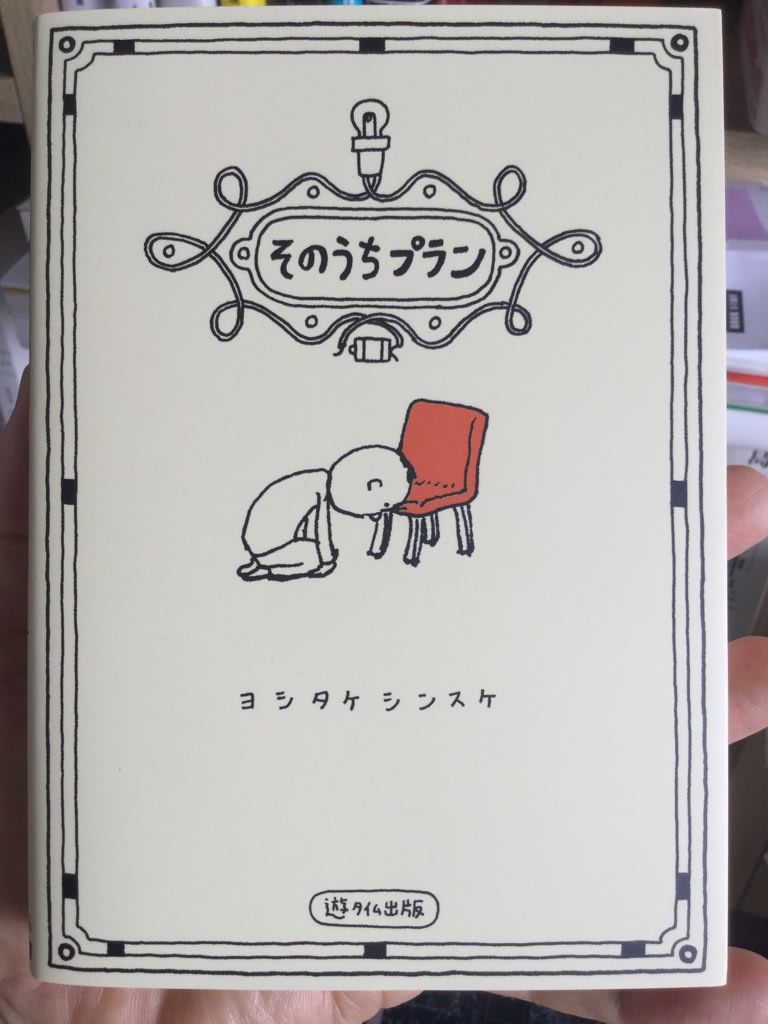

「荘重なラルゴで始まったのが、アンダンテ、アレグロを経て、プレスティシモになったと思うと、急激なデクレスセンドで哀れに淋しいフィナーレに移っていく」
「西洋の学者の掘り散らした跡へ、はるばる遅ればせに鉱石のかけらを捜しに行くもいいが、我々の足元に埋もれている宝をも忘れてはならないと思う」
「蠅が黴菌を撒き散らす。そうして我々は、知らずに年中少しずつそれらの黴菌を吸い込み呑み込んでいるために自然にそれらに対する抵抗力を我々の体中に養成しているのかもしれない。そのおかげで、何かの機会に蠅以外の媒介によって多量の黴菌を取り込んだときでも、それに堪えられるだけの資格がそなわっているのかもしれない」
「例えば、野獣も盗賊もない国で安心して野天や開け放しの家で寝ると、風邪をひいて腹をこわすかもしれない。◯を押さえると△が暴れ出す」
「もちろん、烈震の際の危険は十分わかっているが、いかなる震度の時に、いかなる場所に、いかなる程度の危険があるかということの概念がはっきりしてしまえば、無用な恐怖と狼狽との代わりに、それぞれの場合に対する臨機の処置ということがすぐ頭の中を占領してしまうのである」