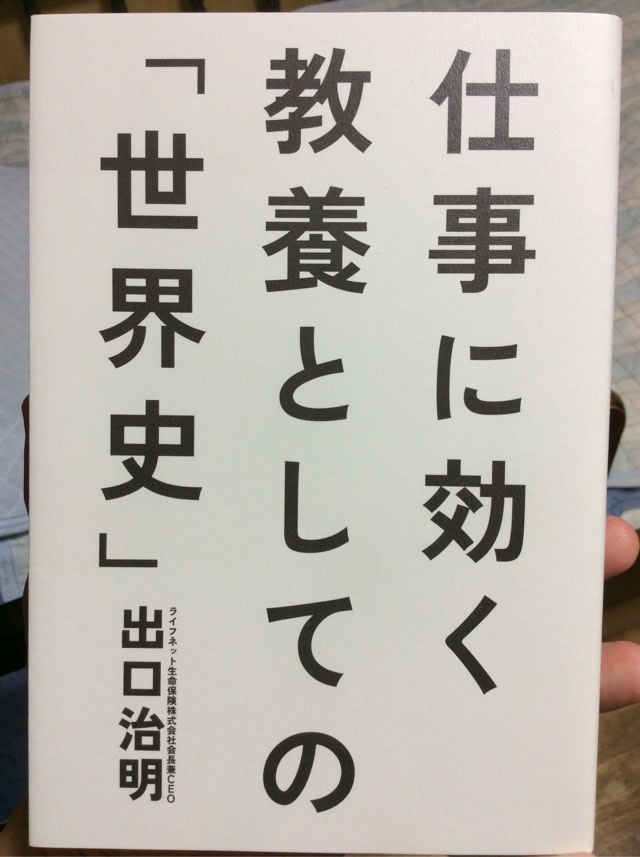『「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー』
高橋秀実著、新潮社(新潮文庫)、2014年(元本は2012年、新潮社より刊行)
毎年200人近くが東京大学に合格するという「日本一の進学校」開成高校。
その一方で、スポーツの世界での知名度はほとんどなかったというこの高校が、やにわに注目を浴びることになったのが平成17年夏のこと。この年の全国高校野球選手権大会の東東京予選で、開成高校の硬式野球部はベスト16にまで勝ち進んだのです。
しかしながら、開成野球部がグラウンドで練習できるのは、わずか週1回。それも3時間ほどの練習です。さらには、選手たちのプレイは異常なまでに下手でエラーだらけ。にもかかわらず、のベスト16進出だったのです。
「なんで開成が?」という驚きとともに、その「強さ」の秘密を探るべく開成野球部を取材したのが、独特の面白さを持ったノンフィクションで人気のある本書の著者、高橋秀実さんです。
本書は、開成野球部の監督による、野球の常識を覆すような独創的なセオリーと、下手でありながらも生真面目に野球に打ち込む選手たちの姿を、絶妙な笑いを誘う筆致で描いたノンフィクションです。
一般的な野球のセオリーは「確実に取り、確実に守る」というものですが、開成野球部のそれは相手の不意を突いて大量点を取るという、監督いわく「ドサクサに紛れて勝っちゃう」「ハイリスク・ハイリターンのギャンブル」。なので、勝つときも負けるときも大量点差のコールドゲームで「開成の野球には9回がない」のです。
一般的な野球のセオリーと同じ、普通のことをしていたらウチは絶対に勝てない、という監督に高橋さんは「開成は普通ではないんですね」と言います。すると監督は「いや、むしろ開成が普通なんです」と返して、このように語ります。
「高校野球というと、甲子園常連校の野球を想像すると思うんですが、彼らは小学生の頃からシニアチームで活躍していた子供たちを集めて、専用グラウンドなどがととのった環境で毎日練習している。ある意味、異常な世界なんです。都内の大抵の高校はウチと同じ。ウチのほうが普通といえるんです。」
わたくしは読んでいて、この言葉に妙に頷けるものがありました。
高校野球やスポーツ全般はもちろん、それ以外の分野においても、常に勝ち続けて上に行くような「勝ち組」なんてほんの一握り。その他大勢は普通、もしくは弱くて目立たない存在でしょう。そのような弱くて目立たない存在が、常勝組と渡り合うためには、普通のやり方ではダメなのだ、という考え方はとても腑に落ちるものでした。
普通のセオリーとは違うゆえ、監督は多少のエラーがあろうと動揺したりはしませんし、小賢しい野球をしようとせずに思い切って勝負にこだわることを選手たちに求めます。
「野球には教育的意義はない、と僕は思っているんです」ときっぱりと言う監督は、このように続けます。
「野球はやってもやらなくてもいいこと。はっきり言えばムダなんです」
「とかく今の学校教育はムダをさせないで、役に立つことだけをやらせようとする。野球も役に立つということにしたいんですね。でも果たして、何が子供たちの役に立つのか立たないのかなんて我々にもわからないじゃないですか。社会人になればムダなことなんてできません。今こそムダなことがいっぱいできる時期なんです」
「ムダだからこそ思い切り勝ち負けにこだわれるんです。じゃんけんと同じです」
これらの言葉も、なんだか胸に沁みてくるものがありました。ムダを排斥し、“教育的意義”なるものを強調しすぎる学校教育、さらには社会のあり方が、ともすれば子どもたちを狭い価値観の中に押し込めているのではないか•••。そんなことにも思いを巡らせてくれました。
独創的なセオリーを持つ監督のもとに集まっている選手たちも、一人一人がまた実にユニークな存在なのです。
さすが「日本一の進学校」だけあって、選手たちも頭の良い子揃いだなあ、という印象なのですが、やたら考え過ぎなところがあったりして「なにもそんなコトまで考えんでも•••」と思ってしまったりします。
「僕は球を投げるのは得意なんですが、捕るのが下手なんです」という内野(ショート)の選手に、高橋さんは「苦手なんですね」と相槌を打ちます。すると件の選手は「いや、苦手じゃなくて下手なんです」と応じます。どういうこと?と首を傾げる高橋さんに答えていわく••••••
「苦手と下手は違うんです。苦手は自分でそう思っているということで、下手は客観的に見てそうだということ。僕の場合は苦手ではないけど下手なんです」
かくのごとく珍妙なやりとりが至るところに出てくるので、読んでいて笑いを抑えることができないのですが、選手たちの野球に取り組む姿勢はあくまでも生真面目。その姿勢には素直に好感が持てます。そして、そんな選手たちの中からも、ハッとさせられるような言葉が飛び出したりします。
将来はプロ、それもメジャーリーガーになりたいという夢を語る長身の選手。「あんまりプロ向きの高校ではないよね、開成は」という高橋さんに、その選手はニヤリと笑って「逆に、開成に来たからプロになりたいと決意できたんです」と答えるのです。そのココロは••••••
「プロになる環境としては、ここは最悪じゃないですか。設備もないしグラウンドも使えないし。でもなんていうか、ここで頑張れたら、この先どこでもやっていける感じがするんです。(中略)プロって自己管理が大切だと思うんです。その点、開成はすべて自分で管理しなきゃいけない。人間関係とかじゃなくて、本当の野球の厳しさがここにあるんです」
実にまっとうな考え。これにもまた「むむむ」と唸らされましたね。ここにもまた、マイナスの状況を強みに変えようとするしたたかさがありました。
弱くても、というより「弱いからこそ」、できることがあるんだなあ。
本書を読んで、そのようなことにあらためて気づかされ、なんだか勇気が湧いてくるようでありました。
しかしそれより何より、本書は場外ホームランのようにめったやたらと面白いのです。初めから終わりまでずーっと、大笑いと含み笑いを抑えられなかったくらいで。実のところ、わたくしは高橋さんの本を読んだのは本書が初めてだったのですが、この一冊ですっかり、気になる書き手の一人となりました。
正直、こんなヘタッピな紹介文では、本書の面白さの10分の1、いや100分の1も伝えきれていないなあと、忸怩たる思いなのであります。
「とにかく面白くて楽しめることは間違いないのでどうぞお願いだからお読みくだされ!」
結局のところは、その一言に尽きるのであります。
まもなく、高校球児たちの夏が始まります。開成高校野球部にとっての2014年の夏は、いかなるものとなるのでしょうか。ちょっと楽しみな気がいたします。