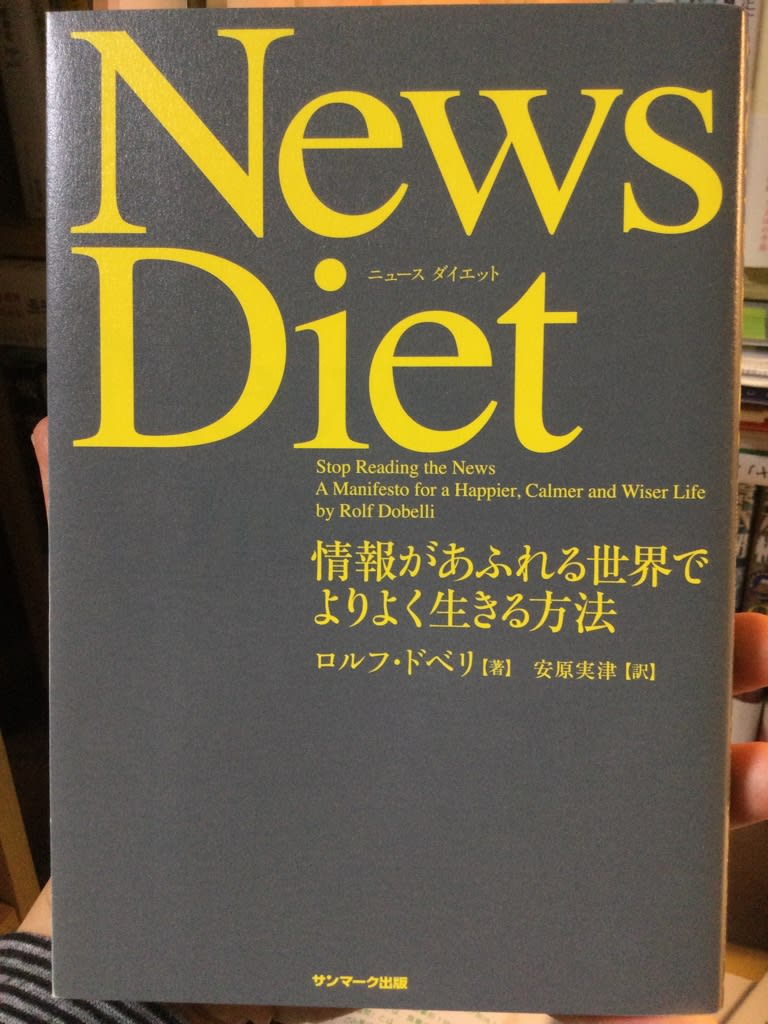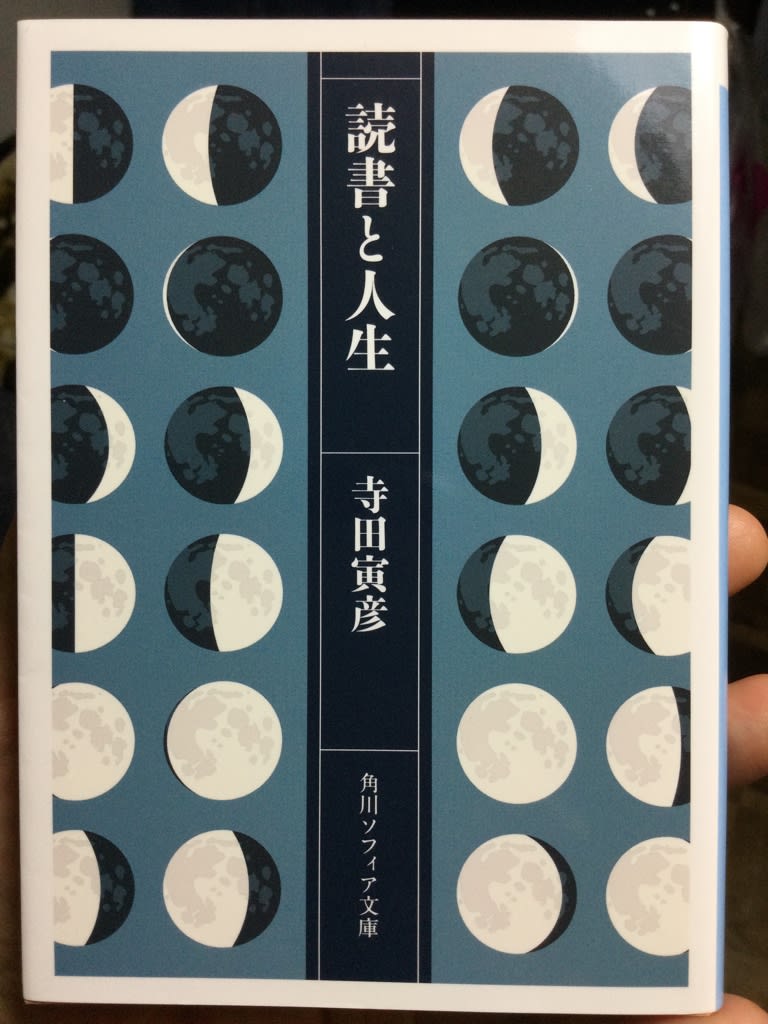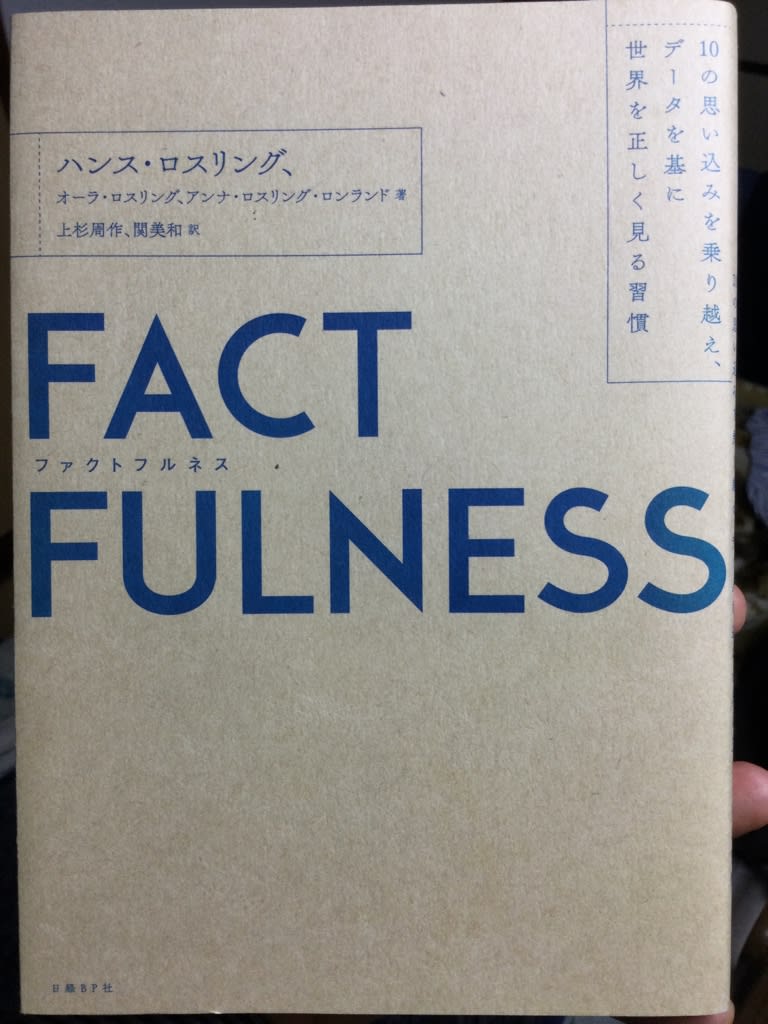『文体練習』
レーモン・クノー著、朝比奈弘治訳、朝日出版社、1996年
混雑する正午のバスの車内。編んだ紐を巻いた帽子をかぶった首の長い若い男が、隣に立っていた乗客に文句をつけ始める。誰かが横を通るたびに乱暴に身体を押してくる、というのがその理由だった。しかし、若い男はそれをすぐにやめると、慌てて空いた席に腰をかける。その2時間後、駅前の広場で再び若い男の姿を見かける。彼は連れの男から「きみのコートには、もうひとつボタンを付けたほうがいいな」というアドバイスを受けていた・・・。
「事件」と呼ぶことすら大袈裟に思えるような、そんな他愛ない出来事を、多種多様な文体や形式を駆使して書き分けていくのが、本書『文体練習』です。以前からその存在を知ってはいたのですが、遅まきながらようやく読んでみました。一読してみると、もう笑いと驚きの連続。こんなに愉快で面白く、刺激的な本と出逢えたのは、実に久しぶりのことでありました。
著者のレーモン・クノーはフランスの作家。ルイ・マル監督により映画化された『地下鉄のザジ』などの、奇想天外なユーモアに満ちた小説を発表する一方、自ら立ち上げた「ポテンシャル文学工房」、略称「ウリポ」なるグループを通じて「ことば遊びによる文学的実験の試み」(巻末の「訳者あとがき」より)を行っていたのだとか。本書『文体練習』は、その試みを代表する成果というわけなのでしょう。
本書に盛り込まれた多種多様な文体と形式は、なんと99通り。末尾に加えられている3つの「付録」まで含めると103通りもあります。出来事の一部始終を淡々と記した【1・メモ】に始まる、趣向を凝らしたことば遊びの饗宴から、一部を紹介してみますと・・・。
【2・複式記述】
「昼の十二時の正午頃(中略)公共乗合自動車バスに乗り込んで乗車した。ほぼだいたい満員でいっぱいなので・・・」という調子で、同じ意味のことばを重複させて記述したもの。
【5・遡行】
「もうひとつボタンを付けたほうがいいな、きみのコートには、と連れの男が彼に言った」から始まって、そもそもの発端であるバスの中の出来事へとさかのぼって記述。
【11・以下の単語を順に用いて文章を作れ】
「持参金 銃剣 敵 チャペル 空気 バスティーユ広場 手紙」という7つの単語を、問題の出来事の記述へ巧みに・・・というか、半ば強引に入れ込んだもの。
【14・主観的な立場から】
帽子をかぶった若い男の主観で、問題の出来事を振り返るという内容。逆に、若者に文句をつけられた男の主観から出来事を振り返る【別の主観性】や、当事者である二人以外の第三者から見た【客観的に】というのも。
【20・アナグラム】
「S統計のロバ扇子のなか、雑婚する佳人。がなひょろい首をして・・・」といった調子で、文字を並べ替えた語句によって記述。
【24・新刊のご案内】
出版社が新刊書を宣伝する案内状の形式で、問題の出来事を記述。
【27・念には念を】
「ある日の正午頃、わたしはほぼ満員のS系統のバスに乗った。ほぼ満員のそのS系統のバスには、かなり滑稽なひとりの若者が乗っていた。わたしは彼と同じバスに乗り合わせたわけだが・・・」と、文中で同じことを何度も何度もくどくど繰り返す。
【34・同一語の連続使用】
「わたしは納税義務者でいっぱいのバスに乗った。車内には、納税義務者たちが納税義務者なりの旅ができるよう便宜をはかる納税義務者がいて・・・」というふうに、〝人〟をさすことばをすべて〝納税義務者〟に置き換えたもの。
【35・語頭音消失】
「 たしは とで っぱいの スに った」というように、単語の頭の音を消して記述。バリエーションとして【語尾音消失】【語中音消失】【語頭音付加】というのも。
【41・荘重体】
ホメロスの叙事詩のごとき仰々しい文体で、問題の出来事を記述。
「曙の女神の薔薇色の指がひび割れを起こしはじめる時刻、放たれた投げ槍もかくやと思われんばかりの素早さでわたしは乗り込んだ、巨大な体軀に牝牛のごとき眼(まなこ)を備え、うねうねと蛇行する道を行くS系統の乗合バスに。・・・」
【44・コメディー】
問題の出来事を、三幕六場からなる寸劇の台本にして、台詞とト書きにより記述。
【48・哲学的】
「非蓋然的時間的偶然の本質性を現象学的精神性に提示する事は大都会にのみ可能で有る。S系統のバスと言う無意味かつ道具的な非実存的存在物中に時として身を置く哲学者は・・・」と、小難しい哲学用語を散りばめた文章。
【53・ソネット】
ヨーロッパで用いられる14行の定型詩の形式を借りて、問題の出来事を語るもの。
仏頂面に 憂鬱を 浮かべて苦虫 噛みつぶす
鼻もちならぬ 田舎者 首の長さは まるで筒
・・・・・・
【74・品詞ごとに分類せよ】
もとになっている文章を分解して、それらを助詞や名詞、形容詞、動詞などに分類して列記したもの。
【87・医学】
「ちょっとした日光療法を受けたあと、隔離の必要なしと診断されたわたしは、救急車に担ぎ込まれた・・・」といった感じで、医学に関することばで問題の出来事を記述。バリエーションとして【植物学】【食べ物】なども。
【95・幾何学】
幾何学の問題形式で出来事を記述。「方程式84x+S=yによって示される直線上を移動する直方体の内部において、人体面Aは・・・」
【99・意想外】
カフェに集まって問題の出来事を語り合う5人の仲間たちのやりとりが、最後の最後に思いがけないオチがついて終わる。
【付録2・俳諧】
問題の出来事を俳句の形に凝縮したもの。「バスに首さわぎてのちのぼたんかな」。
・・・とまあ、こんな感じなのです。他愛ないダジャレのようなのがあるかと思えば、さまざまな文体と形式を取り入れたパロディやパスティーシュ(模倣)があったり、さらにはけっこう高度な言語改変があったりと、よくぞここまで多彩なバリエーションを考えついたものであります。
語られていることは同じであるはずなのに、語り口や形式を変えることで一つの出来事が違う相貌を見せていく・・・。ことばの持つ面白さとスゴさには笑かされたり、うーむそうくるかあと感心させられたりすることしきりでした。
本書のユニークな趣向もさることながら、これを実に巧みに、ときにはアクロバティックな離れ業を駆使しながら翻訳した訳者の朝比奈弘治さんの力量にも、またつくづく唸らされます。
本書の巻末には、朝比奈さんによる長めの「訳者あとがき」が付されているのですが、本書を日本語に訳す上での苦労や工夫が存分に語られていて、これもまた面白い読みものとなっています。本書には、原文をそのまま訳しても無意味になる部分や、そもそも翻訳自体が不可能な箇所がたくさんあったそうで、それらについては対応する別の日本語に「置き換え」たり、時には原文とはまったく違う形式を借用したりもしたのだとか。
たとえば【古典的】と題された断章。これはギリシア語系の単語や語根をふんだんに使った「きわめて意味の捉えにくい衒学的で気取った文体」で書かれていて、そのままでは訳しようがなかったので、「昼は、バス。満員のころはさらなり。やうやう乗り込んだデッキぎは、人あまたひしめきて・・・」と、『枕草子』の文体を使って訳したのだとか。また、【いんちき関西弁】という断章の原文はフランス語とイタリア語の混合文体という、これまた翻訳不可能なものだったので、東京かどこかの人間が関西弁らしきものを真似ているという設定のもと、「お昼ごろやったかいなあ、バスのうしろん方にデッキいうもんが付いてまっしゃろ」という文体で訳したそうな。
朝比奈さんは、このように一筋縄ではいかなかった本書の翻訳は「フランス語以上に日本語を探検する良い機会になった」といい、「日本語は相当に奥の深い柔軟なことばである」ことを実感したと語ります。翻訳という営為が、単に異なる言語を同じ意味を持つ別の言語に移し替えるだけにとどまらないということ、そして優れた翻訳者は語学に堪能なだけではなく、日本語をよく理解し巧みに使いこなせる人でもあるんだなあ・・・ということを、本書の「訳者あとがき」で認識することができました。
そして、視覚的な美しさと遊びごころを兼ね備えた、仲條正義さんによる凝った造本とレイアウトも、本書をさらに愉しいものにしています。
文字の一部が大きくなっていたり、フォントが別のものになっていたり、赤く印刷されていたり。そうかと思えば文末の活字があらぬ方向に飛んで行ったり、ページの文字列全体が傾いていたり・・・。同じことをくどくどと繰り返す【念には念を】では、章番号も「27・27・27」とくり返しているだけでなく、ページ数のノンブルまで、ごていねいに3回ずつくり返しになっております。本体価格3398円とちょっと高めな本書ですが、ここまで凝りまくった造りであればそれも納得だなあ、と思わされました。
内容の面白さと翻訳の妙味はもちろんのこと、紙の本でなければ味わえない愉しさにも満ちた一冊でした。これからも折にふれて取り出しては、ニヤニヤしながら読みふけることになりそうであります。