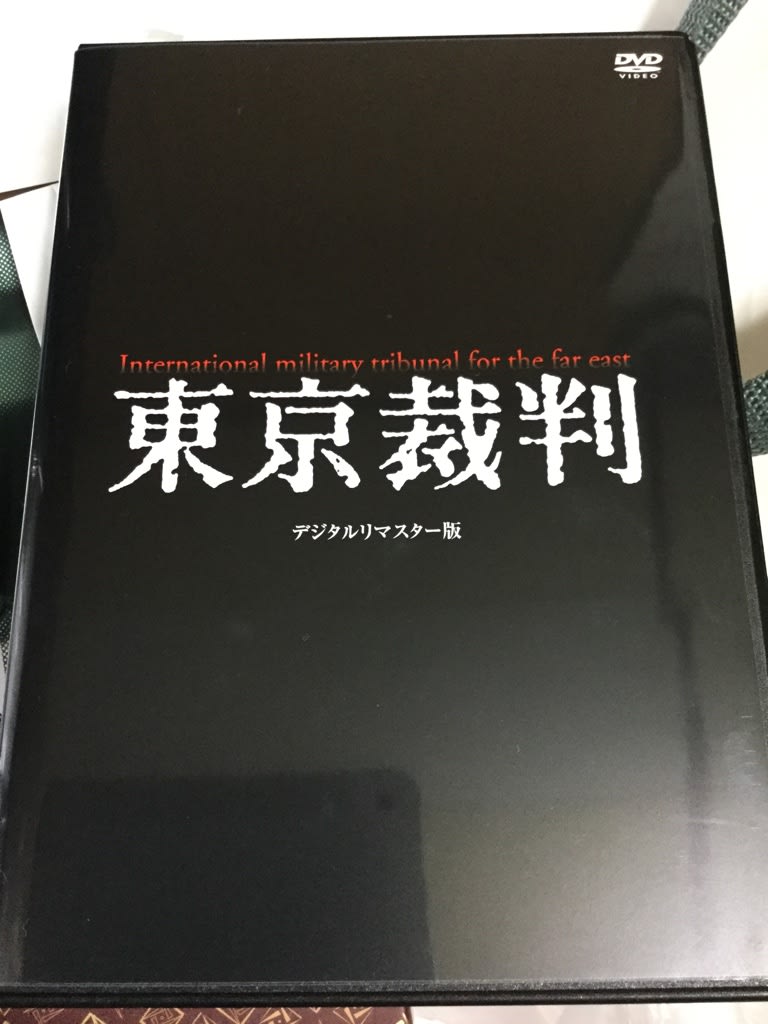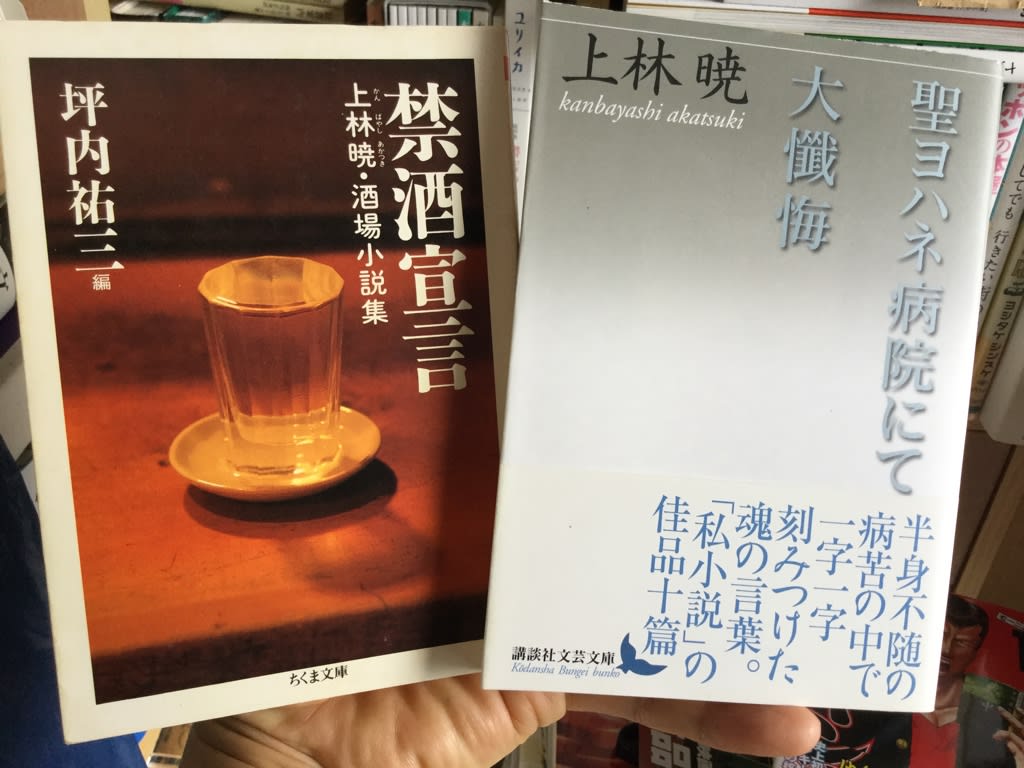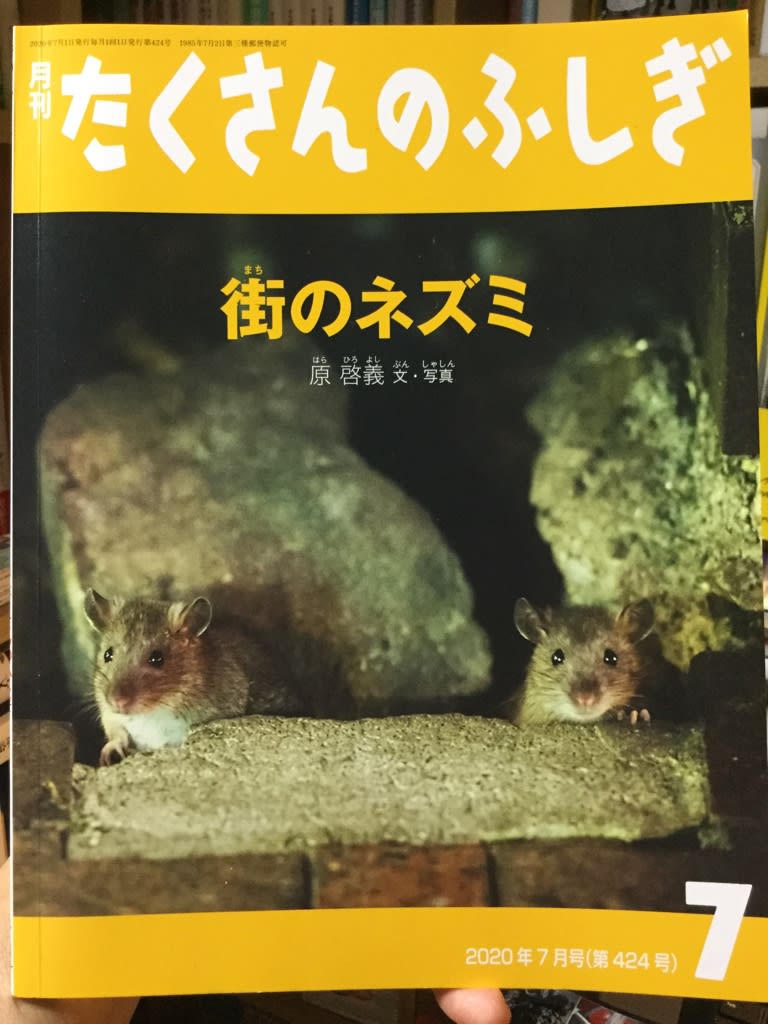『本人の人々』
南伸坊著、マガジンハウス、2003年

『本人伝説』

『本人伝説』
南伸坊著、文藝春秋、2012年(2014年に文春文庫に収録)
※現在はいずれも品切。
最近読んだ別の本についてのレビューを用意していたのですが、本日6月30日が南伸坊さんのお誕生日ということを知り、急遽手元にあったこの2冊を紹介することにいたしました。
イラストレーター、デザイナー、エッセイスト、そして路上観察学会員と、多彩な活動をされている南さんの代表的な持ち芸として知られているのが「顔マネ」。今回紹介する『本人の人々』(以下『人々』)と『本人伝説』(以下『伝説』)は、南さんが内外の著名人や、ニュースを騒がせた人たち「本人」になりきった顔マネ作品を集めています。いずれもかなり久しぶりに開いたのですが、その完成度の高さにところどころで爆笑させられました。
ロマンスグレーのカツラをかぶった「養老孟司」(『人々』)は、右手を後頭部に回して寄りかかっている格好が「本人」の雰囲気たっぷり。「椎名誠」(『人々』)は、目を細めて笑ってるところがいかにも椎名さんっぽい感じです。また「荒木経惟」(『伝説』)も、丸メガネに下唇を突き出した顔面部はもちろんのこと、似顔絵をあしらったシャツが一層「本人」らしさを引き立てております。
この2冊でひときわ完成度が高いのが「スティーブ・ジョブズ」(『伝説』)。メガネの奥からスルドイ視線を放ちながら、顎に手をやっているポーズがもうジョブズそのもので、これがジョブズの伝記の表紙に使われていてもおかしくないくらい(・・・とまでいうのはちょいと言い過ぎか)。口ひげと顎ひげをびっしりと手描きした努力(笑)を含めて、惜しみない拍手を贈りたいのであります。
完成度の高い作品が多い一方で、「安倍晋三」「土井たか子」「梅宮アンナ」「デヴィ夫人」(以上『人々』)や「ヨーコ・オノ」「澤穂希」「宮里藍」「タイガー・ウッズ」(以上『伝説』)などといった、力技・・・というより若干の強引さやムリヤリ感のある作品もあったりいたしますが、それはそれでなんだか味があって笑えてしまいます。なかでも「浅田真央」(『伝説』)は、髪の毛を手描きしたバレバレのカツラと、片脚を持ち上げたビールマンスピン(をかたどった小道具)で真央ちゃん「本人」を表現した「強引すぎる傑作」といってもいい作品になっております。
そのときどきのニュースな人たちが多く取り上げられていることもあって、今ではすっかり忘れ去られてしまったヒトも見受けられます。「大神源太」「アニータ」「タマちゃん」(以上『人々』)という面々を久しぶりに思い出して、「ああ今ごろ元気でいるのかねえこのヒトたちは・・・」と、時の経過の早さに思いを馳せたりいたしました(というか、タマちゃんはそもそもヒトですらないんだけど)。「水嶋ヒロ」(『伝説』)もひと頃はすごく人気者だったけど、最近はとんと見なくなったなあ。『KAGEROU』以降小説を発表したという話も聞かないし。
というわけでこの2冊は、顔マネを楽しめるのみならず、2000年から2010年代はじめにかけてのニュース人名録という側面もあったりいたします。
この2冊には顔マネ写真とともに、それぞれの人物の文体や発言を模写した短文も添えられております。こちらもけっこう笑えるのですが、とりわけ傑作なのが「鈴木宗男」(『人々』)。顔マネのほうはまずまずなのですが、発言の模写がもういかにもムネオっぽいのです。試しに一節を引いておきますと・・・
イラストレーター、デザイナー、エッセイスト、そして路上観察学会員と、多彩な活動をされている南さんの代表的な持ち芸として知られているのが「顔マネ」。今回紹介する『本人の人々』(以下『人々』)と『本人伝説』(以下『伝説』)は、南さんが内外の著名人や、ニュースを騒がせた人たち「本人」になりきった顔マネ作品を集めています。いずれもかなり久しぶりに開いたのですが、その完成度の高さにところどころで爆笑させられました。
ロマンスグレーのカツラをかぶった「養老孟司」(『人々』)は、右手を後頭部に回して寄りかかっている格好が「本人」の雰囲気たっぷり。「椎名誠」(『人々』)は、目を細めて笑ってるところがいかにも椎名さんっぽい感じです。また「荒木経惟」(『伝説』)も、丸メガネに下唇を突き出した顔面部はもちろんのこと、似顔絵をあしらったシャツが一層「本人」らしさを引き立てております。
この2冊でひときわ完成度が高いのが「スティーブ・ジョブズ」(『伝説』)。メガネの奥からスルドイ視線を放ちながら、顎に手をやっているポーズがもうジョブズそのもので、これがジョブズの伝記の表紙に使われていてもおかしくないくらい(・・・とまでいうのはちょいと言い過ぎか)。口ひげと顎ひげをびっしりと手描きした努力(笑)を含めて、惜しみない拍手を贈りたいのであります。
完成度の高い作品が多い一方で、「安倍晋三」「土井たか子」「梅宮アンナ」「デヴィ夫人」(以上『人々』)や「ヨーコ・オノ」「澤穂希」「宮里藍」「タイガー・ウッズ」(以上『伝説』)などといった、力技・・・というより若干の強引さやムリヤリ感のある作品もあったりいたしますが、それはそれでなんだか味があって笑えてしまいます。なかでも「浅田真央」(『伝説』)は、髪の毛を手描きしたバレバレのカツラと、片脚を持ち上げたビールマンスピン(をかたどった小道具)で真央ちゃん「本人」を表現した「強引すぎる傑作」といってもいい作品になっております。
そのときどきのニュースな人たちが多く取り上げられていることもあって、今ではすっかり忘れ去られてしまったヒトも見受けられます。「大神源太」「アニータ」「タマちゃん」(以上『人々』)という面々を久しぶりに思い出して、「ああ今ごろ元気でいるのかねえこのヒトたちは・・・」と、時の経過の早さに思いを馳せたりいたしました(というか、タマちゃんはそもそもヒトですらないんだけど)。「水嶋ヒロ」(『伝説』)もひと頃はすごく人気者だったけど、最近はとんと見なくなったなあ。『KAGEROU』以降小説を発表したという話も聞かないし。
というわけでこの2冊は、顔マネを楽しめるのみならず、2000年から2010年代はじめにかけてのニュース人名録という側面もあったりいたします。
この2冊には顔マネ写真とともに、それぞれの人物の文体や発言を模写した短文も添えられております。こちらもけっこう笑えるのですが、とりわけ傑作なのが「鈴木宗男」(『人々』)。顔マネのほうはまずまずなのですが、発言の模写がもういかにもムネオっぽいのです。試しに一節を引いておきますと・・・
「あるいはマタ私のカオを、ですね。攻撃するマスコミもありました。私の顔はアホの坂田だと、こーいう一方的なですね、きめつけをしておいて証拠は一円も出さない。私の顔のどこが、ドコとドコとドコが一体アホですか、具体的にですね、何平方センチ、ここからここまでアホだと明確にしてもらわないとですね、私は困ります」
もうこのくだりを読んでると、ムネオ氏のあの声と口調が頭の中いっぱいに響いてくるようなリアル感があって、ひたすら爆笑でありました。
こういうのを「バカバカしい」と軽視することは容易いでしょう。ですが、バカバカしいことを手抜きすることなく、とことん突き詰めてやるということは、しっかりとした知性の持ち主でなければなし得ないことではないでしょうか。その意味でも、シンボーさんは尊敬に値する知的遊戯の達人だと、あらためて思います。
シンボーさんはこの2冊のほかにも顔マネ本を何冊か出しておられる(註)のですが、今回紹介した2冊を含めてすべて品切、および絶版となっていることが実に残念、かつ遺憾であります。
どこか奇特な出版社が、シンボーさんの顔マネを集大成した全集を出してくれないものかなあ。出してくれればちょっとぐらい高くても買うぞ。
(註)
以下、刊行順に列挙しておきますと・・・
『みなみしんぼうのそっくりアルバム』(白夜書房、1996年)
『歴史上の本人』(日本交通公社、1997年。2000年に朝日文庫に収録)
『本人遺産』(文藝春秋、2016年)