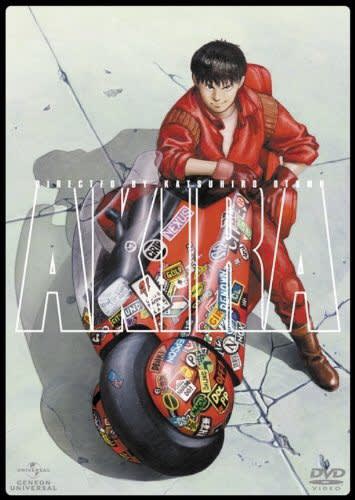7月13日(日曜日)、ついに最終日を迎えた第20回宮崎映画祭。この日は4本の作品を鑑賞いたしました。
まず最初に観たのは、東京藝術大学大学院映像研究科の修了作品として製作された『神奈川芸術大学映像学科研究室』です。
『神奈川芸術大学映像学科研究室』 (2013年 日本)
監督=坂下雄一郎
主演=飯田芳、笠原千尋、前野朋哉
神奈川芸術大学映像学科で助手を務めている主人公の青年、奥田。自らの保身に汲々とする大学のお偉いさんたちと、ひたすら自己中心的な学生たちとの板挟みになりつつも、淡々と雑務をこなす日々が続いていた。そんな中、3人の学生が備品の撮影機材を盗み出そうとして失敗し、機材を破損させるという事件が起こる。例によって自らの体面ばかりを優先させるお偉いさんの指示により、奥田はウソの報告書を書いて庶務課に提出したのだったが•••。
大学院の学生たちによる修了作品ながら、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013の長編部門で審査員特別賞を受賞し、新宿の映画館でレイトショー公開もされたという本作。まるで自分たちが属していた世界をカリカチュアライズしたかのような(冒頭には「この映画の内容はフィクションである」旨の断り書きがありましたが)内容にもビックリだったのですが、何より観る者をしっかりと楽しませてくれる手堅いつくりに感心いたしました。
妙にキャラ立ちした脇の登場人物たちも面白く、とりわけ、大学人というよりヤクザ様のような学科長のキャラは最高でした。
2本目からは、「黒沢清の映画塾」と題して、前日の『CURE』の上映に続き、黒沢清監督をゲストにお迎えしてのトークショーつきの上映でした。まずは、スティーヴン・スピルバーグ監督の代表作にして、『スター・ウォーズ』(エピソード4 「新たなる希望」)とともに、1970年代後半のSF映画ブームの牽引役となった傑作『未知との遭遇 特別編』を観て、スピルバーグ作品について語るという趣向です。
『未知との遭遇 特別編』 (1980年 アメリカ、オリジナルは1977年、その後2002年には「ファイナル・カット版」も)
監督・脚本=スティーヴン・スピルバーグ
撮影=ヴィルモス・ジグモンド
音楽=ジョン・ウイリアムズ
特殊視覚効果=ダグラス・トランブル
主演=リチャード・ドレイファス、フランソワ・トリュフォー、テリー・ガー、メリンダ・ディロン
第二次世界大戦中に行方不明になっていたはずの戦闘機が、突如メキシコの砂漠に現れる。さらにゴビ砂漠には、やはり行方不明になっていた貨物船が出現。時を同じくして、アメリカの各地で謎の発光体が目撃され、原因不明の大停電が起こる。その復旧に向かっていた電気技師のロイ・ニアリーは、光を放ちながら飛行するUFOに遭遇。以来、ロイは取り憑かれたようにどこかの山の形を思い描くようになる。
家の中に侵入した「何か」を追いかける息子を連れ戻そうとした女性、ジリアンも、謎の発光体に遭遇したことでロイと同じように山の形を思い描く。しかし、再び現れた発光体により息子は連れ去られてしまう。
フランス人学者のラコームは、謎の現象を分析する中で異星人からのコンタクトを確信、「彼ら」との接触を図るためのプロジェクトを進めていく。一方、思い描いていた形の山の場所を突き止めたロイとジリアンは、ラコームたちのプロジェクトの拠点がある「デビルズ・タワー」へと向かうのであった•••。
テレビやビデオで観て以来、かなり久しぶりの「遭遇」となった本作。クライマックスである、異星人たちの巨大なUFOの母船が現れる場面に、鳥肌ものの感激を覚えました。母船はミニチュアで表現されたものですが(特撮は『2001年宇宙の旅』や『ブレードランナー』なども手がけたダグラス・トランブル)、スクリーンで観るそれはミニチュアであることを忘れさせるようなスケール感があり、CG全盛の現在の目で観ても十分に迫力を感じました。
どうしても後半の華麗な特撮場面に目を奪われがちになるのですが、そこに至るまでのドラマづくりや盛り上げかたの巧みさも、今回じっくりと味わうことができました。製作当時、スピルバーグ監督はまだ30歳ぐらいだったようですが、それでこれだけ巧みな映画づくりをしていたということに、「やっぱり凄い監督だなあ」ということをつくづく感じさせられました。
上映後の黒沢清監督によるトークショーでは、「白いスピルバーグ」と「黒いスピルバーグ」というキーワードでこれまでの作品群を分析。『シンドラーのリスト』(1993年)を境に、表現技法も作品の内容も大きく変化したことが論じられました。そして黒沢監督はスピルバーグ監督について、「あれだけヒットメーカーとしての地位を得ていながら、自分の殻を打ち破ろうとチャレンジを続ける探究心を持った優れた映画監督」と評価されていました。
「単なる娯楽映画の監督」だの「ピーターパン監督」だのというイメージを持たれがちなスピルバーグ監督ですが、その作品の新たな見方、味わい方を教えられたように思いました。また、過去のいろいろなスピルバーグ作品を見直したくなってまいりました。
続く上映作は、黒沢監督自身による短篇
『ビューティフル・ニュー・ベイエリア・プロジェクト』と『Seventh Code』の2本立てでありました。
『ビューティフル・ニュー・ベイエリア・プロジェクト』 (2013年 日本)
監督・脚本=黒沢清
主演=三田真央、柄本佑、森下じんせい
湾岸地域の開発に携わっている会社の若社長は、開発現場で男たちに混じって働いている女性に一目惚れしてしまう。若社長は女性に思いを打ち明けるが、彼女の態度はあくまで冷淡だった。業を煮やした若社長は、女性が大切にしているモノを奪って逃走する。若社長の会社に単身乗り込んだ女性の前に、屈強な警備員たちが立ちはだかった•••。
黒沢監督も教授として関わっている、東京藝術大学大学院映像研究科の修了作品として製作されながら、監督を務めるはずだった学生が監督できなくなってしまい、急遽黒沢監督ご自身で監督したという本作は、黒沢監督初の格闘アクションでもあります。
わずか30分ほどの短篇でしたが、まるで香港映画を思わせるようなキレの良いアクションで、オトコどもを次々となぎ倒していくヒロインの姿が、実に痛快かつ「ビューティフル」で大いに楽しめました。一方で、どうしようもないボンボン社長を演じた柄本佑さんもいい味を出しておりました。
『Seventh Code セブンスコード』 (2013年 日本)
監督・脚本=黒沢清
主演=前田敦子、鈴木亮平
東京で出逢った松永という男のことが忘れられないヒロインの秋子は、ロシアのウラジオストクで松永と再会するが、松永は「外国では絶対に人を信じるな」と言い残して姿を消してしまう。日本人が経営する食堂で働きながら松永を探す秋子の前に、松永が乗った車が現れる。それを追った秋子は廃工場に辿り着くが、そこはマフィアの取り引き場所であった•••。
前田敦子さんのシングル曲のプロモーションのために製作された60分の作品ですが、謎めいた展開にはグイグイと引き込まれ、しっかりとした「映画」として楽しめる作品でありました(現に本作、昨年のローマ国際映画祭にて監督賞と技術貢献賞に輝いてもいます)。
主演をこなした前田さんも思いのほか魅力的で、これまで単にアイドルとしてしか認識していなかった前田さんを、初めて「女優」として認識することができました。そして終わってみれば、本作も『ビューティフル~』と同様、「強いヒロインの映画」だったのでありました。
2本立て終了後のトークショー。『Seventh Code』の舞台がウラジオストクになったことについて黒沢監督は、企画の秋元康さんから「ロシアなんていいのでは」との提案があったことに加え、日本から近いこともあってウラジオストクに決まった、という話を披露。ヒロインを演じた前田さんについては、「一見目立たないんだけど、それでいて人の目を引くようなところがある」と表しておられました。
すべてのトークショーを終えて挨拶をなさった黒沢監督は、「これまで4回行った映画祭はカンヌ、トロント、ロッテルダム、そして宮崎」とおっしゃってくださいました。
そうなのです。国際的に注目される存在でありながらも、市民ボランティアによる手作り感溢れる宮崎映画祭にも度々足を運んでくださる黒沢監督に、宮崎の人間の端くれとして、あらためて畏敬と感謝の念が湧いてきました。
同時に、黒沢監督にそこまで足を運んでいただけるような映画祭を、20年かけて続けてきた映画祭の実行委員やスタッフの皆さまにも、また畏敬と感謝の念が湧いてきたのであります。
こうして、第20回宮崎映画祭は幕を閉じました。
今回鑑賞したのは11作品。昨年の13作品からは少し減ってしまいましたが、それでも十分に楽しむことができました。
今年は台風の接近もあったりして、実行委員やスタッフの皆さまには例年以上に気の抜けないところがあったのではないかと思います。
しかし、わたくしが鑑賞したどの回にも、実にたくさんの観客が集まっていて(満員というのも2回ありました)、この映画祭が多くの宮崎市民から愛され、期待されているということをあらためて実感いたしました。
これからも、多くの人たちから愛される映画祭であり続けることを、心から願ってやみません。
実行委員やスタッフの皆さま、長丁場本当にお疲れ様でした!そして、ありがとうございました!
終了後、物販コーナーにて黒沢監督のご著書『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ』(蓮實重彦さんとの共著、青土社)を購入いたしました。そして、それにしっかり、黒沢監督からのサインを頂戴することができました。

これは家宝として大切にさせていただきます。黒沢監督、本当にありがとうございました!
まず最初に観たのは、東京藝術大学大学院映像研究科の修了作品として製作された『神奈川芸術大学映像学科研究室』です。
『神奈川芸術大学映像学科研究室』 (2013年 日本)
監督=坂下雄一郎
主演=飯田芳、笠原千尋、前野朋哉
神奈川芸術大学映像学科で助手を務めている主人公の青年、奥田。自らの保身に汲々とする大学のお偉いさんたちと、ひたすら自己中心的な学生たちとの板挟みになりつつも、淡々と雑務をこなす日々が続いていた。そんな中、3人の学生が備品の撮影機材を盗み出そうとして失敗し、機材を破損させるという事件が起こる。例によって自らの体面ばかりを優先させるお偉いさんの指示により、奥田はウソの報告書を書いて庶務課に提出したのだったが•••。
大学院の学生たちによる修了作品ながら、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2013の長編部門で審査員特別賞を受賞し、新宿の映画館でレイトショー公開もされたという本作。まるで自分たちが属していた世界をカリカチュアライズしたかのような(冒頭には「この映画の内容はフィクションである」旨の断り書きがありましたが)内容にもビックリだったのですが、何より観る者をしっかりと楽しませてくれる手堅いつくりに感心いたしました。
妙にキャラ立ちした脇の登場人物たちも面白く、とりわけ、大学人というよりヤクザ様のような学科長のキャラは最高でした。
2本目からは、「黒沢清の映画塾」と題して、前日の『CURE』の上映に続き、黒沢清監督をゲストにお迎えしてのトークショーつきの上映でした。まずは、スティーヴン・スピルバーグ監督の代表作にして、『スター・ウォーズ』(エピソード4 「新たなる希望」)とともに、1970年代後半のSF映画ブームの牽引役となった傑作『未知との遭遇 特別編』を観て、スピルバーグ作品について語るという趣向です。
『未知との遭遇 特別編』 (1980年 アメリカ、オリジナルは1977年、その後2002年には「ファイナル・カット版」も)
監督・脚本=スティーヴン・スピルバーグ
撮影=ヴィルモス・ジグモンド
音楽=ジョン・ウイリアムズ
特殊視覚効果=ダグラス・トランブル
主演=リチャード・ドレイファス、フランソワ・トリュフォー、テリー・ガー、メリンダ・ディロン
第二次世界大戦中に行方不明になっていたはずの戦闘機が、突如メキシコの砂漠に現れる。さらにゴビ砂漠には、やはり行方不明になっていた貨物船が出現。時を同じくして、アメリカの各地で謎の発光体が目撃され、原因不明の大停電が起こる。その復旧に向かっていた電気技師のロイ・ニアリーは、光を放ちながら飛行するUFOに遭遇。以来、ロイは取り憑かれたようにどこかの山の形を思い描くようになる。
家の中に侵入した「何か」を追いかける息子を連れ戻そうとした女性、ジリアンも、謎の発光体に遭遇したことでロイと同じように山の形を思い描く。しかし、再び現れた発光体により息子は連れ去られてしまう。
フランス人学者のラコームは、謎の現象を分析する中で異星人からのコンタクトを確信、「彼ら」との接触を図るためのプロジェクトを進めていく。一方、思い描いていた形の山の場所を突き止めたロイとジリアンは、ラコームたちのプロジェクトの拠点がある「デビルズ・タワー」へと向かうのであった•••。
テレビやビデオで観て以来、かなり久しぶりの「遭遇」となった本作。クライマックスである、異星人たちの巨大なUFOの母船が現れる場面に、鳥肌ものの感激を覚えました。母船はミニチュアで表現されたものですが(特撮は『2001年宇宙の旅』や『ブレードランナー』なども手がけたダグラス・トランブル)、スクリーンで観るそれはミニチュアであることを忘れさせるようなスケール感があり、CG全盛の現在の目で観ても十分に迫力を感じました。
どうしても後半の華麗な特撮場面に目を奪われがちになるのですが、そこに至るまでのドラマづくりや盛り上げかたの巧みさも、今回じっくりと味わうことができました。製作当時、スピルバーグ監督はまだ30歳ぐらいだったようですが、それでこれだけ巧みな映画づくりをしていたということに、「やっぱり凄い監督だなあ」ということをつくづく感じさせられました。
上映後の黒沢清監督によるトークショーでは、「白いスピルバーグ」と「黒いスピルバーグ」というキーワードでこれまでの作品群を分析。『シンドラーのリスト』(1993年)を境に、表現技法も作品の内容も大きく変化したことが論じられました。そして黒沢監督はスピルバーグ監督について、「あれだけヒットメーカーとしての地位を得ていながら、自分の殻を打ち破ろうとチャレンジを続ける探究心を持った優れた映画監督」と評価されていました。
「単なる娯楽映画の監督」だの「ピーターパン監督」だのというイメージを持たれがちなスピルバーグ監督ですが、その作品の新たな見方、味わい方を教えられたように思いました。また、過去のいろいろなスピルバーグ作品を見直したくなってまいりました。
続く上映作は、黒沢監督自身による短篇
『ビューティフル・ニュー・ベイエリア・プロジェクト』と『Seventh Code』の2本立てでありました。
『ビューティフル・ニュー・ベイエリア・プロジェクト』 (2013年 日本)
監督・脚本=黒沢清
主演=三田真央、柄本佑、森下じんせい
湾岸地域の開発に携わっている会社の若社長は、開発現場で男たちに混じって働いている女性に一目惚れしてしまう。若社長は女性に思いを打ち明けるが、彼女の態度はあくまで冷淡だった。業を煮やした若社長は、女性が大切にしているモノを奪って逃走する。若社長の会社に単身乗り込んだ女性の前に、屈強な警備員たちが立ちはだかった•••。
黒沢監督も教授として関わっている、東京藝術大学大学院映像研究科の修了作品として製作されながら、監督を務めるはずだった学生が監督できなくなってしまい、急遽黒沢監督ご自身で監督したという本作は、黒沢監督初の格闘アクションでもあります。
わずか30分ほどの短篇でしたが、まるで香港映画を思わせるようなキレの良いアクションで、オトコどもを次々となぎ倒していくヒロインの姿が、実に痛快かつ「ビューティフル」で大いに楽しめました。一方で、どうしようもないボンボン社長を演じた柄本佑さんもいい味を出しておりました。
『Seventh Code セブンスコード』 (2013年 日本)
監督・脚本=黒沢清
主演=前田敦子、鈴木亮平
東京で出逢った松永という男のことが忘れられないヒロインの秋子は、ロシアのウラジオストクで松永と再会するが、松永は「外国では絶対に人を信じるな」と言い残して姿を消してしまう。日本人が経営する食堂で働きながら松永を探す秋子の前に、松永が乗った車が現れる。それを追った秋子は廃工場に辿り着くが、そこはマフィアの取り引き場所であった•••。
前田敦子さんのシングル曲のプロモーションのために製作された60分の作品ですが、謎めいた展開にはグイグイと引き込まれ、しっかりとした「映画」として楽しめる作品でありました(現に本作、昨年のローマ国際映画祭にて監督賞と技術貢献賞に輝いてもいます)。
主演をこなした前田さんも思いのほか魅力的で、これまで単にアイドルとしてしか認識していなかった前田さんを、初めて「女優」として認識することができました。そして終わってみれば、本作も『ビューティフル~』と同様、「強いヒロインの映画」だったのでありました。
2本立て終了後のトークショー。『Seventh Code』の舞台がウラジオストクになったことについて黒沢監督は、企画の秋元康さんから「ロシアなんていいのでは」との提案があったことに加え、日本から近いこともあってウラジオストクに決まった、という話を披露。ヒロインを演じた前田さんについては、「一見目立たないんだけど、それでいて人の目を引くようなところがある」と表しておられました。
すべてのトークショーを終えて挨拶をなさった黒沢監督は、「これまで4回行った映画祭はカンヌ、トロント、ロッテルダム、そして宮崎」とおっしゃってくださいました。
そうなのです。国際的に注目される存在でありながらも、市民ボランティアによる手作り感溢れる宮崎映画祭にも度々足を運んでくださる黒沢監督に、宮崎の人間の端くれとして、あらためて畏敬と感謝の念が湧いてきました。
同時に、黒沢監督にそこまで足を運んでいただけるような映画祭を、20年かけて続けてきた映画祭の実行委員やスタッフの皆さまにも、また畏敬と感謝の念が湧いてきたのであります。
こうして、第20回宮崎映画祭は幕を閉じました。
今回鑑賞したのは11作品。昨年の13作品からは少し減ってしまいましたが、それでも十分に楽しむことができました。
今年は台風の接近もあったりして、実行委員やスタッフの皆さまには例年以上に気の抜けないところがあったのではないかと思います。
しかし、わたくしが鑑賞したどの回にも、実にたくさんの観客が集まっていて(満員というのも2回ありました)、この映画祭が多くの宮崎市民から愛され、期待されているということをあらためて実感いたしました。
これからも、多くの人たちから愛される映画祭であり続けることを、心から願ってやみません。
実行委員やスタッフの皆さま、長丁場本当にお疲れ様でした!そして、ありがとうございました!
終了後、物販コーナーにて黒沢監督のご著書『東京から 現代アメリカ映画談義 イーストウッド、スピルバーグ、タランティーノ』(蓮實重彦さんとの共著、青土社)を購入いたしました。そして、それにしっかり、黒沢監督からのサインを頂戴することができました。

これは家宝として大切にさせていただきます。黒沢監督、本当にありがとうございました!