http://www.cismor.jp/jp/lectures/2003/documents/report031002a.pdf
日本でキリスト者として生きるときに、仏教や神道など他宗教とその慣習にたいしてどう関わるかが問われます。これは世界的にみるとユダヤ教イスラム教との関わり方にも通じるものです。
最近、日本の神道は、ユダヤ教、旧約聖書の影響を受けていることが言われ始めています。グローバル化とIT革命のおかげで古くからの国際交流の事実が明らかにされつつあるからでしょう。
フルベッキ写真について考えてみますと、さまざまな視点から研究されています。
中でも明治天皇すり替え説という仮説には鹿島史観、日本ユダヤ同祖論、ダビンチ・コードとフリーメイソンそして吉田松陰や伊藤博文、桂小五郎忍者説などの諸説がおりまぜられています。
鹿島史学を支持される松重氏意外にもはマルクス唯物論にも造詣が深い方です。原始キリスト教時代ユダヤ教はキリスト教を迫害する側でしたがヨーロッパが次々とキリスト教化されるとともにユダヤ人たちはその行き場を失っていきました。その反感のなかで反キリスト思想である唯物弁証論が生まれ、ロシア革命においてトロツキーたちユダ人のリーダーが開花させました。
サドカイ派に近いユダヤ教はもともと、「霊や天使、復活」を認めませんでした。ですから復活主を伝えるパウロの宣教の最も手ごわい相手はこの人々でした。
日本宣教の困難な理由の一つに、このような日本の宗教的底流があるのでしょうか。キリスト教とユダヤ教は対決しなければならないのか対話路線を歩むべきなのか、それは日本伝道にもリンクしているといえましょう。
幕末明治の宣教の初め、新派カルヴァン主義と旧派カルヴァン主義の二つの潮流があったことを「二つの福音は波濤を越えて」の中で著者棚村重明氏が指摘され、前者の対話型に対して後者の対決型の神学について触れています。
http://holyspirit.blog.ocn.ne.jp/mmm/2010/06/post_ee67.html
これは20世紀の代表的神学者、カールバルトとパウルティリッヒの論争にも引き継がれているといえるでしょう。
さらには自然神学をめぐるバルトとブルンナーの対決と対話人も通じるものかもしれません。
http://www.kwansei.ac.jp/s_sociology/kiyou/89/89-7.pdf
イスラムとの対話についてですが、マホメットの祈りの中に「神によみがえりますように」という言葉があるとしりました。
復活ということが単に肉体の再生でなく、創造主のもとに生きるという意味だとすれば、まさしく主イエスの復活を意味しており、それは聖霊の内住によってのみ可能であります。
幕末時代に戻りますが、1859年オランダ改革派から派遣されたR・S・ブラウンは新派カルヴァン派に近くフリーメイソンにも属していたといわれます。共に来日し長崎に着任したフルベッキはモラヴィアンの教育を受けブラウンとは友人でありながら信仰は旧派カルヴァン派に近く、真理のためには対決も辞さなかったといわれます。
オランダから1852年渡米したフルベッキは1855年ニューヨーク州オーバン神学校に入学した。オーバンはオンタリオ湖の南方50キロにあり、100キロ西にオンタリオの水がエリー湖に落ちるナイヤガラ大滝があります。
近くにはシラキュースの町もあり、1860年横浜に上陸したバプテストの宣教師ゴーブルはかつてシラキュースの雑貨店主に脅迫状を送って、強盗未遂罪でオーバン刑務所にⅠ846-1848年の2年間服役していました。
獄中から回心の体験を母教会に書き出所後バプテスマを受け、1851年ペリー艦隊海兵隊員となりました。
黒船で出会った仙太郎を連れて、ニューヨーク州のウェイン村に帰り、ともにハミルトンのマジソン大学に入学したのは、フルベッキがオーバン神学校に入った1855年、まったく同じ年です。
仙太郎は1858年3月主を信じてバプテスマを受けた。このニュースが同じニューヨーク州で改革派の神学校にいたフルベッキのもとに届いたかどうか記録はないようです。
主を神の御子と信じることが出来たのは聖霊の光に照らされたからでした。超越者でもある創造主がこの世に介入されることによる奇跡の出来事です。
カールバルトも旧カルヴァン派も、永遠の生命は自然の光ではなく、この創造主ご自身の超越の光によってもたらされたことを強調して、その意味では妥協を許さぬ対決的姿勢をとりました。創造霊である神と出会い交わるのは聖霊によって新生した霊によってのみ可能であることを確信していたからです。
しかし、地球の外からの太陽の光も、地球内部における光合成によって観察され探求されうるように、内側からあるいは下からの神学の可能性もありえます。
バルトとティリッヒの背後には「少なくとも約二千年に及ぶ長い、しかも相異なる神学史的伝統がひかえている」
と古屋安雄氏は「ティリッヒのキリスト教史的バルト解釈」(歴史の神学シンポジウム・山本和編)で述べています。
ティリッヒは「私自身は神秘主義者ではないが、それにもかかわらず経験の神学および内面性の神学を主張する人々の側に立っている。なぜなら私は、神の霊がわれわれのなかに生きていると信じるからである。聖霊の概念は、外から到来する神の言葉とわれわれ内奥において実現する宗教的経験とのあいだの最高の総合を含んでいる。」と語り、「自分とバルトとの対立、人間の内からの神学と、人間の外からの神学との相克は、聖霊の概念によって和解可能だ」と考えました。
他方バルトはこう語るようになりました。(「神学者カール・バルト」J・ファングマイアー
加藤常昭、蘇光正共訳(日本基督教団出版局)「シュライエルマッハーとわたし」(ページ135-138)
「それは、第三項の神学、つまり、支配的に、決定的に、聖霊の神学なるものの可能性であったといえよう。第一項と第二項の理解するところに従い、父なる神と、子なる神とについて信じ、考え、語らなければならないすべてのことは、父と子との間の絆Vinclum pacis inter Patrem et Filium である聖霊なる神によって基礎づけられて、明らかにされ、光を受けなければならないだろう。
被造物に対する神のわざの全体、人間のための、人間の中での、人間と共になされる神のわざの全体は、聖霊の神学、いっさいの偶然性を排除する神学において明らかにされうるであろう。
私が本能的に、『教会教義学』の第四巻の一から三までで、少なくとも教会を、それから信仰と愛と希望を、明瞭に聖霊のしるしのもとにおいたのはよかった。
しかし、義認も聖化も召命も、この聖霊のもとに置かれうるし、そうしなければならなかったのではなかろうか。父なる神の固有のわざである創造については言うまでもない。
いっさいを支配するキリスト論が既に(聖霊によってみごもられ!)、聖霊論から光を受けるべきではなかったか。
神-ご自身の民には、その契約の啓示によって知られ、またそのような方としてこの世の中に宣べ伝えられる神-は、その全面にわたって、霊であられるのではないか(ヨハネ4・24、第一コリント3・17)-すなわち、ご自身に固有の自由と力と智恵と愛によって、ご自身を現在化し、ご自身を適合させてくださる神であられるのではないか。
それは例えば、私の旧友フリッツ・リーブFritz Liebを、彼自身おぼろげにこれを暗示する以上ではなかったが、その最初から波乱の多かったその生涯の晩年の何十年かを、あれほど情熱的に駆り立てたものに似ているのではなかろうか。
そしてまたそれは、今日においては、パーデルボルンPaderbornの、希望に満ちた、若いカトリックの教義学者、ヘリバート・ミューレンHeribert Mühlenが目ざしているものではないか。
いずれにせよ、すべてを最もよく解釈すれば、一種の聖霊の神学というものがシュライエルマッハーの神学的行動の、彼自身意識するのは困難であったろうが、事実上彼を支配している正当な関心事であったという可能性を、私は予想したいのである。そしてただ単に彼の神学的行動というばかりでではない。彼に先行した敬虔主義者たち、合理主義者たち(!)、
そして当然のこととして、18世紀の「低次の秩序のヘルンフート派」、さらにまた宗教改革者たちによってあれほど無理解で乱暴な扱いを受けた「熱狂主義者たち」、更に遡れば、中世紀のすべての聖霊に動かされ、あるいは深い感覚を持っていた人々、つまり、聖霊主義者と神秘主義者にとっても、このような推測は妥当するものと思いたい。本来、西および東のカトリック主義の中で教会について-そしてマリヤについて、われわれにとって快くない仕方で語られ、承認されているあの多くの事柄の中で、結局言おうとしていることは、聖霊の現実、その到来、その業であるということ、そしてこの点からして、これらのことが、積極的-批判的な光を受けるようになること、それはあり得ないことだろうか。
そうなれば、19世紀におけるシュライエルマッハーの悄然たる後継者たちや、我々の20世紀における実存主義神学者たちも(今日の悪いドイツ語の慣用で言えば-「いささかは」»in etwa«)同じことになるのではないか。そうなれば、すべての「教会と異端の歴史」が-しかし「非党派的に」ではなく、むしろ、聖霊によって集められた、唯一の、聖なる、公同の、使徒的なる教会の、いっさいを検証し、その最善のものを保持する「歴史」が、見い出され、理解され、書き記されることが可能になるであろう。・・・
誰かが『同じことを、今や人間の側から』もう一度語ることが大切だなどと考えたりすれば、私のすばらしい夢がどんなに誤解されたことになるだろう!それではシュライエルマッハーが-彼の前の時代の人も、後の時代の人も及ばない輝かしい仕方で-『人間の側から』考え、語ったりしたことこそ、彼における最も深い問題だったということが、なかったようである。」
1968年9月バルトはファングマイヤーとの最後の対話において「神学の研究をなしうるとしたら、第一にローマ・カトリック主義、その次に東方教会、そして次にキリスト教以外の諸宗教である」と語り、しかしそれに付け加えて、通常これらのものに取り掛かるのとは全く別の方法でやる。」と言った。「つまり、普遍的なものが基礎にあって、その上に、おそらくイエス・キリストが最高峰としてそびえるというのではなく、イエス・キリストが根拠であり、この根拠に依って、諸宗教と、おそらくなお全く新しい対話が開かれうるであろう。」と。(81頁)



















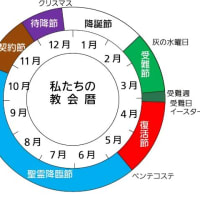







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます