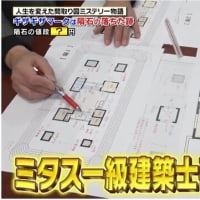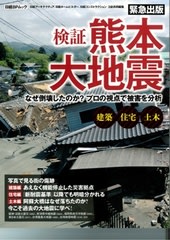
熊本大地震で被害にあわれた皆様に、お見舞い申し上げます。
熊本地震への現地検証に、2週間以上の休みが取れれば
参加できましたが、さすがにそれは無理なので、断念しました。
ニュースでは、様々な報道がなされていましたが、
建築の専門家としての検証結果も出尽くしたようです。
それらを調べて、確信が持てたので取り上げてみます。

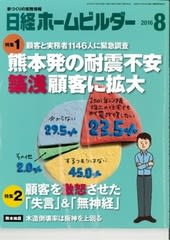
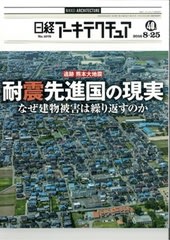
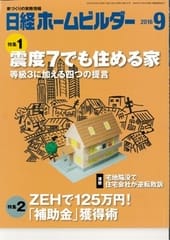

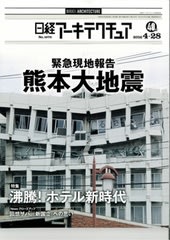
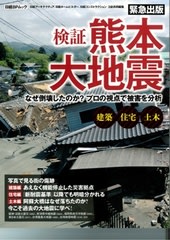
長期優良住宅や新耐震の住宅まで被害を受けて倒壊しました。
なぜでしょうか?
一般の方にわかりやすく簡単に述べるとすると、
京大の専門家チームが発表したように
建築基準法の1.5倍以上の耐力壁のある木造住宅は、
震度7クラスが連続しても問題なかった、という結論になります。
細かくいえば、もっとありますが。
ミタス一級建築士事務所の勉強会に出られた方は、
長期優良住宅の耐震性能は、通常に建築基準法を満たしていれば
耐力壁の量は確保できるので、凄くもなんともない、普通です、
という理由とカラクリを説明しているので、
何となくお分かりだと思います。
ミタス一級建築士事務所では、以前から1.5倍以上を原則とするだけでなく
偏心率も0.15以下を原則にして設計してきました。
偏心率は、耐力壁の平面的なバランスで
簡易な四分割法の手計算ではなく、
コンピューターを使って、リアルタイムで調整しながら
耐力壁の位置と強さを検討します。
しかし、このふたつは数値で出てくるので検討やチェックは客観的に可能ですが、
大切なのは、このふたつよりも、地震力の伝わり方がどうなるかです。
これは、プラン作成時に検討するアナログ的なものなので、
数値化は難しいです。
地震力が働いたときに、
屋根から2階、2階から1階、1階から基礎、基礎から地盤へと
力をどのように逃がしていくかということと、
また、その過程で接続部分が破断しないようにしなければ
なりません。
直下率とは、似ているところはありますが異なります。
偏心率とは異なり、
耐力壁の上下の位置関係と床面剛性とその配置で
普段は問題なく荷重を受けている柱と梁の接合部分を
大きな地震が起こったときに、
破断から守れるかどうかということをアナログ的に考えます。
これは、耐力壁や筋交いの配置に関係してきます。
すなわちプランの状態から考えておく必要があります。
許容応力度計算をすれば良いのではないかと専門家なら思います。
阪神大震災までは、私もそう信じてきました。
特に木造住宅では、木構造をずっと研究してきた第一人者ともいえる大家が
「木造は、実はわからないことが多過ぎて、構造計算できない。無理にしている。」という
趣旨の本音とその理由を漏らしたのを聞いてから、
確かにそうだと私も納得したので
大地震の場合には、許容応力度構造計算で大丈夫であっても
実際に本当に大丈夫か、信じきれていない部分があります。
阪神高速道路は、もっとも構造計算しやすいモデルのような形状を
していましたし、工事も設計通りに造りやすい形状でしたが、
1本足のかなりの頭でっかちで、
見た目には、大地震が来たら絶対無理だろうという
とっても不安な形をしていました。
結果は、ご存知の通りです。
阪神大震災の以前から、大地震が起こるたびに
新しい想定外や問題、未対応が起こっているからです。
関連して、筋交の掛け方の質問は多いのですが、
基本事項だけでなく、詳細に述べるには、
長文となる説明と専用の図を用意しないといけませんので
かなりの時間と労力を費やすことになり、まだ実現していません。
すみません。
ミタス一級建築士事務所では、さらに制震装置についても
15年以上、ずっと検討してきました。
毎年ある建材展やその他同様の展示会、
メーカーからの面談説明、資料送付含めて、
たくさんの種類を検討しましたが、
欠点や疑問も同時にあり、これなら良いと思うものが無かったので、
お勧めしていませんでした。
東北大震災では、ある有名ハウスメーカーの制震装置は
役に立たなかったということも聞いています。
しかし、これは考えれば、事前にわかることでした。
今回、これなら良いのでは、というものをようやく見つけたので
リフォーム工事で、追加で採用して取り付けました。
制震よりも部材の破断を守ることを期待して、部分的に採用しました。
また、現在、着工したばかりので新築でも制震を期待して
急遽、追加で採用してもらうことにしました。
安くするため、メーカーから直接購入して、支給する形です。
1 耐力壁を1.5倍以上、
2 偏心率を0.15以下
3 地震時の力の流れを考えて耐力壁や筋交い、床面の剛性、位置を
プラン時から考える
4 地震時に局部的に大きな力、引き抜き力が掛からないようにする
5 採用した制震装置で揺れの減少や接合面の破断を守る
1~4に加えて、今後は、5 を新たに加えて、より進化させます。
……………………………………………………………………………
ご意見があれば、お気軽にどうぞ!
注文住宅 横浜市
横浜市 一級建築士事務所