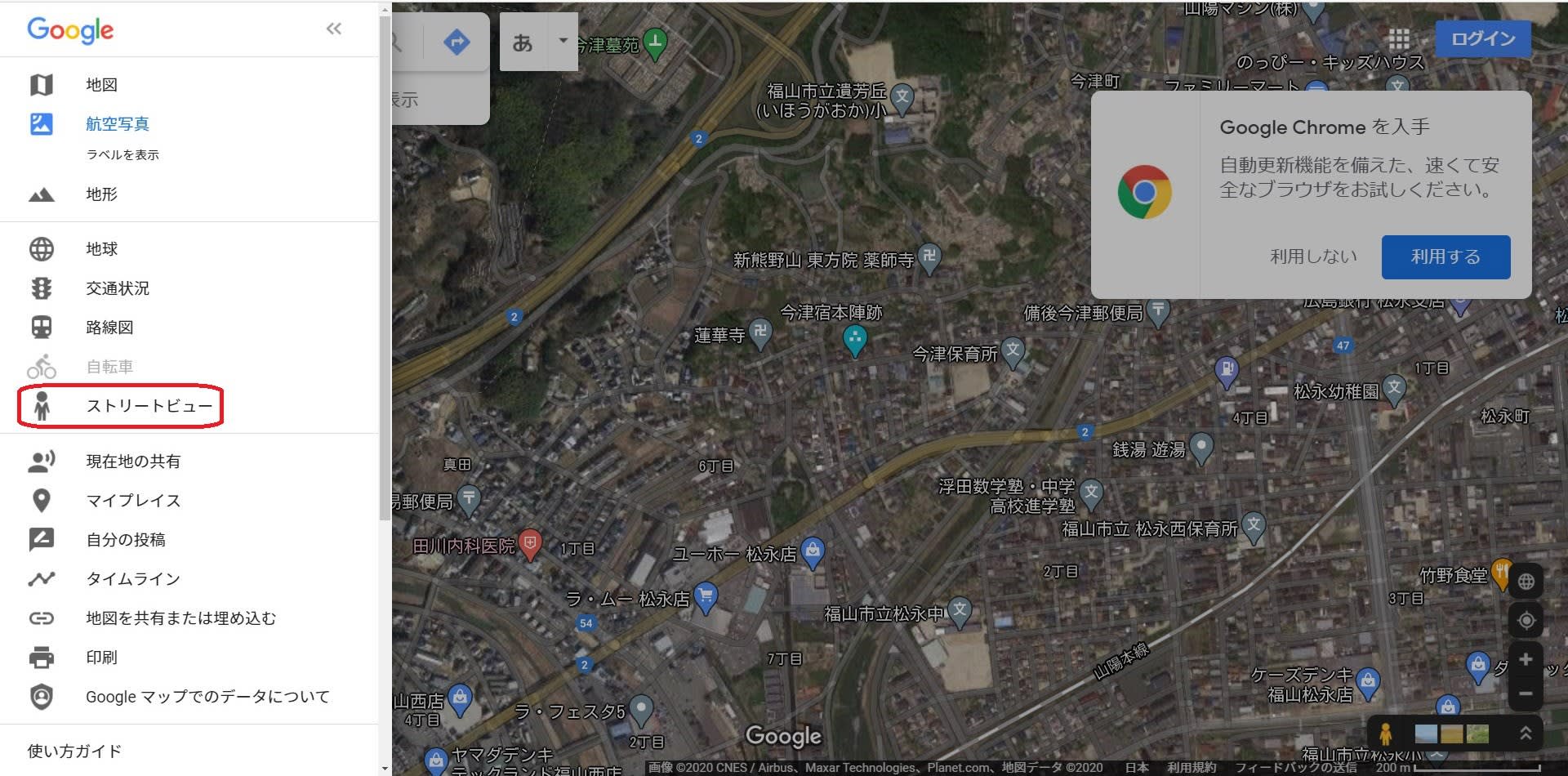国語史・国文学関係の文献はかなり前からときどき紐解くようにはしてきたが今回は浪華城南隠士著『安部野童子問(あべのどうじもん)』つながりで話題にした記事;”一揆物語と太平記読み”を一歩前進させるために今井の大著「『太平記秘伝理尽鈔』研究」にズームインしてみようと言うわけだ。
取りあえずは加美宏提示の先行学説
を押さえておこう。それでは
目次
序章 『太平記秘伝理尽鈔』の登場
第一部 『理尽鈔』の世界
第一章 「伝」の世界
第二章 「評」の世界――正成の討死をめぐって――
第三章 兵学――『甲陽軍鑑』との対比から――
第二部 『理尽鈔』以前
第一章 『天文雑説』『塵塚物語』と『理尽鈔』
第二章 『吉野拾遺』と『理尽鈔』
付論 『塵塚物語』考――『吉野拾遺』との関係――
第三章 『軍法侍用集』と『理尽鈔』――小笠原昨雲著作の成立時期――
付.『軍法侍用集』版本考
第三部 『理尽鈔』の伝本と口伝聞書
第一章 加賀藩伝来の『理尽鈔』
第二章 『理尽鈔』の補筆改訂と伝本の派生
第三章 『理尽鈔』伝本系統論
第四章 『恩地左近太郎聞書』と『理尽鈔』
第五章 『陰符抄』考――『理尽鈔』の口伝聞書――
第六章 『陰符抄』続考――『理尽鈔』口伝史における位置――
第七章 『理尽鈔』伝授考
第四部 『理尽鈔』の類縁書――太平記評判書の類――
第一章 「太平記評判書」の転成――『理尽鈔』から『太平記綱目』まで――
第二章 『理尽鈔』と『無極鈔』――正成関係記事の比較から――
第三章 『無極鈔』と『義貞軍記』
第四章 『無極鈔』と林羅山――七書の訳解をめぐって――
付.甲斐武田氏の『孫子』受容
第五部 太平記評判書からの派生書
第一章 『楠正成一巻書』・『桜井書』の生成
第二章 『恩地左近太郎聞書』『楠正成一巻書』『桜井書』と『理尽鈔』
第三章 『楠判官兵庫記』と『無極鈔』
第六部 太平記評判書とは別系統の編著
第一章 南木流兵書版本考――類縁兵書写本群の整序を兼ねて――
付.南木流覚書――『理尽鈔』との関わり――
第二章 肥後の楠流
補.誠極流と『太平記理尽図経』/付.『軍秘之鈔』覚書
第七部 『理尽鈔』の変容・拡散・・・「理尽鈔」は「太平記」の記述に対する異伝/真相(と称するもの)を語り、その立場から登場人物の言動を論評するもの(本書636頁)
第一章 『太平記秘鑑』伝本論
第二章 『太平記秘鑑』考――『理尽鈔』の末裔――
第三章 「正成もの」刊本の生成――『楠氏二先生全書』から『絵本楠公記』まで――
付.『楠正行戦功図会』覚書
第四章 明治期の楠公ものの消長――『絵本楠公記』を中心に――
第五章 「楠壁書」の生成
付.正成関係教訓書分類目録
終章 「正成神」の誕生と『理尽鈔』の終焉
付録.太平記評判書および関連図書分類目録稿
Ⅰ.太平記評判書および関連書
Ⅱ.太平記評判書を用いた編著 付.楠関係の謡曲
Ⅲ. 正成関係伝記
Ⅳ.楠兵書 付.『秘伝一統之巻』覚書
所蔵者略称一覧
あとがき・索引(人名・書名〈資料〉・『理尽鈔』〈版本〉引用箇所・事項)
私の心境としては『安部野童子問』/『自白法鑑』再検討のため、敢えて道草を食うという感じ。
まだ図書館より借りだして間がないので前書き程度しか読んでないが、この本は『太平記秘伝理尽鈔』の文芸作品としての成立過程(伝本調査とその系統分類作業)に焦点を当てたもののようだ。
ってことは『太平記秘伝理尽鈔』の、それも講釈にスポットを当てつつ、その中の兵法論・道徳論・政道論を論じたものではない。
この辺りのことは従来(例えば前掲の加美宏「『太平記秘伝理尽鈔』とその意義・影響・研究史」)からもかなり取り上げられ、最近では今井正之助門下の若尾政希が幕藩制国家の現実との関わりの中でそれを精力的に研究しているのだと。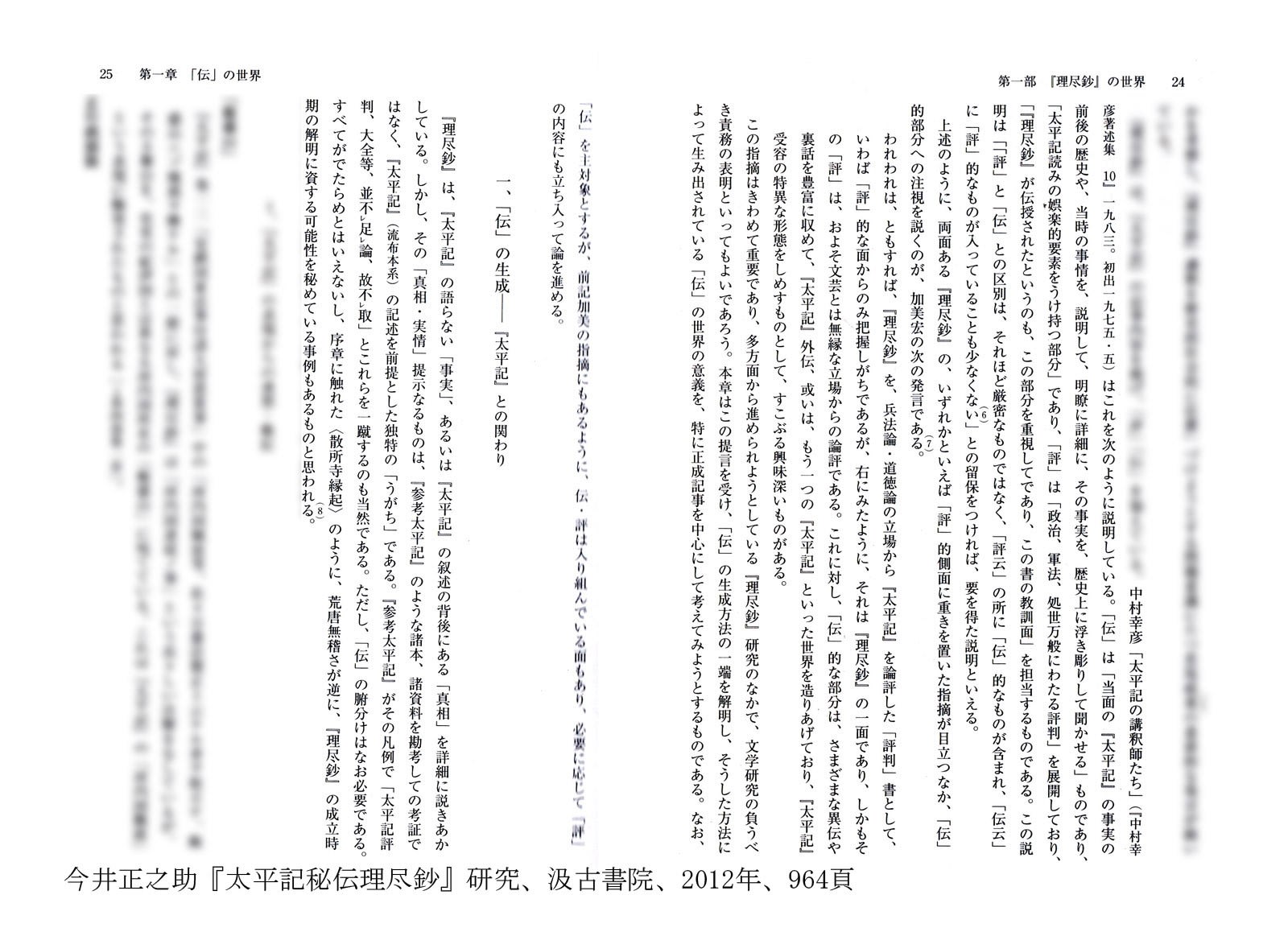
若尾政希自身は著書「近世の政治思想論―『太平記評判秘伝理尽鈔』と安藤昌益,」148頁(注3)において大和和雄のコメント:「著者(若尾)が明らかにした思想史の動きが、なぜ《太平記》との関わりの中で進行したのか、日本人が歴史を先例として読むのではなく、史上の人物に託して、政治の論評を行い、歴史の解釈を通じて政治思想を表現するようになることの、思想史的な意味を考えてみたい」(「デジタル月刊百科」1999年10月)を紹介。史上の人物といえば「行基」「聖徳太子」「小野小町」などもそうだったと思うが、そこまで対象を拡げなければ「嗚呼忠臣楠子之墓」の忠臣楠氏以外では忠臣蔵(大石内蔵助)も同様だ(若尾「近世の政治思想論―『太平記評判秘伝理尽鈔』と安藤昌益」123頁が指摘するような『太平記評判秘伝理尽鈔』に説く、「あるべき治者像」=為政者像のようなものではなくここではむしろ「あるべき臣下(忠臣)像」がハイライト化されている)。こういう部分を含めて私が知りたいのはそれは単なる修辞法上の問題に過ぎなかったのか、それとも『太平記秘伝理尽鈔』やその講釈師たちを支えている(通俗的なものも含めて)思想基盤があったとすればそれはどのようなものだったのかと言う点なんだが・・・・。
いずれにせよ教える側も教えられる側も中国の古典籍類には刃が立たず、為に「倭学」(桑田忠親『大名と御伽衆・増補新版』、1969、264-276頁 桑田は倭学=本朝の古典文学とするが、むしろ『太平記』のような軍記物主体の国書類の評釈/講釈を指すヵ)に傾斜せざるを得なかった事情が、戦乱続きの中世後期の武家社会にはあっただろうことが何となく透かし見えてきそうだ
そんな思いを懐きつつこれからしばらく今井正之助『太平記秘伝理尽鈔』研究を読んでいくことになる。
これまで『自白法鑑』を熊沢蕃山との関わりで考えてきたが、熊沢蕃山の政道論は池田光政時代の岡山藩ではあまり浸透しなかったと言うような意味の話を若尾政希の著書(若尾『「太平記読み」の時代』、平凡社、254-289頁)で学んでから、いまの私は意識としては一旦熊沢を外して『自白法鑑』を見つめ直す必要性をも迫られ始めている次第なのだ。
福沢諭吉は賢く、陰陽五行説や儒教的名分論を盲説として否定。村田露月編著『松永町誌』は本庄重政『自白法鑑』の支離滅裂さを品よく「幽玄」ということばで処理。この辺がこの史料との付き合い方としては正解なのかもしれない。