
背景は亀山士綱『尾道志稿』付図・仮称尾道水道沿岸展望図。その原画と思われる林寅山(はやしいんざん)の『尾道浦絵屛風』

以下では『向島町史』・通史編の古代部分で見かけた表記の話題(福山市今津町の高諸神)に関連した記事についてを紹介したい。すなわち、
『向島町史・通史編』を見ていたら延喜式内社として高諸神(福山市今津町)という記事を見つけたと言う話題だ。
これが間違いであることはわたしの検証作業を通じて明白なのだが、こういう部分の誤りが昭和55年刊の式内社研究会編纂『式内社調査報告』第二十二巻、山陽道に所収された金指正三執筆の以下の記述などを通じて、もの知らぬ読者たちにまき散らされ続けている訳だ。
近世の地図や地誌類(『西備名区』)の中では沼隈郡高須村の何処かにあったと考えているものがある。蓋然性が高いのはそちらの方かなと思うが(直観でものを言うと偽史言説の火種になりかねないので、それ以上のことは判らないと述べておこう)、神道系の人は歴史的経緯はどうであれ、この名称が消滅せずどこかの神社に残っていることの方が大切なのかも知れない。金指さん曰く「剣大明神すなわち高諸神社」<ンンンンンンンンンンンンンンンww 喝!
剣大明神≠(沼隈郡式内社3座の内の一つたる)高諸神社であることは菅茶山編『福山志料』が強弁している通り。『広島県史』古代編は菅茶山の否定論を紹介するも当たり障りのないように両論併記。
くどいようだが、高諸神社という名称は沼隈郡今津村庄屋・今津宿本陣を兼ねた剣大明神の神主・河本氏が安永8(1779)年に河本之政/和義(ちかよし)父子の時代に制作した偽史言説の一つ。「高諸神社石橋」の文字はおとがめを受けたことが関係しているのだろうか、鏨(たがね)か何かで削られかなり不鮮明だ。それにしても大先生から"嘘つくな"と藩主提出の『福山志料』の中で厳しく叱責された訳だから河本和義らとしては大赤面だったことだろう。ただ、息子である河本四郎左衛門(神主・庄屋、在方扶持人=福山藩御用商人)の時代になると、喉元過ぎれば熱さ忘れるで、いやはや、今度は剣大明神という(沼隈郡本郷村の枝村にすぎなかった)今津村の村鎮守に対し備後国一ヶ国惣鎮守だと言い出す始末。
後日談 よほど今津村(本郷村八幡さんの氏子圏内の村)の村鎮守の社格をUPさせたかったとみえ、百姓神主河本伝十郎時代に伊藤梅宇の撰文で『剣大明神縁起』を制作していたのに、どこにあったか定かでない式内社高諸社の祭神(高諸神)を強引に持ってきて明治7年には河本之政/和義以来の念願だったその名称と元禄13年検地帳記載以来の名称・剣大明神(通称「お剣さん」)という社名とを置換。合祀という話は王子山にあった王子神社を境内社にしたということを指すのであって、この恣意的な社名変更によって本来的にfairy taleにすぎなかった『剣大明神縁起』は皮肉にも骨抜きにされ、その後は当該縁起で語られた白鳳期の村長田盛庄司安邦が神主家のご先祖だという部分だけが史実だと云わんばかりに一人歩き中だ(これらはすべて江戸中期に横行した過去の偽造の結果=fakeloreであることはすでにわたしが論証済み→メモ:村が自らの歴史・由来を語り始めること=久留島風に「自己認識」という枠の中で近世中期以後の新庄村(沼隈郡本郷村)の枝村からの脱皮と絡めながら今津村のあり様を論理化する)。要するに江戸時代は文学(虚構)と歴史(史実)との境界が曖昧、いな両者の間には垣根がなかったのだ。
参考までに藩政村今津村(中世新庄内今津浦)村鎮守・剣大明神は中世新庄つる木浦の産土(現在は松永潮崎神社=旧松永剣大明神)を勧請したもの。ちなみに中世新庄今津の荘鎮守は新庄村=本郷八幡宮だった。村落祭祀面では明治期まで藩政村今津は神村八幡と本郷八幡の氏子圏とに分かたれていた。
文化文政期の神辺ー今津間の小休所:郷分の小畠定雄、山手の三谷荘右衛門、赤坂の中村五郎左衞門そして松永の石井四郎三郎(『赤坂村史』、507頁、小休所は本陣に準ずる補完施設で,規模的には同等)。
【メモ】われわれの発する言葉は無意識のうちに制度や権力と不可分に結びついており、抑圧・排除・差別などといった制度的権力の構図を内包している。言説=ディスクールとはそのような性格を有する言語的述説(M.フーコー)。
わたしが使った言説とはフーコー流。
小学館日本国語大辞典での用例
ここでいう「偽史言説」とはfakeloreの一種のこと。
【参考】用語解説
現代において「実際には決して起こっていないのに、事実として語られる話 (story which never happened told for true)」を意味するのが「都市伝説」。もうひとつ、ジェームズ・スティーヴンスとの論争の中で生み出されたのがいわゆる「フェイクロア(fakelore)」(本物として提示されたものだが、実際には捏造された民間伝承を指す言葉)。「近世沼隈郡今津村にみる歴史制作の歪んだ実態」というのはこのフェイクロアに関わる事柄。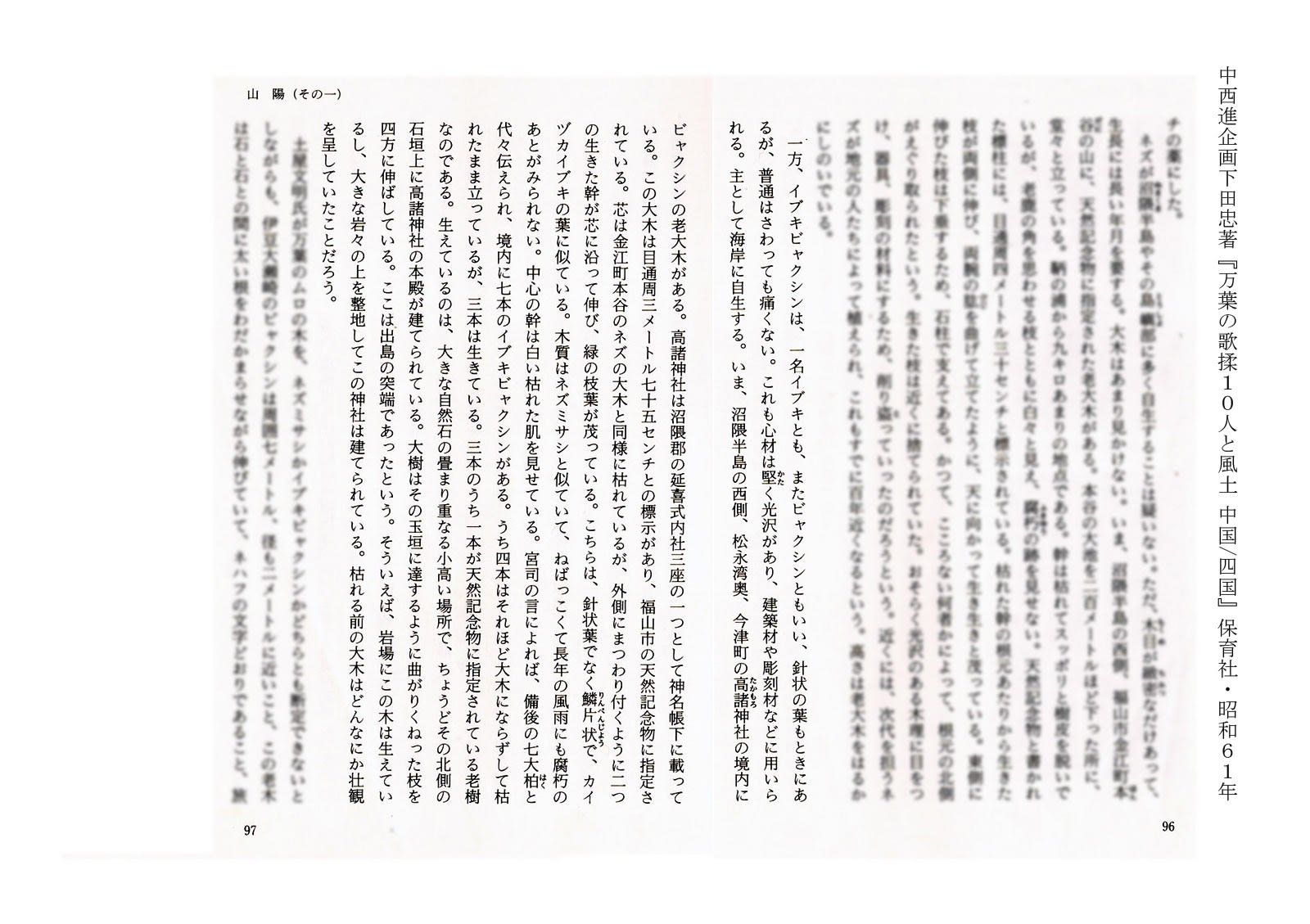 史料批判が欠如すると万葉学者下田忠(福山市立女子短期大学)のような誤解を招きかねない。犬養孝氏は下田の「瀬戸内の万葉」昭和59,198頁の序文では「(万葉集の歌に詠まれた)故地の古代に遊び、現代を探り、さながら万葉人の瀬戸内が、生き生きと今日に躍り出る臨場感の溢れるものを感じた」と書いていた。ただし、船旅をしていた奈良時代の詠い手たちを陸地からの視点から風光明媚な今日風の風景写真や史跡写真付きで思い入れたっぷりに解説すること学問的な意義ってそんなにあるのだろうか。
史料批判が欠如すると万葉学者下田忠(福山市立女子短期大学)のような誤解を招きかねない。犬養孝氏は下田の「瀬戸内の万葉」昭和59,198頁の序文では「(万葉集の歌に詠まれた)故地の古代に遊び、現代を探り、さながら万葉人の瀬戸内が、生き生きと今日に躍り出る臨場感の溢れるものを感じた」と書いていた。ただし、船旅をしていた奈良時代の詠い手たちを陸地からの視点から風光明媚な今日風の風景写真や史跡写真付きで思い入れたっぷりに解説すること学問的な意義ってそんなにあるのだろうか。