松永史談会6月例会のご案内
開催日時6月28日 午前10-12時
場所 蔵
話題:『国立公文書蔵版・芸藩通志』に見る頼杏坪の地誌編纂のセンスについて
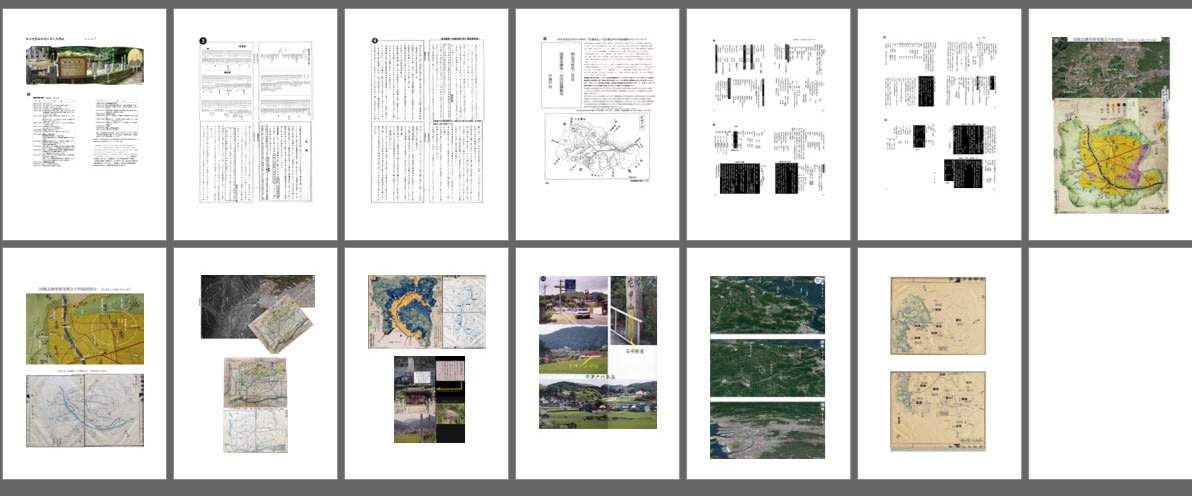
なお、先月予告の通り、松永史談会の活動報告をかねて引き続き令和6年度市民雑誌投稿論攷(無査読)の抜刷・雑誌本体を配布予定

関連記事
➊(亀山士綱)、➋(古川古松軒、馬屋原重帯)
参考資料及び文献:
広島藩の地方(ぢかた、=地域)情報及び地方支配に関する諸規則を集めた役用マニュアル本=『芸備郡要集』や国郡志編纂用佐伯郡辻書出帳など(『廿日市町史』資料編2/付図付き,1975.に所収)。

『芸藩通志』・『防長注進案』に関しては羽賀祥二「記録の意図と方法-19世紀日本地誌と民俗記述-」(若尾祐司・羽賀祥二『記録と記憶の比較文化史』、名古屋大学出版、2005、57-88頁)・・・ダメ論文
西村晃「世羅郡の『国郡志御編集ニ付下調べ書出し帳』の編集について」、広島県立文書館紀要13号、2015、p193-217
広島県内の自治体史には域内の『国郡志御編集ニ付下調べ書出し帳』の紹介やその郡単位での編纂過程について説明したものが各種存在する。例えば『東城町史・古代中世・近世資料編』、1994.『呉市史』近世Ⅱ、1999など。
最近では広島県立文書館が西向宏介「近世芸備地方の地誌」で史料紹介など、ほか多数。

賴杏坪論関係では
頼 祺一「朱子学者の政治思想とその実践-賴杏坪の場合-」(上・下)、芸備地方史研究64(1-14頁)、および65/66合併号(20-29頁)、1967参照のこと。
頼 祺一や重田定一(『賴杏坪先生伝』、明治四一年の著者)らによると、賴杏坪の場合は29才時に藩儒(朱子学、陽明学を否定)として登用され、70才過ぎには三次町奉行になった人物で、いわゆる朱子学の教説を信奉した教養ある吏員ではあった。『芸藩通志』編纂を見る限り『防長風土注進案』を編纂する長州藩の長州藩家老村田清風や国学者近藤芳樹ららに比べ広島藩の取り組みはどの程度のものだったかはちょっと気になるところ。なお福山藩の場合は『備後郡村誌』と菅茶山ら編纂の藩主用政治書・教養書『福山志料』どまり。
【メモ】貝原益軒『筑前国続風土記』
巻2ー河内地名(山間一谷内にある村々、例えば筑前国那珂郡岩戸河内 12ヶ村構成)、世羅郡宇津戸村や沼隈郡山南村ー谷中
貝原益軒はGeosophie(生活環境をデザインする時代的知や社会的知の在り方)研究の対象者として把握予定。
開催日時6月28日 午前10-12時
場所 蔵
話題:『国立公文書蔵版・芸藩通志』に見る頼杏坪の地誌編纂のセンスについて
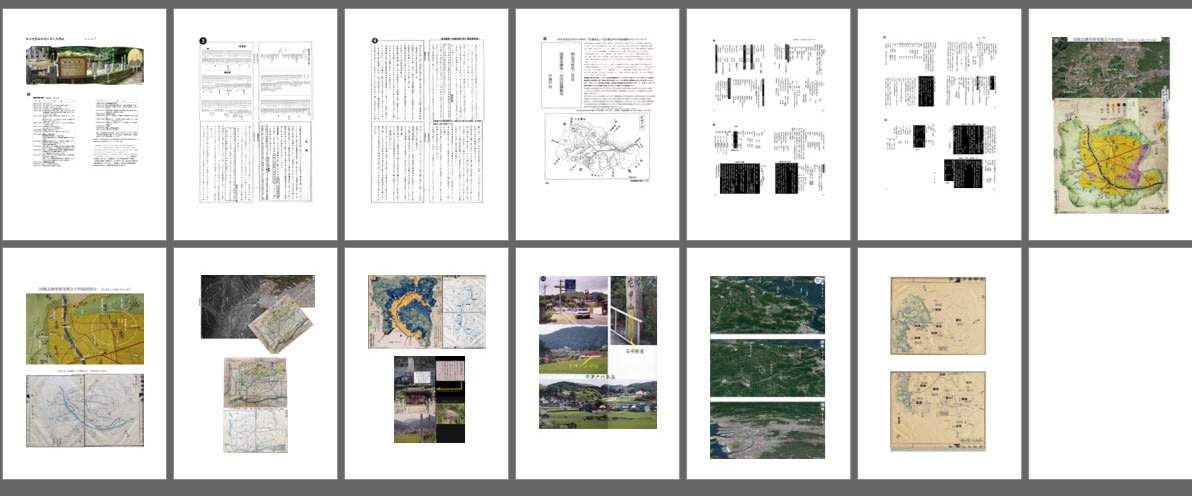
なお、先月予告の通り、松永史談会の活動報告をかねて引き続き令和6年度市民雑誌投稿論攷(無査読)の抜刷・雑誌本体を配布予定

関連記事
➊(亀山士綱)、➋(古川古松軒、馬屋原重帯)
参考資料及び文献:
広島藩の地方(ぢかた、=地域)情報及び地方支配に関する諸規則を集めた役用マニュアル本=『芸備郡要集』や国郡志編纂用佐伯郡辻書出帳など(『廿日市町史』資料編2/付図付き,1975.に所収)。

『芸藩通志』・『防長注進案』に関しては羽賀祥二「記録の意図と方法-19世紀日本地誌と民俗記述-」(若尾祐司・羽賀祥二『記録と記憶の比較文化史』、名古屋大学出版、2005、57-88頁)・・・ダメ論文
西村晃「世羅郡の『国郡志御編集ニ付下調べ書出し帳』の編集について」、広島県立文書館紀要13号、2015、p193-217
広島県内の自治体史には域内の『国郡志御編集ニ付下調べ書出し帳』の紹介やその郡単位での編纂過程について説明したものが各種存在する。例えば『東城町史・古代中世・近世資料編』、1994.『呉市史』近世Ⅱ、1999など。
最近では広島県立文書館が西向宏介「近世芸備地方の地誌」で史料紹介など、ほか多数。

賴杏坪論関係では
頼 祺一「朱子学者の政治思想とその実践-賴杏坪の場合-」(上・下)、芸備地方史研究64(1-14頁)、および65/66合併号(20-29頁)、1967参照のこと。
頼 祺一や重田定一(『賴杏坪先生伝』、明治四一年の著者)らによると、賴杏坪の場合は29才時に藩儒(朱子学、陽明学を否定)として登用され、70才過ぎには三次町奉行になった人物で、いわゆる朱子学の教説を信奉した教養ある吏員ではあった。『芸藩通志』編纂を見る限り『防長風土注進案』を編纂する長州藩の長州藩家老村田清風や国学者近藤芳樹ららに比べ広島藩の取り組みはどの程度のものだったかはちょっと気になるところ。なお福山藩の場合は『備後郡村誌』と菅茶山ら編纂の藩主用政治書・教養書『福山志料』どまり。
【メモ】貝原益軒『筑前国続風土記』
巻2ー河内地名(山間一谷内にある村々、例えば筑前国那珂郡岩戸河内 12ヶ村構成)、世羅郡宇津戸村や沼隈郡山南村ー谷中
貝原益軒はGeosophie(生活環境をデザインする時代的知や社会的知の在り方)研究の対象者として把握予定。











 。
。




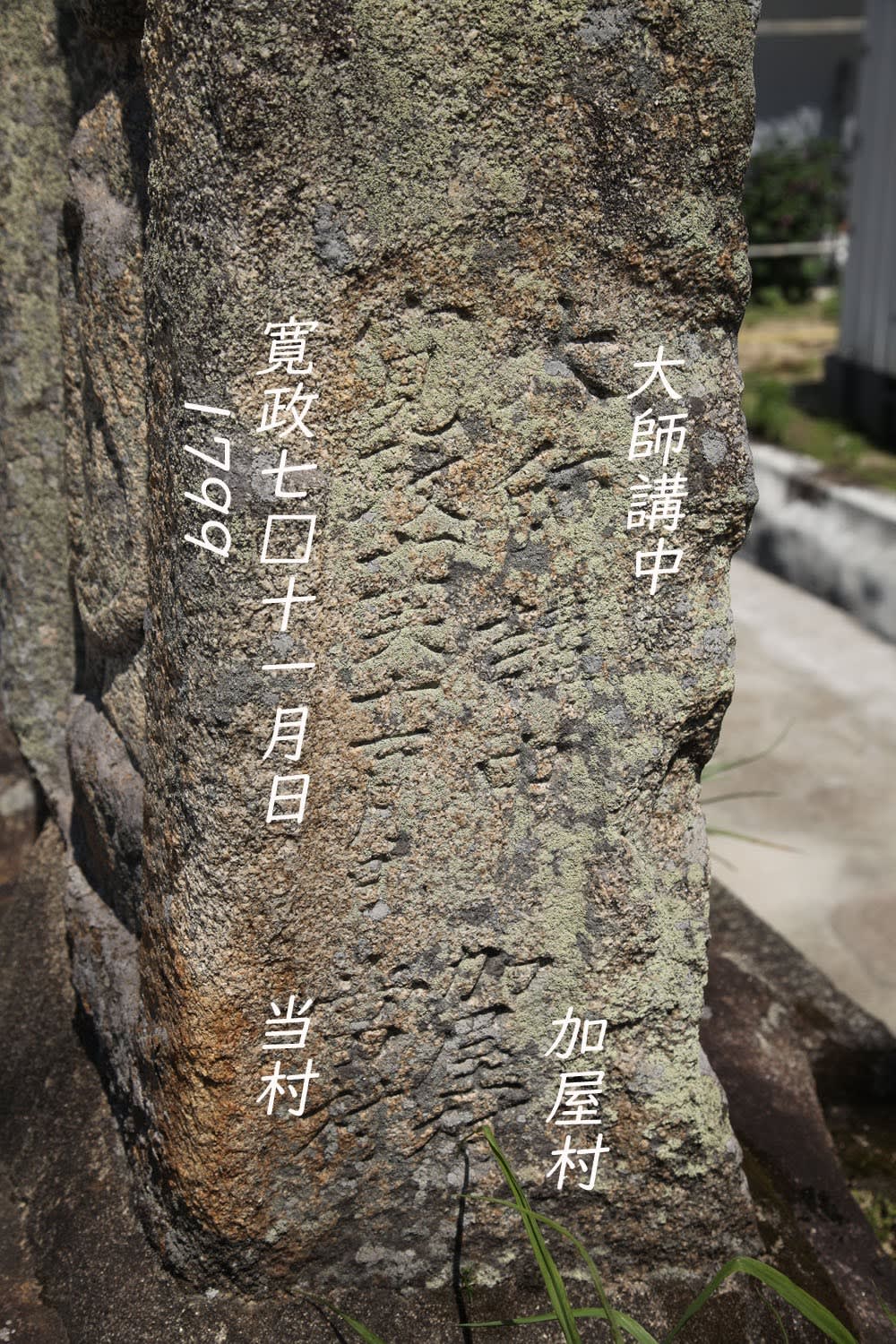

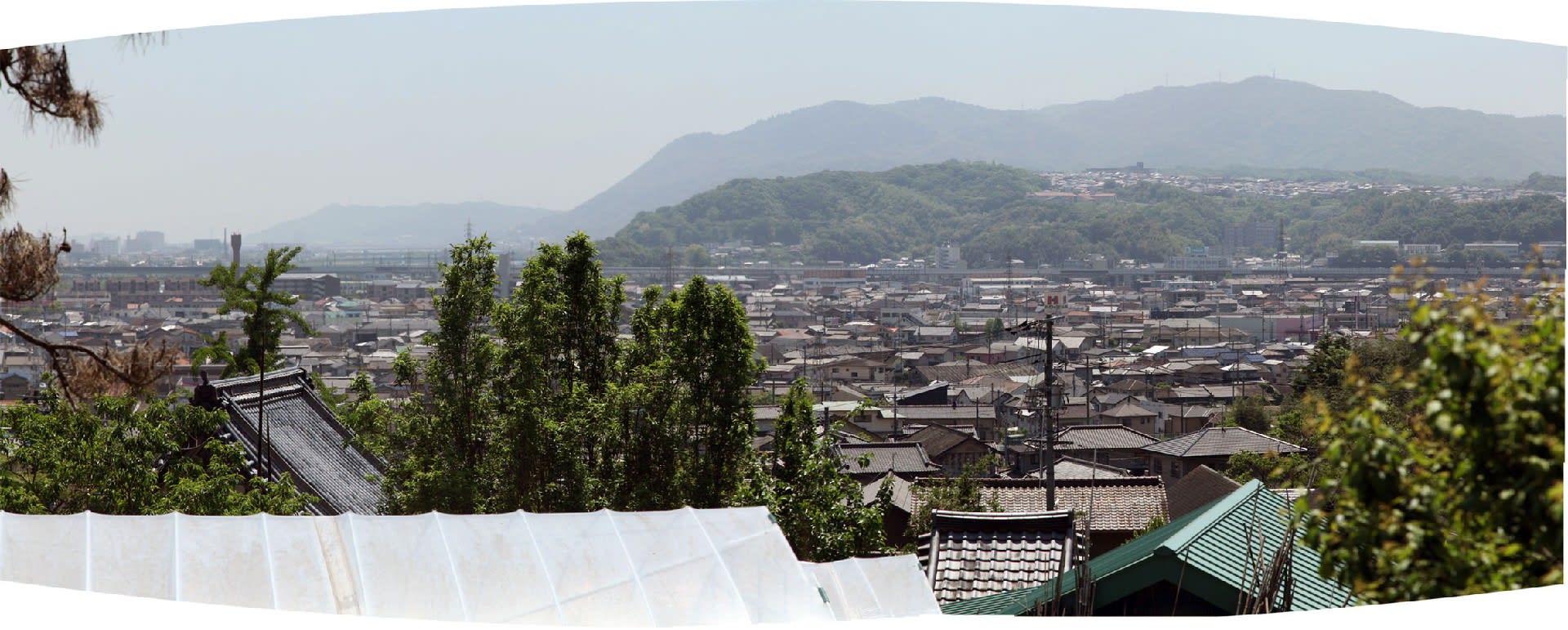


 。考古学的な確認作業に関しては不知だが、
。考古学的な確認作業に関しては不知だが、





