ずっと昔の講義ノート (「社会思想入門」) からアーレントやカントのレジュメをアップしてきましたが、
まだ少しネタ帳が残っているのでこの機会に全部アップしてしまいましょう。
まずはヘーゲルとヘーゲル左派です。
カントの哲学とヘーゲルの哲学はその方向性が真反対ですので、
カントが好きな人はヘーゲルが嫌いだし、ヘーゲルが好きな人はカントをバカにしているというように、
互いに相容れないことが多く、私もそのご多分に漏れずヘーゲルは大嫌いなのですが、
講義の構成上やむをえず、カントを2回講義したあと、
ヘーゲルとヘーゲル左派についても私から1回講義をしました。
私の次の担当者がマルクスの専門家だったので、
カントとマルクスのあいだを埋める必要があったのです。
今から掲載するレジュメのなかにはあからさまに書いたりはしませんでしたが、
講義をするときには自分がどれほどヘーゲルが嫌いか、
ヘーゲル哲学のどこがダメなのかを口頭でものすご~く強調しました。
自分でもちょっと公正を欠いてたなと反省するほどだったのですが、
あとで学生のミニットペーパーを読んでみると意外とヘーゲルのほうがよかったという学生が多く、
自分の教員としての説得力のなさを痛感させられたものです。
それにしても、私としては当時できるかぎりわかりやすく書いたつもりですが、
今読み返してみるとやっぱり相当難しいですね。
これを初めて読んで理解するのは至難の業でしょう。
まあ、ヘーゲルとヘーゲル左派をたったA4用紙2~3枚でわかりやすく説明し尽くせというのが
どだいムリな注文ですので、よくがんばったと自分を褒めてあげることにいたしましょう。
ヘーゲルとヘーゲル左派 「歴史の弁証法的展開 ―観念論から唯物論へ―」
Ⅰ.弁証法による二元論の克服
カントは人間の有限性を直視したがゆえに、理想と現実の二元論を堅持し続けました。しかし、理想は永遠に理想であってけっして実現されることはない、それにもかかわらずその実現に向けて永遠に努力し続けなければならないという、この過酷な要求に人間は耐えきれるのでしょうか。理想がけっして実現されえないのだとしたら、人間は理想への努力を放棄してしまうのではないでしょうか。
カントが提起した問題は、プロイセンの若き哲学者たちフィヒテ、シェリング、ヘーゲルらに受け継がれていきました。彼らは総称して 「ドイツ観念論 (理想主義)」 と呼ばれています。中でもヘーゲルは、若い頃にはカント哲学に惹かれていた時期もありましたが、やがてカントと訣別して、カント的な二元論を克服することを自らのライフワークとしました。そしてその果てに壮大な哲学体系が構築されたのです。最後の主著 『法の哲学』 の中でヘーゲルは、「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」 と述べていますが、これはまさにカント的な二元論に対する勝利宣言にほかなりません。
ヘーゲルによれば、理想と現実とはまったくかけ離れたものではなく、そもそも 「絶対的精神」 という理性的なるものが自己展開していくことによって、自然界や精神界などが形成されていったのであり、したがって現実に存在するものはすべて理性的法則によって貫かれているのです。このような理性的法則のことをヘーゲルは 「弁証法」 と呼びました。
弁証法とは矛盾律 (同一律) と対峙する新しいものの見方です。古くからある矛盾律という見方では、AはAであってそれ以外のものではありえません。カントもまた矛盾律を重視しました (抵抗権・革命権を否認するときにも、その概念自体の矛盾を問題にしていたはずです)。この矛盾律というのはたしかに常識にかなっており形式的には正しい考え方かもしれませんが、これでは変化・生成といった出来事を説明することができません。なぜ種子が芽を出し花を咲かせていくのか、なぜ子供が大人になっていくのか、このことを理解するためには、AはAであると同時にAではない、というふうに考えなくてはならないでしょう。この 「~ではない」 という否定的な要素はすべてのものの内に見いだすことができます。あらゆるものは自らの本質を余すところなく展開し発現させていくのですが、それと同時に、自らの内に孕まれていた否定的要素も膨れあがらせていきます。そしてそのものが絶頂に達した瞬間に、自己内矛盾も極限に達して、新たな高次の段階へとバトンタッチされていくのです。
このような弁証法というものの見方によって、ヘーゲルは世界の一切を捉えようとしました。『哲学的諸学のエンツィクロペディー綱要』 に見られるヘーゲルの哲学体系は、純粋かつ単純な 「存在 (=ある)」 から始まって、そこに含まれた否定的要素が展開していくことによってしだいに論理の世界 (ことば、理性、理念) が成熟していき、絶対的理念にまでいきついたところで今度は自然の世界へと外化 (エントオイセルング) する、そして自然の世界が完全に展開し終わったところで今度は精神の世界へと再び外化していくという形で、世界の一切を理念の自己展開運動である弁証法によって解き明かそうとする壮大な試みでした。
Ⅱ.人倫の弁証法
この弁証法は、社会や歴史を考察するときにとりわけ威力を発揮します。『エンツィクロペディー』 の第3篇 『精神哲学』 の第2部 「客観的精神」 の章 (のちにこの部分だけ取り出されて 『法の哲学』 として詳論されました) は、「A 法」、「B 道徳性」、「C 人倫」 の3部から成っています。まったく外的な人間関係だけを扱う法の世界、逆にまったく内的な人間の意志のあり方を扱う道徳性の世界、カントが扱ったのはこの二つの世界だけでした。これに対してヘーゲルは、それら両者の対立を止揚し、ありうべき理念が現実の社会へと外化した共同体のあり方を 「人倫」 の世界として描いています。
社会の最小単位は家族です。家族の本質は子供の育成にあります。二人の男女が結婚して家族をつくり、子を産み、育てていく。子供が成長し一人前となって、家族の目的が達成されるやいなや、子供は家族から巣立っていき、家族は崩壊します。こうして次の段階、市民社会が要請されます。
市民社会は独立した個人が相互の利害によって結ばれる経済社会で、そのモデルは先進国イギリスです。アダム・スミスと同時代のカントは経済を学問的対象として本格的に取り上げることができなかったのですが、ヘーゲルはスミスが描き出した理想的な市民社会を問題化し、その内に孕まれている否定的要素を見据えています。「欲求の体系」 としての市民社会においては、増大し多様化した諸個人の欲求に対応すべく、分業と機械化が進んでいくことによって、国富がどんどん増大して経済的に繁栄していくのですが、しかしそれとともに労働の抽象化による人間疎外と、貧富の差も増大していき、また市民社会の持続的発展のために植民地支配を強めていかなくてはなりません。こうして市民社会は矛盾の極みに達して、国家という最高の段階を要請せざるをえなくなるのです。
Ⅲ.国家から世界史へ
ヘーゲルの言う国家は、市民社会における所有や諸個人の自由・安全を法的に保障するような近代的な夜警国家のことではありません。人々が連帯と共同性を最高度に発揮し、国家の目的が個人の目的であるような、その意味で諸個人と国家が有機的全体として一つにまとまっているような国家をヘーゲルは考えています。そして国家の理想形態として 「立憲君主制」 を掲げました。これは、カントが 「共和制」 を提唱していたのに比して時代に逆行しているようにも見えるため、ヘーゲルはプロイセン国家の御用哲学者にすぎないのだという評価もなされてきました。その一方で、憲法も議会も存在せず、立憲君主制を称えること自体が危険視されていた時代のなかで、プロイセン国家からベルリン大学に招聘されたという身分にあったにもかかわらず、『法の哲学』 を出版して、リベラルな立憲君主制を称えた彼は、まさに進歩的自由主義者として思索し行動していたのだ、と評価する声が昨今では高まってきています。その点については皆さんがそれぞれ判断していただきたいと思います。
さて、ヘーゲルが構想した、人々の連帯と共同性を最高度に発揮させるような国家として、戦時体制下の国家を思い浮かべることができるでしょう。じっさいヘーゲルにとって戦争は重要な意義を持ちます。ヘーゲルはカントとはちがい、永遠平和を最終的な目的とは考えていません。国家は最高の段階ですから、それ以上の発展段階 (国際連盟など) が考えられてはいませんし、ヘーゲルに言わせると、そもそも平和は諸国民を腐敗させるのです。したがって諸国家間の対立は戦争によって決着をつけられる以外にありません。そして国家間の対立に最終的な審判を下すのは世界史なのです。
無数の国家が相争って盛衰を繰り返す場、それが世界史であり、この歴史そのものが弁証法的な発展過程をたどっています。カントは永遠に実現されることのない未来の目的への無限の努力の過程を歴史ととらえましたが、ヘーゲルはこれまで過去に展開されてきた歴史の流れそのものを、絶対的精神の弁証法的発展過程として把握しようとしたのです。
Ⅳ.ヘーゲル左派の 「疎外」 論
ヘーゲルがベルリン大学に就任して以来、彼の哲学は圧倒的な影響力をもち、彼の下に優秀な門弟が集まってヘーゲル学派が形成されました。ヘーゲルの死後もすぐに全集が刊行され始めるなど、ヘーゲル学派の勢いはとどまるところを知りませんでした。しかしながら、ヘーゲルの宗教哲学をどのように解するかについて学派内に意見の相違があったところに、1835年シュトラウスが 『イエスの生涯』 を著し、イエスではなく人類そのものを神人ととらえる汎神論的解釈を提出するにおよんで、その是非をめぐって学派は一気に分裂していくことになります。理性と現実の関係に即して言うならば、現実的なものはすでに理性的であるのだとするヘーゲル右派、理性的なものを現実化していかなければいけないとするヘーゲル左派、両極の媒介を図ろうとする中央派の三つに分かれていきました。特に左派には急進的な若者が集い、青年ヘーゲル学派とも呼ばれました。
その中で、フォイエルバッハは、宗教を人間の立場から捉え返そうとする人間学を提唱しました。神とは人間自身がもつ類的本質が外化されたものにすぎないのですが、その点が見失われてしまい、人間からは超絶した疎遠な存在者として人間に対立するようになってしまっている。このような事態をフォイエルバッハは 「疎外 (エントフレムドゥング)」 と呼び、疎外状態からの回復の必要性を訴えました。とりわけ、ヘーゲルによって理性のみが神格化されていったわけですが、その過程で疎外されてしまった感性 (愛) や自然を真の存在として捉え直すことによって、「唯物論」 という新しい哲学を打ち立てようとしました。
宗教批判からさらに政治批判へと向かう人々も現れました。バウアーは宗教を、歴史の特定の段階において現れる自己意識の疎外態とみなして、宗教と癒着した国家体制の批判にまで進んでいきました。そして、フォイエルバッハの疎外論や唯物論の影響を受けつつ、独自の社会・経済批判を育みつつあったのが、若きマルクスやエンゲルスだったのです。
まだ少しネタ帳が残っているのでこの機会に全部アップしてしまいましょう。
まずはヘーゲルとヘーゲル左派です。
カントの哲学とヘーゲルの哲学はその方向性が真反対ですので、
カントが好きな人はヘーゲルが嫌いだし、ヘーゲルが好きな人はカントをバカにしているというように、
互いに相容れないことが多く、私もそのご多分に漏れずヘーゲルは大嫌いなのですが、
講義の構成上やむをえず、カントを2回講義したあと、
ヘーゲルとヘーゲル左派についても私から1回講義をしました。
私の次の担当者がマルクスの専門家だったので、
カントとマルクスのあいだを埋める必要があったのです。
今から掲載するレジュメのなかにはあからさまに書いたりはしませんでしたが、
講義をするときには自分がどれほどヘーゲルが嫌いか、
ヘーゲル哲学のどこがダメなのかを口頭でものすご~く強調しました。
自分でもちょっと公正を欠いてたなと反省するほどだったのですが、
あとで学生のミニットペーパーを読んでみると意外とヘーゲルのほうがよかったという学生が多く、
自分の教員としての説得力のなさを痛感させられたものです。
それにしても、私としては当時できるかぎりわかりやすく書いたつもりですが、
今読み返してみるとやっぱり相当難しいですね。
これを初めて読んで理解するのは至難の業でしょう。
まあ、ヘーゲルとヘーゲル左派をたったA4用紙2~3枚でわかりやすく説明し尽くせというのが
どだいムリな注文ですので、よくがんばったと自分を褒めてあげることにいたしましょう。
ヘーゲルとヘーゲル左派 「歴史の弁証法的展開 ―観念論から唯物論へ―」
Ⅰ.弁証法による二元論の克服
カントは人間の有限性を直視したがゆえに、理想と現実の二元論を堅持し続けました。しかし、理想は永遠に理想であってけっして実現されることはない、それにもかかわらずその実現に向けて永遠に努力し続けなければならないという、この過酷な要求に人間は耐えきれるのでしょうか。理想がけっして実現されえないのだとしたら、人間は理想への努力を放棄してしまうのではないでしょうか。
カントが提起した問題は、プロイセンの若き哲学者たちフィヒテ、シェリング、ヘーゲルらに受け継がれていきました。彼らは総称して 「ドイツ観念論 (理想主義)」 と呼ばれています。中でもヘーゲルは、若い頃にはカント哲学に惹かれていた時期もありましたが、やがてカントと訣別して、カント的な二元論を克服することを自らのライフワークとしました。そしてその果てに壮大な哲学体系が構築されたのです。最後の主著 『法の哲学』 の中でヘーゲルは、「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」 と述べていますが、これはまさにカント的な二元論に対する勝利宣言にほかなりません。
ヘーゲルによれば、理想と現実とはまったくかけ離れたものではなく、そもそも 「絶対的精神」 という理性的なるものが自己展開していくことによって、自然界や精神界などが形成されていったのであり、したがって現実に存在するものはすべて理性的法則によって貫かれているのです。このような理性的法則のことをヘーゲルは 「弁証法」 と呼びました。
弁証法とは矛盾律 (同一律) と対峙する新しいものの見方です。古くからある矛盾律という見方では、AはAであってそれ以外のものではありえません。カントもまた矛盾律を重視しました (抵抗権・革命権を否認するときにも、その概念自体の矛盾を問題にしていたはずです)。この矛盾律というのはたしかに常識にかなっており形式的には正しい考え方かもしれませんが、これでは変化・生成といった出来事を説明することができません。なぜ種子が芽を出し花を咲かせていくのか、なぜ子供が大人になっていくのか、このことを理解するためには、AはAであると同時にAではない、というふうに考えなくてはならないでしょう。この 「~ではない」 という否定的な要素はすべてのものの内に見いだすことができます。あらゆるものは自らの本質を余すところなく展開し発現させていくのですが、それと同時に、自らの内に孕まれていた否定的要素も膨れあがらせていきます。そしてそのものが絶頂に達した瞬間に、自己内矛盾も極限に達して、新たな高次の段階へとバトンタッチされていくのです。
このような弁証法というものの見方によって、ヘーゲルは世界の一切を捉えようとしました。『哲学的諸学のエンツィクロペディー綱要』 に見られるヘーゲルの哲学体系は、純粋かつ単純な 「存在 (=ある)」 から始まって、そこに含まれた否定的要素が展開していくことによってしだいに論理の世界 (ことば、理性、理念) が成熟していき、絶対的理念にまでいきついたところで今度は自然の世界へと外化 (エントオイセルング) する、そして自然の世界が完全に展開し終わったところで今度は精神の世界へと再び外化していくという形で、世界の一切を理念の自己展開運動である弁証法によって解き明かそうとする壮大な試みでした。
Ⅱ.人倫の弁証法
この弁証法は、社会や歴史を考察するときにとりわけ威力を発揮します。『エンツィクロペディー』 の第3篇 『精神哲学』 の第2部 「客観的精神」 の章 (のちにこの部分だけ取り出されて 『法の哲学』 として詳論されました) は、「A 法」、「B 道徳性」、「C 人倫」 の3部から成っています。まったく外的な人間関係だけを扱う法の世界、逆にまったく内的な人間の意志のあり方を扱う道徳性の世界、カントが扱ったのはこの二つの世界だけでした。これに対してヘーゲルは、それら両者の対立を止揚し、ありうべき理念が現実の社会へと外化した共同体のあり方を 「人倫」 の世界として描いています。
社会の最小単位は家族です。家族の本質は子供の育成にあります。二人の男女が結婚して家族をつくり、子を産み、育てていく。子供が成長し一人前となって、家族の目的が達成されるやいなや、子供は家族から巣立っていき、家族は崩壊します。こうして次の段階、市民社会が要請されます。
市民社会は独立した個人が相互の利害によって結ばれる経済社会で、そのモデルは先進国イギリスです。アダム・スミスと同時代のカントは経済を学問的対象として本格的に取り上げることができなかったのですが、ヘーゲルはスミスが描き出した理想的な市民社会を問題化し、その内に孕まれている否定的要素を見据えています。「欲求の体系」 としての市民社会においては、増大し多様化した諸個人の欲求に対応すべく、分業と機械化が進んでいくことによって、国富がどんどん増大して経済的に繁栄していくのですが、しかしそれとともに労働の抽象化による人間疎外と、貧富の差も増大していき、また市民社会の持続的発展のために植民地支配を強めていかなくてはなりません。こうして市民社会は矛盾の極みに達して、国家という最高の段階を要請せざるをえなくなるのです。
Ⅲ.国家から世界史へ
ヘーゲルの言う国家は、市民社会における所有や諸個人の自由・安全を法的に保障するような近代的な夜警国家のことではありません。人々が連帯と共同性を最高度に発揮し、国家の目的が個人の目的であるような、その意味で諸個人と国家が有機的全体として一つにまとまっているような国家をヘーゲルは考えています。そして国家の理想形態として 「立憲君主制」 を掲げました。これは、カントが 「共和制」 を提唱していたのに比して時代に逆行しているようにも見えるため、ヘーゲルはプロイセン国家の御用哲学者にすぎないのだという評価もなされてきました。その一方で、憲法も議会も存在せず、立憲君主制を称えること自体が危険視されていた時代のなかで、プロイセン国家からベルリン大学に招聘されたという身分にあったにもかかわらず、『法の哲学』 を出版して、リベラルな立憲君主制を称えた彼は、まさに進歩的自由主義者として思索し行動していたのだ、と評価する声が昨今では高まってきています。その点については皆さんがそれぞれ判断していただきたいと思います。
さて、ヘーゲルが構想した、人々の連帯と共同性を最高度に発揮させるような国家として、戦時体制下の国家を思い浮かべることができるでしょう。じっさいヘーゲルにとって戦争は重要な意義を持ちます。ヘーゲルはカントとはちがい、永遠平和を最終的な目的とは考えていません。国家は最高の段階ですから、それ以上の発展段階 (国際連盟など) が考えられてはいませんし、ヘーゲルに言わせると、そもそも平和は諸国民を腐敗させるのです。したがって諸国家間の対立は戦争によって決着をつけられる以外にありません。そして国家間の対立に最終的な審判を下すのは世界史なのです。
無数の国家が相争って盛衰を繰り返す場、それが世界史であり、この歴史そのものが弁証法的な発展過程をたどっています。カントは永遠に実現されることのない未来の目的への無限の努力の過程を歴史ととらえましたが、ヘーゲルはこれまで過去に展開されてきた歴史の流れそのものを、絶対的精神の弁証法的発展過程として把握しようとしたのです。
Ⅳ.ヘーゲル左派の 「疎外」 論
ヘーゲルがベルリン大学に就任して以来、彼の哲学は圧倒的な影響力をもち、彼の下に優秀な門弟が集まってヘーゲル学派が形成されました。ヘーゲルの死後もすぐに全集が刊行され始めるなど、ヘーゲル学派の勢いはとどまるところを知りませんでした。しかしながら、ヘーゲルの宗教哲学をどのように解するかについて学派内に意見の相違があったところに、1835年シュトラウスが 『イエスの生涯』 を著し、イエスではなく人類そのものを神人ととらえる汎神論的解釈を提出するにおよんで、その是非をめぐって学派は一気に分裂していくことになります。理性と現実の関係に即して言うならば、現実的なものはすでに理性的であるのだとするヘーゲル右派、理性的なものを現実化していかなければいけないとするヘーゲル左派、両極の媒介を図ろうとする中央派の三つに分かれていきました。特に左派には急進的な若者が集い、青年ヘーゲル学派とも呼ばれました。
その中で、フォイエルバッハは、宗教を人間の立場から捉え返そうとする人間学を提唱しました。神とは人間自身がもつ類的本質が外化されたものにすぎないのですが、その点が見失われてしまい、人間からは超絶した疎遠な存在者として人間に対立するようになってしまっている。このような事態をフォイエルバッハは 「疎外 (エントフレムドゥング)」 と呼び、疎外状態からの回復の必要性を訴えました。とりわけ、ヘーゲルによって理性のみが神格化されていったわけですが、その過程で疎外されてしまった感性 (愛) や自然を真の存在として捉え直すことによって、「唯物論」 という新しい哲学を打ち立てようとしました。
宗教批判からさらに政治批判へと向かう人々も現れました。バウアーは宗教を、歴史の特定の段階において現れる自己意識の疎外態とみなして、宗教と癒着した国家体制の批判にまで進んでいきました。そして、フォイエルバッハの疎外論や唯物論の影響を受けつつ、独自の社会・経済批判を育みつつあったのが、若きマルクスやエンゲルスだったのです。










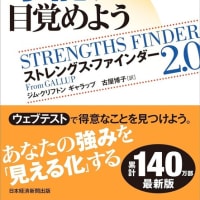









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます