ちょっと気が早いですが、1月のてつカフェは映画 『ハンナ・アーレント』 を見ての、
シネマ de てつがくカフェになることがほぼ決定しましたので、
ハンナ・アーレントという人がどんな哲学者だったのか紹介するための資料をアップしておきましょう。
もうだいぶ以前のことになりますが、私が 「社会思想入門」 という総合科目を担当していた頃、
ハンナ・アーレントについて90分話したことがありますので、
まずは、そのときに配付した資料のほうをアップしておきます。
アーレントは幼い頃からものすごい才女でした。
略年譜のなかの1920年のところを見てください。
このとき彼女はまだ14、5歳ですよ。
それぐらいの歳の頃ぼくや純ちゃんはウーとかアーぐらいしか話せなかったはずです。
22歳で博士号取っちゃってるし。
しかもめちゃくちゃ美人。
師匠であるハイデガーとの色恋沙汰は有名ですが、
さすがにそのことは略年譜には載せていません。
アーレントの言葉も少しだけ引用しておきました。
この資料だけ見てもまだよくわからないだろうと思いますが、
とりあえずこれをご覧いただいておいて、次回は私が書いた解説のための文章をアップします。
興味をもった方はぜひ1番下に載せておいた参考文献のどれかを読んでみてください。
ハンナ・アーレント 資料
1.アーレント略年譜
1906年 ドイツ、ハノーバー近郊のリンデンにてユダヤ系ドイツ人として生誕。父母は裕福な中産階級で社会民主党員。
1913年 父パウル、5年の闘病の末死去。
1920年 母再婚。授業ボイコットを組織し放校処分。この頃、ギリシア語、ラテン語、カント、キルケゴールなどを学ぶ。
1924年 マールブルク大学でハイデガーに学ぶ。
1926年 ハイデルベルク大学でヤスパースに学ぶ。
1928年 『アウグスティヌスの愛の概念』で博士号取得。
1929年 ユダヤ人哲学者ギュンター・シュテルンと結婚。
1930年 『ラーエル・ファルンハーゲン―ドイツ・ロマン派のあるユダヤ人女性の生涯』の執筆開始(59年出版)。
1933年 ベルリンで反ナチ活動に従事。ゲシュタポに逮捕、8日間拘留。パリへ亡命。[ヒトラー政権掌握。国会放火事件。ユダヤ人迫害政策開始。ハイデガー、フライブルク大学総長に就任、ナチス入党。]
1935年 青少年のパレスチナ移住支援組織で活動。
1937年 離婚。
1940年 共産主義活動家ハインリッヒ・ブリュッヒャーと再婚。敵性外国人としてギュルス収容所に抑留されるが、パリ陥落の混乱に乗じて解放され、南フランスへ逃亡。
1941年 アメリカへ亡命。
1942年 [ユダヤ人問題の 「最終的解決」(=ユダヤ人絶滅政策) 決定。]
1943年 アウシュビッツ強制収容所での虐殺の報を聞きショックを受ける。
1948年 母マルタ死去。[イスラエル建国。第一次中東戦争勃発。]
1951年 『全体主義の起源』。アメリカ市民権獲得。
1958年 『人間の条件』。
1961年 アイヒマン裁判を傍聴。『過去と未来の間』。
1963年 『革命について』。『イェルサレムのアイヒマン』。
1972年 『共和国の危機』。
1975年 死去。
1977年 『精神の生活』。
1982年 『カント政治哲学の講義』。
2.アーレントからの引用
①諸権利を持つ権利
「人々は奪うべからざる人権、譲渡することのできぬ人権について語るとき、この権利はあらゆる政府から独立した権利であり、あらゆる人間に具わる権利としてすべての政府によって尊重されるべきだと考えてきた。ところが今、政府の保護を失い市民権を享受し得ず、従って生まれながらに持つ筈の最低限の権利に頼るしかなくなった人々が現れた瞬間に、彼らにこの権利を保障し得る者は存在せず、いかなる国家機関もしくは国際機関もそれを護る用意がないことが突如として明らかになった。…無権利者の不幸は、彼が生命、自由、幸福の追求、法の前の平等、いわんや思想の自由などの権利を奪われていることではない。これらすべては所与の共同体の内部の諸権利を守るために定式化されたものであり、それ故に無権利者の状態とは何の関係もない。無権利状態とは、これに対し、この状態に陥ったものはいかなる種類の共同体にも属さないという事実からのみ生まれている。…人権の喪失が起こるのは通常人権として数えられる権利のどれかを失ったときではなく、人間が世界における足場を失ったときのみである。この足場によってのみ人間はそもそも諸権利を持ち得るのであり、この足場こそ人間の意見が重みを持ち、その行為 (活動) が意味を持つための条件をなしている。」(「全体主義の起源 2」)
②人間の条件
「〈活動的生活 vita activa〉 という用語によって、私は、3つの基本的な人間の活動力、すなわち、労働、仕事、活動を意味するものとしたいと思う。この3つの活動力 activity が基本的だというのは、人間が地上の生命を得た際の根本的な条件に、それぞれが対応しているからである。
労働 labor とは、人間の肉体の生物学的過程に対応する活動力である。人間の肉体が自然に成長し、新陳代謝を行い、そして最後には朽ちてしまうこの過程は、労働によって生命過程の中で生み出され消費される生活の必要物に拘束されている。そこで、労働の人間的条件は生命それ自体である。
仕事 work とは、人間存在の非自然性に対応する活動力である。…仕事は、すべての自然環境と際だって異なる物の『人工的』世界を作り出す。その物の世界の境界線の内部で、それぞれ個々の生命は安住の地を見いだすのであるが、他方、この世界そのものはそれら個々の生命を超えて永続するようにできている。そこで、仕事の人間的条件は世界性 worldliness である。
活動 action とは、物あるいは物質の介入なしに直接人と人との間で行われる唯一の活動力であり、複数性 plurality という人間の条件、すなわち、地球上に生き世界に住むのがひとりの人間 man ではなく、複数の人間 men であるという事実に対応している。たしかに人間の条件のすべての側面が多少とも政治に関わってはいる。しかしこの複数性こそ、全政治生活の条件であり、その必要条件であるばかりか、最大の条件である。」(『人間の条件』)
③悪の陳腐さ [=凡庸さ]
「やったことはとんでもないことだが、犯人 (今、法廷にいる、すくなくともかつてはきわめて有能であった人物) はまったくのありふれた俗物で、悪魔のようなところもなければ巨大な怪物のようでもなかった。彼にはしっかりしたイデオロギー的確信があるとか、特別の悪の動機があるといった兆候はなかった。過去の行動及び警察による予備尋問と本審の過程でのふるまいを通じて唯一推察できた際だった特質といえば、まったく消極的な性格のものだった。愚鈍だというのではなく、何も考えていない thoughtlessness ということなのである。」(『イェルサレムのアイヒマン』)
3.参考文献
〈アーレントの翻訳書〉
・『全体主義の起源 1・2・3』(大久保和郎他訳、みすず書房)
・『人間の条件』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫)
・『革命について』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫)
・『イェルサレムのアイヒマン』(大久保和郎訳、みすず書房)
・『カント政治哲学の講義』(浜田義文監訳、法政大学出版局)
〈アーレント思想の解説書・研究書〉
・川崎修『現代思想の冒険者たち17 アレント』(講談社)
・杉浦敏子『ハンナ・アーレント入門』(藤原書店)
・矢野久美子『ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考の場所』(みすず書房)
・吉田傑俊他編『アーレントとマルクス』(大月書店)
・エルジビェータ・エティンガー『アーレントとハイデガー』(大島かおり訳、みすず書房)
シネマ de てつがくカフェになることがほぼ決定しましたので、
ハンナ・アーレントという人がどんな哲学者だったのか紹介するための資料をアップしておきましょう。
もうだいぶ以前のことになりますが、私が 「社会思想入門」 という総合科目を担当していた頃、
ハンナ・アーレントについて90分話したことがありますので、
まずは、そのときに配付した資料のほうをアップしておきます。
アーレントは幼い頃からものすごい才女でした。
略年譜のなかの1920年のところを見てください。
このとき彼女はまだ14、5歳ですよ。
それぐらいの歳の頃ぼくや純ちゃんはウーとかアーぐらいしか話せなかったはずです。
22歳で博士号取っちゃってるし。
しかもめちゃくちゃ美人。
師匠であるハイデガーとの色恋沙汰は有名ですが、
さすがにそのことは略年譜には載せていません。
アーレントの言葉も少しだけ引用しておきました。
この資料だけ見てもまだよくわからないだろうと思いますが、
とりあえずこれをご覧いただいておいて、次回は私が書いた解説のための文章をアップします。
興味をもった方はぜひ1番下に載せておいた参考文献のどれかを読んでみてください。
ハンナ・アーレント 資料
1.アーレント略年譜
1906年 ドイツ、ハノーバー近郊のリンデンにてユダヤ系ドイツ人として生誕。父母は裕福な中産階級で社会民主党員。
1913年 父パウル、5年の闘病の末死去。
1920年 母再婚。授業ボイコットを組織し放校処分。この頃、ギリシア語、ラテン語、カント、キルケゴールなどを学ぶ。
1924年 マールブルク大学でハイデガーに学ぶ。
1926年 ハイデルベルク大学でヤスパースに学ぶ。
1928年 『アウグスティヌスの愛の概念』で博士号取得。
1929年 ユダヤ人哲学者ギュンター・シュテルンと結婚。
1930年 『ラーエル・ファルンハーゲン―ドイツ・ロマン派のあるユダヤ人女性の生涯』の執筆開始(59年出版)。
1933年 ベルリンで反ナチ活動に従事。ゲシュタポに逮捕、8日間拘留。パリへ亡命。[ヒトラー政権掌握。国会放火事件。ユダヤ人迫害政策開始。ハイデガー、フライブルク大学総長に就任、ナチス入党。]
1935年 青少年のパレスチナ移住支援組織で活動。
1937年 離婚。
1940年 共産主義活動家ハインリッヒ・ブリュッヒャーと再婚。敵性外国人としてギュルス収容所に抑留されるが、パリ陥落の混乱に乗じて解放され、南フランスへ逃亡。
1941年 アメリカへ亡命。
1942年 [ユダヤ人問題の 「最終的解決」(=ユダヤ人絶滅政策) 決定。]
1943年 アウシュビッツ強制収容所での虐殺の報を聞きショックを受ける。
1948年 母マルタ死去。[イスラエル建国。第一次中東戦争勃発。]
1951年 『全体主義の起源』。アメリカ市民権獲得。
1958年 『人間の条件』。
1961年 アイヒマン裁判を傍聴。『過去と未来の間』。
1963年 『革命について』。『イェルサレムのアイヒマン』。
1972年 『共和国の危機』。
1975年 死去。
1977年 『精神の生活』。
1982年 『カント政治哲学の講義』。
2.アーレントからの引用
①諸権利を持つ権利
「人々は奪うべからざる人権、譲渡することのできぬ人権について語るとき、この権利はあらゆる政府から独立した権利であり、あらゆる人間に具わる権利としてすべての政府によって尊重されるべきだと考えてきた。ところが今、政府の保護を失い市民権を享受し得ず、従って生まれながらに持つ筈の最低限の権利に頼るしかなくなった人々が現れた瞬間に、彼らにこの権利を保障し得る者は存在せず、いかなる国家機関もしくは国際機関もそれを護る用意がないことが突如として明らかになった。…無権利者の不幸は、彼が生命、自由、幸福の追求、法の前の平等、いわんや思想の自由などの権利を奪われていることではない。これらすべては所与の共同体の内部の諸権利を守るために定式化されたものであり、それ故に無権利者の状態とは何の関係もない。無権利状態とは、これに対し、この状態に陥ったものはいかなる種類の共同体にも属さないという事実からのみ生まれている。…人権の喪失が起こるのは通常人権として数えられる権利のどれかを失ったときではなく、人間が世界における足場を失ったときのみである。この足場によってのみ人間はそもそも諸権利を持ち得るのであり、この足場こそ人間の意見が重みを持ち、その行為 (活動) が意味を持つための条件をなしている。」(「全体主義の起源 2」)
②人間の条件
「〈活動的生活 vita activa〉 という用語によって、私は、3つの基本的な人間の活動力、すなわち、労働、仕事、活動を意味するものとしたいと思う。この3つの活動力 activity が基本的だというのは、人間が地上の生命を得た際の根本的な条件に、それぞれが対応しているからである。
労働 labor とは、人間の肉体の生物学的過程に対応する活動力である。人間の肉体が自然に成長し、新陳代謝を行い、そして最後には朽ちてしまうこの過程は、労働によって生命過程の中で生み出され消費される生活の必要物に拘束されている。そこで、労働の人間的条件は生命それ自体である。
仕事 work とは、人間存在の非自然性に対応する活動力である。…仕事は、すべての自然環境と際だって異なる物の『人工的』世界を作り出す。その物の世界の境界線の内部で、それぞれ個々の生命は安住の地を見いだすのであるが、他方、この世界そのものはそれら個々の生命を超えて永続するようにできている。そこで、仕事の人間的条件は世界性 worldliness である。
活動 action とは、物あるいは物質の介入なしに直接人と人との間で行われる唯一の活動力であり、複数性 plurality という人間の条件、すなわち、地球上に生き世界に住むのがひとりの人間 man ではなく、複数の人間 men であるという事実に対応している。たしかに人間の条件のすべての側面が多少とも政治に関わってはいる。しかしこの複数性こそ、全政治生活の条件であり、その必要条件であるばかりか、最大の条件である。」(『人間の条件』)
③悪の陳腐さ [=凡庸さ]
「やったことはとんでもないことだが、犯人 (今、法廷にいる、すくなくともかつてはきわめて有能であった人物) はまったくのありふれた俗物で、悪魔のようなところもなければ巨大な怪物のようでもなかった。彼にはしっかりしたイデオロギー的確信があるとか、特別の悪の動機があるといった兆候はなかった。過去の行動及び警察による予備尋問と本審の過程でのふるまいを通じて唯一推察できた際だった特質といえば、まったく消極的な性格のものだった。愚鈍だというのではなく、何も考えていない thoughtlessness ということなのである。」(『イェルサレムのアイヒマン』)
3.参考文献
〈アーレントの翻訳書〉
・『全体主義の起源 1・2・3』(大久保和郎他訳、みすず書房)
・『人間の条件』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫)
・『革命について』(志水速雄訳、ちくま学芸文庫)
・『イェルサレムのアイヒマン』(大久保和郎訳、みすず書房)
・『カント政治哲学の講義』(浜田義文監訳、法政大学出版局)
〈アーレント思想の解説書・研究書〉
・川崎修『現代思想の冒険者たち17 アレント』(講談社)
・杉浦敏子『ハンナ・アーレント入門』(藤原書店)
・矢野久美子『ハンナ・アーレント、あるいは政治的思考の場所』(みすず書房)
・吉田傑俊他編『アーレントとマルクス』(大月書店)
・エルジビェータ・エティンガー『アーレントとハイデガー』(大島かおり訳、みすず書房)










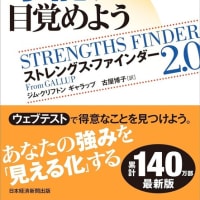









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます