
山川出版の 『倫理用語集』 です。
受験のときにお世話になった人も多いことでしょう。
「倫理」 で受験しなかった人も、『日本史用語集』 や 『世界史用語集』、
『現代社会用語集』 などのいずれかにはお世話になったんではないでしょうか。
私は以前から左側のやつを持っていましたが、このたびある仕事で必要になったために、
新しい版が出てないかと思って本屋さんに行ってみたら、やはりありました。
それが右側の 『改訂版 倫理用語集』 です。
私が持っていた一番最初のやつは1996年に初めて出版されています。
昔からあったような気がしていましたが、私が高校生の頃にはなかったんですね。
たぶん 『世界史用語集』 と混同しているのでしょう。
その後、何回かの学習指導要領の改訂があり、教科書も書き改められていますので、
旧版では最新の情報に対応できていないのではないかと推測して探してみたのですが、
改訂版は2009年に出されていました。
(この前に2005年に新課程用というのも出されていたようです。)
この新しいのを手にしてみてとにかく驚かされたのは、
旧版に比べてものすごく厚くなっているということでした。
写真で左の旧版と右の改訂版を見比べていただいても一目瞭然でしょう。
旧版は総頁数225ページ。
それに対して改訂版は334ページもあります。
110ページもの増量、1.5倍の厚さになっています。
さすがに項目数を数えるほどヒマではありませんでしたが、
アマゾンの記述によれば、2000語強だったものが3000語強に増えているそうです。
ほんの15年ほどのあいだにそんなに倫理用語は増えてしまっていたんですかっ!
これはいったいどういうことでしょうか?
「公民科教育法」 の授業で私は 「倫理」 の学習指導要領の解説とかをしているのですが、
例の、学校週休2日制化以来、学習指導要領が改訂されるたびに、
「先哲の基本的な考え方を取り上げるに当たっては、
内容と関連が深く生徒の発達や学習段階に適した代表的な先哲やその言説を精選し、
細かな事柄や高度な事項・事柄には深入りしないこと」
という注意が何度も繰り返されているのです。
にもかかわらず、教科書に記載される倫理用語は反対にどんどん増えていっています。
今まで教科書に載っていなかったような新しい思想家が取り上げられるようになり、
細かな事柄への言及も増えていっているのです。
これは大学入試センター試験の出題が年々高度化してきているためだと思われます。
出題する側からするならば、
過去問との重複を避けるという入試作成上の慣例に従ってしまうと、
どうしても新しいこと、細かいことに流れざるをえません。
そして学校現場ではセンター試験に出るようなことが載っていない教科書を採用するのは難しく、
したがって教科書会社側としては、センター試験に対応できるような教科書を作らざるをえない、
という悪循環が生じてしまうのです。
その結果がこの 『倫理用語集』 の大幅増頁という形で表れているわけです。
文科省の方針や学習指導要領の拘束力は、この流れを食い止めることができません。
私は別に学習指導要領で教育内容を縛ったり、
文科省が教科書を検閲したりすることをいいこととは思っていませんが、
細かな事柄や高度な事項・事柄には深入りしすぎないのは大事なことだと思っていますので、
センター試験や教科書がそれとは反対の方向に向かっているのはいいこととは思えません。
これは上述したような出題の際におけるテクニカルな問題に起因していますので、
そこは改められるなら改めたほうがいいだろうなとおもっております。
センター試験で過去問を出題してもいいことにしたのは、
なかなかいい決定だったんではないでしょうか。
ゆくゆくは自動車免許の筆記試験のように、ストックしてあるたくさんのセットの問題から、
テキトーなローテーションで出題していくというくらいになってもいいような気がします。
毎年毎年気をすり減らしながら、過去問やどこかの模擬試験ともかぶらないように、
日本中の研究者からも高校の先生たちからも何一つクレームがつかず、
正答が正答であり誤答が誤答であることが絶対的に明確で、
かつ全員が正答してしまうわけではないような、
マークシートの四択で答えられるような良問を作り続けることなんて、
学者の無駄遣い以外のなにものでもないように思います。
分厚くなった 『倫理用語集』 を見ながら、
これを使って勉強しなければならない高校生たちのことと同時に、
今もどこかでセンター試験を作り続けているであろう、
かわいそうな同業者たちのことに思いを馳せてしまったのでした。
受験のときにお世話になった人も多いことでしょう。
「倫理」 で受験しなかった人も、『日本史用語集』 や 『世界史用語集』、
『現代社会用語集』 などのいずれかにはお世話になったんではないでしょうか。
私は以前から左側のやつを持っていましたが、このたびある仕事で必要になったために、
新しい版が出てないかと思って本屋さんに行ってみたら、やはりありました。
それが右側の 『改訂版 倫理用語集』 です。
私が持っていた一番最初のやつは1996年に初めて出版されています。
昔からあったような気がしていましたが、私が高校生の頃にはなかったんですね。
たぶん 『世界史用語集』 と混同しているのでしょう。
その後、何回かの学習指導要領の改訂があり、教科書も書き改められていますので、
旧版では最新の情報に対応できていないのではないかと推測して探してみたのですが、
改訂版は2009年に出されていました。
(この前に2005年に新課程用というのも出されていたようです。)
この新しいのを手にしてみてとにかく驚かされたのは、
旧版に比べてものすごく厚くなっているということでした。
写真で左の旧版と右の改訂版を見比べていただいても一目瞭然でしょう。
旧版は総頁数225ページ。
それに対して改訂版は334ページもあります。
110ページもの増量、1.5倍の厚さになっています。
さすがに項目数を数えるほどヒマではありませんでしたが、
アマゾンの記述によれば、2000語強だったものが3000語強に増えているそうです。
ほんの15年ほどのあいだにそんなに倫理用語は増えてしまっていたんですかっ!
これはいったいどういうことでしょうか?
「公民科教育法」 の授業で私は 「倫理」 の学習指導要領の解説とかをしているのですが、
例の、学校週休2日制化以来、学習指導要領が改訂されるたびに、
「先哲の基本的な考え方を取り上げるに当たっては、
内容と関連が深く生徒の発達や学習段階に適した代表的な先哲やその言説を精選し、
細かな事柄や高度な事項・事柄には深入りしないこと」
という注意が何度も繰り返されているのです。
にもかかわらず、教科書に記載される倫理用語は反対にどんどん増えていっています。
今まで教科書に載っていなかったような新しい思想家が取り上げられるようになり、
細かな事柄への言及も増えていっているのです。
これは大学入試センター試験の出題が年々高度化してきているためだと思われます。
出題する側からするならば、
過去問との重複を避けるという入試作成上の慣例に従ってしまうと、
どうしても新しいこと、細かいことに流れざるをえません。
そして学校現場ではセンター試験に出るようなことが載っていない教科書を採用するのは難しく、
したがって教科書会社側としては、センター試験に対応できるような教科書を作らざるをえない、
という悪循環が生じてしまうのです。
その結果がこの 『倫理用語集』 の大幅増頁という形で表れているわけです。
文科省の方針や学習指導要領の拘束力は、この流れを食い止めることができません。
私は別に学習指導要領で教育内容を縛ったり、
文科省が教科書を検閲したりすることをいいこととは思っていませんが、
細かな事柄や高度な事項・事柄には深入りしすぎないのは大事なことだと思っていますので、
センター試験や教科書がそれとは反対の方向に向かっているのはいいこととは思えません。
これは上述したような出題の際におけるテクニカルな問題に起因していますので、
そこは改められるなら改めたほうがいいだろうなとおもっております。
センター試験で過去問を出題してもいいことにしたのは、
なかなかいい決定だったんではないでしょうか。
ゆくゆくは自動車免許の筆記試験のように、ストックしてあるたくさんのセットの問題から、
テキトーなローテーションで出題していくというくらいになってもいいような気がします。
毎年毎年気をすり減らしながら、過去問やどこかの模擬試験ともかぶらないように、
日本中の研究者からも高校の先生たちからも何一つクレームがつかず、
正答が正答であり誤答が誤答であることが絶対的に明確で、
かつ全員が正答してしまうわけではないような、
マークシートの四択で答えられるような良問を作り続けることなんて、
学者の無駄遣い以外のなにものでもないように思います。
分厚くなった 『倫理用語集』 を見ながら、
これを使って勉強しなければならない高校生たちのことと同時に、
今もどこかでセンター試験を作り続けているであろう、
かわいそうな同業者たちのことに思いを馳せてしまったのでした。










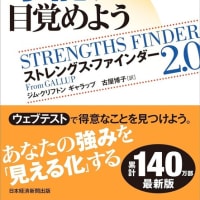









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます