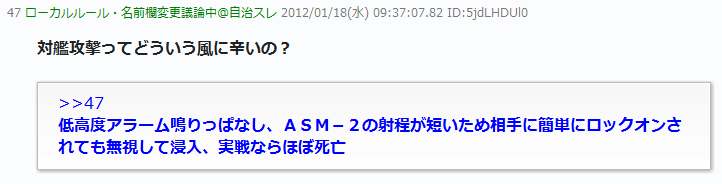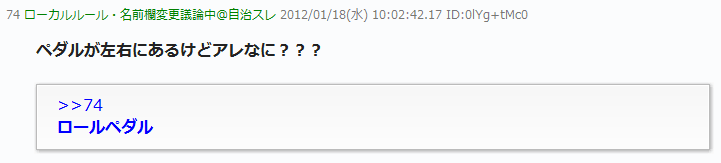古来より戦争では、必要に応じて
要塞が築城された。
要塞とは、要所を防衛もしくは避難する為の機能を持たせた強固な建築物であり、
それは土や石やレンガを素材にしたり、コンクリートや鉄筋で固められていたり、
地上にあったり地下にあったり山肌にトンネルを掘ったり、時代や場所によって様々である。
古代や中世では要塞として城や砦などが世界各地に築城されていたが、
これらの背が高い城壁は火薬と砲の発達と共に格好の標的となり、有効性を失っていった。
やがて要塞は背を低く、厚さを増し、隠蔽され、火砲を据え付けるようになり、
このように軍事テクノロジーが進歩するごとに要塞も姿形を変えてきた。
 |
| 第一次世界大戦の塹壕 |
日露戦争や第一次世界大戦の時代の近代的な要塞で主流のものは、コンクリートや土で補強された堡塁が建造され、
複数の堡塁はお互いに援護し合える配置で、さらにそれらは連絡路として塹壕で接続されていた。
こういった要塞は砲撃に対して強く、また砲台や新兵器である
機関銃を据え付けることにより、
塹壕や堡塁に生身で突進して取り付こうとする敵歩兵部隊に弾丸の雨を浴びせ薙ぎ倒すことができた。
さらにこの塹壕と堡塁の陣地はその後ろにも同様のものが築城され、何重もの陣地線とされ、
一番前の塹壕と堡塁が陥落してもまたそのすぐ後ろの同様の陣地線が立ちはだかるというものだった。
当時の歩兵は生身で突撃するしかなく、機関銃の弾幕の前に倒れて倒れてようやく一番手前の塹壕線を確保したところで、
また同様の陣地がそのすぐ後ろにあり、それを確保する為にさらに甚大な被害を被らなければならないという。
こういった機関銃と砲撃の発達による防御力の向上は、第一次世界大戦を長期化させ、人口をすり減らすような消耗戦を生じさせた。
要塞の欠点として、その土地に築城されるものであるから、当然移動できないというのが最大の弱点であった。
つまり要塞そのものに正面から当たらず迂回すれば良い、という
機動戦の考えは当時からあり、
実際に第一次世界大戦の緒戦では迂回・包囲されあっさり陥落した要塞も多い。
しかし西部戦線のフランスとドイツは国境線に沿い競って塹壕線を伸ばし、ついには海峡にまで達し、
騎兵や歩兵で進軍すれば機関銃や砲撃に薙ぎ倒され、平野における機動戦を不可能にした。
こういった状況を打開する為に、大戦中の1916年、史上初の
戦車という兵器が戦場に登場する。
機関銃の弾幕や砲撃の破片をものともしない装甲と、歩兵に引っ張られずとも自ら機動できる動力を有し、
歩兵の盾となりながら敵の塹壕線まで前進し、搭載された機関銃や砲で敵歩兵を蹂躙する。
戦車という兵器の当初の発想はまさに
「移動できる要塞」であった。
 |
| 第一次世界大戦時のドイツ軍の初歩的な戦車 |
時代を経て1939年、第二次世界大戦が勃発する。
またもやフランスとドイツは対峙することになるが、両国の戦術は違っていた。
フランスの防衛戦略は25年前の第一次世界大戦での戦術の延長線上にあるもので、
ドイツとの国境に沿って穴なく配置された巨大な要塞群、
マジノ線を築城し、マジノ線を少数兵力で強固に防衛し、
その分余った戦力で主力軍を形成し中立国ベルギーとの国境に配置するものであった。
実際にドイツは第一次でも第二次でも両大戦でベルギーから迂回しての突破戦略を採用しているので、
フランスのこの防衛戦略は決して的違いではなかったが、新兵器の戦車の運用法がまだ確立していなかった。
フランスの戦車の運用法は第一次世界大戦と同じく歩兵支援に尽きるもので、
歩兵師団の中に散りばめて配備し、その装甲と火力で歩兵戦闘の直接支援を行うものであった。
一方ドイツの戦車の運用法は、戦車と歩兵輸送車輌を主体に装甲師団を編成し、
さらに装甲師団をまとめて集中運用することにより戦線の一点突破を図る。
その突破口に後続の歩兵部隊を雪崩込ませて穴を広げ、その間も戦車部隊はさらに奥へ奥へと進撃し敵軍司令部や物資集積所を制圧、
指揮系統を破壊しつつそこから生じた混乱の中で、優れた機動力で敵野戦軍を包囲・殲滅するものであった。
戦車を歩兵部隊に散りばめていてはその部隊の機動力は結局歩兵と同じであるが、戦車は戦車で運用すれば機動力を発揮できる。
その戦車部隊の機動力に通常は牽引・設置などに手間取る砲兵部隊が追従できるはずもないが、
ドイツ軍はこれまた前大戦から投入された新兵器である
航空機を
「空飛ぶ砲兵」と称し、
敵戦線に高速に食い込む戦車部隊を爆撃機から降らす爆弾で空から支援した為に、
最大限の機動力と攻撃力を両立・発揮させることに成功した。
これらの戦車と爆撃機という新兵器の運用法、
電撃戦によるドイツ軍の進撃速度は、
フランス軍が想定していた戦いの局面とは全く別のものであり、フランスは1ヶ月で降伏することになる。
 |
| マジノ線は現在も残っており、観光地となっている |
フランス軍はマジノ線という要塞群と歩兵とその支援という、第一次世界大戦型の戦術で圧倒的敗北を喫した。
近代兵器の機動力の前にはもはや要塞は存在意義を失ったものという認識が世界各国に広まったが、
迂回できない地形や、重要な戦略目標そのものが要塞化されていた場合はまだ有効性を保っていた。
ブレスト要塞、セヴァストポリ要塞、オマハ・ビーチ、硫黄島の戦い、などは第二次世界大戦で要塞が有効性を発揮した著名な戦闘である。
現代戦に於いては、一般的な要塞はさらに無用の長物と化す。
コンクリートで塗り固められたトーチカは強固には違いないが、現代の航空機は目標にピンポイントで誘導爆弾を投下する能力を有しており、
通常の航空爆弾ごときでトーチカは破壊されないが、貫通力を高めた
バンカー・バスターはコンクリートやシェルターでも貫通し内部から爆破する。
また事前に要塞の場所が判明していれば、航空機を飛ばすまでもなく
巡航ミサイルで一方的に破壊することも可能である。
しかし完全に全ての要塞が無用となったのではなく、例えば地下シェルターなどは隠蔽場所にもってこいで、
ゲリラ戦の根拠地となったり対地ロケットやミサイルなど兵器や物資を隠していたりと厄介な場面もあり、
直接戦闘となれば現代兵器の的となるが、秘密基地的な隠れ家という性格で言えば有用性は残っている。
また最新戦闘機による空爆や巡航ミサイルなどの支援はあてにできる国のほうが少ないので、
先進国以外の途上国軍隊同士の戦争であれば、未だに要塞やトーチカというのは有効性を十分に発揮し得る。
また要塞というのを強固な建築物や構造物という見た目のみに捉えず、
「敵軍に対して強力な火力と防御力を発揮し、攻略困難と認識させ、プレッシャーを与えるか迂回を強要させる特火点である。」
という概念上のものとして捉えれば、現代の先進国同士の軍隊でも要塞という概念は残っている。
高射砲や対空ミサイル、対艦ミサイルや対戦車ミサイル、ロケット砲や機銃などが多数設置され、
そのように厳重に防護された航空基地や離島などはそれ自体が概念的には要塞であり、
近づくことも危険で迂回せざるを得ない、またはそこにあるだけで敵軍に対して大きなプレッシャーとなり得るものだ。
つまり軍事テクノロジーの進歩によって一見存在意義を失ったように思える要塞も、
現代型として大きく形を変えて、そのようにして今後も残っていくだろう。