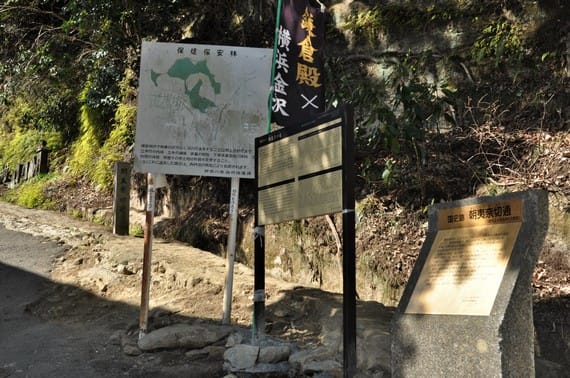【神奈川・横須賀市】京浜急行線堀ノ内駅とJR横須賀線衣笠駅の間のエリア(三春町と公郷町)に点在する庚申塔を巡った。 堀ノ内駅から三春町の住宅街を通って西側の丘陵を上っていくと、丘陵の住宅地を結ぶ狭い道の路傍2カ所に庚申塔が鎮座。 丘陵を下って公郷トンネルに向かい、トンネルの北側(東京湾側)の脇から丘陵を上りつめると、最初の民家の道沿いに庚申塔が鎮座。 丘陵の衣笠側を下り、JR衣笠駅に向かうバス道路にでて少し進むと、バス停「公郷トンネル」のすぐ傍の崖下のコンクリート台座上に庚申塔が鎮座。
■堀ノ内駅西側の丘陵の路傍に鎮座する庚申塔■

位置の説明が難しいが、堀ノ内駅西側の丘陵(三春町)の上の路傍2ヶ所に庚申塔が鎮座している。 1ヶ所目は樹林を背にして鎮座する4基の文字庚申塔と「弁財天」文字塔で、3基は江戸時代の元禄・延享・明和の造立、残り1基は約90年前の昭和八年(1933)に造立されたもの。 庚申信仰が昭和の時代にも連綿と続いていた証であり興味深い。
2ヶ所目は日当たりのよい三叉路の角地に、昭和九年(1934)造立の「山坂弁財天」文字塔と江戸前期の貞享元年(1682)造立の庚申塔で「奉勧請南無帝釈天王御加護」と陰刻されている。

△丘陵の住宅地(三春町)の路傍に佇む4基の文字庚申塔と「弁財天」文字塔....右端は昭和八年(1933)造立の駒型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「南無庚申塔」の陰刻



△明和五年(1768)造立の櫛型文字庚申塔....「南無庚申塔」の陰刻/延享四年(1747)造立の笠を失った笠付型(?)文字庚申塔(3猿)....「南無庚申」の陰刻/元禄十六年(1703)造立の板碑型文字庚申塔(日月瑞雲)....「南無妙法蓮華経勧請帝釈天王」の陰刻

△京急線堀ノ内駅西側の丘陵(三春町)に佇む庚申塔

△丘陵上の三叉路の路傍に佇む1基の庚申塔と、左は昭和九年(1934)造立の「山坂弁財天」文字塔


△貞享元年(1684)造立の笠付型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)....「奉勧請南無帝釈天王御加護」の陰刻/庚申塔の3猿
■公郷トンネルがある丘陵の住宅地の民家脇に鎮座する庚申塔■

JR衣笠駅に向かうバス道路を横断し、公郷トンネル右脇の坂道を上った丘陵地(三春町)に幾つかの住宅が建ち、民家脇(多分、私有地)のコンクリート台座の上に9基の庚申塔が整然と並んでいる。 江戸時代の延宝二年(1674)から明治三年(1870)に造立されたいずれも文字庚申塔。 一番古い江戸前期の延宝二年造立の庚申塔は、「南無妙法蓮華経庚申○○」の陰刻があり、日蓮宗の題目と庚申信仰とを組み合わせた珍しいものと思う。

△住宅地の民家脇に整然と鎮座する9基の文字庚申塔

△右側3基の庚申塔.....右は文政七年(1824)造立の柱状型文字庚申塔で「庚申供養塔」の陰刻、中は弘化五年(1848)造立の駒型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「奉納帝釈天王」の陰刻、左は安永五年(1776)造立の駒型文字庚申塔で「奉納庚申供養塔」の陰刻

△中央3基の庚申塔.....右は文政十三年(1830)造立の駒形文字庚申塔(日月瑞雲)で「南無帝釈天王」の陰刻、中は宝永八年(1711)造立の笠付型(笠欠落と思う)文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「奉納南無帝釈天王現安後善守所」の陰刻、左は延宝二年(1674)造立の柱状型文字庚申塔(3猿)で「南無妙法蓮華経庚申○○」の陰刻

△左側3基の庚申塔....右は明治三年(1870)造立の駒型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「帝釈天王」の陰刻、中は天明八年(1788)造立の駒型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「青面金剛」の陰刻、左は文化四年(1807)造立の駒型文字庚申塔(日月瑞雲、3猿)で「青面金剛塔」の陰刻


△右端に置かれたこの笠は中央の宝永八年造立の文字庚申塔のものか?/笠の後方に鎮座する小さな地蔵石仏(造立年号不明)
■バス停「公郷トンネル」近くの崖下に鎮座する庚申塔■

丘陵の住宅地から坂道を下り、JR衣笠駅に向かうバス道路を少し南に進むと、まもなく三春町と公郷町の町境近くに「公郷トンネル」というバス停があり、傍の道路沿いの崖下のコンクリート台座の上に10基の庚申塔が東面で並んでいる。 江戸時代の寛文十一二年(1671)から明治三十年(1897)に造立されたいずれも文字庚申塔。 江戸前期の寛文十二年と元禄五年(1692)に造立された庚申塔には、それぞれ「南無妙法蓮華経」、「妙法蓮華経帝釈天王守護所」と陰刻されている。 日蓮宗の題目が庚申塔に現れる文字としては珍しく、この地域では、江戸時代前期は日蓮宗の法華経信仰と庚申信仰とが結びついて信仰されたようで興味深い。

△バス道路に面してコンクリート基壇上に並ぶ10基の文字庚申塔....左端は笠と基礎のみの笠付型庚申塔

△右側3基の駒型庚申塔....右は明治三十年(1897)造立の駒型文字庚申塔(3猿)で「南無帝釈天王」の陰刻、中は安永十年(1781)造立の駒形文字庚申塔(3猿)で「奉納庚申塔」の陰刻、左は文政八年(1852)造立の駒形文字庚申塔(3猿)で「青面金剛塔」の陰刻

△中央3基の庚申塔....右は慶応四年(1868)造立の駒型文字庚申塔(3猿)で「帝釈天王」の陰刻、中は嘉永元年(1848)造立の駒型文字庚申塔(3猿)で「庚申供養」の陰刻、左は安政五年(1858)造立の柱状型文字庚申塔で「帝釈天王」の陰刻

△左側3基の庚申塔....右は明治十九年(1886)造立の笠付型(笠無し)文字庚申塔(3猿)で「帝釈天王」の陰刻、中は寛文十一年(1671)造立の駒型文字庚申塔(3猿)で「南無妙法蓮華経」の陰刻、左は元禄五年(1692)造立の箱型文字庚申塔で「妙法蓮華経帝釈天王守護所」の陰刻