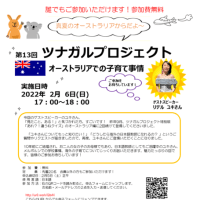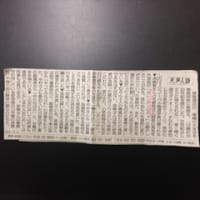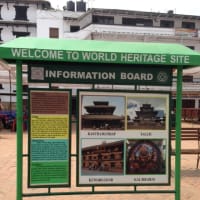私のスクールの小学1-2年生ではエリックカールの絵本’Brown bear, brown bear, what do you see?’を音読します。
この絵本では色と動物を学ぶことができますが、もうひとつ、動物の鳴き声についても言及します。
授業は英語で行いますので、英語で動物の鳴き声も紹介します。
以前私が子どもたちに’A dog says bow-wow.’と言ったら、ひとりの男の子が、
「すごいな、アメリカの犬は英語で吠えるんだね 」と言いました。
」と言いました。
その発想がかわいくて、私の方が爆笑してしまいました 。
。
聞こえているのは同じ鳴き声ですが、日本語では「ワンワン」、英語では’bow-wow’ となります。
となります。
にわとりの「コケコッコー」は’cock-a-doodle-doo’ です。
です。
こういう音を言葉にしたものを「擬音語」英語では「オノマトペ ‘onomatopoeia’」と呼びます。
それにしても日本語の擬音語は数も多く、繊細です。
例えば、「風」の吹き方ひとつをとっても、「そよそよ」「びゅーびゅー」
「ぴゅーぴゅー」とありますし、「雨」にしても「ぽつぽつ」「ざーざー」「しとしと」と日常的に使い分けています。
おそらく日本人独自の感性で自然の音を捉えているのでしょう。昔から和歌や俳句にも季節の風情や心情をこれら擬音語で伝えてきました。
外国人には理解しづらいでしょう。日本語検定を受ける外国人の友人たちは、「数量詞」同様、この「擬態語・擬音語」が「超むずかしい」と言います。
人間の脳は、音を処理する右脳と、言語(特に文字)を処理する左脳にわかれています。音は本来、右脳で処理されていますが、日本人は自然の音を左脳で聴いているのかもしれません。
以前、次男がアメリカにホームステイに行った時に、日本の漫画の「ブリーチ」英語版を買って帰ってきました。この漫画に描かれている擬音語や擬態語がなかなかおもしろかったのです。
例えば「ピンポン玉を抜き取る音」は日本語では「ゴポッ」なんですが、これに相当する英語はないんでしょう・・・かわりに’pull up’を音化して’pl-up’となっている。苦肉の策です。
日本の漫画はオノマトペだらけですから、英語にするのは本当に至難の業と察します。
日本語のオノマトペ・・・’S’は「スイスイ」「スラスラ」「スルスル」・・・。「滑らかさが洗われる。Sが持っている音声的な正確です。人間には共通の感覚があると思う」と述べられたのは「日英オノマトペ大辞典」を完成させた田守育啓さん(もと兵庫県立大教授)。
なぜ日本人はオノマトペを愛し、工夫してきたのか?
「日本人は自然の音と敵対せずに調和しようとしてきたから」(朝日新聞、ニッポン人脈記より抜粋)
なーるほど 日本人は音と文字に敏感なのかもしれませんね。
日本人は音と文字に敏感なのかもしれませんね。
この素晴らしい精神と文化を子どもたちにも伝えていきたいものです。
この絵本では色と動物を学ぶことができますが、もうひとつ、動物の鳴き声についても言及します。
授業は英語で行いますので、英語で動物の鳴き声も紹介します。
以前私が子どもたちに’A dog says bow-wow.’と言ったら、ひとりの男の子が、
「すごいな、アメリカの犬は英語で吠えるんだね
 」と言いました。
」と言いました。その発想がかわいくて、私の方が爆笑してしまいました
 。
。聞こえているのは同じ鳴き声ですが、日本語では「ワンワン」、英語では’bow-wow’
 となります。
となります。にわとりの「コケコッコー」は’cock-a-doodle-doo’
 です。
です。こういう音を言葉にしたものを「擬音語」英語では「オノマトペ ‘onomatopoeia’」と呼びます。
それにしても日本語の擬音語は数も多く、繊細です。
例えば、「風」の吹き方ひとつをとっても、「そよそよ」「びゅーびゅー」
「ぴゅーぴゅー」とありますし、「雨」にしても「ぽつぽつ」「ざーざー」「しとしと」と日常的に使い分けています。
おそらく日本人独自の感性で自然の音を捉えているのでしょう。昔から和歌や俳句にも季節の風情や心情をこれら擬音語で伝えてきました。
外国人には理解しづらいでしょう。日本語検定を受ける外国人の友人たちは、「数量詞」同様、この「擬態語・擬音語」が「超むずかしい」と言います。
人間の脳は、音を処理する右脳と、言語(特に文字)を処理する左脳にわかれています。音は本来、右脳で処理されていますが、日本人は自然の音を左脳で聴いているのかもしれません。
以前、次男がアメリカにホームステイに行った時に、日本の漫画の「ブリーチ」英語版を買って帰ってきました。この漫画に描かれている擬音語や擬態語がなかなかおもしろかったのです。
例えば「ピンポン玉を抜き取る音」は日本語では「ゴポッ」なんですが、これに相当する英語はないんでしょう・・・かわりに’pull up’を音化して’pl-up’となっている。苦肉の策です。
日本の漫画はオノマトペだらけですから、英語にするのは本当に至難の業と察します。
日本語のオノマトペ・・・’S’は「スイスイ」「スラスラ」「スルスル」・・・。「滑らかさが洗われる。Sが持っている音声的な正確です。人間には共通の感覚があると思う」と述べられたのは「日英オノマトペ大辞典」を完成させた田守育啓さん(もと兵庫県立大教授)。
なぜ日本人はオノマトペを愛し、工夫してきたのか?
「日本人は自然の音と敵対せずに調和しようとしてきたから」(朝日新聞、ニッポン人脈記より抜粋)
なーるほど
 日本人は音と文字に敏感なのかもしれませんね。
日本人は音と文字に敏感なのかもしれませんね。この素晴らしい精神と文化を子どもたちにも伝えていきたいものです。