あらゆる法律問題について一つ一つ論理の上での解決の道筋をつけていったとき、最後の最後に残されるのが、「無罪判決が言い渡された殺人事件の被害者遺族」だろうと思います。そして、無論その中でも優劣はつけられませんが、殺人が逆縁をもたらした場合の無罪判決は、その我が子をこの世に生み出した両親の人生を粉砕するだろうと思います。もとより人間が作る法は不完全なものである以上、法律家は無罪判決が被害者遺族の人生を破壊する現実の前に謙虚でなければならないはずです。
天災と人災を比較した場合、人災をもたらす際の不可欠な構成要素が、人間の脳内の抽象名詞です。そして、その抽象名詞が物理的な動きを生じさせる場合よりも、脳内で作られた抽象名詞の束であるシステムのみで人間の精神を破壊させる場合が、絶望的な人災の極致だろうと思います。この言語による構成物の最たるものが法であり、特に殺人と死刑を定める刑法のシステムです。刑法によって崩壊させられた人生の足跡を辿るとき、私はその限界点に「無罪判決が言い渡された殺人事件の被害者遺族」の存在を見ます。
人間は必ず間違いを犯すものであり、法律は不完全であるという命題は、法律学においては「絶対に冤罪をなくす」という点でゴールに達します。灰色無罪であろうと冤罪であろうと、1人の無辜をも罰しないために99人を無罪放免にすれば終わりです。しかし、法律家が拠って立つこの理論は、あくまでも半面の正義であり、これを絶対化して事足れりとするのは法律学の驕りだと思います。そのゴールの先の先を見れば、最後の限界まで深い絶望が続いており、しかも出口のない苛酷な人生を強制される者が必ず生み出されています。
弁護士にとって、無罪判決の獲得は憧れの的です。弁護士人生に燦然と輝く勲章であり、裁判官からも検察官からも一目置かれます。特に、死刑と無罪という究極の二択が生じ得る場面において、死刑台からの生還を勝ち取った弁護士は、まさに弁護士名利に尽き、天にも昇る心地だろうと想像します。人間が行うことは不完全である以上、有罪と無罪には互換性があり、1審と2審の結論も人為的に変わります。今回の弁護士は、文字通り無罪を奪い取ったのであり、一生忘れられない瞬間になったことと思います。
それでは、その瞬間に同時に生じた被害者遺族の絶望について、その発生に寄与した弁護士はどう考えているのかと言えば、何も考えていないと思います。私自身の狭い経験からですが、建前を除いた本音の部分をストレートに述べれば、「知ったことではない」という心情が最も強いはずです。被告人の側からのみ物事を見ていると、別の角度からのピントが合わないということです。また、被害者遺族の側に何が起ころうとも、「正当な弁護活動が責められるべきではない」という憤慨以外の心情は起きないだろうと思います。










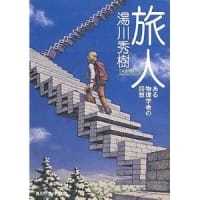
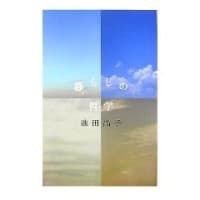
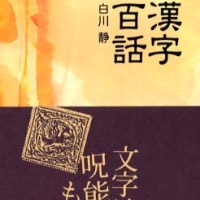
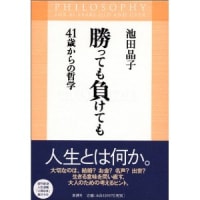
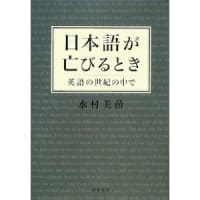
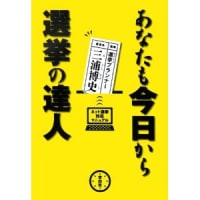
殺人事件につき無罪判決が出た被害者遺族の絶望は、まさしく人災であることに異論はありません。
しかしながら、この人災の発生においては、仮に被告人が真犯人であるならば有罪判決を得るために立証活動をなしえなかったことについて、被告人が真犯人でない場合について誤った捜査方針に基づき無辜の人間を起訴してしまったことについて、当然検察も責めを負うはずであって、弁護人についてのみ言及されていることはいささか一面的な見方のように存じます。
そもそも、本事件で被告人が真犯人であることを当然の前提のような書き方をなさっているように見受けられ、違和感を覚えます。
「必ず真犯人を罰して欲しい、そして目の前で裁判を受けているこの被告人が真犯人であって欲しい」というのは、被害者遺族として当然の心情でしょう。
ただ、そうした心情に対して過剰に没入しておられるのではないでしょうか。
>仮に被告人が真犯人であるならば
「仮に被告人が真犯人であるならば」という不安定な推論を免れ得るのは、真犯人である被告人と、死者である被害者の2名のみだと思います。そして、死者は客観的世界という表象の前提となる間主観性を失う以上、真犯人である被告人が全ての論理の支配者となり、全てを見通す絶対的な地位を得ます。この「私1人だけ正解を知っている」という地位から見渡せる光景は、背徳的な愉悦感で満たされたものと思います。
社会的地位の高い裁判官・検察官・弁護士といった人々が、自分だけのために真剣にああでもない、こうでもないと議論重ねているのを見て、その誤りと正解とが手に取るようにわかる被告人の状態は、全能の神の視点に等しいと思われます。自分の一言で捜査官が右往左往し、巨大な組織が総動員されて奔走し、その関係者の家族の人生まで操れるのも、なかなか倒錯した快感を生じ得る地位であると想像します。
正解がわからない者が正解を求めて疲労困憊している場において、正解を唯一知っている者が正解を語れば、そこで用いられている論理には足払いが掛かり、人々は一斉になぎ倒されます。しかし、真犯人である被告人は、口が裂けても正解を語りませんから、人々は倒されません。情況証拠による事実認定の議論は、裁判官・検察官・弁護士が真犯人である被告人の手のひらの上で大真面目で踊っている状態なのだと思います。
上記は、あくまでも私個人の考えであり、他の方に押しつけるものではありません。
確かに黙秘や否認を続ける真犯人たる被告人の心理には、そうした側面もあることでしょう。
ただ、実際に否認を続ける被告人の供述の信用性を判断するうえでは、正直申し上げると有害な推論だと考えます。
ある事件において被告人が真犯人ではなく、したがって正解を知らないがために正解を語らないという可能性は、被告人の供述内容そのものが現実にはありえないと即断できるようなものでない限り、情況証拠を十分に検討したうえでなければ排除できないのですから。
コメントへのお返事になっているかはわかりませんが、続きを書きました。http://blog.goo.ne.jp/higaishablog/e/18de9a22ee29a6955ce9df6b2e5fe848
法律学や社会科学が人間の生命と死という根源的な問題について自ずと限界を抱えていること、こうした問題は哲学の領域に属するものであり、人間の生命と死に関する哲学は法律学的考察に先行するものであるという点につきまして、私も賛同いたすところです。
今後考察をするにあたり、参考とさせていただきます。
情況証拠による殺人罪の事実認定について詳細な議論を戦わせているところに、「そもそもなぜ人を殺してはいけないのか」という問いを突然持ち込まれれば、人は虚を突かれて一瞬回答に詰まるだろうと思います。
私の駄文が、通りすがり様の今後の考察の一助となれば幸いです。