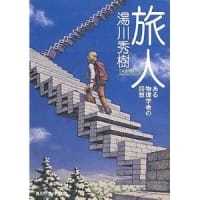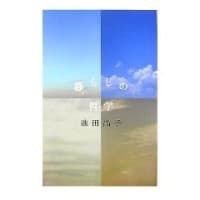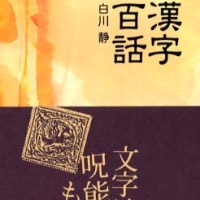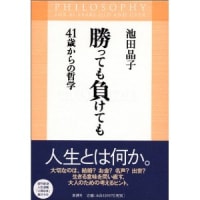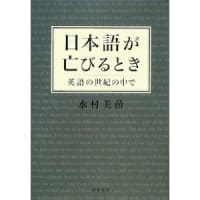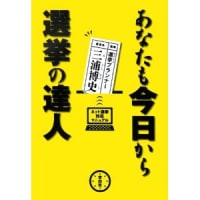犯人の視線からの逃走劇は、エンターテインメントの定番である。ドラマの主人公は逃亡のスリルを楽しみ、いつも生き生きとしている。気の緩みを全国から責められ、なおかつ自分自身の気の緩みを責めている公務員にとって、その姿は眩しすぎる。組織内の責任の押し付け合いにおいて、純粋な自責の念は際限ない負の感情を生じ、もう何もかも投げ出したくなる気分を生むものだ。
身柄を確保された容疑者は、「疲れました」と語ったとのことである。この疲れは極めて単線的であり、恐らく一晩寝れば消える。そもそも、容疑者は自分が逃走しなければ全く疲れなかったのだ。これに対し、その周辺で大真面目に原因が分析され、再発防止策と責任の所在が論じられ、儀式で訓示が垂れられる現場の無数の疲弊は、比較にならないほど人間の精神を複雑に打ちのめす。
このような状況において、場を支配する力は逃走者に握られている。警察の威信にかけて逃走者を追うとき、そのシステムは自己目的化している。すなわち、不条理な強姦被害に対する償いや、良心の呵責などの倫理の問題は完全に消失し、逃走者が作り上げた力関係の前に屈伏させられるのみである。最後には、「国民の皆様に不安を与えたこと」への儀礼的なお詫びだけが残る。
容疑者が述べる「疲れました」と同じ言葉を捜査側の者が口に出せば、これは社会人失格であり、仕事の厳しさを知らないということになる。過労で病弊して精神を病もうが、この程度の容疑者に自分の人生観が右往左往されようが、そんな弱音は許されないということだ。このどん底から、公共の利益のための労働意欲を掻き立てるには、かなりの虚無感に打ち克つことを必要とする。
(続きます。)