秋葉原の通り魔事件の後、ネットでの犯罪予告による補導・逮捕者が続出している。「今から池袋に行って100人殺す」、「東京競馬場に爆弾を仕掛けた」、「JR新潟駅に放火し無差別殺人を起こす」などの書き込みをした容疑者が、次々と脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪などに問われている。これだけ「犯罪になります」という情報が流れている中で、この逮捕者はあまりにも多い。犯罪になるとわかっていたならば完全な確信犯であるが、「確信犯」の名に値するほどの立派な思想もなさそうである。逆に、犯罪になるとわかっていなかったならば、単なる軽率な行為であり、やはり立派な思想はなさそうである。いずれにしても、本人はここまで大げさになるとは思わなかったといった感じであり、重い罪名と軽い意識とのギャップが際立っている。
伝統的に刑法の脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪が想定しているのは、このようなネットにおける予告ではなく、手紙による予告である。まずは文案を練って推敲し、それを筆記したり印刷したりして、脅迫状を完成させる。それから、封筒に入れ、宛名を書いて切手を貼ってポストに投函する。差出人がわからないようにしたいときには、指紋が付かないように、すべての過程で手袋を忘れてはならないし、筆跡も身元が割れないようにしなければならない。脅迫状1通を出すにも一苦労である。これをすべて遂行するには大変な時間と労力がかかる。従って、十分に考え直す時間もあり、「こんなことはやめよう」と引き返す時間もある。本来、犯罪の実行へのハードルは、このように非常に高いはずのものであった。
ネット社会は、このハードルを恐ろしいほど低いものにした。もちろんこのような社会では、どのようなことを書けば犯罪になるのか、その境界線の情報も提供される。例えば、「死ね」は罪にならないが「殺す」は罪になることがあり、その判定は目的と手段の具体性・現実性によって判定されるといったガイドラインも作られている。そして、どこまでがセーフか、どこからがアウトか、具体例も豊富に作られている。しかし、どんなに詳細なガイドラインを作ったところで、重い罪名と本人との軽い意識とのギャップは解消できない。これは、犯罪を実行するまでの時間の長さの問題、すなわち犯行を思い止まる時間の長さの問題である。ネットにおける犯罪予告は、掲示板で煽り合ってカッとなれば、ほんの10秒で実行されてしまう。送信ボタン1つである。
近年の法律をめぐる問題は、社会の変化の早さに法律の改正が追いつかないことだと言われてきた。そして、行政刑法をどんどん増やし、それでも次々と抜け穴が見つけられてしまうという問題が起きていた。ところが、ネットにおける犯罪予告の問題は、方向性としては完全に逆である。社会の変化の早さによって、プリミティブな刑法犯の構成要件の網が広くかかってしまった。実際に放火や殺人の予定は毛頭なくても、それ自体が脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪の構成要件的故意であるから、錯誤論は使えない。刑法の謙抑性と言っても、従来の手紙による脅迫状の構成要件論を前提とすれば、同じことをネットですれば必然的に犯罪成立ということになる。結局、法治国家は、軽い意識の下で重い罪がどんどん成立する状況を止めることはできない。
それでは、実際に国民はどうすればいいのか。どのガイドラインを見ても、月並みなことしか書かれていない。例えば、「軽い気持ちで爆破の予告を書き込んだだけでも、警備員が隅から隅まで調べたり通行人を避難させたりして、多くの人を混乱させることになりますので、絶対にしてはいけません」。科学技術の粋を極めた高度情報化社会の象徴という割には、昔の小学校の先生のお説教のようである。大人に対するお説教なら、次のようなものがある。「モラル教育が必要なのは、子供だけではない。現代社会の我々全員である。人間は、その貧相な内容に不釣合いな技術を所有してしまったのである。進歩したのは技術であって、間違っても人間の側ではない」。(池田晶子著『勝っても負けても 41歳からの哲学』13ページ、「パソコンに罪はない」より)
伝統的に刑法の脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪が想定しているのは、このようなネットにおける予告ではなく、手紙による予告である。まずは文案を練って推敲し、それを筆記したり印刷したりして、脅迫状を完成させる。それから、封筒に入れ、宛名を書いて切手を貼ってポストに投函する。差出人がわからないようにしたいときには、指紋が付かないように、すべての過程で手袋を忘れてはならないし、筆跡も身元が割れないようにしなければならない。脅迫状1通を出すにも一苦労である。これをすべて遂行するには大変な時間と労力がかかる。従って、十分に考え直す時間もあり、「こんなことはやめよう」と引き返す時間もある。本来、犯罪の実行へのハードルは、このように非常に高いはずのものであった。
ネット社会は、このハードルを恐ろしいほど低いものにした。もちろんこのような社会では、どのようなことを書けば犯罪になるのか、その境界線の情報も提供される。例えば、「死ね」は罪にならないが「殺す」は罪になることがあり、その判定は目的と手段の具体性・現実性によって判定されるといったガイドラインも作られている。そして、どこまでがセーフか、どこからがアウトか、具体例も豊富に作られている。しかし、どんなに詳細なガイドラインを作ったところで、重い罪名と本人との軽い意識とのギャップは解消できない。これは、犯罪を実行するまでの時間の長さの問題、すなわち犯行を思い止まる時間の長さの問題である。ネットにおける犯罪予告は、掲示板で煽り合ってカッとなれば、ほんの10秒で実行されてしまう。送信ボタン1つである。
近年の法律をめぐる問題は、社会の変化の早さに法律の改正が追いつかないことだと言われてきた。そして、行政刑法をどんどん増やし、それでも次々と抜け穴が見つけられてしまうという問題が起きていた。ところが、ネットにおける犯罪予告の問題は、方向性としては完全に逆である。社会の変化の早さによって、プリミティブな刑法犯の構成要件の網が広くかかってしまった。実際に放火や殺人の予定は毛頭なくても、それ自体が脅迫罪・強要罪・威力業務妨害罪の構成要件的故意であるから、錯誤論は使えない。刑法の謙抑性と言っても、従来の手紙による脅迫状の構成要件論を前提とすれば、同じことをネットですれば必然的に犯罪成立ということになる。結局、法治国家は、軽い意識の下で重い罪がどんどん成立する状況を止めることはできない。
それでは、実際に国民はどうすればいいのか。どのガイドラインを見ても、月並みなことしか書かれていない。例えば、「軽い気持ちで爆破の予告を書き込んだだけでも、警備員が隅から隅まで調べたり通行人を避難させたりして、多くの人を混乱させることになりますので、絶対にしてはいけません」。科学技術の粋を極めた高度情報化社会の象徴という割には、昔の小学校の先生のお説教のようである。大人に対するお説教なら、次のようなものがある。「モラル教育が必要なのは、子供だけではない。現代社会の我々全員である。人間は、その貧相な内容に不釣合いな技術を所有してしまったのである。進歩したのは技術であって、間違っても人間の側ではない」。(池田晶子著『勝っても負けても 41歳からの哲学』13ページ、「パソコンに罪はない」より)










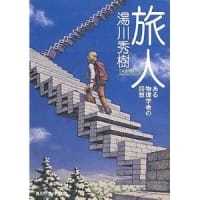
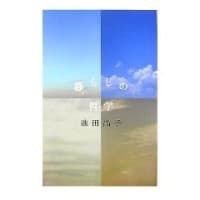
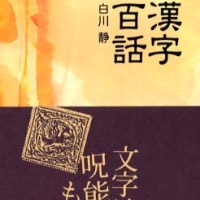
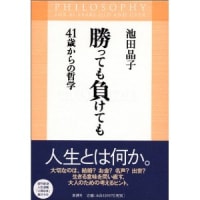
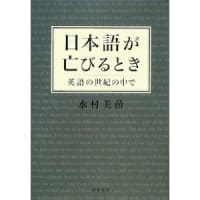
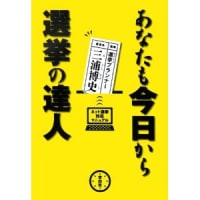
「自分は捕まらない」と思っているのでしょうか?自分だけは違うって。
おそらく、「ネットに何かを書けば一瞬にして世界中に情報を発信したことになる」という現実が、人間の実感を超えるためでしょうか。正直に言って、このネット社会で、その現実の実感はなかなか難しいと感じます。私も、このブログのアクセス数が増えたとか減ったとか言って一喜一憂しているわけですから、その実感はまるでできておりません。
秋葉原の事件の犯人も、携帯の掲示板への書き込みに対して何の反応もなかったことから孤立感を深めたと述べていましたね。「世界中の人々が見ることができる」というのは可能性としては事実でしょうが、あの犯人にとっては、何の意味もない事実だったわけです。