6月10日午後1時頃、大阪市中央区東心斎橋の路上で、通行人の男女2人が刺されて亡くなりました。礒飛京三容疑者(36歳)は、「2人とは面識はない」、「誰でもいいから殺そうと思った」、「自殺しようと思って現場近くで包丁を購入したが死にきれず、人を殺せば死刑になると思ってやった」と供述しているとのことです。
「人を殺せば死刑になる」といった屁理屈にもならない理不尽な動機は、以前にも別の通り魔事件でも語られていたと思います。その際の論評の中には、「死刑制度の存在こそが犯行を招いたのであり、死刑が廃止されるべきことの証左だ」といった主張もあり、屁理屈に屋上屋を架されている気がしたことを覚えています。
もともと言語には限界があり、自らの殺意を正確に言語化できる者はこの世に存在するはずがないと思います。本人が動機を正確に語れないとなると、有識者が本人に代わって語ろうとすることになりますが、本人でさえよく説明できないものを周りが解説しても虚しいだけです。私もこれまでの人生で、人並みに何回も瞬間的な殺意を覚えたことはありますが、その内容を説明しろと言われても無理です。
殺意とは何かという定義については、刑法の文献を見れば詳細に解説されていますが、私が最も納得しているのが、通訳・作家の米原万里氏の著書の中で見た説明です。すなわち、殺意とは、脳のある部分が耐え切れなくなって上げる悲鳴です。この悲鳴は、現に目的を達成してしまえば完全に消えるしかなく、その後の脳は抜け殻であり、言葉は嘘を語るしかないと思います。「死刑になりたくて人を殺した」という言い回しは、「ムシャクシャして痴漢した」「ムシャクシャして火をつけた」と同じく、この場面での1つの言語規則に過ぎないと思います。
(続きます。)










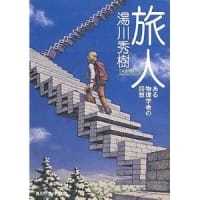
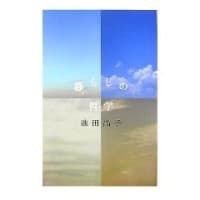
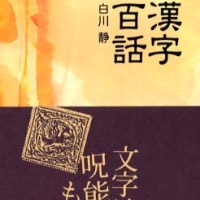
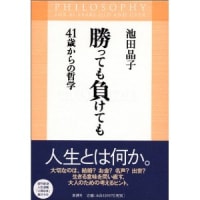
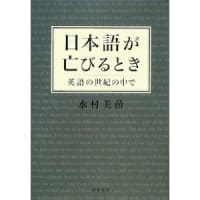
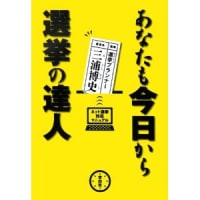
なるほど、と思いました。
「死刑になりたかったから殺した」という言葉をなぜ簡単に受け入れ、それを根拠として何か意見をすることができるのか、疑問に思いました。
その言葉を発した人は、殺人を犯したばかりの人なのに、なぜその言葉は理性的なものと捉えられてしまうのでしょう?(死刑制度に反対する根拠としてその言葉をとらえることができるということは、感情的にうっかり言ってしまった言葉とは捉えられていないのだろうと思います。)それに対し、被害者が被害を受けてから自問を繰り返した末に「死刑にしてほしい」と発言することに対し、死刑廃止論者が「それは感情からくる言葉だから死刑存置の根拠としては弱い」などということがあります。
この非対称性は不思議です。
松井大阪府知事の談話に賛否両論が盛り上がり、例によってすぐに消えたようで、何だか容疑者の一言に世論が右往左往させられた徒労感だけが残りますね。
語る必要のある言葉はなかなか言葉にできず、語る必要のない言葉は簡単に言葉にできるという法則を手放してしまうと、人は「議論のための議論」をするしかなくなるのだと思います。
非対称性の不思議さについては、多くの法律家はこれを不思議と思わないのみならず、非対称であることにも気付かないものと思います。先に誰かが考えた受け売りの思想であるほど、ある者が自問を繰り返した末の言葉を一笑に付しがちですから、「自由と正義」ほど恐ろしいものはないと感じます。