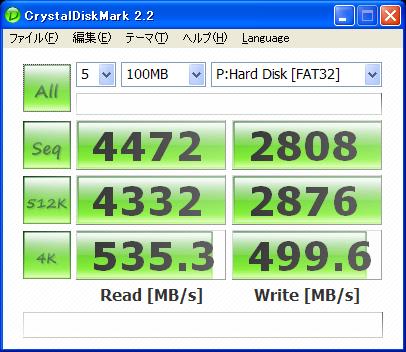地上アナログの終了も来年に迫るなかで、転居して共同アンテナが地上デジタルに対応している状況になったため、そろそろ地上デジタル対応省電力パソコン(以降、「テレパソ(地デジ版)」)の世界に足を踏み入れることにしました。
現行の地上アナログ対応省電力パソコン(以降、「テレパソ(地アナ版)」)が、基本24時間/365日運用で他のパソコンデータのバックアップ機、仮想サーバホストマシンと兼ねており、家庭内でテレビの自動録画および視聴機としても日常的によく使われていることから、いきなりの移行は厳しいと考え、テレパソ(地デジ版)との並行運用を検討することにしました。
(1)テレパソ(地デジ版)の条件
・省電力の構成であること
・連続運用に耐え得る構成であること
・操作性が良いこと省電力である=比較的パワーが足りない構成 がある意味通説と思っていますが、地上デジタル機では、そういう構成では、性能を満足しないのが実情だと思います。視聴しているときは、最低限の電力を消費するのは目を瞑るが、使っていないときは極限まで消費電力を軽減する仕組みが必要です。使っていないときはスタンバイが仕組みとして簡単ですが、バックアップ機としてつかっていたり、視聴する際のレスポンスを考えると「操作性」を犠牲にしかねません。よって、1番目の条件は、
・性能の上限が高く、かつ省電力の構成であること
かな。。。
(2)パソコンの構成要件
・CPU:地上デジタル、仮想サーバ等複数のタスクを実行するため、できるだけ多くのコア/スレッドを搭載すること。
・メモリ:仮想サーバを搭載するためできるだけ多くのメモリを搭載できること。
・ディスク:最低限の性能を担保しつつ、システムディスク、データディスク共に大容量のディスクを採用。
・M/B:性能の高いオンボードグラフィックスを搭載すること。
・OS:搭載するアプリケーションと共に安定していること。メモリの要件に連動して64bitであること。
・電源:変換効率が高いこと
・すべてのパーツに共通する要件は、やはり省電力ということになります。
(3)現行テレパソ(地アナ版)の構成
・CPU、M/B:Atom N270(on M/B)、Jetway JNF94-270-LF
・メモリ:SO-DIMM DDR2-800 2GB 1枚
・ディスク:Seagate ST9500325AS 1台(システム)、Samsung HD103UI 2台(データ)
・OS:Windows Xp SP3
・電源:SRD2D080V21
これまで運用してきた中で気がついた問題となるポイントですが、・仮想サーバの動作がかなり厳しい。CPUが仮想対応でないことも相俟って、かなり遅く感じる。
・CrystalDiskInfoを常駐させて監視しているが、SeagateとSamsungの1台で「代替処理済のセクタ数」の警告発生。
よかった点ですが、
・地上アナログの視聴、録画操作では十分な性能で、IOデータのリモコン使用で操作性が家電並みによい。
・ACアダプタの採用で極限まで消費電力を削減できて、冷却機構もケースファン径12cmが1台のみになるようにエアーフローを工夫しているので、騒音がほとんどしない。
(4)次期テレパソ(地デジ版)の構成
以上のことから、マルチコア/スレッド、仮想対応の低TDP+アイドル時消費電力が少なくなる機構をもつCPUが望まれるところです。
モバイル用CPUを用いるのが最適ですが、CPU、M/B共にコストが高くなり現実的ではありません。
で昨年末から流通し始めたAMD Athlon II X4 Quad-Core 605e : 2300MHz 、AM3、二次キャッシュ:2048KB、TDP45W
をターゲットにM/Bを選ぶことにしました。
当初、GeForce8300チップセットのM/Bを検討していましたが、ちょうど、巷の評判でそれを上回る性能を誇る785Gチップセットのマザーボードが流通し初めていたので、これにEPU/EPU-4 engineという省電力機能をもつ
ASUS M4A785D-M PRO
を選びました。DDR3のタイプもありますが、DDR2を流用するためこちらを選択しました。
地上デジタル対応キャプチャーボードは、使い慣れたmAgicTVが使用できて、消費電力が2.1Wと少ない
IOデータ GV-MVP/HS3
を選定しました。B-CASカードが、SDカード相当サイズとなり非常にコンパクトになっています。
以下左はM/Bを置いてみた感じで、右は実装完成です。左側から右側へのエアフローを意識しています。
ハードディスクは、余っていた500GBディスク(HITACHI HDP725050GLA360)を使用、8月まで使用可能なWindows7 Ultimate 64bit RC版を導入し、しばらく機能検証することとします。
実験機なので通常のATX電源(EVERGREEN HK550-14GP)を使用するも、ピーク消費電力約85W、アイドル時約56Wとそこそこ良好です。