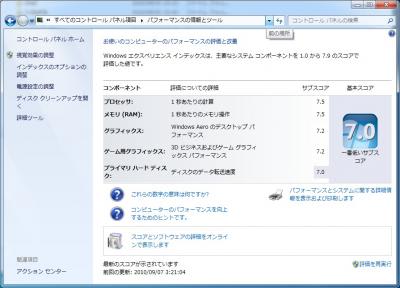Core i7シリーズCPUのラインナップが充実し価格もいい感じになってきました。現在のメインマシン(Core2Duo)も導入から3年以上になるため、更改に向けた次期メインマシンの実験機構築をしようと思います。今回の移行はWindowsXp→Windows7への変更にもなるため、しばらくアプリケーションの移行検証が必要と考えています。
1.パーツの調達
(1)ケース : Yeong Yang W203-AK2/WOPS
現行テレパソ(地アナ版)運用機(ケース:SilverStone LC16M)の役割を廃止したため、次期テレパソ(地デジ版)運用機(ケース:Yeong Yang W203-AK2/WOPS )の中身をそっくりLC16Mに移して、Yeong Yang W203-AK2/WOPS に実装します。
(2)CPUクーラ : サイズ 忍者参 (SCNJ-3000)

現行メインマシンで使用してお気に入りの初代 忍者 (SCNJ-1000) からの第3世代製品です。つくりが初代よりもしっかりしていて、見た目も美しくなっていますが、Core i7 のマザーボードにうまくつくか事前情報がつかめなかったので、人柱になる予定です。
(3)CPU : Intel Core i7 870 BOX 2.93GHz


私が買った8月中旬ころは、もっともコストパフォーマンスがよいモデルでした。
(4)メモリ : コルセア DDR3-1600 2GBx2 CMX4GX3M2A1600C9

経験上無用のトラブルを避けたいという一念から、Core i7 / i5 CPU と相性が保証されている実績のあるモデルを選択しました。
(5)マザーボード : ASUS P7P55D-E EVO



売れ筋の P7P55D-E でもよいかと思われましたが、SPDIF端子(同軸タイプ)がなかったことと、SLIに対応していない(まあ使わないですが)とか、LANインタフェースが2つあると便利かもと思い、P7P55D-E EVO を購入しました。
(6)グラフィックボード : PowerColor HD5750 SCS3 (中古、ファンレス)


グラフィックボードは、故障が少なく、中古で豊富で出回っているパーツなので中古で購入しました。やはり、静音性を追求するためにはファンレスが必要と考えており、現行メインマシンで使用している8800GTファンレスボードと同様、ファンレスを導入します。5750は、”ガンガン”ゲームに使用しない私にとっては十分な性能をもっていて、DirectX11にも対応しています。
2.パーツの組立て
(1)CPUの取付
CPUを向きにさえ気をつければ、簡単に取り付けできます。


(2)CPUクーラーの取付
マザーボードを裏返して、付属のプレートを向きに気をつけて置きます。マザーボード裏の金属プレートを固定している3本のビス穴位置にプレートの穴を合わせます。

以下、置いた様子です。ただ置いただけです。プレートの裏は2mm厚程度の非電導と思われる薄いスポンジが貼り付けられています。手前の半田付けの突起がスポンジにあたってしまっています。締め付けたときにスポンジを貫通しないことを祈るばかりです。貫通しても半田付け部分がGNDであれば問題ないかもしれませんが。

CPUクーラーの本体側を組み立てます。

なかなか難しいのですが、手でプレートを押さえながらマザーボードをひっくり返して、上からクーラー本体を置きつつ、下から4本のビスで締め付けます。4方向横からCPUとクーラの接触面をみて4本均等に締め付けます。締め付けすぎるとマザーボードに無理な力がかかりそうなので締め付けすぎもよくなさそうです。あと、さきほど気になっていた半田付け部分の貫通も注意して見ます。 後々問題にならないように、慎重にやる必要があります。以下写真は締め付け後下から撮った様子です。

半田付け突起の貫通が気になりつつも、取り付け完了です。初代の忍者よりひとまわりサイズが大きいせいか、だいぶ目立ちます。

(3)メモリの取り付け


最近多い放熱のために背が高いメモリでも、ぎりぎりで忍者と接触しなさそうです。
(4)ケースへのマザーボード、グラフィックボードの取り付け

グラフィックボードを取り付けます。昔のボードに比べるとだいぶ省電力になりましたが、6ピンの電源を忘れないように取り付ける必要があります。CPUクーラーにはCPUファン(Scythe S-FLEX SFF21D)も取り付けました。CPUクーラーに付属のファンとコントローラは、うわさに聞くところ爆音ということで使用しません。

(5)その他パーツの取り付け
電源、SSD(Cドライブ)、HDD(Dドライブ)、DVDドライブ(元から実装済み)を組み込んで配線し、完了です。(写真右側、左側は現行メインマシン) このあと、IOデータのGV-MC7/VSを実装しています。