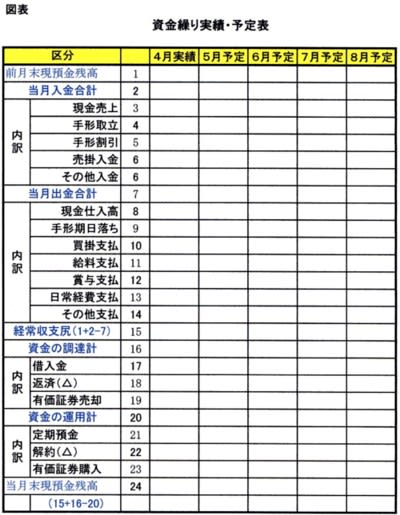大手製造会社であれば必ず原価計算を行い、値決めやコストダウン等の経営戦略資料として利用している。もちろん経理部門も関与するものの、こと標準原価においては、購買部門や製造部門を経験した者でないとなかなか難しい。部品の値段や物の作り方が分からないからである。
それで大企業では、それらの部署を経験した職人を集めて、原価企画とかコストセンターという部署を創り、標準原価の策定や全般的な原価の管理を行っている。経理はそこで作られた標準原価を利用して、毎月原価計算を行っているのである。
ところが小さな会社では、そんな余力も知識もないため、正確な原価計算は行わず、どんぶり勘定で大雑把に原価を把握するのが精一杯であろう。
標準原価とは、ある製品を作るために通常必要な材料費、労務費、経費を予測し集計した原価のことである。具体的には、統計資料や科学的調査に基づき次のように計算される。
①許容範囲の歩留まりを加えた材料の消費量×通常の予想購入単価
②能率的な状態での労働時間数×製造部門の平均賃率
③製造に直接必要な経費
④製造に間接的に必要な経費を合理的に配賦
これら①~④を集計した金額となる。
こうして計算式をみるだけなら原価計算は単純で簡単のようなのだが、実際に計算するとなるとかなり大変なのだ。ことに大企業となると製品の種類が多く、その製品を構成する部品点数も何百とか何千というレベルになるからである。そうなると、これはもう人間の手には負えず、かなりハイレベルのコンピューターシステムが必要となる。
また能率的な状態での労働時間と言っても、実際にはどのようなやり方が能率的な状態なのかを判断するのも素人には無理であり、その時間数をカウントするのも簡単ではない。従って専門的に扱う部署が必要になるのである。
そしてなによりもやっかいなのは、1962年に企業会計審議会から「原価計算基準」が発表されて以来全く手付かずであること。原価計算を扱った書籍は、学者の書いたものばかりで実用的ではないこと。さらには会社ごとに原価計算の仕組みは異なるが、それらの具体的手法については全く公開されていないという状況なのだ。
いずれにせよ大企業の原価計算システムを創設した人達は、大変な努力を重ねて今日の原価計算を構築したはずである。だが小さな会社では、製品数や部品点数も少なく、全体の製造工程や製品の流れを見渡せるので、経理マンが標準原価を作る事も不可能ではない。
経理マンが標準原価を作るためには、まず現場作業を全て経験し、作業の流れと内容を把握しておかねばならない。また作業の難易度や問題点などについて、現場のリーダーに十分なヒアリングを行う必要があるだろう。
小さな会社では、大企業のように原価計算を財務会計と結合させる必要はない。目的は経営管理のためオンリーと割り切り、なるべく時間と金をかけずに済む独自の手法を築けば良いのである。
つぎに私が編集プロダクション時代に行った標準原価の仕組みを簡単に紹介しよう。純粋な製造業ではないが、本の製作をしている訳であるから、ある意味で製造業ではないかと考えて原価計算を行った。
①まず編集長、デザイナー、カメラマン等とそれぞれヒアリングを行い、本の種類と形態、本が出来るまでの工程、作業手順や外注依存度などを克明に調査した。
②製作頻度の一番多いB6判モノクロ224頁を、基本編集パターンと定め、このパターン通りなら編集作業時間600時間と決めた。
③224頁を超える場合、またはそれ以下の場合には、2.7時間を加算または減算した。
④また本のサイズが、B6判以外の場合や、写真・図版等が一定の使用量を超えた場合などにも③と同様の加算・減算を行った。
⑤全編集者の平均給与から時間当たりの平均賃率を算定し、それに合計時間数に乗じて、一冊当たりの直接社内労務費を算出した。
標準原価を作成したのは、この社内労務費部分だけであり、その他の費用は全て実績額を加算して直接原価を算出した訳である。大企業の経理マンからみると、単純かつ会計と直結しない中途半端な原価計算に映るが、小さな会社ではこれで十分なのだ。
この原価計算の結果は、オーナー出版社に対する編集料値上げ交渉にも使用したが、真の目的は編集担当者の人事評価であった。つまり一人の編集者が、年間に編集完了した標準労務費と、実際にその編集者に支給した給与を比較した訳である。
そう、実際に支給した給与のほうが高ければ採算ベースに乗らない訳であるから、当然人事評点は低くなる。むろん標準より低ければ利益貢献度が高まり、人事評点も高くなるということになる。
このようにして、言葉は悪いが編集者達を脅したり、褒めたりしながら競わせて、全社の編集作業効率を50%アップさせたのだった。この様に小さな会社では、幹部のコンセンサスさえ得られれば、思い切った原価管理、いや経営管理が実現出来るのである。
★下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。
 にほんブログ村
にほんブログ村

注)会社のPCでクリックすると、ランキングに反映出来ない場合があります。出来れば自宅のPCからもクリックしてくれると凄く嬉しいです。