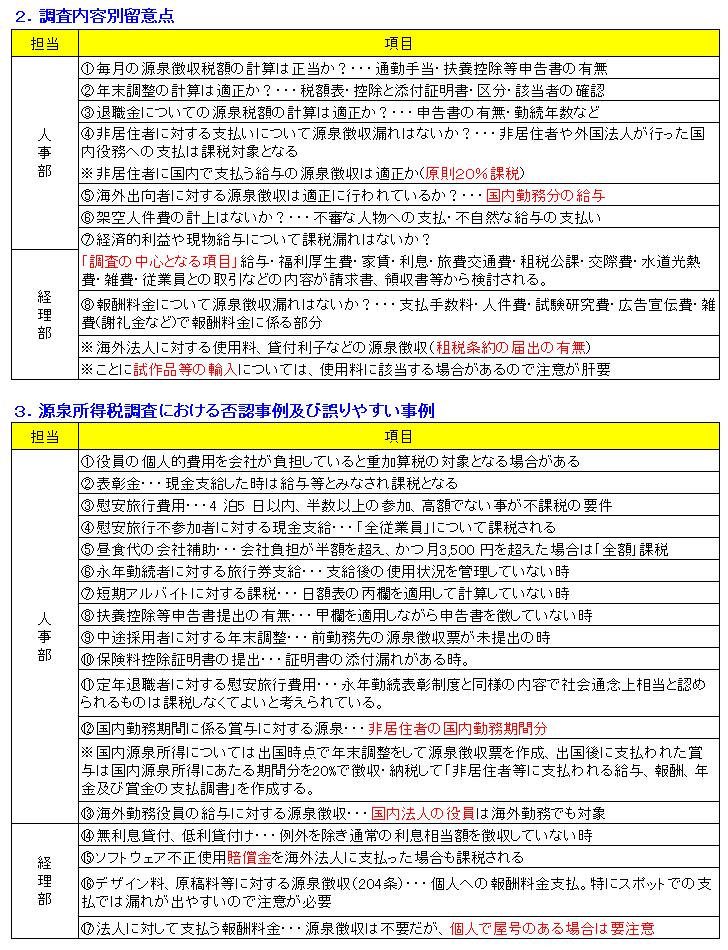1.APA(事前確認)の申請について
APA(Advance Pricing Arrangement)とは、移転価格税制で課税される前に、相手国の税務当局と国税庁に対して相互協議で独立企業間価格の調整を行ってもらうための事前申請手続きである。
その効果として・・・対象期間中に相互協議で決定された価額(利益率)レンジの中で取引がなされれば、移転価格税制に抵触しないこととなり、どちらの国からも課税されないこととなる。またAPA申請期間中は国税局の税務調査による寄付金課税も緩和または凍結されることになる。
『具体例』
2003年3月期より米国子会社が赤字化し、米国税務当局からの移転価格課税防御のため 2008年6月、日米同時にAPA申請を行った。その後当局への書類提出・審査、関係者間の打合せ等を経て、ほぼ予定通り日米相互協議が終了した。
2.日米相互協議の主な合意内容
①対象期間 6年+ロールバック1年=7年間が対象となる(主な租税条約上の時効が7年) その決算期の申告期限が申請初年度となる
②対象取引 米国子会社へ販売する製品及び商品、予備部品等の有形資産取引
③独立企業間価格の算定方法(TPM Transfer Pricing Method )
●米国側 CPM法(comparable profit method利益比準法)
CPM法は、対象会社全体の営業利益率で独立企業間価格が適正なのかを判定する
●日本側 TNMM法(Transactional Net Margin Method取引単位営業利益法)
TNMM法は、対象となった取引部分を集約したPLの営業利益率を使用する。 どちらも営業利益率を目安とするなど基本構造が似ているため、双方余りこだわりがない
④営業利益率
米国子会社の対象期間中の累計営業利益率が、2%~6%のレンジ内であること(商社の場合)。 孫会社を含まない、米国子会社単体PLより、営業外取引とみなされるもの(リストラ費用、訴訟費用等の一部等)を除外して計算する。
⑤補償調整
対象期間中の米国子会社の累計営業利益率が、2%~6%のレンジ内で納まった場合は調整しない(国税庁はなるべく最低レンジ前後での着地を望んでいる) 米国子会社累計営業利益率が2%未満の場合は、2%に達するまでの金額を日本で費用・米国で収入処理する。
米国子会社累計営業利益率が6%超の場合は、6%を超える金額を、米国で費用・日本で収入処理する。
原則としてこの処理は、対象期間の終了事業年度に行う。
最終年度の2013年3月に会計伝票を1枚入れて送金(相殺)処理する方法と、税務申告調整する方法があるが、税務申告調整は日米での手続きが煩雑なため、伝票処理が望ましいと国税庁の担当官が話していた。
⑥重要な前提条件
対象取引に関して、日本国親会社と米国子会社の事業活動や機能、負担しているリスク、使用資産、財務・税務処理方法が申請時と大きく変わらないこと。
具体的には、商社である海外子会社で、研究開発や製造を行うなどの大幅な事業変更等があった場合は、再度レンジの見直しや取り消しが行われるということである。
3.APA締結後の実務処理
①米国子会社の累計営業利益率が、最低レンジ2%に到達するための方策を検討する
●米国子会社独自の収益改善
●対象期間に限定した、日本からの輸出価格の値下げ(対象期間後、元に戻しても国税庁は了解とのこと)
②毎年「年次報告書」を提出し、国税庁から質問や資料の追加提出を求められる。また当然のことながら、最終年度まで重大な事業変更等や仮装隠蔽等を行わないことが求められる。
③さらに2013年3月以降も継続してAPA申請をする場合は、再度税理士法人から見積もり(今回の6~7割の費用)が提出され、それから3ヶ月以内をめどに再契約するという流れとなる。
★下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。
 にほんブログ村
にほんブログ村