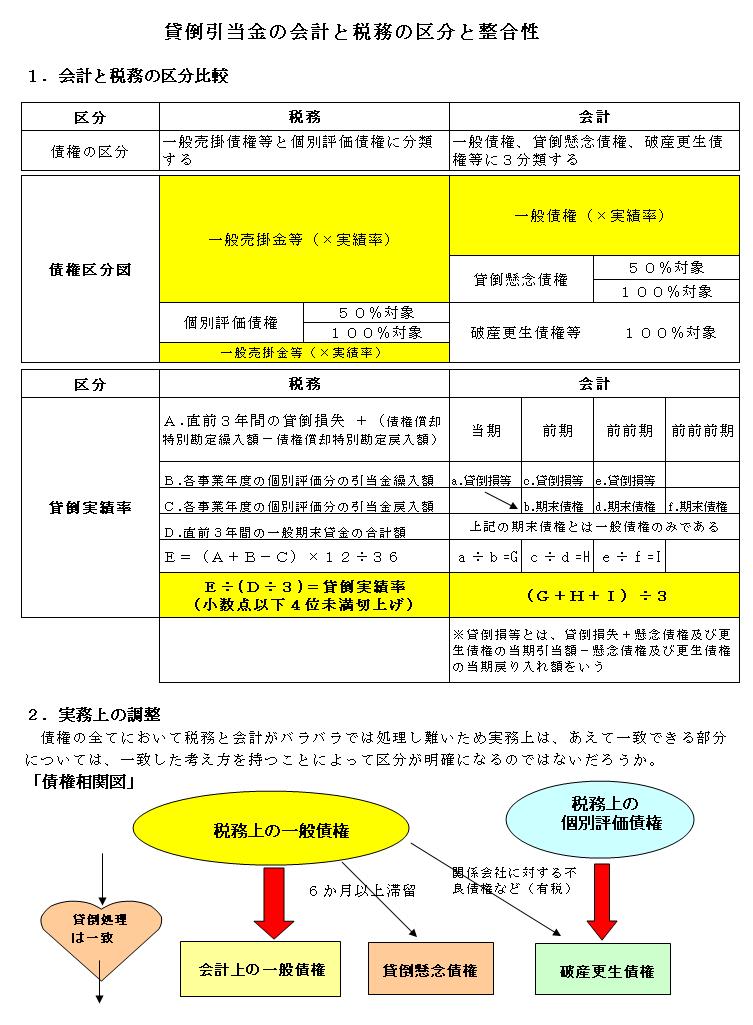移転価格税制では、独立企業間価格が基準となると述べたが、頭のよい人ならすぐに、では実際にその独立企業間価格をどうやって算定するのだという疑問を持つだろう。実に良い疑問である。現実的には全ての仕様において完璧に同一の製品が存在することはあり得ないし、製品ごとの個別取引について、それが適正か否かなどの判定をすることは実務上不可能である。従って運用上は「会社全体」又は「企業が管理会計上分類しているPL区分」ごとの営業利益またはその利益率などで判断することが通例になっている。そして自社の利益率が適正だと主張するためには、国際的な企業の経済データーベースで標準的な利益率を算定して比較検討しておく必要があるのだ。
結局は移転価格調査に入られる前に、日本と相手国の税務当局にAPA(事前申請)を同時に行い、税務リスクを回避する方法が有力となるのだが、国際的経済データーベースを持たない一般企業独自では困難であり、結局KPMG等の大手会計事務所に依頼することになる。だが上場会社なら最低でも約1億円程度の手数料を会計事務所から請求され、そのうえかなりの資料集めや当局とのやりとりは、申請会社自身が行うことになるため膨大な工数を必要とする。場合によっては税金として支払ったほうが得な場合もあるので、APAを申請する場合は事前に社内で十分な検討が必要となる。
先に述べたとおり、移転価格の対象取引と対象者がからむ国際的な税務なので、「税」という名は付くものの経理部だけで対処できるものではなく、経営者・企画部・海外子会社・営業部・海外事業部・会計事務所などが一体となって戦わなくてはならない。従ってその役割分担を定めておく必要がある。
「役割分担例」
●経理部:各国税制概略の把握、日本での移転価格税制研究、移転価格ポリシー・日本版同時文書等の骨子作成、関連部署へ税務情報のアナウンス、移転価格税制の総合事務局
●経営者:移転価格税制の理解とグループ会社の役割・利益方針決定、社内外で発生する会計・税務リスク等の掌握
●企画部:経営計画、子会社業績管理などの運用面にて、移転価格税制を考慮する
●営業部、海外事業部:子会社との輸出(ロイヤリティー含む)・輸入品の価格の決め方をルール化し文書化しておくこと
●海外子会社:各国の税務事情の情報収集・研究と、子会社側の提出資料の作成・海外税務当局との折衝など
「注意事項」
●子会社からの配当
たとえ子会社から十分な配当を得ているとしても、それは通常の取引ではなく、投資に対するリターンに過ぎないため、移転価格税制の適用にはなんら影響を及ぼすものではない。従って、子会社側が経営成績を上げようと過度な利益を毎年計上し、それを「配当で支払えば良いだろう」といった考え方は廃止すべきである。(子会社が強い場合)
●寄付金課税との関連性
寄付金課税という制度は、日本にしか存在しない制度である。また国外関連者への寄付金は、交際費同様100%損金不算入となり、取引した子会社では関与しないため二重課税となる。一方、移転価格税制では、日本で損金不算入となれば、海外子会社等で損金算入となり、税率差はあるものの二重課税とはならない。(税金がどちらの国に所属するかということ) ただ日本の税務調査現場では、国際間の調整がからむ面倒な移転価格税制としては扱わず、確実に税金を回収出来る寄付金課税に持っていく風潮がある。 従って、簡単に寄付金課税を受けず、場合によっては「移転価格税制」として扱ってもらい海外当局との相互協議を目指すという手段もある。そのためには、寄付金と移転価格の違いをしっかりと見定めておかねばならないだろう。
「法人税法の寄付金の定義」
「寄附金、きょ出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合の金銭若しくは金銭以外の資産又は経済的な利益の額(その供与の時の価額による。)をいう。ただし、広告宣伝費、交際費及び福利厚生費とされるべきものを除く」と定義されている
★下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。