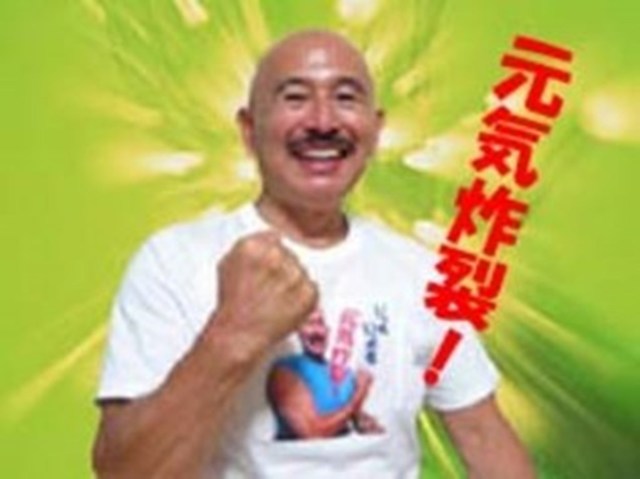一昨日、姉夫婦の健康状況の確認を兼ねて久しぶりに神戸の自宅を訪ねた。
食事を含む滞在時間は僅か5時間だったが二人とも大変喜んでくれてお互いに
嬉しく楽しい時間を過ごした。
今年84歳になる義兄は足の痛みも激しいようで週に何度かは訪問ケアなどを
受けており、やはり歩行が一番辛いようだった。
姉は1年半前に会った時よりはかなり痩せていたが気持ちは相変わらず若く、
子供の頃からの綺麗好きな性格といつも生活を便利にするための何か小物などを
作ったり加工したりする様子は全く変わっていなかった。
姉も決してスイスイと歩けるわけではないが、義兄が動けない分、一人で活動
しなければならずその大変さや苦労も大きく伝わってきたのでやっぱり行って
良かったな・・・としみじみ思った。
往復15時間の旅はあっという間に終わり、今こうして自宅で一昨日のことを
ふり返ると真っ先に思うことは双方の希望であるなるべく近いうちに再会したい・・・
というお互いの願いを早く実現しなければ・・・ということである。
5人兄弟の長男、次男、そして弟も既に亡くなっているので二人きりとなった
姉と私は兄弟の分まで長生きしようと約束しているのだが…
さて、今回はとんぼ返りの旅だったが、新幹線の車窓から見る京都や大阪も
過去に何度か訪れた時のいろんなことが思い出されなんとなく懐かしく嬉しくも
あった。
私が勤務していた会社は本社が大阪にあったので、在職中仕事関連で行くときは
勿論、定年退職者の表彰などを受けた時も新幹線を利用していたが定年退職後の
大阪行きはすべて車を利用していた。
それは私が車の運転が好きで定年退職後に選んだ仕事が『運送業』だったこと。
車を持ち込み、委託契約先から請け負う仕事に地方への配送も多かったことなどで、
関東地方は勿論、関西の大阪や京都、三重、西方面では岡山、広島、島根、四国の
各県、北方面は青森、秋田、岩手などへも時々行き、車窓から見る景色を楽しんだ。
昨年、定年後16年にわたる運送の仕事での走行距離を確認すると108万キロにも
及んでいた。
実に地球27周であり好きなこととは言え私自身もよくやったと思う。
昨年、妻のサポートのために元気なまま辞めたがその直近3年半は毎日埼玉から
群馬にかけての220キロを走る定期コースだったので地方(遠距離)はなくなり
規則正しい生活ができていたのも長期間できた要因かもしれない。
話は大きく逸れてしまったので一昨日の神戸行きに戻そう。
新神戸駅や乗換駅のエスカレーターに乗る時に前を行く人の動きにふと気づき、
思わず『そうだった・・』とうしろの妻にエスカレーターの右側に乗るように促した。
以前から聞いてはいたし、何度かの大阪訪問でも体験していたのですぐに反応し、
我々もすぐに右側の列に続き、左側が追い越しスペースであることをニヤッと
いう感じで確認する自分がいた。
関東では左に並び、関西では右に並ぶ・・・というマナーはいつごろからどんな
きっかけで始まり拡がっていったものなのだろう。
本来エスカレーターは急いで歩く人のために片側を空ける必要はない筈じゃないのか?。
安全上からも真ん中に乗るべきじゃないのか?。
我々もなんとなくこの暗黙のルール(マナー)に従って行動しているが、以前に
真ん中に乗るのが正しいと聞いたことがある。
エスカレーター使用時の注意として真ん中に乗るような指示、表示がないのは
どうしてなのか?
関東、関西、左右は違うが利用する人たちはいずれも忙しい中でおそらくそんな
ことは考えもせず無意識に、ごく自然に利用しているのであろう。
今日はこれをちょっと調べてみようと思うと僅かだがドキドキもする・・・さて・・・。
食事を含む滞在時間は僅か5時間だったが二人とも大変喜んでくれてお互いに
嬉しく楽しい時間を過ごした。
今年84歳になる義兄は足の痛みも激しいようで週に何度かは訪問ケアなどを
受けており、やはり歩行が一番辛いようだった。
姉は1年半前に会った時よりはかなり痩せていたが気持ちは相変わらず若く、
子供の頃からの綺麗好きな性格といつも生活を便利にするための何か小物などを
作ったり加工したりする様子は全く変わっていなかった。
姉も決してスイスイと歩けるわけではないが、義兄が動けない分、一人で活動
しなければならずその大変さや苦労も大きく伝わってきたのでやっぱり行って
良かったな・・・としみじみ思った。
往復15時間の旅はあっという間に終わり、今こうして自宅で一昨日のことを
ふり返ると真っ先に思うことは双方の希望であるなるべく近いうちに再会したい・・・
というお互いの願いを早く実現しなければ・・・ということである。
5人兄弟の長男、次男、そして弟も既に亡くなっているので二人きりとなった
姉と私は兄弟の分まで長生きしようと約束しているのだが…
さて、今回はとんぼ返りの旅だったが、新幹線の車窓から見る京都や大阪も
過去に何度か訪れた時のいろんなことが思い出されなんとなく懐かしく嬉しくも
あった。
私が勤務していた会社は本社が大阪にあったので、在職中仕事関連で行くときは
勿論、定年退職者の表彰などを受けた時も新幹線を利用していたが定年退職後の
大阪行きはすべて車を利用していた。
それは私が車の運転が好きで定年退職後に選んだ仕事が『運送業』だったこと。
車を持ち込み、委託契約先から請け負う仕事に地方への配送も多かったことなどで、
関東地方は勿論、関西の大阪や京都、三重、西方面では岡山、広島、島根、四国の
各県、北方面は青森、秋田、岩手などへも時々行き、車窓から見る景色を楽しんだ。
昨年、定年後16年にわたる運送の仕事での走行距離を確認すると108万キロにも
及んでいた。
実に地球27周であり好きなこととは言え私自身もよくやったと思う。
昨年、妻のサポートのために元気なまま辞めたがその直近3年半は毎日埼玉から
群馬にかけての220キロを走る定期コースだったので地方(遠距離)はなくなり
規則正しい生活ができていたのも長期間できた要因かもしれない。
話は大きく逸れてしまったので一昨日の神戸行きに戻そう。
新神戸駅や乗換駅のエスカレーターに乗る時に前を行く人の動きにふと気づき、
思わず『そうだった・・』とうしろの妻にエスカレーターの右側に乗るように促した。
以前から聞いてはいたし、何度かの大阪訪問でも体験していたのですぐに反応し、
我々もすぐに右側の列に続き、左側が追い越しスペースであることをニヤッと
いう感じで確認する自分がいた。
関東では左に並び、関西では右に並ぶ・・・というマナーはいつごろからどんな
きっかけで始まり拡がっていったものなのだろう。
本来エスカレーターは急いで歩く人のために片側を空ける必要はない筈じゃないのか?。
安全上からも真ん中に乗るべきじゃないのか?。
我々もなんとなくこの暗黙のルール(マナー)に従って行動しているが、以前に
真ん中に乗るのが正しいと聞いたことがある。
エスカレーター使用時の注意として真ん中に乗るような指示、表示がないのは
どうしてなのか?
関東、関西、左右は違うが利用する人たちはいずれも忙しい中でおそらくそんな
ことは考えもせず無意識に、ごく自然に利用しているのであろう。
今日はこれをちょっと調べてみようと思うと僅かだがドキドキもする・・・さて・・・。