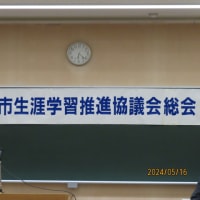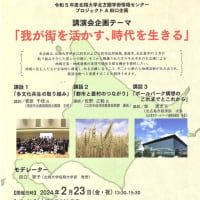北海道が擦文文化からアイヌ文化の時代へ移行しようとしていた12、13世紀頃、北緯40度以北の東北北部も大きな転換期にありました。
前9年の合戦(1053-1062)と、後3年(1083-1087)を経て12世紀前半には平泉藤原氏が台頭し、津軽海峡まで東北全域が国家支配の下に組み込まれるようになりました。
そして、このころから文書には、エミシに代わってエゾなる言葉が登場しました。
浅ましや千鶴のえぞのつくなるとくきのや社暇はもるなれ (藤原顕輔)
えそかすむつかろの野辺の萩盛こやきゝのたてるなる覧 (藤原親隆)
碑やつがろの遠にありときくえぞ世中を思ひ離れぬ (藤原清輔)
「千嶋のえぞ」「えそかすむ津軽」とあるように、平安時代末期から鎌倉時代の和歌のなかで、エゾは北海道と津軽地方の住民にほぼ限定された使われ方をしています。
つま理、古代にエミシと呼ばれていた津軽蝦夷が、中世に入るころからエゾと呼ばれるようになったのです。
やがて、蝦夷という漢字もエゾと読まれるようになり、近世にかけて、エゾ(蝦夷)は北海道の住民をさす言葉として定着しています。
なぜ、エミシからエゾへの呼称の変化が起きたのかは定かではありません。
ただ、次のような推測は成り立つのではないでしょうか。
当時の北海道には擦文文化が広がっており、その影響は津軽や下北地方にも及んでいました。
中央政府の支配が東北北部まで及び、こうした地域と直接接するようになったとき、そおに形成されていた文化・社会は、京都の人たちの目に極めて異質なものに映りました。
それは、かつてのエミシに対したとき以上に、異類、異族という印象だったのではないでしょうか。
そのことが、呼称の変化に反映した、と。
そして、平安時代末期以降の記録に現れる蝦夷(エゾ)とは、近世のアイヌに直接繋がる人々と考えて間違いないように思われます。
津軽海峡まで中央政府の支配が及ぶようになったことで、北海道のアイヌ社会にはますます多くの本州製品が流入してきました。
一方、擦文時代にかなりの規模で行われていた雑穀農耕は、アイヌ文化の時代に入ると次第に衰退に向かったと考えられ、近世段階では極めて小規模で粗放な略奪農業(林善茂『アイヌの農耕文化』)が、漁猟に対してあくまで付随的に行われるにすぎなくも、衰退していったものと考えられます。
アイヌの人々は、土器の製作、農業、鍛治など、物をつくことからだんだんと離れて行くと共に、工具、容器、穀類などあらゆる産品において、交易への依存度を高めていきました。
さらに、自ら捕獲した陸獣の毛皮やサケなどの水産物を交易の対価物に当てていただけでなく、北方や本州方面から持ち込まれる産品の仲介交易も担っていました。
アイヌ文化とは、交易に拠ってこそ成り立つ文化だったといえます。
このようにみていくと、従来のアイヌ=狩猟民という見方は、必ずしも的を射ていないように思えてきます。
擦文文化からアイヌ文化への移行、すなわちエミシからエゾへ移行は、「漁猟民・農耕民」から「交易民」への転換であったという見方も成り立ちます。
註 :江別市総務部「新江別市史」49-50頁.
中