
<添付画像>Yahoo映画情報〔硫黄島からの手紙:Letters from Iwo Jima〕より、画像転載
本日(昨日:1月29日)午後、どうしても映画館で観ておきたい映画「硫黄島からの手紙」を見に行った。
「・・・!」
こんな映画、今まで観たことのない「質感」の映画であった・・・
映画館に入る前、当然ながらブログ記事にする予定在ったけれど、鑑賞し終わってから後、とてもじゃないが「思い出したくない」映画となった・・・
とにかくこの映画のこと、思い出したくない。
話したくない!感想文なんて書けない、、、。
どうしても観ておきたかった映画であるけれど、決して二度と観たくない映画なのです。
しかし今、今夜は、どうしても眠れない。眠れないからブログに書きとめておくことにした・・・
上映時間2時間31分の長い映画。とてもじゃないが、重く、暗い、無味乾燥な映画でした。尚、今にして想えば、いかにもクリントイーストウッド的映画か?
最初は、ブログに「映画鑑賞感想記事、書いてやろうじゃないか!?」と張り切っていたのですが、観終へて映画館を出る時には、すでに、とてもじゃないが感想など書けない精神状態になって夜の巷に繰り出したりの居酒屋寄り道や不良中年的道草なるもの皆無にて、真直ぐ帰宅しました、、、。
映画を観て、こういう状態になるなんて、過去に経験したことなく、珍しい!
私の尊敬する作家のお一人「開高健」先生、何かのエッセイの片隅に書いていましたね、、、。
「小説エッセイその他諸々文芸作品を読み終え、その後、まずは爽やか豊かな気分になり、後には感想も残らず心地よい泡と消える、そんな何も後に残らない文芸作品、これを秀作という?!(エセ男爵流の意訳)読書感想など残るはずもないものがベストである!」
等と、、、。
それとはまた、ずいぶん意味違うけれど、「硫黄島からの手紙」を鑑賞し終えて後、映画鑑賞感想文など書けない、書きたくない。画像も音声もストーリーも、二度と思い出したくない。思い出したくないけれど、しかし、とっくに夜深けになった今も尚、耳を劈(つんざ)かれんばかりの各種轟音、つまり、大砲(野砲・山砲・カノン砲)、軍艦の艦砲射撃の大口径大砲の轟音、大砲の弾丸が飛来してくる音、戦車砲の音、重機関銃や軽機関銃の連続発射音、ロケット砲(曲射砲)の音、ライフル銃発射時の鋭利鋭敏なる音、手榴弾の炸裂音、拳銃(ピストル)のひ弱な発射音、火炎放射器の放つ炎の音、兵士の叫び声(歓声か悲鳴か)、上官の怒鳴り声、等々等々、耳に付いて今も離れません・・・
とてつもなく悲壮・無残・残酷・無常・無情なる水分枯渇飢餓地獄と化した「絶海の孤島・硫黄島」の戦場を直視するのみにて思想やイデオロギー抜きの描写はリアリズムそのもの、且つ無機質、、、。つまり、平和主義とか戦争反対とか、共産主義とか帝国主義とか独裁主義とか、民主主義とか全体主義とか、はたまた戦争で引き裂かれる男女の恋愛離別問題とか、お涙ちょうだい的な典型的戦争映画表現など、この映画には皆無、、、。(ま、無くも無いが、表現はほんの僅か・・・)
映画をひたすら観ている私自身、何故か精神的にずいぶん乾いていて、パリパリのクリスピー(crispy)状態、加えて頭は空っぽ、気分としては素っ裸になって何もかもかなぐり捨て、ただひたすらこの映画の展開、「始まりと終わり」を空虚に見守っただけである。
でも、映画のシーンの逐一、渡辺健さん扮する栗林中将の一挙手一投足を思い出すと、もうダメです、今にも大粒の涙が出てきそうで、堪りません。
さて、
監督クリントイーストウッドの描きたかったものは何か?
を、あらためて整理すると、たぶん、栗林中将か・・・?
栗林中将を、イーストウッド監督の「描きたい円」の中心に置いて円を描くと、日本帝国陸軍の一兵卒から下士官へ、さらに将校に至るまで将兵全員、そのものを描きたかったに相違ない、と観る。日本陸海軍(陸軍将校栗林中将の云うことを聞かない?理解できない軍部の集団あり。つまり陸軍出身の栗林中将をコバカにしている海軍陸戦隊将兵も硫黄島に存在し、陸軍海軍の間で大きく命令系統統率系統を欠いたものであったらしく、その中でも栗林中将の指導力は卓越しつつも・・)将兵全員、硫黄島に留まって圧倒的な兵力をもつ米軍と戦(いくさ)した日本陸軍将兵と海軍陸戦隊の有体を、淡々冷徹に描きつつ、最後に云いたかったのは「栗林中将」の個性と人格であったか。
クリントイーストウッドの描きたかった個性とは、当時の日本帝国陸軍軍人、栗林中将に内在する(あの当時、稀なる)真っ当な軍人精神、すなわち《武士道》を表現したかったに他ならないと考えます。
それ以上も、以下も、この映画の中から抽出することは不可能、、、。もって、『武士道』を描きたかったモノなのか。と、留めたく、それ以上の思考は、完全停止する。私自身は「これ以上のこと」を、この映画から抽出し分析したり等々、(これ以上のことは)何も考えたくない。
〆て、本投稿記事は映画鑑賞感想文にあらず!・・・
PS:ブログに記事として認(したた)めた後、想うことあり。
どうしても「父親達の星条旗」を観たくなった、、、。この映画「硫黄島からの手紙」とワンセットになっているので、必ずや観ておかねばならぬ映画となった、、、。
PS(平成19年2月9日、追記):計らずも、「硫黄島からの手紙」の第2弾!?関連記事!?書いてしまいました。是非にもご一読頂きたく、こちらからお入りください!
------------------------------------------------------
<関連サイトURLの紹介>
* ウイキペディア百科事典「映画・硫黄島からの手紙」
* ウイキペディア百科事典「太平洋戦争」
Yahoo映画紹介
* 父親達の星条旗
本日(昨日:1月29日)午後、どうしても映画館で観ておきたい映画「硫黄島からの手紙」を見に行った。
「・・・!」
こんな映画、今まで観たことのない「質感」の映画であった・・・
映画館に入る前、当然ながらブログ記事にする予定在ったけれど、鑑賞し終わってから後、とてもじゃないが「思い出したくない」映画となった・・・
とにかくこの映画のこと、思い出したくない。
話したくない!感想文なんて書けない、、、。
どうしても観ておきたかった映画であるけれど、決して二度と観たくない映画なのです。
しかし今、今夜は、どうしても眠れない。眠れないからブログに書きとめておくことにした・・・
上映時間2時間31分の長い映画。とてもじゃないが、重く、暗い、無味乾燥な映画でした。尚、今にして想えば、いかにもクリントイーストウッド的映画か?
最初は、ブログに「映画鑑賞感想記事、書いてやろうじゃないか!?」と張り切っていたのですが、観終へて映画館を出る時には、すでに、とてもじゃないが感想など書けない精神状態になって夜の巷に繰り出したりの居酒屋寄り道や不良中年的道草なるもの皆無にて、真直ぐ帰宅しました、、、。
映画を観て、こういう状態になるなんて、過去に経験したことなく、珍しい!
私の尊敬する作家のお一人「開高健」先生、何かのエッセイの片隅に書いていましたね、、、。
「小説エッセイその他諸々文芸作品を読み終え、その後、まずは爽やか豊かな気分になり、後には感想も残らず心地よい泡と消える、そんな何も後に残らない文芸作品、これを秀作という?!(エセ男爵流の意訳)読書感想など残るはずもないものがベストである!」
等と、、、。
それとはまた、ずいぶん意味違うけれど、「硫黄島からの手紙」を鑑賞し終えて後、映画鑑賞感想文など書けない、書きたくない。画像も音声もストーリーも、二度と思い出したくない。思い出したくないけれど、しかし、とっくに夜深けになった今も尚、耳を劈(つんざ)かれんばかりの各種轟音、つまり、大砲(野砲・山砲・カノン砲)、軍艦の艦砲射撃の大口径大砲の轟音、大砲の弾丸が飛来してくる音、戦車砲の音、重機関銃や軽機関銃の連続発射音、ロケット砲(曲射砲)の音、ライフル銃発射時の鋭利鋭敏なる音、手榴弾の炸裂音、拳銃(ピストル)のひ弱な発射音、火炎放射器の放つ炎の音、兵士の叫び声(歓声か悲鳴か)、上官の怒鳴り声、等々等々、耳に付いて今も離れません・・・
とてつもなく悲壮・無残・残酷・無常・無情なる水分枯渇飢餓地獄と化した「絶海の孤島・硫黄島」の戦場を直視するのみにて思想やイデオロギー抜きの描写はリアリズムそのもの、且つ無機質、、、。つまり、平和主義とか戦争反対とか、共産主義とか帝国主義とか独裁主義とか、民主主義とか全体主義とか、はたまた戦争で引き裂かれる男女の恋愛離別問題とか、お涙ちょうだい的な典型的戦争映画表現など、この映画には皆無、、、。(ま、無くも無いが、表現はほんの僅か・・・)
映画をひたすら観ている私自身、何故か精神的にずいぶん乾いていて、パリパリのクリスピー(crispy)状態、加えて頭は空っぽ、気分としては素っ裸になって何もかもかなぐり捨て、ただひたすらこの映画の展開、「始まりと終わり」を空虚に見守っただけである。
でも、映画のシーンの逐一、渡辺健さん扮する栗林中将の一挙手一投足を思い出すと、もうダメです、今にも大粒の涙が出てきそうで、堪りません。
さて、
監督クリントイーストウッドの描きたかったものは何か?
を、あらためて整理すると、たぶん、栗林中将か・・・?
栗林中将を、イーストウッド監督の「描きたい円」の中心に置いて円を描くと、日本帝国陸軍の一兵卒から下士官へ、さらに将校に至るまで将兵全員、そのものを描きたかったに相違ない、と観る。日本陸海軍(陸軍将校栗林中将の云うことを聞かない?理解できない軍部の集団あり。つまり陸軍出身の栗林中将をコバカにしている海軍陸戦隊将兵も硫黄島に存在し、陸軍海軍の間で大きく命令系統統率系統を欠いたものであったらしく、その中でも栗林中将の指導力は卓越しつつも・・)将兵全員、硫黄島に留まって圧倒的な兵力をもつ米軍と戦(いくさ)した日本陸軍将兵と海軍陸戦隊の有体を、淡々冷徹に描きつつ、最後に云いたかったのは「栗林中将」の個性と人格であったか。
クリントイーストウッドの描きたかった個性とは、当時の日本帝国陸軍軍人、栗林中将に内在する(あの当時、稀なる)真っ当な軍人精神、すなわち《武士道》を表現したかったに他ならないと考えます。
それ以上も、以下も、この映画の中から抽出することは不可能、、、。もって、『武士道』を描きたかったモノなのか。と、留めたく、それ以上の思考は、完全停止する。私自身は「これ以上のこと」を、この映画から抽出し分析したり等々、(これ以上のことは)何も考えたくない。
〆て、本投稿記事は映画鑑賞感想文にあらず!・・・
PS:ブログに記事として認(したた)めた後、想うことあり。
どうしても「父親達の星条旗」を観たくなった、、、。この映画「硫黄島からの手紙」とワンセットになっているので、必ずや観ておかねばならぬ映画となった、、、。
PS(平成19年2月9日、追記):計らずも、「硫黄島からの手紙」の第2弾!?関連記事!?書いてしまいました。是非にもご一読頂きたく、こちらからお入りください!
------------------------------------------------------
<関連サイトURLの紹介>
* ウイキペディア百科事典「映画・硫黄島からの手紙」
* ウイキペディア百科事典「太平洋戦争」
Yahoo映画紹介
* 父親達の星条旗










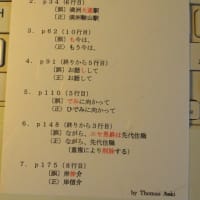
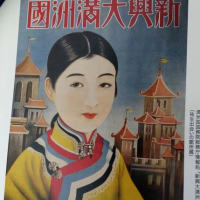

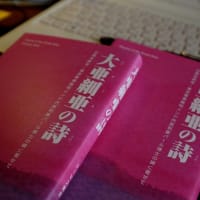
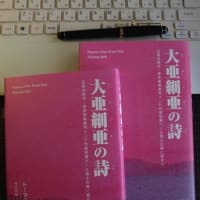


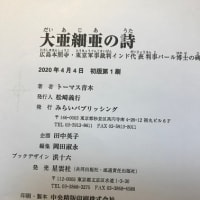
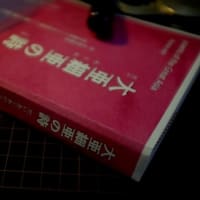

実は先週末の昼下がり、自宅近くの映画館(ルート170と言う)にふらりと立ち寄る。この映画見ようと思ったら午後3時半が次の上映時間、2時間近くもあり、またタイミング合わず。今日までまだ未鑑賞。
鑑賞前のコメントは口幅ったいが、同監督のファンにてお許しを!
この映画の前に、イーストウッドという人、自作自演で西部劇で有名になった。そう、夕日のガンマン、荒野の用心棒...。一言で言えば、ストーリーはあるが、最初から最後まで容赦しないガンマンぶり(藤田まことの仕置き人みたいな)で、拳銃、ライフル、マシンガンを駆使する。ただただ主役とストーリーをハードボイルドに仕上げている。もちろん、見る人には息もつかせないし、感想も許さない、というよりか感想は不要...というところか。そういう意味では西部劇ではリオブラボーや荒野の七人などのジョンウエインとその作品の方が...「映画というものは楽しいですね、いいですね...」となる。エセ男爵さん、感想もないし、感想したくもない、恐らくこの作品がイーストウッド監督の所以か、このあきさんも近日中に見て確かめたい。
オレも見たいなぁ…。オレの好きなクリント・イーストウッドが手がけた映画だし…。
ポチ。
「父親達の星条旗」も見ましたが感想は省きます。
「硫黄島からの手紙」について
>あらためて整理すると、たぶん、栗林中将か・・・?
私もそう思います。
先般TVで栗原中将の身の回りの世話をしていた軍属の方が出ておられましたが、何処について言っても穏やかにそして優しかった中将が、硫黄島に行くときには「付いてくるな!」と言われたと語っておられました。
それでもその軍属の方は、サイパンまで行ったらしいのですが、軍用電話で話した時に「本土に帰れ」と、初めて厳しい口調で「命令」されたと仰っていたように記憶しています。
映画でも有りましたが、応援が来ないのは知っていたようですから、帰れないのは分かっていたのですね。
そこで、映画ですが、
元憲兵の回想シーンや、一兵隊が上司の命令を無視して自決を逃れる理由に栗原中将の言葉を利用する等が引っ掛かりました。
考えてみたのですが、米国在留で自由社会を知る中将の賞賛は米国の賞賛とは言いませんが、日本帝國軍人を賞賛した映画で無いと感じました。
先般TVで栗原中将の身の回りの世話をしていた軍属の方が出ておられましたが、何処について言っても穏やかにそして優しかった中将が、硫黄島に行くときには「付いてくるな!」と言われたと語っておられました。
それでもその軍属の方は、サイパンまで行ったらしいのですが、軍用電話で話した時に「本土に帰れ」と、初めて厳しい口調で「命令」されたと仰っていたように記憶しています。
映画でも有りましたが、応援が来ないのは知っていたようですから、帰れないのは分かっていたのですね。
イーストウッドが、ある意味よく此処まで作ったなとは思いましたが、特に栗原中将の人間的な部分は、やはりアメリカ人から見た日本人でしか描いてなかったと勝手に感じました。
当たり前と言えば当たり前ですし、もちろん私が栗原中将を知っているわけではありませんが。。。
まとまりなく、ウダウダと申し訳ないです。
>でも、映画のシーンの逐一、渡辺健さん扮する栗林中将の一挙手一投足を思い出すと、もうダメです、今にも大粒の涙が出てきそうで、堪りません。
これが男爵様の感想なのでしょうね。
私も観たいと思ってるのですが、
果たして観れるかどうか…
後日DVDで観る事になりそうです・・・
いやいや、私も貴兄と同じ状態にて、この映画の第2回上映時刻始まって1時間30分経過時点にて「映画館の前」にたどり着いたのは午後2時15分過ぎ・・・
入場するかどうか、映画館の前で数十秒考えた。
次回上映時刻は、午後4時。
それまで待てば、約1時間30数分間もの長き?にわたる時間を過ごさねばならない。また、4時から映画を観始めると、終了時間は午後6時30分を回り、映画を観終わって夜の繁華街に脇目も振らず、真直ぐ帰ったとしても、帰宅時刻は午後8時近くになる。
少し迷ったが、そのまま映画館に入った。
小生、映画を途中から観始めて、途中で観終わり、前後テレコにてインプットされた「映画のストーリー」を観終えてつなぎ合わせる脳内作業技術は(高校時代から特訓に特訓をかさね修練した経緯あり)、前後が逆になったストーリーを整合させる技・技能には卓越したものあり。以って自信あり。
実は、この修練の集積に関し、高校時代の思い出がある。昼の弁当を食べ終わって午後の授業をサボり、そのまま映画館に直行するは毎週必ず一回以上。そのまま2流洋画館に行けば、3本立ての洋画をレンチャンで見せてくれたのだ。(たぶん、貴兄ご承知!)時間来れば、いかにも真面目に学業を終えた時間帯に帰宅する、軟派的高校時代の後半を過ごしていた。
こんな経緯で、当時培ったシナリオさかさま鑑賞の技、いまだ衰えず、、、。
そんなこんなで、この「硫黄島からの手紙」を途中から鑑賞した。
小生は、もう、二度とこの映画を観たくないけれど、それは一度見た人間の言うセリフ。
貴兄には、何が何でも必ず映画館へ馳せ参じて「得と鑑賞すべし」・・・
申し上げておくが、我が郷里の封切映画館上映スケジュールを参照すれば、何と明日2月2日を以ってこの映画は一旦完了するとの事。
本日午後又は明朝一番にて、急ぎ鑑賞されるべし・・・
再度御礼申し上げる。
貴兄からの初コメント記入、たいへんありがとうございました。
旧知の中とて逆に遠慮召されず、今後もどしどしコメント頂きたく、あらためてお願い申し候、、、。
<注>:「あきさん」こと、Mr.Akiは大学時代の同期生。同じクラブ部員として活動していた旧友。英語の達人の一人。仕事を通して外国生活経験豊富な国際派の人物です。例の旧友UT氏も、同じクラブ活動をやっていた仲間です・・・
若い方に是非観ていただきたい映画ですが、以外や以外、理解するのは難しいかも・・・
いや、理解する必要なし。
これを切っ掛けに、「太平洋戦争史」を紐解かれるようお願いしたいです。
たぶん、私は私自身と同年代同世代の人たちよりも、より多くの太平洋戦争歴史資料の断片を習得している心算<つもり>です。にもかかわらず、いや、だからこそ?かくして映画化された日米両軍将兵による太平洋戦争中もっとも死傷した将兵の多い(絶対数は勿論、確率的に)「硫黄島の死闘」を直視するには、心身ともに耐えがたいものあり・・・
例の第二次世界大戦中のヨーロッパ戦線における連合軍フランス上陸作戦(D-Day)時に、連合軍の蒙った被害、すなわち上陸作戦時に失った死傷兵の絶対数を上回る米軍海兵隊将兵の死傷者数が、この硫黄島の戦いであったそうです。旧日本軍将兵に於ける戦(いくさ)の最後は、食糧欠乏・飲料水欠乏・弾薬欠乏・人間が生きていく上に於いて「絶対必要不可欠」なモノを5日間以上も飲まず食わずして、灼熱炎熱地獄の中、最後に取るべき戦術は肉弾突撃以外に無し。たぶん最終攻撃は夜襲にて、突如暗闇から現われ出でるミイラの如く朽ち果てる寸前の日本軍将兵に襲われ、死の恐怖に戦慄しない米軍将兵は皆無であったと考えます。昨夜、期せずして、ヒストリーチャンネルで硫黄島の戦いを放映していました。硫黄島の戦いに参戦し辛うじて生き残った元米軍将兵のインタヴューを聴いていましたけれど、インタヴューに答えているどの将兵も、表情は暗く哀れみの表情にて、今にも泣き出しそうな面持ちにて、当時の硫黄島の決戦の思い出を語っていました。。。。
そして、
たぶん、「父親たちの星条旗」も、必ず観ておかねばならない映画だと思っています。観なければ、たぶん「辻褄(つじつま)」が合わないかも?・・・
わたしは如何しても「父親たちの星条旗」を観てのち、「硫黄島からの手紙」の自己脳内整理を致したく、あわせてイーストウッド監督の表現したかったこと、総合的に整理してみたいと思っています。
ムム・・・
やはりそうですか・・・
すでに殿下はこの映画を観ておられるのですね。しかも『父親たちの星条旗』までも、、、。
さすがです。
もちろん、殿下のご感想は聞くまでも無し、エセ男爵にして、ほぼ想像がついています。
太平洋戦争の倫理的「是非」や「可否」?
すでに歴史の彼方にて、いまさらその様な野暮天なる愚問愚論、誰に問うまでもありません。
19世紀的世界に於いては、いずれも植民地獲得の目的が唯一最大の国家戦略は、欧米列強の政治的目標であったこと否定できません。領土拡大植民地拡大の為の富国強兵の大きな潮流の中、明治維新を経てのち後発にて、地球世界に踊り出でた日本国として、かの太平洋戦争は米国(他の連合国を含め)の、日本シナ大陸を包括するアジア地域(当時は諸国と云えない状況?)の覇権争いにて、動かさざる我国の地理的立地条件は宜しくなく、如何なる状況に於いても米国の標的になったは避けうる事叶わず、かくして日本は経済封鎖を受けて戦争に突入せざるを得なかったは事実無比なる歴史の事実と、私は受け止めています。
米英と戦になれば、必ず負けると分かっていた栗林中将にして「戦わざるをえなかった」状況とそれに挑む心境は、所謂モノノフの為せるところ。すなわち、米国軍人から見た「栗林中将」に対する純粋なる視点観点は、日本の理想的なる軍人精神を持ち合わせた高級将校、すなわち武士道精神の持ち主であること、アメリカ人は理解していたという証明があってこそ、映画「硫黄島からの手紙」を創作した最大要因と考えるのです。
かくして、
殿下おおせの「国を護る」大切さ、、、、。
竹島問題、
国旗国歌の問題等々、
教育問題、
社会性モラルの超低下、
我国政治の軟弱性、
マズ塵の体たらくさ、
いまだ寸足らずにて国際感覚の脆弱性、
等々、、、
21世紀のわが国に於いて、日本人として真面目に考えなくてはならないこと、山積です。
この映画を観終えたのち、いろいろ思いを廻らせれば益々、殿下ブログに謳っておられる事柄事項の大切さを、あらためて感じ入っている今日この頃なのです、、、。
かくして、
>>でも、映画のシーンの逐一、渡辺健さん扮する栗林中将の一挙手一投足を思い出すと、もうダメです、今にも大粒の涙が出てきそうで、堪りません。・・・
>これが男爵様の感想なのでしょうね。・・・
さすが刀舟さん!
恐れ入りました。
実は、感想無き感想としては、唯一、ご指摘の個所、ご指摘の一行のみ!
これが私の感想です。
決して「涙しない・エセ男爵!」にして、我が心の中で魂のまん中で、「涙溢れて泊まらず・・・」的な心境でした。単に悲しくての「涙」は間違っても決して流さないけれど、勇壮無念且つ悲願達成ならず口惜しくて「涙」する事、稀にあり。栗林中将なる日本人、彼の軍人としての本分、すなわち武士道精神を「まっとう」せんがための立派な「立ち居振る舞い」を目の当たりにして、感動!
そしてそのような雄姿と言動に対し、感極まって(心の中で)涙すること、多々あります・・・
そんな心境にて、この記事書き殴った次第!
「・・・!」
お忙しい刀舟さんに於かれましても、是非この映画鑑賞して頂きたく、遠く歴史の彼方を紐解いてて頂きたく、願わくば、時に触れ、事に触れ、折に触れ、「子弟の教育」に反映して下さいますこと、願って止みません・・・
○戦陣訓戦後の定説では、虜囚の辱=敵国の捕虜と解釈。軍人が敵国の捕虜になる場合は、①戦時下の投降(部隊・個人)、②戦時下の負傷のため投降(個人)、③終戦による投降(国の敗戦)と、戦後の定説(虜囚の辱=敵国の捕虜)に従うと三者三様の捕虜が存在することになる。
戦後の定説で要約してみよう。戦陣訓には敵国の捕虜の判別の明記が無いので、①「捕虜となるよりは自殺せよ」②気を失ったり、動けない負傷者も「捕虜となるよりは自殺せよ」③終戦後の捕虜も、戦陣訓には敵国の捕虜の判別の明記が無いので、当然、「捕虜とならず自殺せよ」と、なる。
戦陣訓には戦時下の投降、終戦による投降の区別が無い。あくまでも捕虜は捕虜で解釈すべきで戦陣訓に記載の無いものを、勝手に区別し解釈するのは、捏造以外の何物でも無い。
②は動けず実行不可。③は終戦なのに自殺せよと矛盾し実行不可。よって、(虜囚の辱=敵国の捕虜)は成立せず。
大東亜戦争終戦後も、ソ連64万人(民間人含む)など多くの人が捕虜になっている。戦後捕虜となり、皆自決しましたか?。否。終戦前は戦後のような矛盾だらけの解釈など誰もしなかったし、ほとんどの人が「戦陣訓」など、念頭に無かった。終戦前は戦陣訓の一人歩きなど皆無、。終戦後マスコミと鵜呑みした鵜人が、一人歩きさせた。
○(虜囚の辱=敵国の捕虜)では文意に合致しない。(虜囚の辱=日本国の囚人)で文意に合致。
○「軍人勅諭」に一切明記の無い(降伏禁止)を、「戦陣訓」に記載は出来ない。それでも(降伏禁止)記載ありと主張するのは、捏造以外の何ものでもない。
不可抗力で捕虜になるのが恥辱とは、そんな愚かな軍紀は古今東西どこにも無い。戦後の捏造だ。
『戦陣訓』の真実、詳細は下記。
真実史観日本護国史戦勝国歪曲党売国党狂惨党に仕組まれ捏造された大東亜戦争
http://www.tofu-ryohin.co.jp/siten.htm
貴コメント内容並びに貴ホームページ、確かに拝読致しました。
貴殿の「戦陣訓」に関する御説、ごもっともです。
さて、
拙ブログ本記事に関し、純粋純朴に「映画・硫黄島からの手紙」鑑賞後の雑記にて、文末に申しましたとおり感想文にもならない独り言であります。
また、硫黄島戦闘に関する日本近代史観及び太平洋戦争、さらには、すでに近代史として顧みるべき日本帝国陸海軍軍人への「客観的視点」は、凡そ本映画の監督クリントイーストウッド氏及び助監督?スティーヴンスピルバーグ氏の主観客観に立脚するものと考え、鑑賞後直ちに「戦陣訓」の是非に結び付けるを、敢えて行なっていません。
なお、
戦陣訓に関し、昨年8月8日投稿記事「拝啓櫻井よしこ様・・・戦陣訓、云々・・」(下記URL参照)
http://blog.goo.ne.jp/baron24ese/e/89fba2b0116205e53631ec97e24e17bd
により、
不肖・エセ男爵なりの「見解」を述べておりますこと、お伝え致します。
是非上述記事にもご訪問下されば幸いです。
これを機会に、「真実史観さま」に於かれましては、今後とも、どうぞ宜しくご友誼下さいますよう、お願い申し上げます。