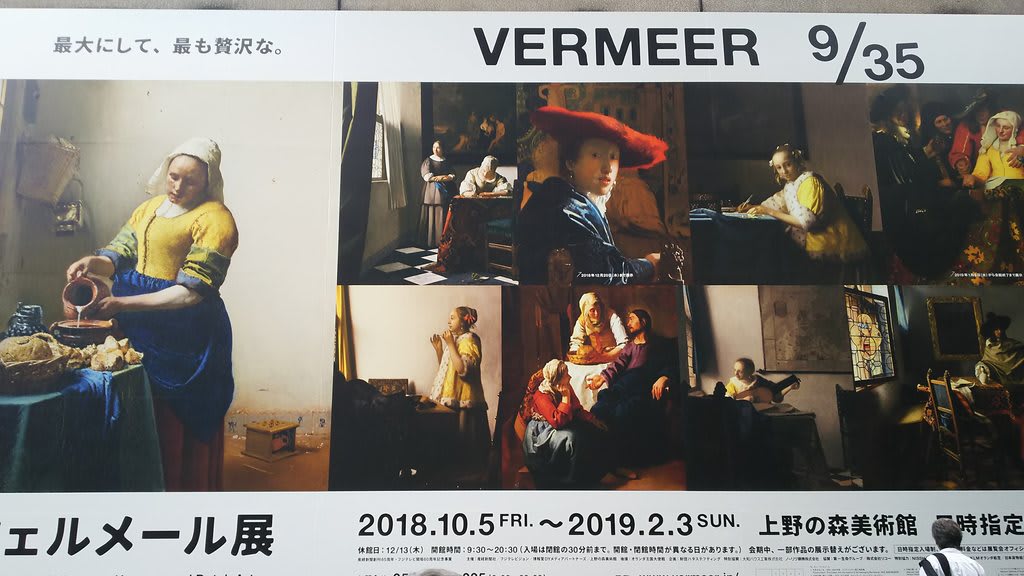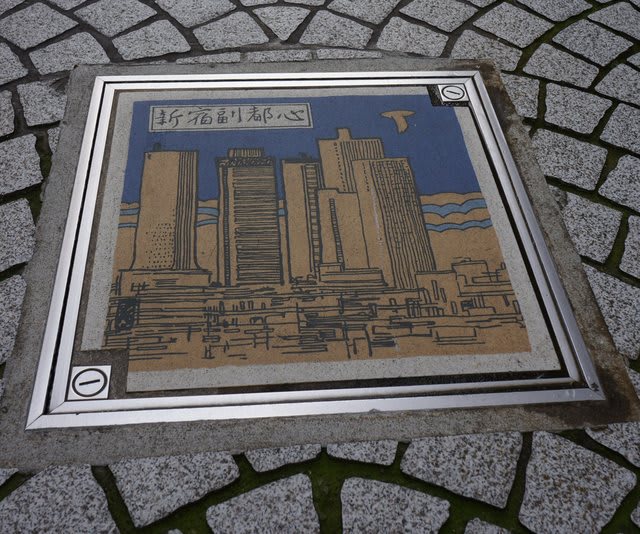季節ごとの魅力を楽しみに多くの人々が集う
上野恩賜公園内の不忍池の歴史を遡る特別展です。
はるか昔、東京湾の入り江が南下していった際、
取り残されてできた池が、
後に不忍池になったのだそうです。
江戸時代に寛永寺を創建した天海大僧正が
池を琵琶湖に見立て、弁天堂を建立して以来、
桜や蓮の花見、月見、雪見の名所として
江戸の人々に親しまれてきました。

不忍池は何度となく眺めていますが、
その歴史を知りたいと台東区立下町風俗資料館へ。

明治時代に上野の山が公園として開放されると、
池の周囲は競馬場や博覧会など様々な催しの会場として
昭和初期まで大きな賑わいを見せたそうです。
その歴史に関する錦絵や写真、地図などの資料を展示、
様々な角度から、人々が集う不忍池の魅力を知りました。

2階には、台東区内の銭湯で
実際に使われていた番台の展示も。
1階は、古き良き江戸の風情をとどめる
東京・下町の大正時代を再現しています。

「谷中七福神巡り」のコース場にあった
下町風俗資料館付設展示場(旧吉田屋酒店)
<台東区上野桜木2-10-6>
江戸時代以来の老舗で、1986年まで営業、
1910年に建てられたものを移築しています。
店先には明治から昭和の時代にかけて実際に
使われていた秤、樽、枡などを展示されており、
台東区指定の文化財になっています。
台東区立下町風俗資料館
東京都台東区上野公園2-1
2019.1.10