大森周辺は、江戸時代には質量ともに
全国一を誇った海苔の産地でした。
東京湾の埋め立てにより1963年に
海苔の生産地としての歴史は閉じましたが、
大森周辺には海苔問屋が多く、
現在も海苔流通網の重要な拠点の一つです。

一番奥が大田区に唯一残る海苔船(伊藤丸)、
入り口を入ってすぐ正面に展示されています。
昭和33年造船の全長13mの海苔船です。

3階は休憩コーナー・展望テラス、
大森ふるさとの浜辺公園を一望できます。

2階は展示室・講座室
国の重要有形民俗文化財に指定されている
海苔生産用具を展示しています。
「大森および周辺地域の海苔生産用具」の名称で
国の重要有形民俗文化財に指定され、
海苔の歴史を伝える貴重な文化遺産になっています。

こちらの施設では「海苔つけ体験」や
「海苔すづくり」など事前申し込みにて
体験できる日があるようです。

何でもやってみたい私は、すぐにできる
「海苔下駄体験コーナー」で海苔下駄を履きました。
(靴を履いたまま下駄を履きます。)

こちらも海苔下駄ですが、
とても履けそうにありません。
この海苔下駄は、海苔を養殖する資材を建てるため
下駄を履いて振り棒で海底に穴をあける
作業をする際に履いたようです。

海苔採りざるだけでも色々な種類があるものです。
海苔づくりは、300年程前の享保年間に
始まったといわれます。
品川から大森周辺の海辺、浅瀬の広がる
大森周辺は大きな産地として発展し、
江戸時代の終わり頃、ここから各地へと
海苔づくりは伝わり始めました。

私たちが利用している羽田空港は、
海苔づくりの跡地であったというわけですね。

都心に近い飛行場は、とても便利ですが、
東京湾の埋め立てで仕事を奪われたり、
居住する場所を変えなければならなかった
住民の方々がいたことも忘れてはなりません。
東京都大田区平和の森公園2-2
2018.9.9


































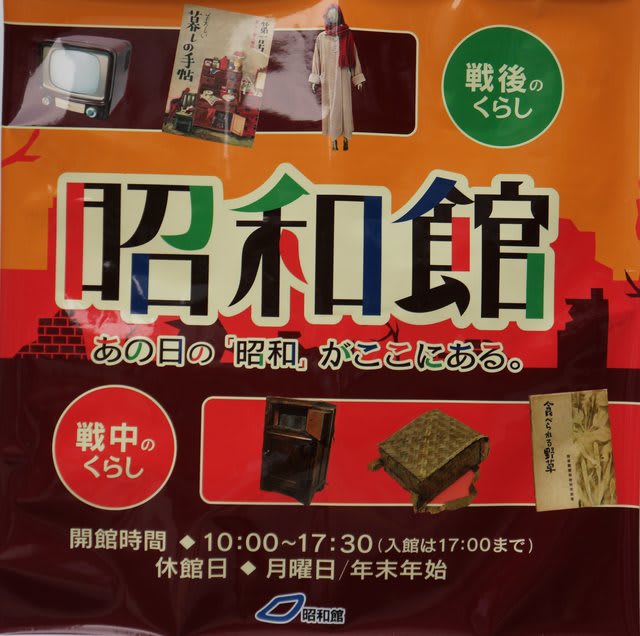











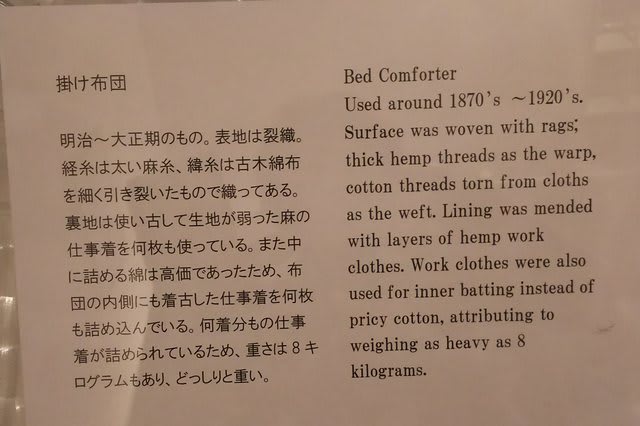

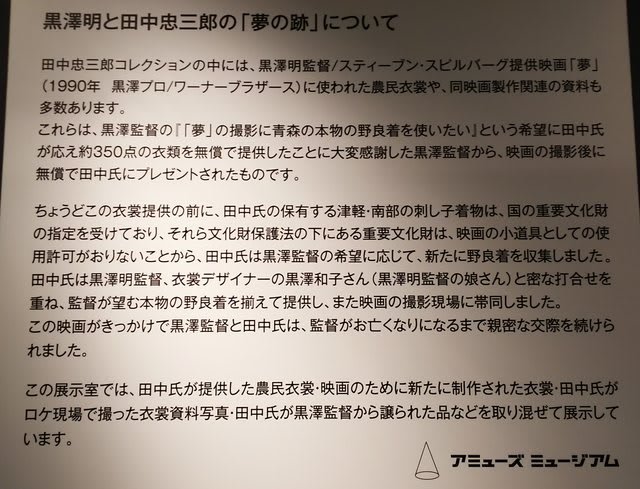




















 )
) 観ておけば良かった
観ておけば良かった



