
[目次]
第1章 日本経済の実力―ドルは凋落し、円は上昇する
第2章 日本の外交力―外務省を廃止せよ
第3章 間違いだらけの“食料安保論”―自給率低下は日本のアキレス腱か
第4章 脱石油の時代―原発技術は日本の独壇場だ
第5章 消費税アップ不要論―やるべきことはこれだけある!
第6章 「日本・格差社会」論のウソとホント―日本に「格差社会」はない
<2009年の日本はこうなる - 反日勢力を斬る(2) - Yahoo!ブログ>
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponko2007/28201273.html
本書は、2009年1月5日に刊行されています。今年も半年が経ようとしていて、日下さんのどんな予測をし、それは果たしてどうなっているのか、そんな思いで手に取った一冊。経済、外交、食糧、エネルギー、そして格差社会といった問題に、快刀乱麻を断つ日下イズムで切り込む鋭い一刀は本書でもいかんなく発揮されていました。
例えば円高・・・
「2007年の輸出(83兆9314億円)と輸入(73兆1359億円)の差額は約10兆円である。これはざっくりとした計算であるが、たとえそこで円が一割高くなったとしても一兆円の損。二割高くなったとしても二兆円の損で、貿易黒字が失われるわけではない」。
例えば外交・・・
「私の結論を言えば、『外務省は廃止せよ』である。外交はいま外務省がやっている程度でよければ、内閣官房で十分にできる。世界中がトップ外交になっているからである」。
「ODA一兆円を二割削減すれば2000億円浮く。これで『国際貢献基金』をつくる。内実は『世界謀略基金』で、この機関でやることは、世界中から人を雇い、いろいろなアイデアを出してもらい、日本にとって有利な世界戦略を練り、それを実行する」。
「目的はもちろんより良い世界をつくることで、これは日頃日本人が考えていることをそのまま書き出せばよい。そのために補助金か奨励金を配るのであれば日本人が考える条件を書き出す。例えば、①隣国と紛争を起こしていないこと②国内で言論の自由があること③軍事費を増加させていないこと④環境破壊防止に努力していること⑤食糧検査は日本並みにすること・・・など何でも書き出しておけば奨励金欲しさに努力する国が現われて、世界は良くなるはずである。そして目標を数値化しておけば達成度が分かるし完了もわかる」。
例えば、食糧自給率・・・・
「食糧自給率を上げるもっとも簡単な方法は、まずわれわれが食べる量を減らせばいい。『飽食の時代』といわれ、日本人は食べ過ぎて、メタボリック症候群を心配するほどになっている。『朝バナナダイエット』などがはやるように、ダイエットをして痩せたいという人はいくらでもいる」。
「それなら、いま食べている量を半分に減らせば、自給率は一挙に倍の八割になる。食べる量を減らせば、きれいで健康になるというのなら、消費を減らせばいいのである。しかも健康になれば医療費も抑えられるので、食糧自給率を上げ、健康保険の赤字も少なくなるという一石二鳥である」。
頻繁に使われる食糧自給率、カロリーベースで計算しているので、野菜の生産は統計に入っていないんだとか。
例えば、石油・・・
「(石油資源)の計算は、埋蔵量が年々の消費量の何倍あるかだが。そもそも埋蔵量という数字が不思議である。それは、いまの技術で経済的に採取できる量(確認埋蔵量)で、そして、あと何年でなくなるというのは、『可採年数』といって、ある時点における確認埋蔵量をその時点での年間消費量で割ったものである」。
「したがってこの確認埋蔵量は、石油価格の変動、渉猟の変動、そして技術の進歩によって、新たな油田の発見がなくても、毎年変化する。石油資源が少なくなり、需要が多くなれば、そのときは価格が上がるが、しかし、価格が上がれば、新たな油田や新しい技術の開発が促進される。そして技術の進歩によって、それまでは採算が合わなかった油田を開発できるようになる。これまで採算が合わないと放っておかれた『オイルサンド』や『オイルシェール』などからも石油を取り出すようになり、そこで北米の埋蔵量がはねあがった。埋蔵量とはそのようなことで変動する」。
例えば、消費税・・・
「消費税を引き上げて喜ぶのは、自民党や財務省で、当然、国民は喜ばない。財務省が消費税を引き上げようとしている旗印は財政再建だが、もう一つ直間比率の是正というのもある。まず、消費税を上げずに済ます方法を述べてみよう」。
「一つは無駄な公共事業をやめれば歳出を大幅にカットできる。実際、すでに公共事業費はどんどん減っているが、それをさらに広げていく。もちろん土木建築などの業界には反対がある。それから族議員が反対する。第二は、赤字の国営事業を民営化する。中曽根首相は国鉄をJRにした。第三は、国有資産を売却する。小泉首相は郵便局を株式会社にした。どちらも国家が大株主として残っているが、その株式を売却すれば国有財産を売って収入にしたことになる」。
「消費税の議論はまずここから再出発するのがよいと思う。『消費税は福祉目的税にする』とかの主張はこの問題から逃げるために考えられたもので、結局は増税だから国民の同意は得られていない。国家財政の危機と赤字国債累積の問題にもどって、最終的にはどうなるのか—--を述べておこう。借金累積の問題には簡単な答えがある」。
「その一、やがて誰も貸してくれなくなるから借金は累積しない。その二、返済不能になったときは貸し手があきらめてくれる。したがって返済累積問題は最終的には、貸し手が自分は『甘かった』と反省し、借り手が『すまなかった』と謝る問題で決着になる。これは個人間でも企業間でも国家間でも変わらない信用の世界の法則である」。
「かつて1990年はじめにバブルがはじけて日本中が真っ暗になったとき、1994年の個人金融資産は1200兆円もあった。当時は、経済評論家などみな暗い見通ししかいわなかったが、そのとき私は『日本人の個人金融資産は1200兆円のあるのだから大丈夫だ』といっていたが、賛成してくれたのは竹村健一さんだけだった。いまは1500兆円になっている。それだけ個人金融資産があって、不景気だと幸いでいるのが不思議である」。
例えば、「格差」・・・
「『格差』とは、収入に『差がある』という程度問題ではなく、『格が違う』というように、その間に大きな溝が開いて、その間には隔絶した『段違い』があることが条件である。だから、『これは格が違うから、あいつとはもう争わない』というように、回復不能といったニュアンスがある。社会学的にいうならば、『追いつくことができるかどうか』が問題で、ヨーロッパでは、収入差の原因には身分差があって、ほとんど『生まれ』で決まっているから追いつくことができない。それがほんとうの『格差』である」。
「イギリスでは、貴族などの上流階級と労働者階級は、言葉遣いも違えば、生活も違う。そして、お互いに『あちらの人間は別の人間だ』と割り切っている。下流階級の人は、自分たちが上流階級になれると思っていないし、またなりたいとも思わない。日本では、生まれ育ちはそれほど問題にされないから、頑張れば誰でも追いつくことができる。いまの日本が『格差社会』かどうかの議論にはもっと強烈な格差社会が外国にはあることを考慮に入れてもらいたい」。
<日本の底力を知る、「こんなにすごい日本人のちから だから、日本の未来は明るい!」(日下公人著)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/efafc92125ef954976624574400f43d0
第1章 日本経済の実力―ドルは凋落し、円は上昇する
第2章 日本の外交力―外務省を廃止せよ
第3章 間違いだらけの“食料安保論”―自給率低下は日本のアキレス腱か
第4章 脱石油の時代―原発技術は日本の独壇場だ
第5章 消費税アップ不要論―やるべきことはこれだけある!
第6章 「日本・格差社会」論のウソとホント―日本に「格差社会」はない
<2009年の日本はこうなる - 反日勢力を斬る(2) - Yahoo!ブログ>
http://blogs.yahoo.co.jp/nipponko2007/28201273.html
本書は、2009年1月5日に刊行されています。今年も半年が経ようとしていて、日下さんのどんな予測をし、それは果たしてどうなっているのか、そんな思いで手に取った一冊。経済、外交、食糧、エネルギー、そして格差社会といった問題に、快刀乱麻を断つ日下イズムで切り込む鋭い一刀は本書でもいかんなく発揮されていました。
例えば円高・・・
「2007年の輸出(83兆9314億円)と輸入(73兆1359億円)の差額は約10兆円である。これはざっくりとした計算であるが、たとえそこで円が一割高くなったとしても一兆円の損。二割高くなったとしても二兆円の損で、貿易黒字が失われるわけではない」。
例えば外交・・・
「私の結論を言えば、『外務省は廃止せよ』である。外交はいま外務省がやっている程度でよければ、内閣官房で十分にできる。世界中がトップ外交になっているからである」。
「ODA一兆円を二割削減すれば2000億円浮く。これで『国際貢献基金』をつくる。内実は『世界謀略基金』で、この機関でやることは、世界中から人を雇い、いろいろなアイデアを出してもらい、日本にとって有利な世界戦略を練り、それを実行する」。
「目的はもちろんより良い世界をつくることで、これは日頃日本人が考えていることをそのまま書き出せばよい。そのために補助金か奨励金を配るのであれば日本人が考える条件を書き出す。例えば、①隣国と紛争を起こしていないこと②国内で言論の自由があること③軍事費を増加させていないこと④環境破壊防止に努力していること⑤食糧検査は日本並みにすること・・・など何でも書き出しておけば奨励金欲しさに努力する国が現われて、世界は良くなるはずである。そして目標を数値化しておけば達成度が分かるし完了もわかる」。
例えば、食糧自給率・・・・
「食糧自給率を上げるもっとも簡単な方法は、まずわれわれが食べる量を減らせばいい。『飽食の時代』といわれ、日本人は食べ過ぎて、メタボリック症候群を心配するほどになっている。『朝バナナダイエット』などがはやるように、ダイエットをして痩せたいという人はいくらでもいる」。
「それなら、いま食べている量を半分に減らせば、自給率は一挙に倍の八割になる。食べる量を減らせば、きれいで健康になるというのなら、消費を減らせばいいのである。しかも健康になれば医療費も抑えられるので、食糧自給率を上げ、健康保険の赤字も少なくなるという一石二鳥である」。
頻繁に使われる食糧自給率、カロリーベースで計算しているので、野菜の生産は統計に入っていないんだとか。
例えば、石油・・・
「(石油資源)の計算は、埋蔵量が年々の消費量の何倍あるかだが。そもそも埋蔵量という数字が不思議である。それは、いまの技術で経済的に採取できる量(確認埋蔵量)で、そして、あと何年でなくなるというのは、『可採年数』といって、ある時点における確認埋蔵量をその時点での年間消費量で割ったものである」。
「したがってこの確認埋蔵量は、石油価格の変動、渉猟の変動、そして技術の進歩によって、新たな油田の発見がなくても、毎年変化する。石油資源が少なくなり、需要が多くなれば、そのときは価格が上がるが、しかし、価格が上がれば、新たな油田や新しい技術の開発が促進される。そして技術の進歩によって、それまでは採算が合わなかった油田を開発できるようになる。これまで採算が合わないと放っておかれた『オイルサンド』や『オイルシェール』などからも石油を取り出すようになり、そこで北米の埋蔵量がはねあがった。埋蔵量とはそのようなことで変動する」。
例えば、消費税・・・
「消費税を引き上げて喜ぶのは、自民党や財務省で、当然、国民は喜ばない。財務省が消費税を引き上げようとしている旗印は財政再建だが、もう一つ直間比率の是正というのもある。まず、消費税を上げずに済ます方法を述べてみよう」。
「一つは無駄な公共事業をやめれば歳出を大幅にカットできる。実際、すでに公共事業費はどんどん減っているが、それをさらに広げていく。もちろん土木建築などの業界には反対がある。それから族議員が反対する。第二は、赤字の国営事業を民営化する。中曽根首相は国鉄をJRにした。第三は、国有資産を売却する。小泉首相は郵便局を株式会社にした。どちらも国家が大株主として残っているが、その株式を売却すれば国有財産を売って収入にしたことになる」。
「消費税の議論はまずここから再出発するのがよいと思う。『消費税は福祉目的税にする』とかの主張はこの問題から逃げるために考えられたもので、結局は増税だから国民の同意は得られていない。国家財政の危機と赤字国債累積の問題にもどって、最終的にはどうなるのか—--を述べておこう。借金累積の問題には簡単な答えがある」。
「その一、やがて誰も貸してくれなくなるから借金は累積しない。その二、返済不能になったときは貸し手があきらめてくれる。したがって返済累積問題は最終的には、貸し手が自分は『甘かった』と反省し、借り手が『すまなかった』と謝る問題で決着になる。これは個人間でも企業間でも国家間でも変わらない信用の世界の法則である」。
「かつて1990年はじめにバブルがはじけて日本中が真っ暗になったとき、1994年の個人金融資産は1200兆円もあった。当時は、経済評論家などみな暗い見通ししかいわなかったが、そのとき私は『日本人の個人金融資産は1200兆円のあるのだから大丈夫だ』といっていたが、賛成してくれたのは竹村健一さんだけだった。いまは1500兆円になっている。それだけ個人金融資産があって、不景気だと幸いでいるのが不思議である」。
例えば、「格差」・・・
「『格差』とは、収入に『差がある』という程度問題ではなく、『格が違う』というように、その間に大きな溝が開いて、その間には隔絶した『段違い』があることが条件である。だから、『これは格が違うから、あいつとはもう争わない』というように、回復不能といったニュアンスがある。社会学的にいうならば、『追いつくことができるかどうか』が問題で、ヨーロッパでは、収入差の原因には身分差があって、ほとんど『生まれ』で決まっているから追いつくことができない。それがほんとうの『格差』である」。
「イギリスでは、貴族などの上流階級と労働者階級は、言葉遣いも違えば、生活も違う。そして、お互いに『あちらの人間は別の人間だ』と割り切っている。下流階級の人は、自分たちが上流階級になれると思っていないし、またなりたいとも思わない。日本では、生まれ育ちはそれほど問題にされないから、頑張れば誰でも追いつくことができる。いまの日本が『格差社会』かどうかの議論にはもっと強烈な格差社会が外国にはあることを考慮に入れてもらいたい」。
<日本の底力を知る、「こんなにすごい日本人のちから だから、日本の未来は明るい!」(日下公人著)>
http://blog.goo.ne.jp/asongotoh/e/efafc92125ef954976624574400f43d0










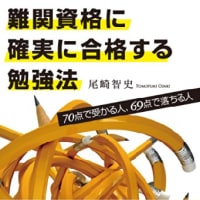
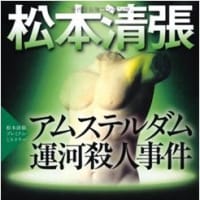
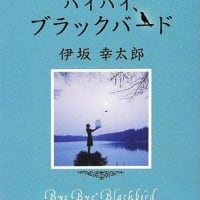

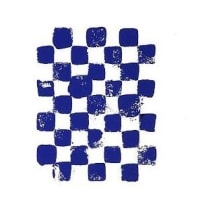
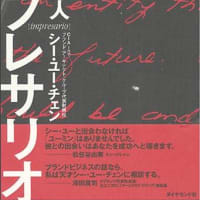



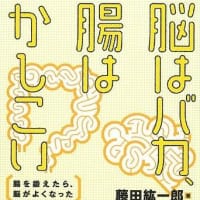
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます