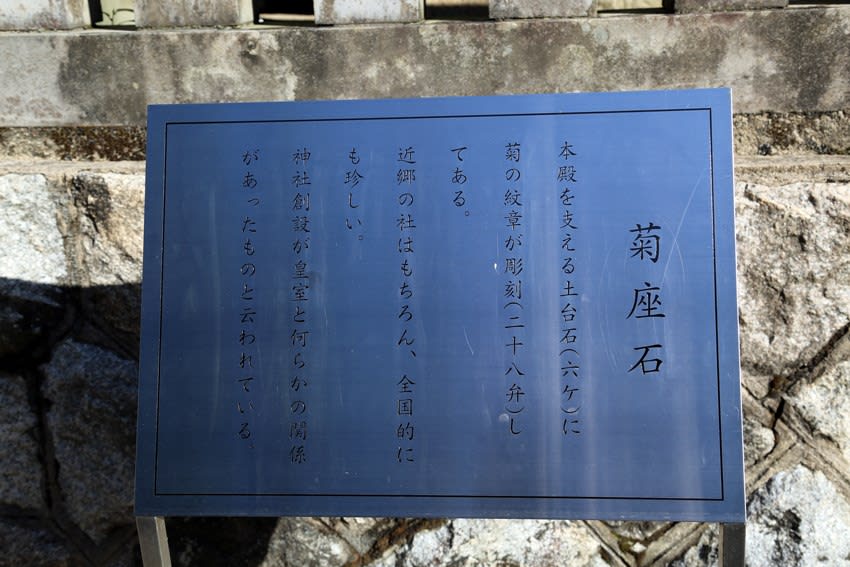大神山神社奥宮
大山寺の本堂横に大神山(おおがみやま)神社奥宮へ続く参道がある

もともとは天台宗の寺院(中門院、南光院、西明院)を総称して「伯耆大山寺」と呼ばれていた
明治8年の神仏分離政策により、大神山神社へと名称が変えられた

吉持地蔵
江戸中期、吉持甚右衛門の寄進。自然石に刻まれた地蔵

立体感を表現するための工夫が為されているなと考えながら呼吸を整える

石畳
昭和初期に自然石を使って造られた。
この敷き詰められた石が不揃いで、私の歩幅に合わず苦労した

鳥居が見えたが社殿の気配はない

御神水
延命長寿との記載があったので、一口飲んでみた

奥宮神門(後ろ向き門)
県指定有形文化財。元大山寺西楽院の表門を移設

明治8年、神社に引き渡された際にそのまま移転したので「後ろ向き」になったといわれている

ということはこちらが正面になる。人との比較で大きな門だということがわかると思う

狛犬
最近好んで撮るようになったのが狛犬


拝殿らしきものが視界に入ってくる。この最後の階段が長く感じてしまう。衰えたものだ

拝殿(重要文化財)
奥宮は、大山に登った修験者が、海抜900mほどの場所に簡易な遥拝所を設置したのが起源とされる
日本最大級の権現造り。正面の長廊は、両翼約50m。

写真では人物は写っていないが、大山登山を終えた人が帰りに立ち寄り参拝している
奥宮幣殿内(重要文化財)の拝観もできると云うので申し込む
神社内に初めて入ったが、柱や壁、天井画に至るまで豪華絢爛、別世界に入り込んだような感じだった。良い経験をした

拝殿の彫刻も素晴らしい


左回りに周辺を歩いてみる
下山神社(重要文化財)
津和野藩主、亀井公の寄進



弁財天社

奥宮 本殿(重要文化財)


苦手な石畳、多くの登山者に追い越される度、安全第一とつぶやき坂を下りる

賽の河原




参道に戻る。石仏に見守れながら無事駐車場へ
途中、入浴施設があることもわかり次回来たときのための参考にしようと思った

撮影 平成29年9月30日
大山寺の本堂横に大神山(おおがみやま)神社奥宮へ続く参道がある

もともとは天台宗の寺院(中門院、南光院、西明院)を総称して「伯耆大山寺」と呼ばれていた
明治8年の神仏分離政策により、大神山神社へと名称が変えられた

吉持地蔵
江戸中期、吉持甚右衛門の寄進。自然石に刻まれた地蔵

立体感を表現するための工夫が為されているなと考えながら呼吸を整える

石畳
昭和初期に自然石を使って造られた。
この敷き詰められた石が不揃いで、私の歩幅に合わず苦労した

鳥居が見えたが社殿の気配はない

御神水
延命長寿との記載があったので、一口飲んでみた

奥宮神門(後ろ向き門)
県指定有形文化財。元大山寺西楽院の表門を移設

明治8年、神社に引き渡された際にそのまま移転したので「後ろ向き」になったといわれている

ということはこちらが正面になる。人との比較で大きな門だということがわかると思う

狛犬
最近好んで撮るようになったのが狛犬


拝殿らしきものが視界に入ってくる。この最後の階段が長く感じてしまう。衰えたものだ

拝殿(重要文化財)
奥宮は、大山に登った修験者が、海抜900mほどの場所に簡易な遥拝所を設置したのが起源とされる
日本最大級の権現造り。正面の長廊は、両翼約50m。

写真では人物は写っていないが、大山登山を終えた人が帰りに立ち寄り参拝している
奥宮幣殿内(重要文化財)の拝観もできると云うので申し込む
神社内に初めて入ったが、柱や壁、天井画に至るまで豪華絢爛、別世界に入り込んだような感じだった。良い経験をした

拝殿の彫刻も素晴らしい


左回りに周辺を歩いてみる
下山神社(重要文化財)
津和野藩主、亀井公の寄進



弁財天社

奥宮 本殿(重要文化財)


苦手な石畳、多くの登山者に追い越される度、安全第一とつぶやき坂を下りる

賽の河原




参道に戻る。石仏に見守れながら無事駐車場へ
途中、入浴施設があることもわかり次回来たときのための参考にしようと思った

撮影 平成29年9月30日