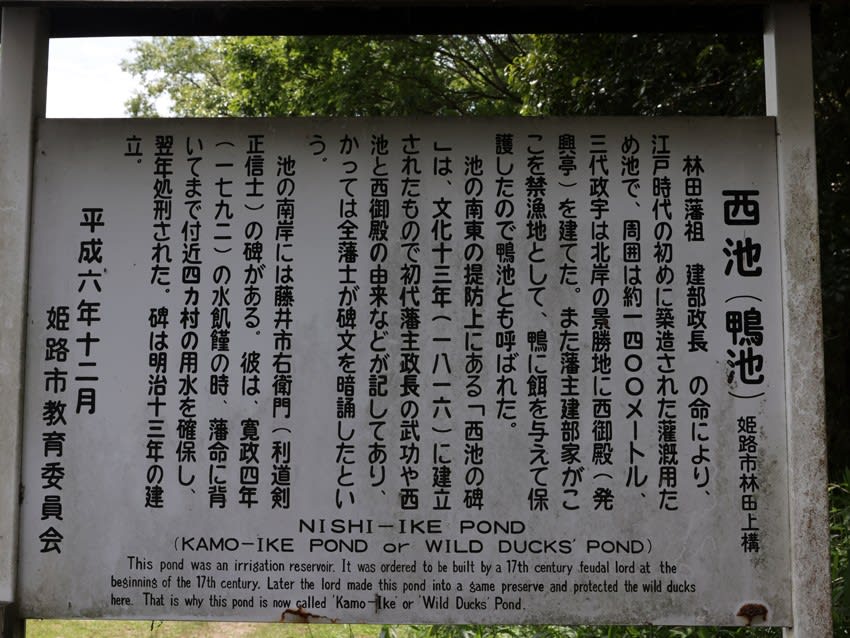シリーズ塔(九州・沖縄地方)7<三重塔・五重塔・多宝塔他>
長崎県(西教寺<新規>)
42 長崎県
42-01 高野山 最教寺(長崎県平戸市岩の上町1206番地1)
三重大塔
三重大塔は、最教寺が弘法大師の1150年御遠忌を記念して、奥の院本殿横に建立した
相輪までの高さは33.5m



長崎県(西教寺<新規>)
42 長崎県
42-01 高野山 最教寺(長崎県平戸市岩の上町1206番地1)
三重大塔
三重大塔は、最教寺が弘法大師の1150年御遠忌を記念して、奥の院本殿横に建立した
相輪までの高さは33.5m