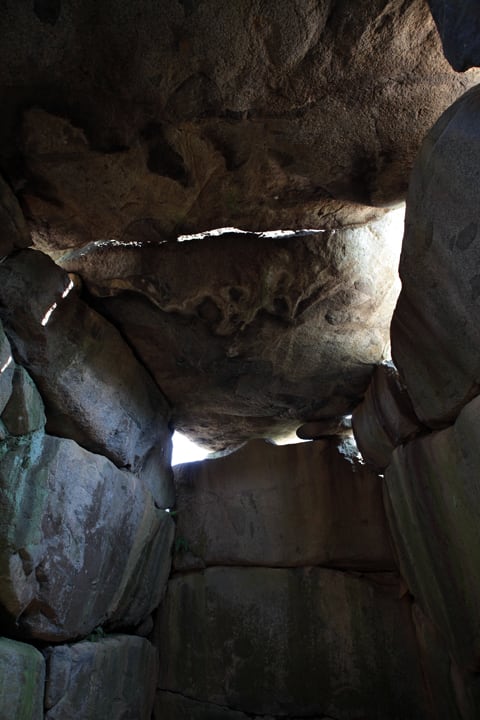三仏寺から道の駅に向かっている途中に幻想的な湖があり、近くに駐車場があったので車を駐め外に出た。
近くにいる人に何という湖ですかと尋ねると「東郷池」と教えてくれた。
東郷池
池の中央付近の湖底からは温泉が湧くという全国でも珍しい池であり、湖畔にははわい温泉と東郷温泉がある。
冬には池から湯気が立つ神秘的な風景も見られることがある。

左側を見ると池の上に家が浮かんでいるような感じがする。

車から望遠レンズを取り出し撮してみる

右側を見ると「ここは日本なの」という不思議な光景が

中国風の建物が並んでいて、何か不思議な感じがする

ここは公園になっていて、親子連れや、釣り人なども多い

とてもリラックスできる場所で1時間近く遠くを見ていた

撮影 平成25年10月31日
近くにいる人に何という湖ですかと尋ねると「東郷池」と教えてくれた。
東郷池
池の中央付近の湖底からは温泉が湧くという全国でも珍しい池であり、湖畔にははわい温泉と東郷温泉がある。
冬には池から湯気が立つ神秘的な風景も見られることがある。

左側を見ると池の上に家が浮かんでいるような感じがする。

車から望遠レンズを取り出し撮してみる

右側を見ると「ここは日本なの」という不思議な光景が

中国風の建物が並んでいて、何か不思議な感じがする

ここは公園になっていて、親子連れや、釣り人なども多い

とてもリラックスできる場所で1時間近く遠くを見ていた

撮影 平成25年10月31日