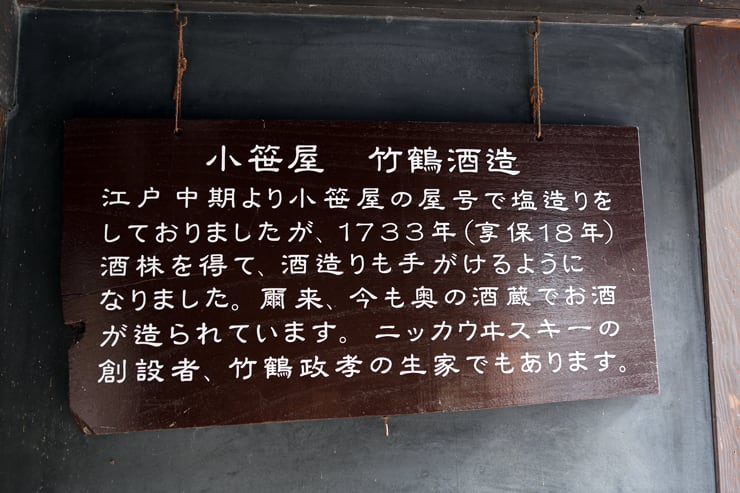旅をしていると全国各地に芭蕉ゆかりの土地がある
この象潟(きさかた)は芭蕉が訪れた北限の地としても有名である
史跡 名勝 天然記念物 象潟
元禄2年(1689年)に芭蕉が訪れた
『奥の細道』のなかで、「九十九島(つくもじま)」と呼ばれた当時の象潟の景観を絶賛

ここで芭蕉は、中国の悲劇の美女西施を思い浮かべ、「ねぶ」を「ねむの花」と「眠る」にかけて、
「象潟や 雨に西施が ねぶの花 」

雨にけむる象潟は、あたかもまぶたを閉じた西施のように美しいと詠んでいる

芭蕉が訪れた頃、象潟は「九十九島、八十八潟」、あるいは「東の松島、西の象潟」と呼ばれた
かつては現在の松島と同じ様に無数の小島が浮かぶ入り江だった

その昔、芭蕉は舟で「九十九島」を巡ったようである

芭蕉は雨の日に舟で、私は快晴の象潟をカメラを首にぶら下げ遊歩道で

天気も良く、このような青空も久し振りだ。実に気持ちがいい

文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で突然干潟に変わった
現在は多くの土地で米作りがおこなわれている

地元に人の話しによると「鳥海山」がこれほどはっきり見えるのは珍しい。良いときに来た、運がいいと言われた

終着が見えない「九十九島」巡りに、疲れもあり、後悔していたところだったが頑張る力となった

芭蕉が訪れた百年後に大地震で土地が隆起した

鳥海山の別名「出羽富士」「秋田富士」「庄内富士」

九十九島は紀元前466年の噴火で形成された
形成当時は海中の小島であったが 1804年象潟地震により隆起し特徴的な地形となった

さて、九十九島を巡る所要時間だが、私はゆっくり写真を撮りながら歩いたため約1時間

普通の人なら30~40分で回ることができる

普段、歩くという習慣がない私がこうして歩いているのも旅の力だと思う

もうひとつ魅力的だったのが青空の中の雲の形

形のいい雲を探して撮っていたような気がする。この雲、龍に見える

撮影 平成28年5月15日
この象潟(きさかた)は芭蕉が訪れた北限の地としても有名である
史跡 名勝 天然記念物 象潟
元禄2年(1689年)に芭蕉が訪れた
『奥の細道』のなかで、「九十九島(つくもじま)」と呼ばれた当時の象潟の景観を絶賛

ここで芭蕉は、中国の悲劇の美女西施を思い浮かべ、「ねぶ」を「ねむの花」と「眠る」にかけて、
「象潟や 雨に西施が ねぶの花 」

雨にけむる象潟は、あたかもまぶたを閉じた西施のように美しいと詠んでいる

芭蕉が訪れた頃、象潟は「九十九島、八十八潟」、あるいは「東の松島、西の象潟」と呼ばれた
かつては現在の松島と同じ様に無数の小島が浮かぶ入り江だった

その昔、芭蕉は舟で「九十九島」を巡ったようである

芭蕉は雨の日に舟で、私は快晴の象潟をカメラを首にぶら下げ遊歩道で

天気も良く、このような青空も久し振りだ。実に気持ちがいい

文化元年(1804年)の大地震(象潟地震)で突然干潟に変わった
現在は多くの土地で米作りがおこなわれている

地元に人の話しによると「鳥海山」がこれほどはっきり見えるのは珍しい。良いときに来た、運がいいと言われた

終着が見えない「九十九島」巡りに、疲れもあり、後悔していたところだったが頑張る力となった

芭蕉が訪れた百年後に大地震で土地が隆起した

鳥海山の別名「出羽富士」「秋田富士」「庄内富士」

九十九島は紀元前466年の噴火で形成された
形成当時は海中の小島であったが 1804年象潟地震により隆起し特徴的な地形となった

さて、九十九島を巡る所要時間だが、私はゆっくり写真を撮りながら歩いたため約1時間

普通の人なら30~40分で回ることができる

普段、歩くという習慣がない私がこうして歩いているのも旅の力だと思う

もうひとつ魅力的だったのが青空の中の雲の形

形のいい雲を探して撮っていたような気がする。この雲、龍に見える

撮影 平成28年5月15日