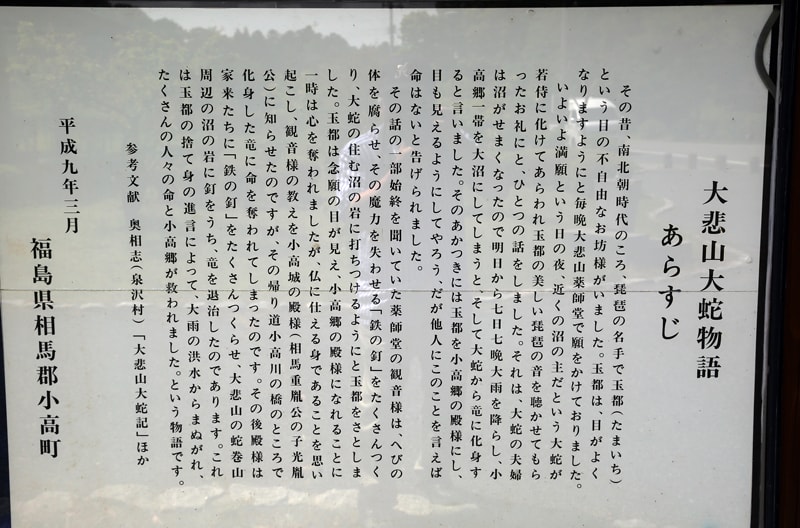忍野八海(世界文化遺産)
自然の美しさに興味のない私でも知っている「忍野八海」、テレビでも何度か視たことがある
「忍野村観光案内所」があったので立ち寄る。美人で親切な女性から資料にて説明を受ける
出口池(一番霊場) 祭神:難陀竜王
「あめつちの ひらける時にうこきなき おやまのみつの出口たうとき」
八海の中で一つだけ離れた場所にあり最も面積が広い池

ブログでは一番から八番霊場の順番になっているが、実際に廻った順とは大きく異なる

お釜池(二番霊場) 祭神:跋難陀竜王
「ふじの根のふもとの原にわきいづる水は此の世のおかまなりけり」
八海の中で最も小さな池

富士山の雪解け水が地下の溶岩の間で、約20年の歳月をかけてろ過され、湧水となって8か所の池をつくっている。

底抜池(三番霊場) 祭神:釈迦羅竜王
「くむからにつみはきへなん御仏のちかひぞふかしそこぬけの池」
忍野八海で唯一個人所有の池。入館料300円

洗物が消えると云う伝説のある池


有料施設だけに良く整備されていて、とても美しい。

本来なら写真中央に富士山が見えるはずだが、数十分待っても雲に隠れたまま。

銚子池(四番霊場) 祭神:和脩吉竜王
「くめばこそ銚子の池もさはぐらんもとより水に波のある川」
縁結びの池と伝えられている

酒を注ぐ銚子の形からこの名が付けられたという
池の底の砂地から砂を巻き上げ水が湧いている

湧池(五番霊場) 祭神:徳叉迦竜王
「いまもなほわく池水に守神のすへの世うけてかはれるぞしる」
八海一の湧水量と景観を誇る池が見えてくる

富士山の頂上付近が視界に入ってきたので望遠レンズで

観光客が覗いて見ている場所にどうしたら行けるのか解らなかった
探すと売店の中に出入口があった。お土産屋の店員から掛けられる声に気持ちが動く

この地を訪れるまで、忍野八海はこのサークルに囲まれた部分だと勘違いしていた

底知れぬ魅力がある場所と感じていたが、水中洞窟を持ち、池の底から最奥部まで約55mあることが確認された
底に光っているのは中国人観光客が投げ入れたコイン。罰金千円の看板もある

周辺の様子

国指定の天然記念物、名水百選に指定

湧水量も豊富で、売店ではこの水も販売している

透明度が高く水草もはっきり見ることができる

水車小屋からの風景

濁池(第六霊場) 祭神:阿那婆達多竜王
「ひれならす竜の都のありさまをくみてしれとやにごる池水」
みすぼらしい行者が一杯の水を求めたが断わられ濁ったといわれる池

湧水は池底から少しだけ湧き出ている

川に隣接している

鏡池(第七霊場) 祭神:麻那斯竜王
「そこすみてのどけき池はこれぞこのしろたへの雪のしづくなるらん」
水面に富士山を映す池と説明があった瞬間、富士山の頂上付近が見えてきた

池に富士山をと思ったが、実に難しい

菖蒲池(第八霊場) 祭神:優鉢羅竜王
「あやめ草名におふ池はくもりなきさつきの鏡みるここちなり」
菖蒲にまつわる美しい伝説が残る池。奥には八海菖蒲池公園がある

八つの池の全てを廻ってみた。所要時間は休憩も含み約2時間

かつてこの地に存在した忍野湖が干上がって盆地になり、富士山や近くの火山山麓の伏流水を水源とする湧水の出口が池として残った姿が忍野八海である
「八海」の名は、富士講の人々が富士登山の際に行った8つの湧泉を巡礼する八海めぐりからきている
1843年に各池に守護神の「八大竜王」が祀られ、出口池を一番霊場、菖蒲池を八番霊場とする巡礼路が整備された
富士山の雪どけ水

周辺が急に賑やかになったと思ったら、中国人観光客を乗せたバスが着いた。一気に雰囲気が変わる

静かな場所を求め、有料施設で「底抜池」のある「榛の木材資料館」に逃げ込むことにした





「はんのき資料館」敷地内の大型の池「榛の木池」は人工池


撮影 平成29年5月16日
自然の美しさに興味のない私でも知っている「忍野八海」、テレビでも何度か視たことがある
「忍野村観光案内所」があったので立ち寄る。美人で親切な女性から資料にて説明を受ける
出口池(一番霊場) 祭神:難陀竜王
「あめつちの ひらける時にうこきなき おやまのみつの出口たうとき」
八海の中で一つだけ離れた場所にあり最も面積が広い池

ブログでは一番から八番霊場の順番になっているが、実際に廻った順とは大きく異なる

お釜池(二番霊場) 祭神:跋難陀竜王
「ふじの根のふもとの原にわきいづる水は此の世のおかまなりけり」
八海の中で最も小さな池

富士山の雪解け水が地下の溶岩の間で、約20年の歳月をかけてろ過され、湧水となって8か所の池をつくっている。

底抜池(三番霊場) 祭神:釈迦羅竜王
「くむからにつみはきへなん御仏のちかひぞふかしそこぬけの池」
忍野八海で唯一個人所有の池。入館料300円

洗物が消えると云う伝説のある池


有料施設だけに良く整備されていて、とても美しい。

本来なら写真中央に富士山が見えるはずだが、数十分待っても雲に隠れたまま。

銚子池(四番霊場) 祭神:和脩吉竜王
「くめばこそ銚子の池もさはぐらんもとより水に波のある川」
縁結びの池と伝えられている

酒を注ぐ銚子の形からこの名が付けられたという
池の底の砂地から砂を巻き上げ水が湧いている

湧池(五番霊場) 祭神:徳叉迦竜王
「いまもなほわく池水に守神のすへの世うけてかはれるぞしる」
八海一の湧水量と景観を誇る池が見えてくる

富士山の頂上付近が視界に入ってきたので望遠レンズで

観光客が覗いて見ている場所にどうしたら行けるのか解らなかった
探すと売店の中に出入口があった。お土産屋の店員から掛けられる声に気持ちが動く

この地を訪れるまで、忍野八海はこのサークルに囲まれた部分だと勘違いしていた

底知れぬ魅力がある場所と感じていたが、水中洞窟を持ち、池の底から最奥部まで約55mあることが確認された
底に光っているのは中国人観光客が投げ入れたコイン。罰金千円の看板もある

周辺の様子

国指定の天然記念物、名水百選に指定

湧水量も豊富で、売店ではこの水も販売している

透明度が高く水草もはっきり見ることができる

水車小屋からの風景

濁池(第六霊場) 祭神:阿那婆達多竜王
「ひれならす竜の都のありさまをくみてしれとやにごる池水」
みすぼらしい行者が一杯の水を求めたが断わられ濁ったといわれる池

湧水は池底から少しだけ湧き出ている

川に隣接している

鏡池(第七霊場) 祭神:麻那斯竜王
「そこすみてのどけき池はこれぞこのしろたへの雪のしづくなるらん」
水面に富士山を映す池と説明があった瞬間、富士山の頂上付近が見えてきた

池に富士山をと思ったが、実に難しい

菖蒲池(第八霊場) 祭神:優鉢羅竜王
「あやめ草名におふ池はくもりなきさつきの鏡みるここちなり」
菖蒲にまつわる美しい伝説が残る池。奥には八海菖蒲池公園がある

八つの池の全てを廻ってみた。所要時間は休憩も含み約2時間

かつてこの地に存在した忍野湖が干上がって盆地になり、富士山や近くの火山山麓の伏流水を水源とする湧水の出口が池として残った姿が忍野八海である
「八海」の名は、富士講の人々が富士登山の際に行った8つの湧泉を巡礼する八海めぐりからきている
1843年に各池に守護神の「八大竜王」が祀られ、出口池を一番霊場、菖蒲池を八番霊場とする巡礼路が整備された
富士山の雪どけ水

周辺が急に賑やかになったと思ったら、中国人観光客を乗せたバスが着いた。一気に雰囲気が変わる

静かな場所を求め、有料施設で「底抜池」のある「榛の木材資料館」に逃げ込むことにした





「はんのき資料館」敷地内の大型の池「榛の木池」は人工池


撮影 平成29年5月16日