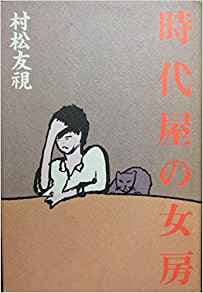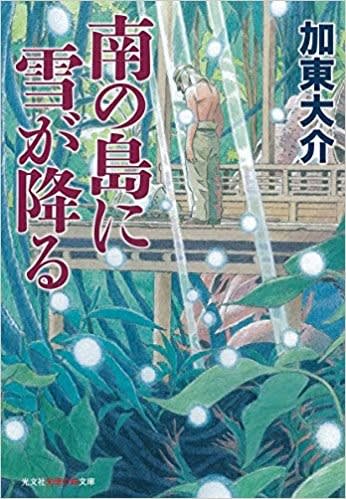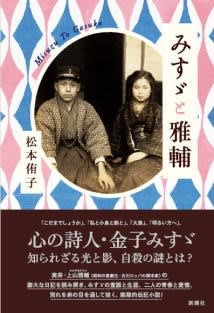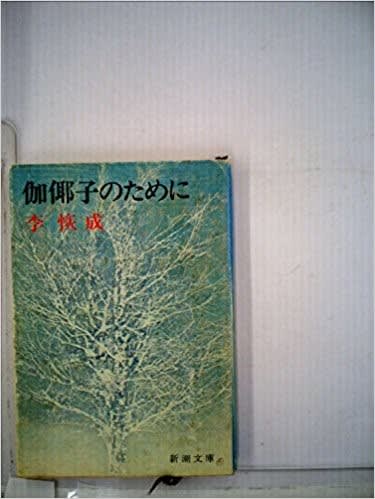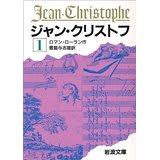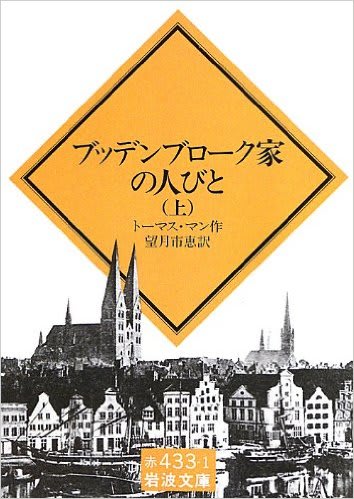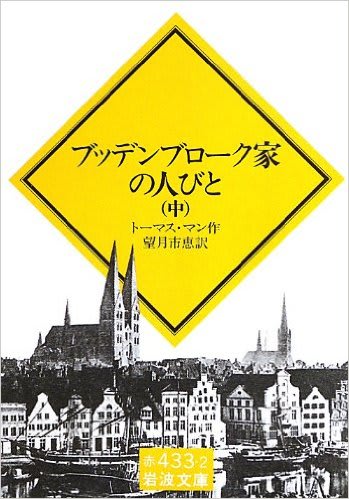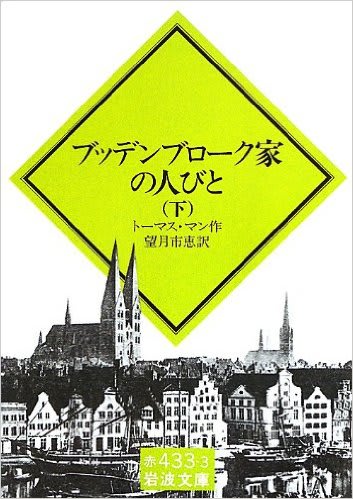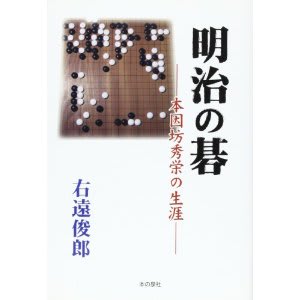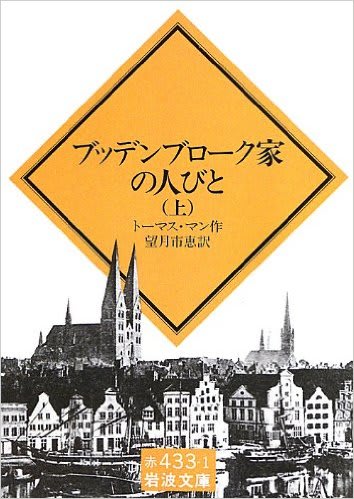
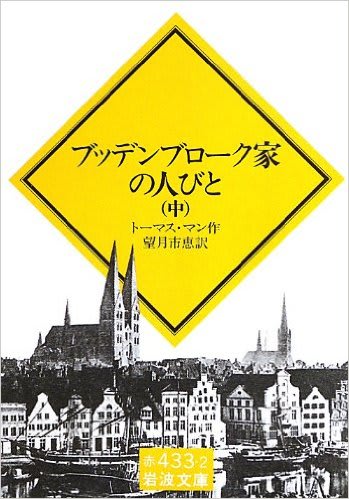
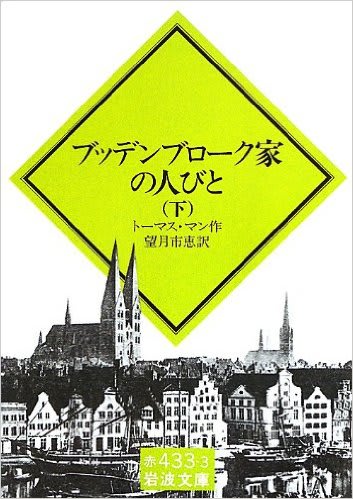
トーマス・マン『ブデンブローグ家の人々』を読了しました(画像は岩波文庫版ですが、わたしは新潮社から出た『トーマス・マン全集1』所収のものを読みました。森川俊夫訳です)。長編です。就寝前に少しづつ読み、2か月半かかりました。わたしにとっては、退屈な小説でした。200年ほど前の北ドイツの小さな都市にあった「商会」の3代にわたる物語で、いまからみれば時代が離れすぎ、また知らない地方の話で、興味があまりわかないのは至極当然、と自分をなっとくさせました。しかし、完読の達成感、醍醐味はあります。
しかし、この長編を26歳のマンが執筆したというは、驚きです。最初は兄のハインリヒと共著の予定だったのが、体調が悪く、ひとりで書いたということです。マンはのちにノーベル文学賞を受賞しますが、この作品の評価が高かったようです。
わたしはこれから少しづつ長編小説を読み進めたいと計画しています。『ブデンブローグ家の人々』は、その手始めでした。なぜ、この作品を選んだかというと、高校時代に北杜夫の小説を読み漁っていましが、その彼が『ブデンブローグ家の人々』に傾倒し、その影響もあって『楡家の人々』を書いたということを知っていたからです。『楡家の人々』は、高校時代に読みました。これはなかなか面白かったです。歌人の斎藤茂吉の家系をあつかっていて、自伝的な要素もありましたが、北杜夫らしいユーモアもちりばめられていて飽きませんでした。『ブデンブローグ家の人々』を読んだのはそういう事情がありました。
600ページに近い(上下2段)この小説のあらましを書くのは容易でありませんが、無理をして大筋だけ記すと以下のようになります。
この作品は、商家ブッデンブロークスの繁栄と没落を描いたものです。冒頭はパーティーの場面。パーティーで祖父にかわいがってもらっている少女アントーニエ(トーニ)は、ヒロインです。トーニにはひそかに想いを寄せていた青年がいましたが、その想いは実現しませんでした。トーニには、グリューンリッヒという男と結婚しまする。最初の夫です。この結婚生活は、グリューンリッヒの破産で終わります。そして、トーニの父ヨハンの死によって第一部が終了します。
父ヨハンの死によってブッデンブローク家の実権は、長男トーマスにゆだねられます。出戻りの妹トーニはペルマネーダーと二度目の結婚を果たしますが、再婚生活は彼の些細な捨て台詞であえなく崩壊してしまいます。一方弟のクリスチアンは体が弱いのを口実に仕事をせず、芝居に夢中になっている根っからの遊び人です。
トーマスの結婚もうまくはいきません。疎遠な夫婦のあいだに生まれたハンノは、およそ商人には向かない内気な性格ですが、芸術的に豊かな才能を持ち、ピアノに天分を示します。将来に不安を抱え経営を任されたトーマス。あにはからんや、ブッデンブローク商会の経営は立ちゆかなくなり、トーマスは財産をめぐる母エリーザベトとの確執のもと次第に自信を失い、疲労をため込んでいきます。
時代は進んで、母エリーザベトの死。トーマスは家の売却が決まります。永眠についた母の遺産をめぐって、トーマスとクリスチアンの兄弟喧嘩が始まります。仕事一徹の兄を冷酷だといって非難する遊び人の弟に対し「ぼくは君のようになりたくなかったからこうなったんだ」とつぶやくトーマス。
心身ともに疲弊し、不出来な息子や妻の浮気によって何も信じられなくなったトーマスは、ふとしたきっかけでショーペンハウアーの『意志と表象としての世界』を手に取ります。「死について」と題された章を一心不乱に読みふけり、その夜の寝室で哲学的真理に目覚めて嗚咽します。だがそれも一夜限りのことで、再びいつもの日常に戻るトーマスは、歯医者の帰りに転倒し、あっけなく帰らぬ人となります。妻からも同情されなかったトーニは、華やかな葬式の挙行で送られます。
遺された一人息子ハンノ。学校での生活は、むなしい日々です。ハンノが戯れに弾く即興曲。そのハンノの早世によって物語は終わります。
隆盛をきわめていた商家が、頽廃し没落していく様子は、トーマス・マン自身の家系の小説化です。